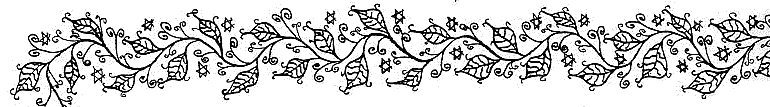
久保貞次郎研究所
「久保貞次郎研究所月報が9の後に、13年分営々と掲載されています。物好きなお方、お読みになって頂ければ幸いです。私の思想らしきものが凝縮されていると自負しております。」
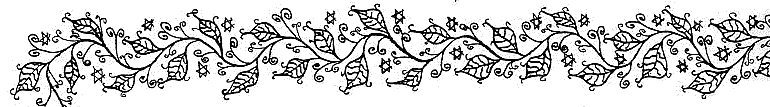
1、名称 久保貞次郎研究所(2010年4月1日設立)
2018年11月26日渡辺淑寛著作集第7巻真岡新聞社より出版
2019年12月9日渡辺淑寛著作集第8巻真岡新聞社より出版
◎2021年7月31日渡辺淑寛著作集第9巻真岡新聞社より出版
◎2023年2月28日渡辺淑寛著作集第10巻真岡新聞社より出版
◎2024年11月11日渡辺淑寛著作集第11巻もおか新聞プラスより出版
[渡辺美術館について」 「真岡市駅前SL館東に、2015年5月渡辺私塾美術館を開館しました。土曜日午後1時~4時開館(但し2名以上でご来館の場合、月~土曜日で午後1時~4時相談の上臨時開館致します。℡090 5559 2434にお問い合わせください。) 前日までに来館の時間をお伝えください。相談の上、5分前に開館するようにします。2019年1月より毎週土曜日午後1時より4時定期開館 2025年中、土曜日午後1時から4時来館者様全員に拙書著作集第11巻を贈呈、入館無料、当分オリジナル版画プレゼント」 2016年2月21日第3回企画展恩地孝四郎展開始 2025年4月現在恩地作品398点展示他計1353点展示(恩地孝四郎作398点展示を記念して、「渡辺私塾美術館」のサブ名称を「恩地孝四郎ミュウジアム」と致します。(貧弱な展示作品目録作成、希望者にプレゼント。「月に吠える」より恩地木版3点、「公刊月映1号」より恩地木版4点追加展示、「飛行官能」、「公刊月映4号」展示) (美術館所在地は 真岡駅東口を少し南下し、信号の有るT字路を左折してすぐ右。渡辺私塾駅前校と隣接)(ヤフーまたはグーグルで、「渡辺私塾美術館」(「渡辺私塾台町本校系列」から左下「渡辺私塾美術館」をクリックすればアクセス出来ます))で検索出来ます)
2016年11月20日より新キャンペーンスタート
「以前アイオーのオリジナル版画を受け取って頂いた方々には、2度目の来館時別作家のオリジナル版画を、当分の間プレゼント、3度目、4度目の来館時にもそれぞれ別作品をプレゼント」5度目以降は、来館の度に、お好きな洋書(英・独・仏・露)1冊プレゼント。 (久保貞次郎氏の小コレクター運動(一人一人がオリジナル作品3点以上を蒐集し、生活の中に芸術を浸透させる)、という思想のささやかな継承を目指して)
(久保氏関連作品も119点展示)
「渡辺私塾美術館」(真岡市台町101-20)・お問い合わせ先・〒321-4306、栃木県真岡市台町3362-2渡辺淑寛まで(電話090 5559 2434)
2016年11月26日、南都麗(私のペンネーム)の意味不明の不気味なペン画4点追加。(南都作品は全部で31点展示)
◎2020年3月開館5周年記念として、ロダン「バルザック像」を展示(ブロンズ最終直前習作、107㎝67㎏、国立西洋美術館蔵、パリ ロダン美術館蔵、フィラデルフィアロダン美術館蔵と同作品)
◎2024年開館9周年記念として、恩地孝四郎油彩画代表作 「三人の女性」(1917年二科展出品作、50号、1988年フジイ画廊恩地孝四郎油絵展No1掲載作品)をNo1212として展示。
◎2025年開設10周年記念として、バルビゾン派7星の一人コンスタン・トロワイヨン油彩画「羊と少年」8号を展示。
2、久保研究所代表 渡辺淑寛
代表略歴
昭和23年栃木県真岡市生まれ
栃木県立真岡高校卒
宇都宮大学工学部工業化学科卒
名古屋大学文学部哲学科美学美術史卒
久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺私塾文庫文庫長
恩地孝四郎 集古十種 アルス日本児童文庫研究家 文学士 工学士
著書 1997年 「愛の三行詩第一章」限定1000部 渡辺私塾出版部
1997年 詩画集「潮に聞け」限定60部 渡辺私塾出版部
1998年 「応援歌 血から知へ果てしなき旅」限定60部 渡辺私塾出版部
1999年「愛の三行詩第二章」限定40部 渡辺私塾出版部
2001年詩画集「潮に聞け」 文芸社
2008年~2024年渡辺淑寛著作集(第一巻~第十一巻) 真岡新聞社、もおか新聞プラス
(2024年現在16冊刊行)
3、所在地 〒321-4306 栃木県真岡市台町3362-2 お問い合わせは℡090 5559 2434(代表渡辺まで)
メールアドレス(nantray@i-berry.ne.jp)(2025年6月1日よりu-84895@moon.ucatv.ne.jp)
4、設立趣旨、活動
ⅰ、久保貞次郎関係本の蒐集(渡辺私塾文庫 所蔵品目録{26}Ⅰ,久保貞次郎関係本参照)
ⅱ、久保貞次郎旧蔵本・旧蔵作品の蒐集(同、所蔵品目録{26}Ⅲ、旧蔵本・旧蔵作品参照)
ⅲ、久保氏(1909~1996)の思想、哲学の研究(久保氏は、①,美術評論家、②,美術品コレクター、③,ヘンリー・ミラー絵画の紹介者、④,多くの芸術家に対する経済的思想的支援者(パトロン)、⑤,現代版画のプロデューサー、⑥,児童絵画には独自の意味と価値が有るという創造美育教育の創設者、⑦,全ての者が一人3点以上のオリジナル作品を持とうという「小コレクター運動」の提唱者、⑧エスペラント学会会長、⑨跡見学園短大学長、⑩町田市立国際版画美術館館長、という多くの側面が有り、多面的な久保研究はほとんどなされていない。この10点について少しずつ研究を進めたいと考えている。
また滝川太郎贋作事件で久保氏が計47点の滝川製贋作を購入したとされる贋作事件についても、地元の久保研究家としては辛い部分もあり、弁護に終始する事になりそうだが、逃げずに取り組みたいと思っている。
更に久保氏とエスペラントについても調べる予定である。久保氏(1909~1996)は、1928年、19才で日本エスペラント学会に入会し、22才で学会評議員に、32才で学会の理事に、1989年に会長に就任し他界するまで在任。1906年孤高のアナキスト大杉栄が日本エスペラント協会を設立したと言われているが(実際には、東大教授黒板勝美が設立したという説が有力)、久保氏の時代も、アナキズムや左翼と関連を持つエスぺランチストが多い中で、久保氏は中道主義の立場をとった。戦前中道主義は、当然反体制であったが、同時に左翼からも堕落したプチブルと非難されたようである。「松本健一~(久保さんと私とエスペラント)、「久保貞次郎を語る」、1997,文化書房博聞社、157ページ参照。」、もし左翼やアナキズムに傾倒していたら、その後の久保氏の活躍は無かったであろうし、世界人、人類人の言語であるエスペラント語と、「全ての人が芸術家である社会」に向けての第一歩である、「小コレクター運動」が結びつく事は無かったであろう。思うに、「全ての人が芸術家で詩人で音楽家で哲学者で宗教家である社会」は、当然国家も、暴力も、貨幣も無い社会であろうから。)
ⅳ、芳賀の高校生へ、久保氏を紹介(20年以上前から、毎年高2英語夏休み特別講義「言語と芸術」で100名弱の高校生に、追悼文と経歴、思想を紹介。(2018年でひとまず終了)、(ホームページTOP,渡辺私塾の活動9、を参照)
ⅴ、久保氏の創造美育教育の流れをくむ「芳賀教育美術展」の支援(同展には「久保賞」という賞があり、私の娘も20年近く前に、2度受賞し、2個の記念メダルを今でも大切に所持している。また娘は大学卒業後家業を手伝う傍ら、油彩画を描き、日洋展に何度か入選している。その記念メダルが無かったら、今絵を描いていないで有ろう。)具体的な支援方法は次のⅵでのべる。2010年から2013年まで毎年740点の副賞を提供してきたが、美術展運営方法の考え方の違いにより、残念ながら支援は一時中断することになった。
ⅵ、久保貞次郎基金の設立(募金はせず、小額ながら代表の私費で設立。原資は取り崩さず運用益で、当面極めて僅かながら、ⅴの「芳賀教育美術展」を支援。具体的には、2010年から副賞を提供させて頂き、2019年度で10回目の支援となる。直近5年間は、毎年740点のオリジナル版画を入賞者の副賞として提供している。経済的にも、精神的にも、時間的にもかなりの負担であるが、その負担は純粋な喜びである。毎年740点のオリジナル版画の提供なので、作品の蒐集は困難を極めているが、この10年間、何故か奇跡的に成功してきた。)2023年、740点の副賞を提供したが、美術展運営方法の考え方の違いにより、芳賀教育美術展への当研究所の支援は、当面休止する予定である。
ⅶ、将来は、機関誌の発行、講演会の開催等を実現できればと願っている。(2010年6月末に真岡青年会議所主催の久保氏に関する講演会が計画されている。詳しくは「5月月報」参照。6月28日講演会が開催された。「2010年7月月報」参照。研究所月報をこのホームページに掲載し、真岡新聞紙上に発表し、2,3年に1度、渡辺淑寛著作集に月報を掲載しているので、当然機関誌発行を兼ねている。2018年で著作集は第7巻まで真岡新聞社から刊行。毎年、芳賀教育美術展表彰式時、副賞紹介を兼ねて、久保研究所代表として、僭越ながら簡単な講話の機会を頂いている。)
ⅷ 渡辺美術館において、久保氏関連作品の展示(2019年10月現在83点展示)
5、久保氏は真岡市で活躍した、日本美術史上希有な美術思想家であり、氏の思い、思想を後世に伝える事が我々真岡市民の責務であろう。
6、当研究所の当面の研究課題 ①,久保貞次郎と恩地孝四郎の関わり(「久保貞次郎を語る」、1997年、文化書房博文社、53ページに両氏をよく知る綿貫不二夫氏の興味深い文がある。)(「久保貞次郎 美術の世界5 日本の版画作家たち」昭和62年、同刊行会、に「恩地孝四郎の一枚綴りの芸術」、「恩地孝四郎を思う」、「恩地孝四郎の思いで」の3編が掲載されていて、3編の根底に、生前の恩地氏を評価できなかった事への、久保氏の厳しい悔恨の念が流れている。それでも「恩地孝四郎の一枚綴りの芸術」の中で、久保氏は、恩地の作品には「前衛的であるためにもつべき拒絶性の欠如」がある、と大胆に指摘している。この指摘に対する私の、一層大胆で向こう見ずな感想は、「渡辺私塾文庫 2恩地孝四郎、Ⅵ恩地孝四郎賛歌 その5(2006年12月1日)を参照)
②,久保貞次郎と精神世界(「久保貞次郎を語る}、112ページに、長倉翠子氏の回想文の中で、久保氏が晩年、精神世界に強い興味を持っていたと書かれている。また同書71ページでも、磯辺行久氏が同様の事を書いている。)
(「恩地孝四郎」と、精神世界の2点は、私の40年来の研究対象であり、非常に好奇心をそそられる内容で興味が尽きない。また私の思想形成における久保氏の影響については、「渡辺私塾文庫」内「蒐集雑感」2003年1月の「私設文庫開設のすすめ」を参照)(平成14年12月号「吾八書房これくしょん63号掲載文。拙著「渡辺淑寛著作集第1巻巻末にも所収。)
7、久保氏については渡辺私塾文庫 所蔵品目録{26}Ⅱ、久保貞次郎追悼文参照)(追悼文は、平成9年2月28日真岡新聞に掲載。また拙書「渡辺淑寛著作集第1巻」(平成20年、真岡新聞社)にも所収)
8、真岡新聞に久保貞次郎研究所関連記事を掲載
9、下野新聞2010年7月6日号「とちぎ温故知人」39,で久保貞次郎の特集記事が掲載された。6月28日2時間ほど、女性記者の取材を受け、久保氏の研究について話を聞いて頂いた。
久保氏関連所蔵品は、「渡辺私塾文庫」「26」を参照
「久保貞次郎研究所月報」
①久保貞次郎研究所2010年4月月報(第1回)
②久保貞次郎研究所2010年5月月報(第2回)
③久保貞次郎研究所2010年6月月報(第3回)
④久保貞次郎研究所2010年7月月報(第4回)
⑤久保貞次郎研究所2010年8月月報(第5回)
⑥久保貞次郎研究所2010年9月月報(第6回)
⑦久保貞次郎研究所2010年10月月報(第7回)
⑧久保貞次郎研究所2010年11月月報(第8回)
⑨久保貞次郎研究所2010年12月月報(第9回)
11月末、日野市在住の大学生が、卒業論文で、久保貞次郎と創造美育運動について書きたいとの趣旨で、数時間かけて来宅してくれました。話を聞きますと、実家は喜連川町にあり、矢板東高校出身で、高校時代から、久保氏と創美運動に興味があり、専門は美術教育との事でした。心躍らせながら、1時間ほど話を聞いてもらい、私の拙本も贈呈致しました。彼は、携帯という文明の利器で、当文庫の久保関連蔵書を撮影していき、楽しい数時間でした。今後の彼の活躍を、北関東の大地から、祈願しております。
12月28日、真岡新聞社から、「続・渡辺淑寛著作集」が届きました。26日日曜日高校3年生の卒業式で、100冊ほど早摺りしてもらい、「潮に聞け」、「著作集」、「続・著作集」の3冊を卒業記念として贈呈出来て嬉しい限りでした。「続・著作集」の中で、第1章第2節と第2章で「久保貞次郎研究所について」と題して、研究所設立の経緯、目的、活動等について書かれておりますので、機会が御座いましたら、一読して頂ければ幸いです。
⑩久保貞次郎研究所2011年1月月報(第10回)
新年1月14日、真岡青年会議所の新理事長と、「芳賀教育美術展」、「創造美育運動勉強会」を実質運営している真岡青年会議所地域教育委員会の旧委員長と新委員長が来宅され、新年度の「美術展」と「創美運動」について話し合った。新年度も、青年会議所の献身的無私無償の活動に対して、当研究所の出来る範囲で極力協力することを約束し、久保基金から微額ながら美術展の運営費の一部として献金できた。今支援できる立場に居ることを、感謝し、望外の喜びと心底感じている。
三人の好青年が帰った後、同席した家内とも話したのだが、三人とも本当にすがすがしい若者で、還暦を過ぎた我々夫婦二人、心の奥の奥から若返る思いであった。そして若者達の晴れ渡るような精神と共鳴できたことを、二人寄り添い共鳴の余韻の中で喜んだ。この様な精神の素朴な震えは、何十年ぶりなのだろうか、それとも初めてだと言うべきなのだろうか。素晴らしい芸術作品と出会えた歓喜から生まれる精神の震えとは異なった、人間同士の共鳴なのかも知れない。
雨巻の山々の麓、同じ真岡市の空の下、彼らの活躍を心から願う。そして私達も「全ての人が詩人であり芸術家である社会」に向けて、微かだか確実な一歩を再度踏み出そう、存在とは進化だから。
⑪久保貞次郎研究所2011年2月月報(第11回)
真岡新聞に、初めて久保貞次郎代表の名で、美術評論2編を掲載しましたので、2月月報は、その2編に換えさせて頂きます。1編は、真岡新聞2月4日号「「真岡・浪漫ひな飾り展」、「海老原真砂米寿記念展」を観て」、もう1編は、2月18日号「宇都宮美術館「荒井孝展」を観て」、で、今年出版予定の「渡辺淑寛著作集第3巻」にも所収の予定です。
今後は、久保氏がそうであったように、地元の芸術家を久保研究所として、微力ながら応援していきたいと思っています。真岡新聞に美術評論を掲載する事もその応援の一つであり、芳賀の大地に新たな文化の微風が僅かでも立ち起これば幸いです。他の応援の方法については現在検討中です。 (2編の拙文は、上の「2月号月報」のクリックで閲覧出来ます。)
⑫久保貞次郎研究所2011年3月月報(第12回)
3月11日悪夢の大震災で真岡市も震度6強の地震に襲われ、文庫館、図書館、書斎の本箱は一瞬にして飛び散り、未だドアの開かない部屋もあって、復旧には数年かかりそうです。それでも塾生が利用する図書館だけは応急処置で本を元に戻しましたが、他はまだ手が着かない状況で、少しずつしぶとく復旧させようと思っています。
久保氏関連の蔵書、作品等は幸運にもほとんど破損を免れ、ほっとしています。
大震災と人類、文明の関係については、「渡辺私塾台町本校ホームページ」に、「鎮魂歌」と「海と文明、悲憤を越えて」~追悼文にかえて~を掲載しましたので一読して頂ければ幸いです。また「鎮魂歌」は3月25日号「真岡新聞に、「「海と文明」は4月1日号真岡新聞に掲載致しました。
先日、昭和44年10月発行の「愛苑」創刊号を読んでいましたら、偶然、120ページで久保氏の「性図書館をつくれ」という論文に出会いました。「性の解法は人間性の回復に計り知れぬ役割をはたす」から性図書館をつくりなさい、という趣旨の論で、今更ながら、久保氏の視野の広さ、見識には驚かされます。なお、この論文の存在は、1997年、文化書房博文社、「久保貞次郎を語る」、執筆編集年譜23ページに掲載されていて既知のようです。
「今月の久保氏関連新収品」 @「版をほる瀬戸の子ら」、1972,瀬戸市図工研究会、限定500部、久保氏編
@「愛苑創刊号」、1969,外苑書房、久保論文「性図書館をつくれ」所収
(2011年3月号より「今月の久保氏関連新収品」を掲載致します。)
⑬久保貞次郎研究所2011年4月月報(第13回)
4月末になっても毎日のように続く地鳴りのような余震の中、今年の芳賀教育美術展の入賞者副賞に予定している、名著「ドレ挿し絵本、ドンキホーテ」の所在が気になり、捜し始めました。ドレ挿し絵本の置いてある部屋は、本箱が幾重にも重なり足の踏み場も無い状態で、ただただ呆然と立ちつくすだけでしたが、芳賀の地に、ギュスターブ・ドレのオリジナル鋼版画が深く浸透する事を思い、三日がかりで探し出しました。そう言えば芳賀の地では、池田満寿夫や瑛久の版画が今でも散見されますが、これは久保氏が50年ほど前、真岡市で小コレクター運動を展開し、驚くほどの廉価で多くのオリジナル版画を浸透させた所産に他なりません。
昨年度はドレオリジナル版画を36名の入賞者に副賞として贈呈致しましたが、今年度は名作「ドンキホーテ」から50点ほどの贈呈を考えています。1863年度版カッセル社「ドンキホーテ」を、神田神保町で捜せば数十万円は下らない貴重本で、これをばらして(画帳くずし)、別々の版画にする事は、愛書家としては、身を裂くような思いであるのは言うまでもありません。それでも、ドレ版画の副賞を10年続けるとしたら、500点近くのドレオリジナル版画が芳賀の地に眠ることになり、100年後、「何故芳賀の地にはドレ版画が沢山あるのだ」と言われる時代が必ずや来るでしょう。そして真岡市が、久保氏の時代のように、再び近代版画芸術の最先端基地になることも夢ではありません。これこそ久保氏が希求した夢の一つであり、当研究所の夢の一つでもあります。
「今月の久保氏関連新収品」 @「森義利版画作品集」、昭和43年、美術出版社、限定950部、久保論文「森義利の芸術」所収
(渡辺私塾文庫、「26」「久保貞次郎所蔵作品」参照)
⑭久保貞次郎研究所2011年5月月報(第14回)
月報も今回で14回を数え、久保研究所を設立して1年が過ぎました。当面、1,芳賀教育美術展への支援、2,研究所代表として真岡新聞に美術評論、大震災についての文明論等を掲載、3,この月報と、2の真岡新聞掲載文をまとめて、「渡辺淑寛著作集」として出版(2011年8月末に著作集第3巻を出版予定)、この3点を中心に活動して行く予定ですが、他の活動として、幾つか考えています。
上述の2,の一環として、真岡新聞5月27日号に「3部作第3、地鎮歌~大地の女神ガイアに告ぐ~」を掲載致しまた。ホームページ「渡辺私塾台町本校」のトップにも掲載しています。一読して頂ければ幸いです。
⑮久保貞次郎研究所2011年6月月報(第15回)
今月は、報告することが2点あります。第1点。日本経済新聞社2011年6月5日号16ページ「川端康成の美意識」④で、26歳の新進画家であった草間弥生の水彩画を川端が2点購入し、いち早く草間の天分を見抜いて、川端は新人発掘の名人である、という趣旨の記事が掲載されていた。その記事の中で、水彩画15点を出品した草間の個展で、作品を購入したのは川端と久保貞次郎であった、という記述もあった。久保氏とは購入金額のオーダーが3桁、4桁少ないであろうが、私も30年来の絵画コレクターであり、草間氏の初期作品は幻想的で魅力的であるのは知っていたが、久保氏が、川端と同時期に購入していたことは、初めて知った。無名作家の作品を画廊の個展で購入するということは、一番難しい購入形態であり、余程自分の審美眼に自信が無ければ不可能に近い事であって、当研究所としても喜ばしい限りで、あらためて久保氏に喝采をおくりたい。
第2点。大学卒業後、家業を手伝いながら、油絵を描いている娘が、幼稚園児、小学低学年の子ども達を集めて、「キッズアート二コ」なる絵画教室を益子で始めた。第1回は、透明な傘に、自由に絵を描くアートで、10数名が参加し、盛況であったようである。嬉しさの余り、家に持ち帰った傘を抱いて寝た子もいたようで、日用品に芸術性を自ら付加するという事は、芸術の原初形態であり、児童絵画に特別の意味と価値を見いだした久保氏も諸手をあげて賛成してくれるであろう。1回の参加料は500円とのことで、傘代、絵の具代、場所代を考えれば完全に赤字であったと聞いたので、赤字分を、当研究所で支援する事にした。微額ながら、芳賀教育美術展と並んで、もう一つ当研究所で支援できる環境が整い、嬉しい限りである。
繰り返しになるが、私は断言する。当研究所では、遥か数千年後数万年後、全ての人が芸術家である社会を夢想しているが、何の規制も偏見もなくおおらかに自由に表現出来る子ども達こそが、その芸術家群の魁である。
⑯久保貞次郎研究所2011年7月月報(第16回)
今月は3点です。第1点。市内の旧家の方が、暑い中、久保氏に関わる貴重な資料を届けてくださいました。生誕100年記念瑛九展と、平成6年に真岡市に寄贈された「宇佐美コレクション」についての重要な資料でした。出版本等は努力すれば入手できますが、パンフレット類の資料は入手困難であり、有り難く頂戴致しました。心より感謝致します。
第2点。渡辺私塾文庫未所蔵の、久保編集「北川民次版画全集」(名古屋日動画廊)と久保監修「竹田鎮三郎メキシコ画集・インディオの祭り」新版2分冊(ブックグローブ社)が入手出来ました。図録を見ながら、久保氏の論文を読むに連れ、久保氏の両名に対する熱い思いにほだされ、当研究所でも両画伯の研究を始めねば、という思いに駆られました。
第3点。娘主宰の第2回「キッズアート二コ」が開催されました。今回は20数名の参加で、Tシャツに自分なりに自由にペイントする内容で、前回同様盛況だったようです。Tシャツ持参の者は参加料300円で、不所持の子は800円であり、子供のお小遣いで参加できる会という思想なのでしょうが、Tシャツ代、絵の具代、会場代等、その参加料では賄える訳もなく、当研究所で微額ながら支援致しました。私の遥かな目標は、「全ての人が芸術家である社会」ですが、子ども達はその魁であり、あるいは既にそれを体現しているのかも知れません。「キッズアート二コ」が長続きされ、遥か未来に向けての小さな核になればと切に願っています。おそらく久保氏もそうでしょう。
⑰久保貞次郎研究所2011年8月月報(第17回)
7月月報第2点で、「当研究所でも両画伯の研究を始めねば、という思いに駆られました」と書いた数日後、神田神保町の古書店目録で、竹田鎮三郎の版画4点が掲載されていましたので、すぐ注文しました。驚くほどの廉価でしたので、エスタンプ(複製版画)ではと思っていましたが、届いた作品を調べましたところ、4点のうちの2点が、7月月報で紹介しました竹田画集「インディオの祭り」の掲載作品「ラカンドン」と「ハゲタカの踊り」(1971年、限定100部)というタイトルのオリジナル作品でした。更にこの2点は、久保氏が作家達を鼓舞して発行した「久保エディション」「エディション久保」と呼ばれる作品だと判明しました。40年のコレクター人生でも、図録を入手した数日後に偶然その掲載作品を所蔵できるということは稀なことであり、それが久保研究所内で起こったということは、なにか見えない力が働いているとしか思えず、身が引き締まる思いです。他の2点も多分「久保エディション」だと思いますが現在調査中です。
⑱久保貞次郎研究所2011年9月月報(第18回)
9月4日芳賀町にて、日本青年会議所栃木ブロック主宰で、真岡青年会議所会員が中心になり、「がんばっぺ祭り」が開催された。大震災の隠れた被災地と言われる芳賀の地で、人々の萎えた心を奮い起こす、真の意味の「祭り」が執り行われ、大盛況であった事は、芳賀郡民にとって、至上の喜びであり、関係者諸兄に惜しみない賞賛の意を表したい。
祭りの一環として、久保氏が提唱した「創造美育」の「お絵かきワークショップ」が実践され、久保氏高弟、高森俊氏が来訪され指導なされた。私は仕事で出席出来なかったが、児童絵画教室(キッズアートニコ)を不定期に開いている娘が参加した。感涙にむせぶお母様も何人か現れたようで、娘も大いに感銘を受けて帰宅した。発展期から円熟期にさしかかった現代日本で、心のおもむくまま自由に絵を描くことによる、児童精神の解放と成長を目的とする「創造美育」運動は、今後一層の使命を担っているのかも知れない。
9月17日、市内旧家の方が、久保氏から直接頂いた版画を見てほしいと来宅された。7,8月月報で言及した竹田鎮三郎の1974年作代表石版画「姉妹」という素晴らしい作品であった。画集を調べるとカラーで掲載されていて、早速画集の掲載ページをカラーコピーしてお渡しした。久保氏が、親交のあった方々に多くの上質な版画作品をプレゼントしたという話は、やはり事実だったのである。30年も芳賀の地に埋もれていた作品が、画集掲載代表作品だと発見できて、私も静かな喜びに浸ることが出来た。
⑲久保貞次郎研究所2011年10月月報(第19回)
9月26日第25回芳賀教育美術展の最終審査会が開かれ、当研究所代表として、初めて審査に参加した。
子ども達が自由に描く児童画に優劣を付けることは、本来かなりの困難さを孕んでいるが、賞を決定する美術展の性格上、その困難さは甘受せねばならない。更に、上位の賞には、デッサンのしっかりした完成度の高い絵が入り、抽象画、抽象版画はやや不遇をかこつ。審査員が10名を越える場合、この流れは不可避なのかも知れない。従って銘記して頂きたいことは、これらの賞は、一視点からの賞であり、他の審査員であれば、結果も変わる可能性があるということである。実際、私見だが、上位賞に劣らぬ作品を選外の作品のなかに数多く発見して愕然とした。だから、選外だったので、もう絵は描かないなどと、ゆめゆめ思わないでほしい。
再確認したい。自由に楽しく絵を描くことは、精神を躍動させ、成長させることである。
昨年同様、今年度も当研究所で、副賞を用意させて頂いた。昨年度は、ギュスタブ・ドレオリジナル版画は、36点であったが、今年度は上位賞73名の方に贈呈できた。特に今年度のドレ木版画は、代表作「ドンキホーテ」挿入作品であり、数十年後、数百年後、何故芳賀の地に、貴重なドレ版画が沢山あるのか、と人々が口々に語り継ぐかも知れない。そんなことを妄想しながら、私は既に、来年の副賞作品に思いを馳せている。
「今月の久保氏関連収集品」 ①「小野忠重版画集、1977,形象社、普及版、久保貞次郎編
②瑛九フォトデッサン型紙、7点、「ときの忘れもの」、2011年第21回瑛九展ポスター掲載作品No6,7,8,10,13,14,29の7点、及び同展ポスター(限定200部)
⑳久保貞次朗研究所2011年11月月報(第20回)
11月初旬、久保氏の高弟の方から、創美運動の歴史についての長いお手紙を2度に渡って頂いた。この方の貴重なご経験が数多く書かれていて、久保研究にとって重要な資料であり、心より感謝したい。
遥か数千年後、「全ての人が芸術家である社会」の実現に向けて、現在今いる場で、微かな一歩を踏み出すことが、40年来の私の目標であり、使命であり、信じる道であるのだが、絵画を通して児童の精神を解放し発展させるという創美運動は、有力な手段であると以前から理解していた。ただ、人間の人格の全的成長、つまりは人類の「進化」には、美術だけでなく、言語、音、動きを通して喜怒哀楽を表現する、文学、音楽、舞踏など、全ての芸術活動を総動員する必要があるとも思ってきた。名大で、多くの芸術を比較検討する「比較美学」を専攻したのもその理由からである。したがって私の思いと、美術にのみに力点を置く創美運動とは、微妙なずれがあることも以前から自覚していた。正直言えば、まだこの「ずれ」は、私の内部では、まだ克服されていない。高2英語内で、夏休み、約20年継続している私の「言語と芸術」講義も、文学、美術、音楽などを総合的に研究した「比較美学」が根底にある。この「ずれ」を恣意的に埋める事が正しいかどうかも未だ不明だ。創美運動を美術の一分野として受容すべきなのか、あるいは、融合を図るべきなのか.、あるいは創美運動と決別すべきなのか。この「ずれ」の考察については、人間関係を離れて、冷徹になされなければならない。思想の発展とは、そういうものであるのだから。そして一定の結論に達し次第、後日の月報で再度触れるつもりである。再度言う、「存在とは進化」であり、「進化」の道は多岐である。
21、久保貞次郎研究所2011年12月月報(第21回)
12月中旬、久保氏と親交のあった、伊藤高義氏の15号油彩画「サポテナ族 メキシコ」を超廉価で入手出来た。当文庫でも、伊藤氏から久保氏へ の献呈画集本を所蔵しており、以前から伊藤氏の秀作を1点所蔵したいと考えていて、月並みだが、願いがかない嬉しい限りである。それにしてもバブル崩壊以来、絵の値段が異常に急落して、我々大衆にとっては幸いと言うほか無い。だがこの現象が、芸術自体にとって、良いことかどうかは多少の考察を要するだろう。
美術品が無くても人間は生きていけるが、「人間が生きる」とは、動物が生きることとは幾分違って、「文化的に生きる」ことだと思う。だとすれば、額縁の中の美しい小さな世界に心を奪われ、自然を背景に屹立する彫刻作品に心を洗われることも、一つの文化的生き方であるに違いない。そして芸術作品に価値を見いだすことは、人類の進化の証左であるのだろう。その意味で、素敵な芸術作品を、我々庶民が廉価で入手出来ることは、芸術の大衆化という意味でも、素晴らしいことである。もちろん画家、画商さん達にとってはこの20年は、茨の道であったろうが、「芸術の大衆化」が浸透すればするほど、良い作品が正当に評価される時代が、必ずや来ると確信している。だから、画家、画商さんの皆様には、あと20年、濁った水を飲んだとしても、鬼の形相で踏ん張り抜くことを切望する。
性急だが結論を言う。美術品の高騰、暴落は、資本主義社会では、21世紀初頭、不可避であり、悠久の人類史、永遠の人類進化から俯瞰すれば、この現象は芸術自体にとっても良いことである。再度言う。特に暴落は、芸術の大衆化という点で、我々にも、芸術自体にとっても良いことである。
22,久保貞次郎研究所2012年1月月報(第22回)
昨年12月の伊藤油彩画に続いて、新年1月、久保氏が支援し育てた木村利三郎氏の銅版画「City 314」とシルク作品「Sunrise 1」計2点を蒐集できた。木村氏については、久保氏の名著「私の出会った芸術家たち」(昭和53年 形象社)で何度も言及されており、同著の特装限定版300部にも、オリジナル銅販画「Letter from New York]が収録されている。当研究所でも、久保氏が支援した版画家達の作品を少しずつ蒐集し、何時の日か、「久保氏の出会った芸術家たち展」が開催できればと夢想している。
昨年12月月報でも触れたが、現在、絵画作品、特に版画は極めて廉価で、前述の芸術性みなぎる木村作品も、1回の食事代でおつりがくるほどであった。繰り返しになるが、我々小コレクターにとっても、また芸術の大衆化と言う意味で、芸術自体にとっても、今は、良い時代である。
「小コレクター」と言えば、そう、一人一人がオリジナル作品3点を持ち、生活の芸術化を願って、「小コレクター運動」を始めたのは久保氏であった。そう、55年前「全ての人が芸術家である社会」に向けての運動を、北関東芳賀の大地、真岡市で始めたのは久保氏であった。
23,久保貞次郎研究所2012年2月月報(第23回)
2月初旬、久保氏の盟友である北川民次氏の弟子で、名古屋の創美運動に関わり、一時久保氏と行動を共にした安藤幹衛氏(1916~2011)の二科会出品作油彩画3点を入手した。1967年二科会出品作「ひかり」25号(安藤幹衛画集NO39、なお同画集では、この作品を「繁栄」100号としているが編集ミスと推察される。)、1972年二科会出品作「キリスト 犠牲」30号(同画集NO48)、1984年二科会出品作「カーニバル」50号(同画集NO63)の3点である。私見だが、安藤氏の作品には、労働者や動植物の強い生命感を描いた師北川氏の影響を超えて、人間の持つ宗教性が垣間見える。
美術作品の価格については、前々回、前回でも触れたことだが、この安藤氏代表作油彩画3点とも、同じ時期に入手した安藤幹衛画集の定価より廉価で購入出来た。恐ろしいことだが事実である。法外な値段で取引されている一部の売れ筋有名作家を横目に、中央で無名に近い画家の作品は、たとえ秀作であっても、額代、絵の具代にならない価格で流通している。小コレクターとしては喜ばしい限りだが、日本の美術市場の現実を前にして、心底では悲しい思いが支配している。
安藤氏は、1952年創造美育協会設立から3年後の、1955年埼玉創美研究会で講師を務め、1960年第6回創造美育児童美術展(愛知県美術館)と、1963年創美愛知支部主催児童公開審査会の審査員であり、同年大分県での第9回創造美育全国セミナールで、「メキシコ気質」と題した講演を行っている。更には、1964年名古屋市での第10回創美展公開審査と創美の集い及び1967年愛知創美児童画公開審査会で、審査員として久保氏と肩を並べている。あまり周知されていないが、安藤氏と、久保氏及び創美運動との関わりは想像以上に深かったと推察される。
24,久保貞次郎研究所2012年3月月報(第24回)
2月末、昭和22年山前小学校で開かれた児童画公開審査に関してのお問い合わせを、千葉県在住の方から頂いた。この方は、9年前にも、私が数十年研究している、抽象創作版画の巨人「恩地孝四郎」について高度なご質問をされた方で、久保氏が提唱した「小コレクター運動」を、千葉の地で見事に実践なさっている方である。「小コレクター運動」とは、略言すれば、数点のお気に入りのオリジナル芸術作品を蒐集し、自らの生活の中に「芸術」を浸透させること」なのだが、このような個々の些細な生活改革が、遙か数万年後、諍いも、差別も、貨幣も、或いは国家も無い、全ての人が芸術家である社会に繋がる微かな一筋の道では、と私は夢想している。
さて、話を元に戻そう。お問い合わせは、1947年春の、山前小学校での児童画公開審査で審査員として久保氏と同席した彫刻家木下繁氏のデッサン画についてであった。木下繁氏(1908~1988)は、1975年日展理事に、1977年日本芸術院会員にまでなった大彫刻家であるが、1947年時はまだ30歳代で美術界では無名に近かった作家である。久保氏が、その若手彫刻家と交流があり、山前小学校公開審査会の審査を依頼したという事実によって、若手作家達の力を看破し、思想的にも経済的にも支援するという久保氏の熱い思い、強固な決意、思想を私たちは、改めて再認識すべきだろう。
お問い合わせの第1点は、木下氏のデッサン画には、久保氏とおぼしきサインがあり、それが久保氏のサインであるかどうか、という点。第2点は、そのデッサン画が、山前小学校から画かれた作品か、それとも久保氏宅から描かれた作品なのか、という質問であった。第1点は、久保氏の直筆献呈本を所蔵しているので、そのコピーを送り、久保氏のサインに近似していると書き添えた。第2点は、難題であったが、デッサン画のコピーが同封されていて、山々の稜線が明確に描かれていたので、翌日山前小学校付近に出かけ、山々の稜線を確認した。65年も前のことなので、建物風景はすっかり変わっていたが、山々の分水嶺は変わりようがなく、喜びの中で山前小学校からの作品であると確信した。その方はこのデッサン画の仮題を「真岡風景」となさっていたので、「山前小学校からの浅間山風景」という仮題もあり得るとアドバイスさせていただいた。多忙な時期でもあったが、僭越にも「久保貞次郎研究所」を名乗っている以上、当然の義務であり、使命であり、この種の調査は、露ほども厭いはしない。
◎今月の久保氏関連蒐集品①「森義利、人物、合羽刷版画、1977年作」、②「展覧会図録、デモクラート1951~1957,デモクラート展実施委員会、1999年」
25,久保貞次郎研究所2012年4月月報(第25回)
今月は、幸運にも久保氏関連版画を廉価で4点蒐集できた。2点は、ヘンリー・ミラーの有名作品「ブルックリン子」、と「愚者の家」(2点とも1980年、叢文社、「ヘンリー・ミラー絵の世界}に所収)で、ミラーの直筆サインは無く、久保監修制作作品で、久保エディションと呼ばれている。ミラーの直筆サイン入り作品よりかなり廉価だが、刷りの完成度に遜色が無く、当研究所としては、久保エディション作品をむしろ探していた。他の2点は、久保氏の盟友瑛久が関西でデモクラート美術協会を結成したときに参加した磯辺行久のシルク作品で、渡辺私塾文庫、当研究所でも初めての収集作家である。
更に今月は、珍しい展覧会図録が入手できた。1991年カルフォルニアで開催された「ヘンリー・ミラー生誕100年絵画回顧展」カタログで、発行者から久保氏への献呈本である。久保氏帰天が1996年であるので、まだ存命中に米国から贈られたものと推測される。そして見開き頁に、発行者の以下の文がペン書きされていた。「For S.KuboーHenry Miller' s most profoud philosopher and most prolific collecter. Great men enhance and complement one another. Gary Koeppel October 1991」(ヘンリー・ミラーの最高の研究者であり最大の蒐集家である久保氏へ。偉大な二人は、お互いを高め合いお互いを完璧にする。1991年10月 ギャリー・クーペル。)(渡辺拙訳) ヘンリー・ミラー絵画作品の日本への紹介者であり研究者である久保氏に対して、大文豪ヘンリー・ミラーと対等の思想家として賛辞をしたためている。多少の世辞はあるにしても、米国における久保氏の高評価が伺い知れる。
近代機械文明によって歪められた人間の解放は、性の解放から、という信念からの、ミラーの大胆な性描写文学作品群が世に受け入れられるに30年近くを要したが、ミラーの絵画が世界美術史上で確かな地位を得るにはもっと時間が必要であろう。多くの美術批評家が、ミラーの絵を一顧だにしないのは、その稚拙さ故なのだが、私には、稚拙であればあるほど、自由な精神が一層輝きを増しているように思えてならない。ミラーは、文章が書けなくなると、阿修羅のごとく絵を描き続けたという。まさに、言葉にならない心の深奥を、形と色で、嘔吐するごとく表現したのであろう。彼には、絵の訓練など全く必要でなく、自由な精神の発露には逆に足かせにさえなったに違いない。だからミラーの絵は稚拙に見えるのである。伝統に縛られ硬直した凡庸な批評家の目には、幼児のような精神の自由な発露が届かないと言ったら言い過ぎであろうか。
遙か数千年後、戦争も差別も国家も貨幣も無い、全ての人が芸術家である社会の中で、我々は、即興の詩を謳い、哲学し、天まで届く歌を謳い、赤銅色の肉体でバレリーナのように宙を舞い、ミラーのように純真な絵を止めどもなく描いていると、私は強く強く夢想する。
26,久保貞次郎研究所2012年5月月報(第26回)
今月は、大浦信行氏の大判シルクスクリーン版画7点(1990,1991年作)が廉価で入手出来た。大浦氏については、久保氏名著「わたしの出会った芸術家たち」(1978年、形象社)236頁で、「かれの最近の大判シルクには、日本的センチメンタリズムの影が消え去り、無表情な西洋文明の拒絶性が浮かび上がっていて無気味である」と書かれている。私見だが、写真に似た、古風な日本女性の裸婦を題材にして、「西洋文明の拒絶性」から、「日本の土着性」に進み、近年の作からは、中世西洋宗教画の香りが漂っている。その東洋と西洋を結ぶ普遍性の中に、私は高い芸術性を感じるのだが、彼の作品が正当に評価されるにはあと数十年はかかるかも知れない。久保氏が感じた「無気味」さの延長のなかで、彼は現在映画監督として、非常に興味深い映画芸術を次々と発表しているが、ここでは触れない。
久保氏が深く関わった「芳賀教育美術展」の入賞者の副賞は、昨年一昨年と、当研究所からの贈呈という形にしていただいたが、今年度も4月から準備に入り、1800年代作のギュスタブ・ドレ木版画73点は、根性で用意できた。3年間で182点のオリジナルドレ版画が、芳賀の大地に宝石のように散りばめられる事になる。50年以上も前、池田満寿夫、瑛九、北川民次、アイオー、泉茂などの版画作品を芳賀の地に散りばめた久保氏も、天で優しい笑みを浮かべているに違いない。また今年度は額入り版画13点を、知事賞、久保賞受賞者13名に贈呈しようと妄想し、現在苦闘中である。実現できるかどうかは、私の頑張りと運次第だろう。
27,久保貞次郎研究所2012年6月月報(第27回)
5月月報で言及した、今年度「芳賀教育美術展」知事賞久保賞受賞者の副賞13点の事であるが、何とか目途がついた。知事賞には、芸大出身若手日本画家の30号大作を、久保賞12名には人間国宝芹沢桂介の型絵染7点と田中正秋の額入りシルク版画5点が用意出来た。ギュスタブ・ドレ木版画73点も含めて、やや豪華過ぎるきらいもあり、美術展実行委員会の許可を得なければならないだろうが、美術展とは本来「芸術のお祭り」なのだから、華やかな事に超したことは無い。「芳賀教育美術展」は副賞が凄い、と評判が立ち、話題が話題をよんで、出品数も更に増え、年々盛大になり、芳賀の大地よ、久保氏が夢見たような芸術の都になれ、と願うのは強欲すぎるだろうか。
4月号月報で取り上げたヘンリー・ミラーのリトグラフ作品「愚者の家」で、ミラーのサイン入りオリジナル作品を数日前入手した。以前から所蔵していた作品は、久保エディションと呼ばれる限定5部の「後刷り作品」だが、ミラーのサイン入り作品は限定200部である。2点を精査してみると、1973の年号が、サイン入り作品にはあり、久保エディションには無い。また久保エディションはやや大きい版画紙に刷られており、刷りむらも少し見受けられたが、それがかえって趣を増している。それでも完成度、芸術性の点から見れば同一版画作品であると言ってよいであろう。優れた版画作品2点を比較出来るこの境遇を、天に感謝したい。
久保氏監修の「ヘンリー・ミラー絵の世界」(1980,叢文社)によると、サイン入り作品は、「刷下 吉原英雄」、「刷り オギノ栄一郎」とあるが、ミラーに200部サインしてもらった後で、それほど間をおかずに、久保氏が、同じスタッフで、5部制作したのではと推察される。大文豪ヘンリ・ミラーは、世界文学史上既に確固たる地位を得ているが、数十年、数百年後世界美術史上においても、必ずや名を刻む芸術家になるであろうから、21世紀初頭、サイン入り作品と久保エディション作品について言及しておくのも少しは意味のある事かも知れない。+
28,久保貞次郎研究所2012年7月月報(第28回)
灼熱の7月、久保研究所として、久保関連版画7点と、リトグラフ入り版画集1点が蒐集出来た。版画7点のうち5点は、2011年8月、9月月報で言及した、竹田鎭三郎作品であり、更にそのうちの2点は、1986年名古屋日動画廊で開催された竹田鎭三郎全版画展出品作品、「この地上に生まれるもの」、「5月の女」の傑作大判リトグラフである。
7点のうち他の2点は、2012年5月月報で「近年の作からは、中世西洋画の香りが漂っている」と紹介した、大浦信行の宗教画風シルクスクリーン2点であった。
また、版画集は、2012年2月月報で触れた、安藤幹衛の版画集「メキシコの偶壺」(限定50部、リトグラフ10葉入り」である。もちろん3氏とも、既述したように、久保氏が支援鼓舞した作家であった事は言うまでもない。
ここ2,3年で版画を中心に久保氏関連作品が数十点入手出来たので、40年かけて蒐集してきた、渡辺私塾文庫内の久保氏関連所蔵品と合わせて、久保氏関連作家展開催を模索し始めたが、震災による破損、散逸が意外に多く、美術展開催の実現は困難であろうというのが実感である。それでも実現に向けて密かに努力を続けようという強い思いは散逸していない。
この夢が叶わない場合には、これらの作品を、数年後「芳賀教育美術展」の副賞として多くの子供達に受け取っていただき、久保氏が進めた「小コレクター運動」の思想を継げればと考えている。そして「小コレクター運動」とは、全ての者が、オリジナル芸術作品を所蔵し、生活の中に芸術を浸透させ、いつの日か、いや遙か数千年後、、全ての人が芸術家である社会を成就するための第一歩の運動なのである。その社会は、当然の事として、戦争、暴力、差別、貨幣、過酷な労働、学校、国家の無い社会であろう。久保氏の思想の根底には、「国家のない社会」、「世界国家」が有った事は、想像に難くない。かつて世界共通言語たらんとし、無政府主義破壊主義と曲解され弾圧されたエスペラント語運動において、久保氏が他界するまで日本エスペラント協会会長の職にあったと言う事実は、その思想の根源から由来するに違いない。
久保氏の思想は、我々の想像を超えて、崇高で深遠である。
29,久保貞次郎研究所2012年8月月報(第29回)
5月号、6月号で言及した、第26回「芳賀教育美術展」の副賞全てを、8月30日実行委員の方に無事お渡し出来た。当研究所で副賞を無償で用意させていただいて3年目であるが、渡辺私塾文庫で数十年前から所蔵している作品、またこの美術展の為に1年がかりで蒐集した作品など86点と、私の拙本124冊、ノート480冊、今年度から新設の「久保研究所賞」用文具セット3点、をお渡しした。86点の内訳は、知事賞用40号日本画1点、久保賞用版画12点、造形教育研究会長賞以上の上位賞用、ギュスタブ・ドレ木版画73点であり、特にドレ木版画は、1863年出版の稀覯本「ドンキホーテ」の挿絵作品で、まさにオリジナル木版画である。ドレ版画は3年目の今年で、計182点芳賀の少年少女に受け取っていただく事になるが、来年分の73点は執念で確保できた。2年後の73点は困難を極めそうだが、いずれにしても、数十年後、数百年後、ドレ作品が、何故芳賀の大地に、宝石のように散りばめられているのかと、口々に語り継がれる日が来るかも知れない。現在でも、池田満寿夫、アイオー、瑛久、北川民次、泉茂等のオリジナル版画が、芳賀の地で散見されるのは、久保氏が「小コレクター運動」の中で、多くの人に廉価で頒布したからに他ならない。当研究所の、やや横柄で無謀に見える、副賞提供というこの振る舞いを、久保氏だけは、天国で喜んでくれていると、私は独り合点している。
「芳賀教育美術展」は、前身の美術展創設時から久保氏も運営に関わり、それ故、久保氏が提唱した創造美育運動の理念が継承され、その象徴が「久保賞」(12名)である。因みに、娘が20年前栄えある「久保賞」を頂き、何かの縁なのだろうか、現在、油彩画を描いている。
だが、「芳賀教育美術展」の最大の特徴は7000点を優に超える出品数であろう。私事だが、10数年前真岡新聞社様の力をお借りして、「文芸賞」を創設したことがあった。3年目は僅か30数点の応募しかなく、泣く泣く休止せざろうえなかった。それに比べれば7000点という出品数は夢のような数字である。だからこそ当研究所で提供する副賞には、やや豪華すぎるという非難も無くはないが、7000点という数の重さと、純真な7000人の児童芸術家達の思いを考慮すれば、まだまだ貧弱である。
30,久保貞次郎研究所2012年9月月報(第30回)
9月初旬、久保氏他界時、跡見学園女子短大学長であった方から、「久保貞次郎とヘンリー・ミラー研究会ー研究会の設立に至るまで」という論文掲載の研究雑誌が、久保研究所宛に寄贈された。ヘンリー・ミラー研究会設立過程については、「久保貞次郎 美術の世界8巻 ヘンリーミラー」にもあまり述べられていないので、興味深く拝読した。この場をお借りして深く感謝したい。今後の久保研究の発展が、その厚情に報いる道であろうと思う。それにしても、都会の一流の学者が、地方の一研究所に注目して、研究誌まで郵送して下さるとは、身の引き締まる思いである。
9月末、今年2月月報で言及した、安藤幹衛氏の二科会出品作で100号の大作4点が入手できた。、2月月報でも触れたが、安藤氏は、久保氏の盟友北川民次の弟子で、名古屋の創美運動に参加し、一時久保氏と行動を共にした洋画家である。今回の4点で、二科会出品作油彩画7点を、当研究所で所蔵することになり、安藤作品の貴重なコレクションになったのかも知れない。
4点の内訳は、「不安」(1961年、画集NO33)、「落馬」(1962年、画集NO34)、「明暗Ⅰ」(1968年、画集NO43)、「謎の失踪」(1978年、画集NO54)で、将来真岡市立久保記念美術館が建立した暁には、心弾ませて寄贈させていただければと願っている。
先月8月月報で、芳賀教育美術展副賞用のギュスタブ・ドレ木版画について、「来年分の73点は執念で確保できた。2年後の73点は困難を極めそうだが」と記したが、幸運にも2年後と3年後の計146点が入手できた。150年ほど前の稀覯本(ドン・キホーテ、ロンドン、カッセル社)であるので、入手困難と言われているが、芳賀の大地の少年少女の手に、宝石のように散りばめたいという崇高な動機のためか、何か大きな力が働いているとしか思えてならない。天に感謝。
31,久保貞次郎研究所2012年10月月報(第31回)
長年、久保氏編集「オノサト・トシノブ文集 実在への飛翔」(限定150部、リトグラフ3点入り)を探していたが、願い叶わず、リト欠の限定本で妥協し、10月末入手した。オノサト氏は、1936年24歳で久保氏と知り合い、以後長年に渡って久保氏と交流の深かった抽象画家である。抽象画の認知度は日本では極めて低いので、オノサト氏も例に漏れず、欧米各国の方が評価は高い。彼の抽象絵画は、円と3原色で、宇宙の秘密に肉迫しようとする過酷な試みであるが、抽象芸術については、私の、10年前の拙文があるので、ここで引用したい。
「幼児の純真な絵の多くは、抽象画であると言われています。物を写す具象作業も、人間の本能的活動でしょうが、内面のやむにやまれぬ思いを非具象の「形」と「色」で表現することも、やはり人間本来の本能的活動の一つでしょう。私たち大人は、子供の絵を見て、「何を書いているの」と思わず尋ねてしまいますが、精神の強い思いを、ただ「形」と「色」で表現したにすぎないのです。この延長上にある、強くて太い芸術表現の道が、抽象芸術であると確信します。」
更に、今、付言すれば、路傍に追いやられた抽象芸術は、その鬱積した巨大なエネルギーゆえ、「実用性」という衣を羽織り、デザイン、文様、装飾、衣装、型染め芸術等のなかで、見事に開花しています。
8年前の7月、東京のオークションで、久保氏旧蔵品ということもあり、加藤昭男の、1966年作テラコッタ(素焼き彫刻)作品6点を入手した。加藤氏については、「近代日本美術事典」(1989,講談社)に掲載されていて既知であったが、数日前詳細な経歴を知ることができた。加藤氏は、東京芸大彫刻専攻科を1955年に終了し、1974年に第5回中原悌二郎賞優秀賞を受賞して名声をはせるが、1966年時は、まだ無名に近い状態であったろうと推察される。久保氏と深い交流のあった彫刻家木村繁については、今年3月月報で言及したが、木村氏も加藤氏も武蔵野美大名誉教授であったので、久保氏と加藤氏のふれ合いの可能性が予感される。少しずつ調べてみたいと思う。
いずれにしても、久保氏は、多くの版画家のみならず、才有る若手彫刻家、陶芸家の経済的思想的支援者であったことは確かであり、その意味で日本美術史上希有な存在である。
32,久保貞次郎研究所2012年11月月報(第32回)
今年9月月報で言及させていただいた、元跡見学園女子短大学長からのヘンリー・ミラー関連本の御寄贈に続いて、11月初旬、創造美育協会の発起人の一人で、10月に帰天なされた元東京学芸大名誉教授のご遺族から、遺稿集と久保氏関連本を頂いた。久保関連御寄贈本は、1952年に創造美育協会が設立された3年後、東京支部から発行された「子供の絵はどう指導したらよいか~チゼック児童美術教育の問答~」(久保訳)という貴重本で、1949年の謄写版刷り旧版と、この新版の存在の噂は耳にしていたが、手に取るのは初めてであり、ご遺族の方々に心より感謝したい。
創造美育協会は久保氏が中心の組織には違いないが、この学芸大教授のように、独自の美術教育理論を携え、創美運動に参加したことを考慮すると、創美思想は、多くの学者や芸術家の結晶体であったと推察される。
昨年の7月月報で言及した「竹田愼三郎画集~インディオの祭り~」の版画3点入り限定100部特装版を、長年捜していたが、11月末、偶然廉価で入手できた。リトグラフ2点と木版1点(木版画の刷りは、真岡市の木版画家浅香公紀氏)のオリジナル作品入りで、所蔵は無理だろうと、とうに諦めていた。一ヶ月早いクリスマスプレゼントなのだろうか、それとも天のなせる御技なのだろうか。
10月末日、ある機会に恵まれて、久保氏のご遺族の方と初めてお会いできた。15年前、久保氏追悼文を、無断で当新聞に掲載し、3年前、無断で久保研究所を設立し、15年間心苦しく、後ろめたい気持ちを持っていたので、「勝手な事ばかりしてきて申し訳ありませんでした」と謝罪したところ、「いえいえ、真岡新聞いつも読んでおりますよ。」と言っていただき、胸のつかえがおりて、ただ頭(こうべ)を垂れた。それにしても、気品漂うご遺族の方の所作、立ち振る舞いに接し、久保氏の思想の崇高さを、違った角度から再認識できた思いである。天よ、あの日は、15年間の贖罪の日であったと思って良いか。そしてこれも汝の御技か。
33,久保貞次郎研究所2012年12月月報(第33回)
年末の2日、休みが取れたので、震災以降入室不能になっていた、文庫館の一室のドアをこじ開けて、未整理の久保氏関連本19冊を何とか救出した。詳細は、①「子どもの絵と教育」、北川民次、昭和28年、創元社、②「瑛九」、2004、渋谷区松波美術館、③「版画の歴史とコレクション」、久保監修、1976,三彩社、④「北川民次とその仲間たち展」、1983,名古屋日動画廊、⑤「北川民次」、1966,日動画廊、久保論文「憑かれた人ー北川民次」所収、⑥「北川民次版画総目録」、1973,現代美術資料センター、⑦「北川民次の壁画」、1959,創造美育協会、久保と北川の対談「壁画を語る」所収、⑧「追悼北川民次先生」、1990,久保貞次郎発行、久保「弔辞」所収、⑨「北川民次版画総目録」、久保編、1956,久保貞次郎発行、⑩「うさぎのみみはなぜながい」、北川絵と文、1962,福音館書店、⑪「日本現代画家選19」、北川民次、1956,美術出版社、久保論文「北川民次論」所収、⑫「アート・トップ65号」、1981,巻頭特集「北川民次」、久保論文「北川民次の芸術」、⑬「瑛九 エロティカ 1,2」、林グラフィックス、1997,限定50部、⑭「瑛九石版画総目録」、昭和49年、瑛九の会、久保論文「瑛九の石版画」所収、⑮「現代フランス版画展」、1958,伊勢丹、久保論文「現代の版画」所収、⑯「瑛九展」、1979,瑛九展開催委員会、久保論文「瑛九のひとと芸術」所収、⑰「北川民次展」、1996,愛知県美術館、⑱「エル・ソル美術展」、1978,名古屋セントラルパークギャラリー、⑲「北川民次油彩画展」、1987,名古屋日動画廊。
19冊とも、当研究所設立前に入手し、精読していなかった本であるので、冬休み、時間を見つけて再読しようと思う。前述の久保氏8篇の小論は、名著「久保貞次郎美術の世界」第1巻、第2巻(昭和59年、60年、叢文社)にほとんど掲載されているが、図録を観ながら、初出の原本で読了するのも、趣がある。
働く人々や野の草木の力強い生命感を描いた、というありきたりの「北川民次論」や、シュールな抽象画やフォトデッサンによって、宇宙の深奥に肉迫した、という難解な「瑛九論」を超えて、彼らは、何故、美術という表現方法を選択したのか、結局、彼らが、顕現したものは何であったのかを、時間をかけて考えてみたいと思う。
34,久保貞次郎研究所2013年1月月報(第34回)
年末に続いて、お正月休みも、多忙の中、散乱した文庫館の整理に時間を割いた。自宅の書斎、図書室は全て復旧済みで、文庫館の他の部屋もほぼ整理でき、最後の部屋の片付けであった。その作業中、年末時と同様、久保関連本5冊を発見した。詳細は、①古川龍生木版全集「田園抒情」、1980,叢文社、久保貞次郎編、久保氏小論「この孤高の版画家」、「あとがき」所収、②古川龍生スケッチ帖、肉筆画7図、昭和7年、③「版画芸術10号」、1973,オノサト・トシノブ特集、④「版画芸術112号」、2001,瑛九特集、⑤「子どもの絵」、島崎清海、阿部明子共編、1991,文化書房博文社、久保氏推薦文掲載。(島崎氏は久保氏の高弟で、芳賀教育美術展の審査委員)
また1月初旬、新たに2点の久保関連本、作品を入手した。1点は「池田満寿夫資料2分冊」、(1974,薔薇科社、限定300部、久保氏小論2点所収)で、池田作品は、個人的に好きでなく、ほとんど蒐集していないが、久保氏との関わりは深く、私見だが、久保氏の厚い支援がなかったら、彼は世に出なかったのでは、と思っている。もう1点は、やはり久保氏が応援した森義利の10号水彩画「浅草寺」で、1970年代の日本美術家連盟展出品作であろうと推察される。
絵の価格については、以前何度も言及したが、この水彩画には額裏に値札が添付されていて、約40年前なのに30万円と記されていた。だが、もちろん、私は、あるオークションで、いつものように、千円単位の金額で購入した。21世紀初頭になっても、日本の美術市場は、投機的バブルと、その「反動」の繰り返しで、未だ美術愛好家が適正な価格で作品を購入し、それ故、芸術家が適正な収入を得て、伸び伸びと才能を具現化出来る、という構造がまだ構築されていないのかも知れない。そうは言っても、この「大反動」の時代は、我々蒐集家にとっては至福の時である。投機的バブルの嵐が来る前、この至福の時代に、かつての久保氏の万分の一の資力ではあっても、私は、少しずつ地を這うように、久保関連作品を芳賀の地にそっと引き寄せ、真岡の文化財にしてしまおうと固く心に決めている。
35,久保貞次郎研究所2013年2月月報(第35回)
2月の久保関連蒐集本は次の4点であった。①「池田満寿夫 May Imagination Map」(昭和49年、講談社)、②「竹田鎮三郎版画総目録」(1975,同後援会)、③「合羽摺 森義利」(久保貞次郎、1977,叢文社)、④「画家ヘンリー・ミラー」(1983,福武書店) 1年で1番忙しい時期ではあったが、暇を見つけて精読できた。詳しい内容については今回は割愛し、久保研究所として、久保氏旧邸跡地の利用について少し述べさせていただきたい。
昨年9月、久保旧邸跡地活用のための「真岡市観光拠点施設等整備・運営検討委員会」に招聘され、14名の委員からなる委員会に毎回出席した。既に下野新聞紙上で公表されたので、差し障りのない範囲で、お話しすることは許されるであろう。市当局は、最初、「飲食施設」、「物産館」、「観光案内施設」、「市民ギャラリー」の4機能を持つ「観光文化拠点」を企図していた。私は、第1回の会議から、「市民ギャラリー」は、「久保記念美術館」であるべきだと主張した。以前市立美術館構想があり、準備委員会までできたが、頓挫したこと、8万都市真岡に公立美術館がないこと、寄付作品があり、展示作品を購入する必要が無いこと、久保旧邸購入時に小美術館を作らねば、半永久的に美術館は作れないだろうということ、それ故、今作らねば、真岡市政史上、末代の恥になるだろうということを、傲慢さを顧みず、孤立し失笑の中、毎回主張した。だが驚いたことに、他の委員が私の主張を納得する前に、市当局が理解を示した。最終的には、長年真岡市に住む尊敬すべき年輩の委員の方々の応援もあり、「久保記念ギャラリー」(仮称)や、物産館の2階に「久保資料室」まで出来る予定となった。まだ最終決定ではないにしても、市当局の高い見識と柔軟性に、賞賛の意を表したい。
「寄付作品があり、展示作品購入の必要なし」についての詳しい説明は、後日に譲るが、真岡市には、瑛九作品を柱とする283点の「宇佐美コレクション」、100点近い「オノサトトシノブ」作品、、多数の児童画、久保氏関連油彩画・版画(宇佐美コレクション以外は寄贈予定)が有り、地方の小美術館としては、世界に胸を張れる作品群であると、私も胸を張って断言する。最後になったが、私が主張したことがもう1点あった。大人も子供も自由に入れて、生活の一部となる入場無料の美術館を作ってほしいと。
36,久保貞次郎研究所2013年3月月報(第36回)
3月の久保関連蒐集品は、竹田愼三郎のリトグラフ1点のみであった。2月、3月は多忙の時期なので、4月からは蒐集と研究のペースを少し上げようと考えている。
知人から、「久保研究所って何をやってるの?」と、時々聞かれるのだが、「久保氏の研究だよ。研究には、久保氏関連本、作品が必要なので、少しずつ集めてるんだ。」と答えることにしている。そして「月報」をホームページに載せて、次に真岡新聞紙上に掲載してもらい、更に、拙書「渡辺淑寛著作集」に所収し、3段階で公表していると言うと、さすがに皆驚く。
久保氏の業績に関しては、私個人は10種に分類している。①美術評論家、②コレクター、③ヘンリー・ミラー絵画の紹介者、④多くの芸術家の経済的思想的支援者、⑤現代版画のプロヂューサー、⑥創造美育教育運動の創設者、⑦小コレクター運動の提唱者、⑧エスペラント運動の指導者、⑨跡見学園短大学長としての教育者、⑩町田市立国際版画美術館館長としての芸術啓蒙者、の10点。現在、主な研究の対象は、⑦、⑧で、久保氏の言う⑦の小コレクター運動とは、多くの人が、3点のオリジナル作品持ち、「生活の中に芸術を浸透させる」事なのだが、私は、「数千年後、全ての人が芸術家である社会の実現」と翻訳している。詳細については、数年後著作集で公にするつもりである。
⑧については周知不足だが、久保氏は、1996年帰天するまで、日本エスペラント学会会長であった。数万年後国家も消滅し、世界が一つの共同体となって、世界共通言語としてエスペラント語を全世界人が使うであろう、という思想なのだが、英語が世界共通語になる可能性もある。何れにしても、孤高のエスペランティストであった久保氏の思想、精神の核について黙考し、国家も戦いも差別も貧困も貨幣もない、遙か数万年後の輝く人類の未来に思いを馳せると、若者のように胸が熱くなる。だが熱い胸だけでは時代は動かない。我々一人一人が、今いるこの試練の場で、ほんの僅かでも進化することが、21世紀初頭を生きる我々一人一人に与えられた不可避の使命に違いないのだ。
37,久保貞次郎研究所2013年4月月報(第37回)
4月の久保関連蒐集品は、久保旧蔵本1点で、「Vinccent Van Goghs LeidensWeg」(ビンセント・バン・ゴッホの苦難の道)の1930年代独語洋書であった。神田神保町の古い古書店シールが貼ってあるので、久保氏が、以前買い求めた稀覯本なのだろうが、北川民次木版の久保氏書票(エクスリブリス)が添付されていて、貴重な久保旧蔵本である。当研究所でも、北川木版書票添付久保旧蔵本を何点か所蔵しているが、古書業界でも、久保旧蔵本は高額になってきて、最近、私としては、購入をためらう場合が多くなっている。
4月初旬、当研究所で大きな動きがあった。隣接する住宅が空家になったので、久保研究所として使用することになり、当研究所所蔵本、作品を搬入中である。震災で被災した渡辺私塾文庫館の復旧もまだ完了していない段階での引っ越しは煩雑であるが、家業の仕事始めで多忙の中、情熱に満ち、寸暇を惜しんで、台車で本を運んでいる。
4月24日、真岡青年会議所から、久保氏に関する15分のスピーチの依頼があり、仕事も休みだったので、30分ほどで資料を作成し、久保氏が提唱した「創造美育運動」の本質について、私の理解の範囲で話を聞いていただいた。
「林檎の絵を描いて」と言われて、丸い輪郭と蔕(へた)を描き赤く染めて、「観念的」に林檎を描くのでなく、林檎を手に取り、香りを知り、頬ずりし、囓ってみて、本当に自分が感じたことを絵にするのが、創造美育の児童画であろうと話した。更に、食べられて泣いている林檎と、笑っている人の絵を描いていた少年が、やがて、食べられる林檎の悲しみを知り、リンゴも人も泣いている絵を描き、最後には、生命の合体、融合に思いを馳せ、林檎も人も笑っている絵を描いたメキシコの少年の話をした。そして、埴谷雄高の「死霊第7章、最後の審判」の中で、ガラリヤ湖の魚を食したため、チーナカ豆を食したため弾劾されたイエスや釈迦に象徴される、他の生命を奪って生きねばならぬ人間の宿業が、「生命の融合合体」というメキシコの少年の絵で、既に止揚、克服されているのでは、と話した。更には、児童は、大人より生まれて間もない故、生命の秘密、宇宙の秘密を、心の深層で記憶しているのでは、ということを、米国の小説家ウイリアム・サローヤンの「ヒューマンコメディー」に触れて、聞いていただいた。短時間でやや難解であったため、理解していただいたかどうかは定かではないが、有意義な15分であった。
スピーチの御依頼があれば、時間の許す範囲で、お話に行きますので、ご連絡いただければ幸いです。
38,久保貞次郎研究所2013年5月月報(第38回)
5月の久保関連蒐集品は、3月同様、竹田愼三郎リトグラフ1点のみで、やや低調であったが、一つ嬉しいことがあって、ここ数日晴れやかな気分でいる。震災以降行方知れずになっていた、浅香公紀木版画100点と、木版画本「旬」が、久保研究所引っ越しの最中、2年ぶりに発見出来たからである。ご子息が、私の教え子であった関係で、浅香氏から直接頂いた作品がほとんどであるが、震災前に、大きな箱にまとめて保管しておいたその箱がどうしても見つからなかった。文庫館で、何かの下敷きになってしまったのでは、と思いこんでいたが、書斎の隣の部屋に秘蔵されていた。震災は家屋を破壊しただけでなく、私の記憶も損壊したのだろうか。
浅香氏は、平成21年に他界された優れた木版画家で、22年10月市内荒町「金鈴荘」で浅香公紀木版画展が開かれ、私も、本紙22年10月22日号で、展評を書かせて頂いた。
久保氏は、「美術の世界3,私の出会った芸術家たち」(昭和59年、叢文社)246頁で、浅香氏に言及し、「美術の世界5,日本の版画作家たち」(昭和62年)260頁で、宇都宮市での「浅香木版画展」の展評を掲載し「野の花と語りあうひと」という副題で、「前よりいっそう色彩が輝きを増している」と賞賛している。浅香氏は、久保氏が認めた画家で、唯一世に出なかった作家であると揶揄する向きもあるが、浅香氏は敢えて自ら世に出ようとしなかっただけであり、更には、存命中に「世に出る」事と、芸術性の高さが無関係であることは、ゴッホを想起すれば、自明であろう。
思い起こせば、浅香氏は 私が二つめの大学で、美学美術史を専攻したことは知らなかったはずであるが、30数年前、「趣味で作っているものです。」と言って、木版画カレンダーを手渡してくれた。生命観あふれる花々の美しさ、芸術性の高さに絶句したことを昨日のことのように覚えている。
久保氏の思想と幾分重なり合えば幸いだが、私は40年に渡って、遙か数千年後「全ての人が芸術家である社会」を夢想してきた。その社会では、戦争も暴力も差別も貨幣も国家も無く、全ての人が詩人で、美術家で、哲学者で、数学者で、舞踏家で、音楽家で、褐色の肉体を所有するアスリートであるだろう。そして有り余る程の衣食住が無償で提供されるそのような社会では、金銭を得る職業は、もはや消滅するに違いない。だとすれば、人間の全ての活動は「趣味」と言って良いのではないのだろうか。
国家消滅を密かに夢み、帰天するまでエスペラント学会会長であった久保氏よ、これ程芸術性に満ちた創作活動を「趣味」と言い続けた浅香氏よ、もしかしたらあなた達も、遙か数千年後「全ての人が芸術家である社会」、「本当の人類の歴史が始まる社会」つまりは「人類の本史」を、心底夢想した、私たちの先達ではなかったか。
39,久保貞次郎研究所2013年6月月報(第39回)
6月の久保関連蒐集品は、先月同様、1点のみで、「画集 泉茂」(1978,今橋画廊、限定600部)であり、久保氏の小論「泉茂の人と芸術」が巻頭を飾っている。泉茂(1922~1995)は、久保氏の盟友瑛九が主宰した関西デモクラートの主要メンバーで、瑛九を通じて久保氏と長年に渡って親交をを持ち、1970年には大阪芸大教授に就任し、久保氏より1年早く他界した画家である。泉茂は、オノサトトシノブ、竹田愼三郎、浅香公紀、安藤幹衛、大浦信行等と共に、今後一層評価される作家になるであろう。
5月末 震災で行方不明になっていた浅香木版100点が発見できたと、5月月報でお知らせしたが、6月末には、久保研究所引っ越しの最中、「久保貞次郎 美術の世界2 瑛九と仲間たち 特装版」(1985、限定100部)を執念で発見した。この特装版は、本の形でなく、30センチx40センチの帖で、中に6点のオリジナル作品が挟んであるだけの薄い稀覯本で、この薄さが1年以上見つからなかった理由なのかも知れない。
作品の内訳は、①瑛九「手紙を持つ女」(フォト・デッサン)、②泉茂「皺の軌跡」(銅版)、③アイオー「手・右」(セリグラフ)、④アイオー「手・左」(セリグラフ)、⑤細江英公「男と女No24」(オリジナル・プリント)、⑥吉原英雄「赤い花」(リトグラフ)で、バブル時、6人兄弟生き別れにされ、小綺麗に額装された各作品が、高額で取引されるのを何度も目撃した。もちろん久保氏は、6点全部でワンセットの作品として制作したのだろうから、「画帳くずし」と命名されるこの種のばら売り行為は、極力避けるべきである。
利益至上主義の資本主義美術市場では、芸術作品が生き延びる上で、多くの受難、苦渋が不可避であるようだが、社会主義美術市場なら良いかと言うとそうも行かない。芸術が国家・党の宣伝(プロパガンダ)として利用された、芸術にとって長い暗黒の歴史があった。それは、芸術が戦争鼓舞に利用された、より醜悪な形態と本質的に同義である。
かつて岡本太郎が、「芸術は爆発だ」と絶叫したとき、彼の真意を理解する者は少なかったが、芸術はあらゆる国家・組織から毅然と独立、自立した、個の精神の激しい発露だ、その発露こそが人類史を良き方向に導くエネルギーだ、と理解する時、我々は、彼の絶叫の中で、「芸術の自立性」という不変の真理と初めて邂逅出来るのである。
今月報では、「画帳くずし」から「芸術の自立と社会」について少し言及したが、「芸術の自立と国家」も私の研究対象なので、何かの機会に詳しく論じたい。
40、久保貞次郎研究所2013年7月月報(第40回)
7月の久保関連蒐集品は、安藤幹衛リトグラフ1点と、オノサトトシノブのシルクスクリーン1点であった。今まで何度も述べたことであるが、一部の売れ筋高名作品が高額で取引されている裏で、優れたオリジナル作品を、画集を買うより廉価で蒐集出来ることは、妙な気分だが、有り難いことでもある。歪んだ日本資本主義美術市場についての論評は別の機会にして、今月報は、月報40回記念として、滝川太郎贋作事件に触れたいと思う。
久保氏は、1938年から約10年間で計47点の滝川製贋作を購入したと言われ、一流の美術評論家が贋作を掴まされるとは何事か、と非難する者もいた。地元の久保研究家としては辛い部分でもあるが、ここ数年間、私は、何の偏見も持たず純白な心で、滝川事件を、次の2点を中心に検証してみた。
第1点は、美術評論家と美術鑑定家は決定的に違うという事。第2点は、滝川太郎という贋作者は、妙な表現だが、極めて優れた、希代の贋作者であるという事。この2点について簡単に述べたい。
テレビの鑑定番組などで、鑑定家が、瞬時に真贋を言い当てる場面がよく放映されるが、実際には、放送前に何人かの専門家が入念に調査した上での放映であることは、関係者の間では周知の事実である。それでも時には誤判定があるらしい。一番信頼できる鑑定法は、放射性炭素年代測定法などの科学鑑定であるが、真作と同時代の絵の具、カンバスを用いて贋作が作られれば、もうお手上げである。それに時間と費用もかかり、大美術館が高額の絵を購入する場合を除いては、非現実的である。75年前、「良質な」滝川作品を、久保氏が贋作と見抜けなかったとしても、何ら不思議ではない。
滝川太郎は、他界する2年前、1969年のインタビューで、「俺の贋作には命がこもっている。原作以上の迫真力がある」、「黒田、安井、梅原にしても本場のコピーじゃないか。本場の本格派の精神まで写す俺のコピーの方が、遙かに価値が有る」と言い放った。3人の作品より滝川贋作が優れているかどうかは別にしても、滝川贋作の「良質」さを象徴する事件が、1956年神奈川県立美術館で開催された「ほんもの・にせもの展」で起こった。久保氏所有の滝川製「にせもの」と、美術館所有の「ほんもの」が同時に並んで陳列されたが、後に、その「ほんもの」も、何と滝川製贋作だと判明したのだ。更に、滝川太郎の超人ぶりを示す事件が、1962年に再度起こる。久保氏が,「滝川は、コロー以外の全ての画家の作品を描ける贋作者」と言ったことを聞きつけて、脳溢血で利き腕が使えなくなったにもかかわらず、左手で、「滝川製コロー」を描き、久保氏に送りつけた。もちろん、コローだって描けるぞ、という空恐ろしい執念を込めた所作であることは言うまでもない。その恩讐に満ちた「滝川製コロー」を調査する機会に恵まれた私は、「左手紀念、コローの15号を想像して4号に無模写で描く、逗子 滝川太郎」「自由画、倣コロー作、非模写、左手」や制作方法などを記したカンバス裏を見た時、背筋が凍り付く思いであった。慣れない左手であり、拙い部分も散見されたが、コローの代表作「モルトフォンテーヌの思い出」(ルーブル美術館)と似た雰囲気を充分創出していた。この滝川作品を言いようのない気持ちで見つめていると、、自己顕示欲とか金銭欲とかを遙かに超えた、怨念の結晶のように思えてきた。たとえ虚像であっても高名にならなければ、絵が売れないという歪んだ日本美術市場への、罪を犯してまでの捨て身の挑戦、憤怒であったのか。何れにしても、滝川太郎は、贋作に手を染めていなかったら、後年日本美術史に名を残す画家になったに違いない。そして、地底から突き上げるような、滝川の怒りと悲しみを熟知していたが故に、贋作の香りがほのかに漂う滝川贋作を、久保氏は敢えて購入し続けたのでは、と書いたら、暴論だとの誹りは免れないであろうが、私も敢えて甘受したい。
久保貞次郎研究所2013年8月月報(第41回)
8月の久保関連蒐集品は、竹田愼三郎リトグラフ「マリアとマンゴ」ただ1点で、やや低調であったが、第27回「芳賀教育美術展」の副賞の準備で多忙であり、余儀ないことであった。今年も、副賞は当研究所で提供させて頂くことになり、関係者諸兄に感謝したい。副賞の無償提供は4年目になるが、今年も、昨年と同様、油彩画1点、版画作品85点と、私の拙本124冊、ノート480冊、久保研究所賞3点が用意出来た。版画作品85点のうち73点は、ギュスタブ・ドレのオリジナル木版画で、バブル時、額入りで高額取引された1863年出版(ロンドン、カッセル社)稀覯本「ドンキホーテ」の挿絵作品である。ドレ版画は今年4年目で計250点、芳賀の少年少女に受け取っていただくことになるが、数百年後、何故芳賀の大地にドレ作品が、宝石のように散りばめられているのかと、口々に語たり継がれる日が来るに違いない。昨年も同じ事を書いたが、現在でも、池田満寿夫、アイオー、瑛久、北川民次、竹田愼三郎等のオリジナル版画が、芳賀の地で散見される理由は、久保氏が、「小コレクター運動」を通して、多くの人に廉価で頒布したからに他ならない。「小コレクター運動」とは、一人一人が、3点のオリジナル作品を持ち、生活の中に芸術を浸透させ、食べていくためだけの「動物的生活」から、芸術を、そして生きることを、つまり存在自体を楽しむ「知的、人間的生活」を企図する運動であったが、その思想は、私の40年来の思索、「遙か数千年後、全ての人が芸術家である社会」の実現、と本質的にそれほど違ってはいない。数千年後そのような社会では、差別、暴力、戦争も無く、ましてや、軍隊も、国家も無く、学校も、試験もなく、不毛な労働も無く、それ故貨幣も無く、全ての人は、生まれながらにして、芸術家で、哲学者で、宗教家で、科学者で、赤銅色に輝く肉体を所有するアスリートで舞踏家で、即興の詩を謳い、世界共通語で(多分英語になるのだろう)、宇宙の秘密を語り合っているに違いない。久保氏は、この遙か彼方にある光り輝く人類の理想を、確かに夢想していた。そうでなかったら、久保氏が他界するまで、何故、世界共通語たらんとしたエスペラント語の「日本エスペラント学会会長」職にあったのかの説明がつかない。
美術展にに話を戻そう。この「芳賀教育美術展」は、前身の美術展の時代から久保氏も運営に関わり、それ故、久保氏が提唱した「創造美育運動」の理念が継承され、その象徴が「久保賞」(12名)である。因みに、娘が20年程前に「久保賞」を頂き、何かの縁なのだろうか、現在油彩画を描いている。そして誰に言われるともなく、子供達を集め、実費のみ頂いて、傘や、Tシャツや、木ぎれなどに絵を描く「キッズアート」を主宰し、ささやかだが児童美術教育に関わっている。また、娘の油彩画が、私の拙本(著作集1巻~4巻)の4種の表紙絵となり、私としては歓喜の極みで、大変贅沢だと恐縮している。もし20年前、娘が「久保賞」を頂かなかったら、娘は今絵を描いていないだろうし、私の拙本も存在していないだろう。
そのような不思議な縁(えにし)を思いながら、副賞の準備をしている時、多忙の中、私は幸せである。
久保貞次郎研究所2013年9月月報(第42回)
9月の久保関連蒐集品は、「竹田鎭三郎 メキシコ画集 インディオの祭り」、(昭和58年、限定100部、リトグラフ2点木版1点入り)で、昨年11月月報で新蒐集品として紹介した稀覯本と同一作品である。既蒐集品は購入を見送るのが原則なのだが、余りに廉価(定価の3%)であったため、予備として蒐集した。心を研ぎ澄ませれば、バブル崩壊の残骸の中に、宝石のような稀覯本を、今でも発見出来ることは、複雑な気持ちだが、嬉しい事でもある。
9月26日、第27回芳賀教育美術展最終審査会に審査員として参加した。審査員としては3回目だが、幼稚園年少の部で、素晴らしい作品2点と邂逅した。大学の専攻が芸術論(比較美学)であったため、人類の最初の芸術活動とは、芸術作品とは如何なるものか、と長年考えてきた。豊饒を願った洞窟画や岩石画(ペテログリフ)よりもっと古く、もっと根源的な芸術表現とは何か。子を授かって、歓喜の中、体に泥を塗って乱舞したのかも知れない。抑えきれない感情を乗せて、涙で濡れた石を、白く乾いた大地に投げつけたののかも知れない。人間は、やむにやまれぬ思いを、踊り、歌、叫び(言葉)、絵などの種々の形に換えるとき、救われたと思う時がある。昇華されたそれらの形を、我々は芸術と呼ぶのだろう。
前述の2作品は、その意味で感動的であった。赤一色の点描画と、青一色の線描画。誰に強制されることなく、幼児等は、強い思いを、見事に、「絵」という形に換えた。初期芸術論では、点描に、「持続」つまり「時間」という要素が入ると「線」になると言われるが、数学で「点」が集まると「線」になるという「カバリエリの定理」と同じである。
その2作品は、一見幼稚で稚拙に見えるので、選にもれるであろうと思い、赤い点描作品を、昨年創って頂いた「久保研究所賞」(落選作品の中から3点私が選抜)に選ぼうと考えていた。ところが、長年創造美育教育を実践されてきた審査員は、この点描と線描の2作品を、数百点の中から、順に1位と2位に、ためらわず決定した。おそらくその2作品の中に、ほとばしる純粋な芸術形態を、確かに見たのだろう。私は、自分の自惚れ、浅薄、高慢を恥じた。それにしても恐るべし、創美理論。未だ未完成の初期芸術論を、創美教育は、長年の実践の中で、既に取り込んでいる。更に驚いた事に、その審査員は、「幼児は点が先で、それから線を描くのですよ。」と解説していた。そして年少の部の「久保賞」決定時(久保賞は創美教育の2人の長老が決定)、もう一人の長老は、「青い線描画」を強く推し、「線描画」が久保賞となった。初期芸術論と、創美教育という異なった2視点から、同じ2作品に辿り着いたのは興味深いが、2人の長老が、瞬時に、自明のようにその2作品を選んだプロセスは、今後の研究課題であろう。再度言う、それにしても恐るべし、創美教育。
9月末日、芳賀町の名士の方から、お電話とお手紙を頂き、久保氏と真岡近代絵画鑑賞頒布会について、貴重なお話を承った。この場をお借りして御礼申し上げたい。詳細は割愛するが、お話から、多くの若手芸術家を育てた久保氏を、当時、芳賀の多くの人達が物心両面で支えていたのではと、推察された。
久保貞次郎研究所2013年10月月報(第43回)
10月の久保関連蒐集品は3点で、①「池田満寿夫20年の全貌」(昭和52年、美術出版社)、②「久保貞次郎美術の世界Ⅰ」特装版(昭和59年、限定100部、北川民次銅版画3点とヘンリー・ミラーセリグラフ1点入り)、③「北川民次画集」特装版(昭和49年、限定150部、日動画廊、飯田画廊、北川民次リトグラフ2点入り、久保編、久保氏論文「北川民次について」所収)。後者の2冊は稀覯本で、名古屋の古書店から運良く入手できた。
「池田満寿夫20年の全貌」所収の「小説・池田満寿夫」(田中穣)を精読した。昭和33年の第1回国際版画ビエンナーレで、久保氏の「この銅版画には色が使われている」という口添えで、3点の池田作品のうち1点が辛うじて最終審査に残ったこと、ドイツの国際審査委員ビル・グローマンが、絶賛したため、文部大臣賞を受賞し、一躍脚光を浴びた事などは、再確認出来た。しかし結論が「子供のような天才画家」というだけで、池田芸術の本質に迫っていないため、やや興ざめであった。そう言えば、以前月報で、池田作品は好きではないと書いたが、何故そうなのか考えてみた。生意気な言い回しだが、私には、池田作品の持つ「エロティシズム」が、中途半端で表面的で、現代風に装飾的で、何か突き抜けるものが無いように思えてならない。例えば、15年前、上野都美術館テートギャラリー展で観た、ラファエロ前派ロセッティの「プロセルピナ」の中に、「突き抜ける」ようなエロティシズム、強さ、怨念を感じた。ややローブロウ気味のボディーブロー受けたようで身動き出来なかった事を今でも覚えている。そしてそのインスピレーションを、荒木飛呂彦の「ジョジョの奇妙な冒険」の男性像群に見いだして、はっとする。
例えば、古沢岩美の妖艶な女体像に、グロテスクという誹りのなかで、私は一つの「思想・希望」を確かに感じた。調べてみると、古沢氏は、中国での地獄の戦争体験を表現した「修羅餓鬼」という強烈な反戦版画集を30数年かけて制作し、その陰惨な戦場で強く生き延びてゆく女性達の中に、「母性・希望」を垣間見、それ故、営々と、艶めかしくも屈強な女性を描き続けたのである。(渡辺私塾文庫28,古沢岩美関係本冒頭参照) この「思想・希望」は、益子のワグナー・ナンドール美術館にある「ハンガリアン・コープス像」で感じた「希望」と寸分違うことはない。そして我々一般大衆は、芸術作品の中にある微かな「希望」や「光り」を、かなりの精度で感知し、共有出来る。だからこそ、この「ハンガリアン・コープス像(ハンガリー兵士の死体)」は、現在、「ハンガリーの希望」と呼ばれ、右手は、人類の進むべき道を指し示すがごとく、力強く天を指している。
話を戻そう。私には、池田作品の中に、どうしても、この希望、思想、光りを見いだせない。これが、小生意気だが、池田作品を好きになれない理由なのだろう。
先日、久保旧邸跡地に設立予定の「真岡市立久保貞次郎記念美術館(仮称)」実現に尽力なさっている真岡市の関係者と会う機会があったので、昨年の9月月報で言及した安藤幹衛の油彩画作品7点(100号4点、50号1点、30号1点、25号1点、7点とも二科会出品作)とそれらが掲載されている画集の、真岡市への寄贈を正式に申請させて頂いた。久保家寄贈の多くの貴重な作品、瑛九を柱とする宇佐美コレクション、寄贈予定のオノサトトシノブ作品、児童画等、多くが版画、水彩画なので、寄贈を是非了承して頂き、久保氏と縁の深い安藤油彩画7点が、真岡市所蔵美術品の末席に連なれればと願っている。
久保貞次郎研究所2013年11月月報(第44回)
10月月報で言及した、安藤幹衛二科会出品作油彩画7点(100号4点、50号1点、30号1点、25号1点)とそれらの掲載画集計8点の、真岡市への寄贈申請を、11月11日付けで、気持ちよく受理していただいた。関係者に心より感謝したい。次回は、整理がつき次第、浅香公紀木版画約百点と伊藤高義油彩画の寄贈申請を予定している。更には順次、久保氏と縁のある作家の作品から、50号、100号の油彩画大作の寄贈も考えている。40年前美学美術史専攻の学生時代から、少しずつ美術品蒐集を始めていたが、自分できちんとした美術館を作れないときは、蒐集品は真岡市に寄贈をしようと、心の片隅で強がって決めていた。芸術作品は、本来公のものであり、私が一時、お預かりをしていたにすぎないのだろう。今は、強がりも、気持ちの揺れも一切無い。
11月末、真岡青年会議所の理事長、副理事長、芳賀教育美術展の担当委員長の若者3名が、美術展副賞提供のお礼にわざわざ当研究所に足を運んでくれた。久保研究所の事、久保氏の業績、思想、真岡青年会議所の未来、可能性などについて数時間話し合った。彼らの、純真で、しなやかで、快活な精神に触れると、私の精神も共鳴し、心なしか若返る。特に理事長の、純真無垢な少年のような立ち振る舞いには、ただ初々しいばかりで、日本の明るい未来が予感される。そう言えば3代前の理事長で、美術展表彰式で「じゃんけんおじさん」を演じてしまった無邪気な好青年にも、同じ予感を確かに感じた。
それにしても「青年会議所」とは不思議で、素晴らしい組織である。彼らは、少なからぬ年会費を払って、かなりの時間をさいて、黙々とボランティア活動に没頭している。彼らは声高に自慢する訳でもなく、僅かな賞賛すら求める訳でもなく、誰かに媚びる訳でもない。若者には過重と思える責務を、仲間の背で分担し、掛け声を合わせながら、見事にその責任を全うし、バトンタッチする。彼らは、現代社会の複雑怪奇な歪んだ人間関係などとは全く無縁な、協調と連帯と利他の精神で、目標を掲げ、それを成就する。その明朗快活、純真無垢、、実行力、団結力、柔軟さは、会員資格が20歳から40歳まで、役職は1年間のみ等の、独特な組織システムの恩恵なのだろうが、企業、政治世界の浄化、発展にとって、「青年会議所」は、多くの示唆に富む可能性に満ちた組織に思えてならない。
私は、彼らの無私の活動を、人類進化の確かな歩みだとみる。私は、彼らを、久保氏も私も夢見た、遙か数千年後、全ての人が芸術家である社会に向けての、屈強な若き戦士だと、密かに思う。
久保貞次郎研究所2013年12月月報(第45回)
12月上旬、長年の探求本「恩地孝四郎版画集」特装本(形象社、1975年,限定55部)が入手出来た。版画欠の特装本は所蔵していたが、恩地木版7点入りの完本は、入手に10年を要した稀覯本である。「日本の現代版画の始祖とも呼ぶべき」恩地と久保氏の繋がりについては未だ未研究の分野であり、多くの版画家を支援し育てた久保氏は、恩地には冷淡であったという風評が一般的であるが、実際は違う。版画集出版費用不足時、久保氏の温かい支援があったと、出版に関わった人から直接話を伺った事がある。出版費用が嵩んだ理由は2つあって、1つは、日本人が、恩地に無関心であった隙に、米国のコレクターが、その芸術性の高さ故、無名の恩地作品を買い占めてしまい、日本には数少ない恩地作品を求めて米国まで行かねばならない事。第2の理由は、米国では恩地作品は極めて高額で、写真を撮るだけでも、法外な金額を要求されたため、とその関係者は話してくれた。
久保氏は、「巨匠が去って二十年たったいま、かれの版画の輝く集積の扉が、世に広く開かれようとしている。いまからでもよい。われわれはかれのもとに急いではせ参じねばならぬ」(恩地孝四郎を思う、1975年、恩地版画集、形象社)、「この独創的で詩情豊かなスケールの巨きな作家の芸術がもっている真の価値を、かれが生きているあいだに見定めることができなかった、ぼくの能力の低さを軽べつし、あわれんだ」(1964年、版画4号)と、後悔の念を書き記しているが、恩地没後、真っ先に高評価の論陣をはったのは、久保氏であった。
私が、恩地孝四郎に興味を持ったのは、40年前、「本は文明の旗だ、その旗は当然美しくあらねばならない」(昭和27年、「本の美術」)という思想に感銘した時で、それ以降、英国のウイリアム・モリスの装飾性に似た、時代を超えたモダニティ溢れる恩地装幀本にも惹かれたからであり、その後も少しずつ蒐集を続けている。
久保氏研究を始める20年前から、私が恩地作品・装幀本・資料の蒐集家であった事。久保氏が、作品を買い上げることで多くの作家を支援している最中、、恩地と面識があったのに彼の作品を購入せず、恩地作品の米国流出を許したという久保氏の終生の悔恨。今、渡辺私塾文庫内に、相当数の恩地資料が有り、小者ながら私が久保研究所代表である事など、この3点が絡まって、不思議な因縁を感じている。私が、恩地と久保氏の2つの巨星を繋ぐ、小さな流星になれれば幸いである。
今月報は、久保氏と恩地孝四郎との関連のみになってしまったが、当研究所の当初からの研究課題でもあったので、僅かだが二人のふれ合いに言及した。今後少しずつ研究を進めたいと考えている。
久保貞次郎研究所2014年1月月報(第46回)
去る1月28日、真岡青年会議所芳賀教育美術展担当新旧委員長と新理事長、新副理事長の4名の方々が、表敬訪問してくださった。昨年末に他界した母通枝の通夜、葬式への御参列、御献花の御礼を述べた後、美術展の将来について語り合った。今後も豪華副賞は、当研究所で用意するとしても、運営費用の枯渇が当面の課題であるとの事であった。経費削減、少額募金等が話題になったが、何れにしても、27年間芳賀教育美術展を物心両面で支えてきたのは、紛うことなく、青年会議所会員の若者達である。少なからぬ会費を払って会員になり、様々なボランティア活動に没頭し、声高に自慢するわけでもなく、無私の精神で裏方に徹する会員弟妹に、我らは、もっと敬意を払うべきだろう。
久保氏とは、直接関係は無いが、長年の探求本「月下の一群」(堀口大学訳、大正14年、第一書房)が入手できた。長谷川潔の重厚な自刻木口木版入り稀覯本である。私は、「月下の一群」を手に、微笑を浮かべる久保氏を想像するに難くない。久保氏が、日本屈指の美術品コレクターであったことは周知の事実だが、愛書家であった事はあまり知られていない。渡辺私塾文庫所蔵の、愛らしい北川民次木版書票(エクスリブリス)が添付された、久保旧蔵洋書、美術書稀覯本が、その証左である。もっとも、献呈本として、数多くの稀覯本が久保氏に贈られたので、愛書家になることは自然な流れだったのかも知れない。久保氏の旧蔵本はほとんど散逸してしまったが、「愛書家としての久保貞次郎」も、困難な作業にになるが、今後の重要な研究課題であろう。
昨年11月、安藤幹衛の油彩画7点と掲載画集を真岡市に寄贈させていただいたが、桜咲く春には、浅香公紀木版画約百点と伊藤高義油彩画の寄贈申請を計画している。現在真岡市には、瑛九作品を中心とした宇佐美コレクション、多数の久保家寄贈作品、浅香木版画等の美術品を所有しているが、日本画、洋画、西洋絵画等が少ないので、渡辺私塾文庫の所蔵品を順次寄贈させて頂ければと、願っている。当文庫の所蔵品は、45年前から、私が少しずつ廉価で蒐集したもので、バブル期は、一切購入せず(正確には、購入できず)、爪に火をともすようにして入手した蒐集品である。書籍が中心だが、30年ほど前数百円で購入した江戸本を、関西の研究者が真岡まで閲覧しに来館すると言うので、贈呈してしまった本、韓国の草書研究者に進呈した稀覯本など20点を超える。多くの書物は、私が地上にいる間は、世の研究者のため当文庫で保管するとして、美術品については、震災後未だ混乱しているが整理がつき次第、少しずつ市への寄贈を考えている。寄贈を受理して頂いた時点で、月報で、喜々として報告する予定である。
久保貞次郎研究所2014年2月月報(第47回)
未だ雪深き長野の山麓から、久保氏最後の弟子、川崎満孝氏の窮状を救うための、「川崎満孝救援頒布会」の案内状が届いた。川崎氏とは「芳賀教育美術展」の審査会で同席し、何度か芸術や哲学の話をしたことは有ったが、まさかそこまで困窮しているとは思わなかった。貧乏は、芸術家の勲章であり、存命中に高評価を受ける芸術家の多くが二流であることは、ゴッホや宮沢賢治をみれば自明だが、貧困にも限度がある。同封された,久保氏高弟、高森俊氏のパンフレットにある「今彼を飢えによって失うことは人類の文化の損失となる」という一文を読んで、その日のうちに、送金して頒布を申し込んだ。アンネの日記、1944年5月3日記、「毎日膨大な戦費が費やされるのに、どうして医療費、芸術家、貧しい人に使うお金は無いのだろうか」、という一節を思い出し、久しぶりにすがすがしい気分に浸っていた矢先、一週間もしないうちに、川崎氏からシルクスクリーン版画2点が送られてきた。「情熱」と「天道を行く天道虫」というタイトルで、貧困の中から生み出された真の芸術作品であった。特に「天道虫」は傑作で、後の電話でのやりとりで、天を行く天道虫は、進化する人類でもあると、川崎氏は述べた。高潔で深遠で思想性に満ちた秀作である。
久保氏は、本物の芸術作品を3点持つことが人類の進化に繋がるという「小コレクター運動」を提唱したが、「天道虫」は、手始めの1点としては、比類無き出色の作品であると私は思う。志有る方は、久保研究所月報を読んだと言って、直接、川崎氏に頒布申込をして頂ければ幸いである。(「天道虫」1点で、送料等込み15000円、℡090-7802-0799川崎まで)
久保研究所を創設して4年、直接の支援は、芳賀教育美術展副賞提供であったが、それは今後も継続するとして、今回の頒布会を契機に、視野を広げる新たな段階にさしかかっているのかも知れない。能力、財力において、久保氏の万分の一にも満たない私だが、微力ながら川崎氏への今後の支援も、当然のように考えている。
2月の久保氏関連蒐集品は、1点で、「現代の版画」、ガスティン・プティ、昭和49年、講談社、久保氏小論「現代日本版画の展開」所収。(この小論は、「久保貞次郎を語る」、1997年、文化書房博文社、久保貞次郎執筆編集年譜に未掲載)
久保貞次郎研究所2014年3月月報(第48回)
久保氏最後の弟子、川崎満孝氏の住む長野の山々にも春は訪れたたのだろうか。先月月報で触れたように、「川崎満孝救援頒布会」に即刻応募し、支援の口火を切ったのだが、高森氏の「今彼を飢えで失う事は・・・」の文面が気になり、失礼だとは思ったが、段ボール一杯に高カロリーの食料品を詰め込んで、3月初め、長野に贈らせていただいた。小食が身に付いているとのお話だったので、2,3ヶ月分は賄えそうであり、6月に、また贈らせていただこう。久保氏がご存命時は、川崎氏の作品を購入するという方法で、久保氏の支援が為されたのだが、久保氏亡き今、久保研究所で微力ながら応援するのは当然である。ただ私は、久保氏の財力からはほど遠いので、失礼ながら食料の直接送付という、一番泥臭い一番有効的方法を採らせて頂くことに決心した。久保氏も天で苦笑いしていることだろう。
3月の久保氏関連蒐集品は、3点あり、1点は、「虹、アイオー版画全作品集」1954~1979、(1979,叢文社)で、小論「アイオーの虹の版画」と「あとがき」所収。2点目は、「東京名所版画集」全5巻、田中邦三、(昭和48年、プリントアートセンター)、第2巻に久保氏寸評所収。3点目は、「北川民次画集」(1974,日動画廊、飯田画廊)、この稀覯本は、2013年10月月報で言及した北川民次画集(特装本)のスーパー特装本。北川民次水彩画入りで、発売時は高額であったが、今回定価の十分の一で購入出来た。なんとかミクスは、美術市場や古書業界では、足音さえ聞こえない。
久保研究とは直接関係ないが、3月20日、渡辺私塾文庫所蔵の、藤井浩佑彫刻2作品(1点は灰皿、1点は立像)を、小平市の平櫛田中彫刻美術館の学芸員が調査研究のため来宅した。田中美術館で本年8月開催予定の「藤井浩佑彫刻展」のための調査で、足利市立美術館所蔵藤井作品2点調査後の訪問であった。当文庫所蔵の2点は、10数年前、東京の小さなオークションで落札した作品で、冷え切った美術市場では、彫刻作品など、一瞥さえされない時代、妙な芸術的存在感があったため、購入した。もちろん入札者は私一人で、最低値の落札金額であった。 久保氏は、オリジナル作品3点を所有する事が、生活の芸術化、人類の進歩に繋がるという、「小コレクター運動」を提唱したが、我々庶民が美術品を購入する場合、高額作品は大美術館にまかせて、気に入った作品を廉価で入手する事が、歪んだ現代日本美術市場ではベストなのかも知れない。
久保貞次郎研究所2014年4月月報(49回)
~真岡市久保講堂「平和の文化と女性展」について~
4月中旬、家内の親類の方が、5月30日から6月2日まで真岡市久保講堂で開催される「平和の文化と女性展」の内容説明、オープニングセレモニー出席依頼、応援依頼に来宅された。「世界平和の実現には女性の力が不可欠である」という趣旨には、私も全く同意見で、久保氏ゆかりの久保講堂で開催されることもあり、微力ながら応援依頼を快諾した。そしてその日の内に、真岡新聞社、いちごテレビに、私から電話をさせて頂いた。「平和の文化と女性展」の報道周知依頼は、既に二社に伝わっていたようだが、久保研究所からも宜しくお願い致します、と申し上げた。
久保貞次郎氏の業績を、①美術評論家、②美術品コレクター、③ヘンリー・ミラー絵画の紹介者、④多くの芸術家の経済的思想的支援者、⑤現代版画のプロデューサー、⑥創造美育運動の提唱者、⑦小コレクター運動の創設者、⑧エスペラント学会会長、⑨町田市立美術館館長、⑩教育者、の10項目に私は分類しているが、⑩教育者について、少し補足したい。久保氏は、50歳から78歳まで、28年間跡見学園短期大学で教鞭を執り、68歳から76歳までの8年間学長を務めている。もちろん跡見学園は女子大であり、久保氏は、既に半世紀前に、女性の力を信じ、うら若き女子大生に、革新的で、斬新で、夢のような芸術教育を実践した。久保氏の若き女性親衛隊が誕生したり、教え子達の中には、日本の歪んだ美術界の中で、歯を食いしばり美術市場を支えている、良心的な美術関係者もいる。従って、「平和の文化と女性展」には、久保氏も諸手を挙げて賛成であろう。
さて前述の「私も全く同意見で」について、僭越だが、言及したい。1995年私が発行した、貧弱な文芸誌「ひかえめな花」第5号から27号(1995~2002)に、私は「長編抒情詩~血球から知丘へ~」という未完の大作を書きつづった(渡辺淑寛著作集第3巻、2011年、真岡新聞社、に目立たぬように所収)。数名のマニア的ファンを除けば、反響は皆無だが、百年後には相当読み込まれるだろうと、強がり混じりの冗談を言っている作品で、その主題は、「母性による政治文化思想無血革命」であり、「女性展」の本質と大きな隔たりは無い。人類の進化には、女性の感性、社会進出が必要だと言われて久しいが、少し掘り下げてみたい。
多くの生物は、種の保存の宿命を背負った女性が優性であり、人間も女性の方が寿命が長い。女性の優位を無意識に知っている男性達は、暴力を背景に、営々と男性社会を築き、営々と戦争を繰り返してきた。きっと西洋の悲惨な魔女狩りも、女性に対する恐怖の裏返しなのだろう。自然災害時、おろおろするばかりの男性達を尻目に、緊急時の女性の悠然さを見るまでもなく、これからの人類の進化には、女性の非暴力性、破滅に対する本能的回避能力、生物学的強靱さが、何としても必要である。世界の政治指導者の半数が女性になり、猪突猛進型の男性指導者を母性で優しく包み込めば、戦争も激減するに違いない。「平和の文化と女性展」は、その意味で、些細な一歩だが、重要な一歩でもある。戦争、差別、暴力の一切無い社会、全ての人が芸術家である社会にむけて、数千年、数万年の遙かなる進化の旅であるが、21世紀初頭、全ての者が旅人であらねばぬ。夜明けはそれほど遠くない。
久保貞次郎研究所2014年5月月報(第50回)
月報を書き始めて4年と2ヶ月、第50回を迎えた。2,3年続けば良いほうだろうと言う、周囲の声も聞こえてきたが、私は意外と粘り強い性格で、この地上に生有る限り、書き続けようと密かに思っている。
5月30日号真岡新聞に、「真岡発:瑛九と前衛画家たち展」を観て~瑛九論試論~を、6月6日号に、「益子ワグナー・ナンドール春期展、小野田寛郎像を観て」の拙文を、久保貞次郎研究所代表として、掲載させて頂いた。一読して頂ければ幸いである。瑛九については、40数年前から注目していたが、作品も表現手段も難解で、本格的瑛九論も少なく、困難な作業であったが良い機会だったので、試論という形で挑戦してみた。
久保研究所とは直接関係は無いが、昨年12月他界した母、通枝の5冊目の随筆集「渡辺通枝遺稿集~五行川~」が、真岡新聞社から7月初旬上梓の予定である。前の4冊は、日本随筆家協会発行であったが、所収作品の多くが、真岡新聞掲載作品であるので、真岡新聞社様にお願いして出版の運びとなった。また、私の著作集第5巻も来年3月、真岡新聞社から、出版の予定で、既に準備に入っている。私にとって9冊目の本になるが、多分私の存命中は、一顧だにされないだろうと充分自覚している。それでも数十年後には、批評文を書く者が現れ、百年後には多くの人に読み込まれるだろうという淡い期待も無くはない。
3月月報での、久保氏最後の弟子、川崎満孝氏への、食料直接送付支援について、すこし反響があった。半分は批判的な指摘で、一流の芸術家に対して食料品を送りつけるのは失礼ではないか、という批判であった。私にしても、食料品の代価を送金して支援する方が、よほど楽なのだが、美術史を学んだ者として、日本の完璧な物流システムを考慮し、熟慮の上で、食料直接送付を選んだ。信じ難い話だが、洋の東西を問わず、餓死した芸術家は数知れない。彼らの周囲には何人かの理解者、支援者がいるのが常で、金銭的支援をうけた彼らは、何と、食料を購入せずに画材を買ってしまい、無自覚に栄養失調から餓死の道を突き進むのである。これが、失礼、不遜という批判を承知の上で、私が食料送付支援を選んだ理由である。食料品を揃えるのには一週間ほどかかり、今日も近くのスーパーで自ら缶詰類を購入した。
今月の久保氏関連蒐集品は、現代版画センター出版本8冊で、「エディション目録第3巻」(1980)並装本と特装本、「大沢昌助オリジナル入り画集」(1980)、「菅井汲オリジナル入り版画カタログ」(1980)、「関根伸夫オリジナル入りカタログ」(1982)、「プリントコミュニケイションNO41~64特装本」(1983)、「同NO65~75並装本」、「同NO76~87特装本」(1983)。久保氏と関係のあった、アイオー、古沢岩美、鈴木信吾、竹田愼三郎、大沢昌助、菅井汲、関根伸夫、吉原英雄、小田襄、木村利三郎の版画が、各冊に1点から4点添付されている。
久保貞次郎研究所2014年6月月報(第51回)
6月下旬、昨年の11月に続いて、久保貞次郎関連美術品を、真岡市に寄付申請させて頂いた。内訳は、浅香公紀木版画98点、瑛九フォトデッサン型紙7点、大浦信行シルク版画4点、木村利三郎版画2点、ヘンリー・ミラーリトグラフ1点、泉茂シルク版画1点、オノサト・トシノブシルク版画1点、安藤幹衛リトグラフ1点、オリジナル版画入りアイオー版画全作品集1冊、森義利10号水彩画、伊藤高義15号油彩画の計118点。今回も、気持ちよく受理してくださるとの事なので、嬉しい限りである。許されるなら、寄付第3回も久保関連作品を、第4回からは、著名作家の洋画、日本画を考えている。
7月3日から6日まで真岡市久保講堂で開催された、第28回真岡市美術展「久保コレクション展」を初日に、妻と二人で観に行った。107点の久保関連作品が、由緒ある久保講堂に整然と陳列され、想像以上に素晴らしい美術展であった。これだけの作品群を、入場無料で自由に鑑賞でき、出品作品目録小冊子も頂ける美術展は、日本でも希有であろう。
真岡市は、農・商・工バランスのとれた住みよい町だけれど、特徴のない町だと、かつては言われたが、今はSLの町と呼ばれ、そして、近い将来、真岡市を、畏敬の念を込めて「久保貞次郎美術の町」と呼ぶ都会の知識人も急増するであろう。その時の到来を早めるよう、当研究所でも最善を尽くすつもりである
本年3月月報で言及した、渡辺私塾文庫所蔵の藤井浩佑彫刻2作品について、平櫛田中彫刻美術館から正式な出品要請があり、7月下旬に、学芸員と美術品専門運送会社が、作品を受け取りに来宅するという。保険をかけて、小平市まで運ぶのだが、多分、2作品の購入代金より、保険代金の方が高額になるであろう。また、先日、当文庫所蔵の竹田愼三郎版画3点調査のため、依頼されて本格的写真を撮っていった方がいた。同様に写真代の方が高額になるに違いない。オリジナル作品3点を持つ事によって芸術に触れ、「生活の中に芸術を浸透させる」という小コレクター運動を提唱したのは久保氏だが、身も心も研ぎ澄ませば、美術展出品依頼が来るような作品を、千円単位で購入出来る現代は、小コレクター運動にとって、実は最適の時なのかも知れない。
今月の久保氏関連蒐集品は、木村利三郎シルク作品「City177」で、30号の秀作。今年度の芳賀教育美術展の副賞にと考えている。
久保貞次郎研究所2014年7月月報(第52回)
7月は、第28回芳賀教育美術展副賞の準備で忙しく、久保氏関連蒐集品は皆無であった。5年前、真岡青年会議所の要請で、当研究所が美術展の副賞を寄付させて頂く事になり、毎年7月末で、ほぼ副賞を揃えるようににしている。最高賞の知事賞には、一昨年、昨年と高額な油彩画、日本画を用意させて頂いたが、さすがに豪華すぎると言う人も少なくなく、今年は、6月月報で言及した「木村利三郎」の30号シルク版画とした。この作品は、限定20部の大作で、世界的に有名なシティーシリーズの中でも入手困難とされており、実質、昨年、一昨年の副賞と引けを取らないであろう。他に久保賞用木版画12点、ノート530冊、私の拙本125冊、久保研究所賞用文具セット3点、それに、ギュスタブ・ドレの木版画73点が用意できた。ドレ版画は、1863年、ロンドン、カッセル社出版の稀覯本「ドンキホーテ」からのオリジナル木版画で、定規とカッターを駆使して原本から切り取る作業は、神経を使い、10枚ほど切り取ると緊張のあまり吐き気をもよおすほどである。その当時、ドレの作品発表形態は、稀覯本の挿絵という形であったので、バブル時、額入りで高額で販売されていたドレ版画は、私がしたのと同じ作業で切り取られた作品であったに違いない。以前にも書いたが、愛書家としては、挿絵を切り取る作業は、本の手足をもぐようで、本当に辛いのだが、73人の笑顔を思い、5年間続けてきた。吐き気の半分は、悔恨の念からなのだろう。今年でドレ版画365点が、芳賀の地に、宝石のように散りばめられることになる。
6月月報で言及した、2度目の真岡市への107点美術品寄付は、気持ちよく承諾して頂いた。3回目の寄付は、許されるのであれば、来年度を予定している。
長野県在住の画家で、久保氏最後の弟子の方に、失礼を承知の上で、食料品を送らせて頂いた。優れた画家は、食料品購入より、画材購入を優先するのが常で、栄養失調で他界した画家は、美術史上珍しくない。久保氏は、無名だが優れた画家に版画制作機器を送りつけて、版画制作を促したが、私は、この才有る画家が正当な評価を受けるまで、叱責覚悟の上で、食料品を送り続けようと思う。
これも6月月報で触れたが、7月21日、小平市平櫛田中彫刻美術館の学芸員と専門運送業者が、当文庫所蔵の藤井浩祐2作品を受け取りに 来宅された。搬入先は、小平市だと思っていたら、岡山県井原市立田中美術館であった。無事到着したという報告書と共に、招待券、ポスター等多数同封されていたが、岡山県では、とても行けない。出品者は、招待の恩恵に浴するのが通例だが、今回は、遙か北関東の地から、展覧会の成功を祈ろう。
久保貞次郎研究所2014年8月月報(第53回)
~長倉翠子氏の芸術~
8月は、久保氏関連品を2点蒐集出来た。、1点は「美術批評」1952年、4月号(美術出版社)で、久保氏小論「欧米の児童美術教育」が4頁に渡って所収されている。技術主義、訓練主義に基づく伝統的美術教育と、オーストリアの美術教育者フランツ・チゼックが提唱した創造的美術教育を対比させながら、英、米、カナダ、北欧、メキシコの現在の美術教育を概説し、日本の美術教育とも比較した秀逸な小論であった。
2点目は、「陶 長倉翠子」(平成2年、毎日新聞社、久保貞次郎編)で、久保氏、小説家立松和平氏、花道家安達瞳子氏、美術評論家室伏哲郎氏の小論と、長倉氏自身による、各作品に添えられた7篇の詩が所収された素晴らしい作品集である。
「思いを込めて ひと握り胎土(つち)を 透かしてみると はるかかなたの 星の光がみえる」という詩の一節に、心震わされ、「作品11、桜A」の、フェルメールブルーに似た青に息を飲み、「作品14,命根」で、悲しみの人類史をふと思い、「作品28,冥A」で、埴谷雄高の「過誤の宇宙史」という言葉が、何故か脳裏をよぎり、「作品34,櫻C」、「作品37,櫻E」を出会った時、これらの作品は、陶芸作品が持つ実用性と対極にある美そのものだと感じた。しかもこの美は、過去世、現世、来世、時空を貫く宇宙根源の美だと、私には思えてならない。アインシュタインは、この宇宙には人間が感得出来ない、遙かに高度な美がある、と言ったが、長倉氏の作品群は、「はるかかなたの 星の光」のごとく、既にアインシュタインの「高度な美」の先触れだと、私には思えてならない。それと同時に、21世紀初頭、長倉氏の胎土による純粋美の表出を理解する人は、それほど多くないだろうとも思えた。それでも、ゴッホ、フェルメール、宮沢賢治をみるまでもなく、時代に先んじて現れる、真の芸術家も少なくない。その意味で、長倉氏も、必ずや後世、歴史を彩る一級の陶芸家として正当に評価されるであろう。
久保氏が、思想的経済的に支援した作家は画家、版画家のみと考えられているが、実際は、無名だが有能な若手彫刻家、写真家、陶芸家も含まれていた。彫刻家の一人は、2012年10月月報で言及した武蔵野美大名誉教授の加藤昭夫氏であり、写真家の一人は奇才、細江英公氏であり、陶芸家の一人は、もちろん長倉氏である。
芳賀教育美術展の入賞者は、以前は真岡新聞紙上、または小冊子報告書で全氏名公表されたが、今年度は予算の関係で、取りやめとなったので、関係者のご理解を得、10月月報内で、上位入賞者77名のみ発表を予定している。ご了承頂きたい。
真岡青年会議所OBで、久保研究所を陰で支えてくれている知人が、久保旧邸近くで、かき氷屋さんを始めましたと、わざわざ挨拶に来宅されたので、妻と二人、試食に行ってみた。お呼ばれで、都会の超有名レストランで何度か食事をしたことがあるぞ、という訳の解らぬ貧弱なプライドから,それらの食事に比べたら大したことは無いだろうと高をくくっていたら、とんでもない。この上なく美味であった。少し俗っぽい言い方だが、お勧めは、ストロベリーと抹茶。(注、「作品34」と「作品37」のタイトル「櫻」は、木偏でなく王偏)
久保貞次郎研究所2014年9月月報(第54回)
~第28回芳賀教育美術展上位入賞者氏名~
9月の久保氏関連蒐集品は2点で、1点目は「宮沢賢治関係所属目録」、昭和59年、跡見学園短期大、久保氏小論「賢治とヘンリー・ミラー」所収。2点目は「幽玄にきらめく土の華 長倉翠子」、平成7年、下野新聞社と「長倉翠子展」、平成10年、東武宇都宮百貨店。この2冊は、長倉氏と9月末お会いする機会があり、長倉氏から直接寄贈して頂きました。
8月月報で言及しましたように、今年度から、芳賀教育美術展の入賞者発表が割愛されることになりましたので、上位入賞者77名のみこの場をお借りして公表いたします。
◎知事賞、榊和平(にしだ幼稚園)、◎久保賞、柳田優奈(田野中1年)、小野澤翠(益子中2年)、粕谷侑里(真岡東中3年)、磯篤(逆川小1年)、川田幸央(逆川小2年)、石川真衣(芳賀南小3年)、白滝悠(真岡小4年)、石渡芽衣(山前小5年)、荒川夏妃(赤羽小6年)、小林凜成(青葉学園保育園)、澤田果莉奈(にしだ幼稚園)、大垣孝介(赤羽保育園)、◎運営委員長賞、澤畑凜奈(茂木中1年)、石崎凪紗(茂木中2年)、土屋友香(茂木中3年)、清水大輝(七井小1年)、小久保心和(中村小2年)、山田航輝(市貝小3年)、田川翔愛(亀山小4年)、伊東舞桜(真岡西小5年)、長嶋優衣茂木小6年)、大森礼公(高ノ台幼稚園)、星美緒音(にしだ幼稚園)、田中琉斗(高ノ台幼稚園)、◎教育会長賞、篠田友珠紀(逆川保育園)、もがき るい(中川保育園)、塚本歩夢(七井幼稚園)、荒健人(赤羽小6年)、谷口あかり(市貝小5年)、土門陽大(真岡西4年)、庄司樹(真岡西小3年)、渡邉照人(大内東小2年)、三村杏南(長田小1年)、羽石楓(芳賀中3年)、武田好民(益子中2年)、能渡紗稀(益子中1年)、◎芸術協会長賞、白川梨央(にしだ幼稚園)、中島初華(高ノ台第二幼稚園)、高木麻尋(赤羽保育園)、阿部桜華(芳賀南小6年)、櫻井拓真(真岡西小5年)、澤琥春(真岡小4年)、近藤大樹(田野小3年)、小野瀬裕人(芳賀南小2年)、横堀彩乃(茂木小1年)、大塚悠太(中村中3年)、大森美侑(茂木中2年)、齋藤花純(益子中1年)、◎造形教育研究会長賞、坂本来夢(山前中1年)、高野颯香(茂木中1年)、長岡紗綾(益子中2年)、石川明日香(久下田中2年)、海老沼美佳(市貝中3年)、谷中愛理(田野中3年)、大島史竜(七井小1年)、岡野優作(芳賀東小1年)、近澤愛姫(逆川小2年)、中山真菜(真岡東小2年)、畠中彩花(大内東小3年)、二瓶もも(茂木小3年)、早瀬大輝(久下田小4年)、古田土明日美(中川小4年)、内田陽(真岡小5年)、平石鈴佳(田野小5年)、横山堅志朗(益子小6年)、川崎寧緒(芳賀東小6年)、福田優衣香(高ノ台第二幼稚園)、鎌田桃歌(にしだ幼稚園)、柳茉那(真岡保育所)、白鞘大飛(真岡杉の子幼稚園)、津村瑠愛(益子保育園)、リベイロ・ジュニオル(萌丘東保育園)、◎立体特別賞、枝川尚生(茂木中1年)、◎久保貞次郎研究所賞、すずき あやめ(西田井保育所)、加藤姫奈(真岡東小4年)、谷口大斗(益子小6年)(敬称は略します。また誤字脱字が御座いましたらご一報下さい。)
久保貞次研究所2014年10月月報(第55回)
~川崎満孝氏の芸術~
10月の久保氏関連蒐集品は、竹田愼三郎木版作品「マリア」と、「池田満寿夫アートワーク展」(平成5年、中日新聞社)、「ヘンリー・ミラー絵画展」(1991,東京放送、毎日新聞社)、川崎満孝「白い蓮 2014 道」(アクリル画3号)、「上高地の紅葉 2014 道」(アクリル・水彩画、変形8号)の5点であった。川崎氏の2作品は、芳賀教育美術展最終審査会の時、川崎氏から直接手渡しで拝受した。芸術性の高さからすればかなり廉価であり、久保研究所で所蔵出来て幸運であった。川崎氏は久保氏最後の弟子と言われ、久保氏は存命中、支援も兼ねて川崎氏の作品を高額で購入していたと聞いたが、万分の一の財力の当研究所としては、廉価購入は余儀なきことであり、申し訳無いと思っている。
2作品を精査して感じる事があったので、川崎氏の芸術について、少し論じてみたい。川崎氏は1946年大宮市に生まれ、日進中学校において、久保氏高弟で、創造美育運動の重鎮である高森俊氏に美術の教育を受ける。25歳で日本放浪の旅を開始し、28歳になると、5年間、東南アジア、インド、ネパール、中近東23カ国を、絵を描きながら放浪し、インドでは、ヨーガ、仏道の修行に励んだ。更に46歳の時1年弱、東アフリカ、ヨーロッパ旅行をしている。
作品を見て誰の作か判断出来ない画家が多い昨今、氏の作品は、一見して作者が解る、現代では希有の作家である。私見だが、フランス素朴派のアンリ・ルソー、アメリカの女流画家グランマ・モーゼス、インド・チベットの仏教美術、曼荼羅、創美理論、ヘンリー・ミラーの自由画等が渾然一体融合し、氏独自の世界を織り成している。そして近年、タイトル、年号の後に「道」と記された作品が多い。これも私見だが、「道」とは、中国哲学で言う、宇宙、美や真実の根源を表す「タオ」の事であり、仏教で言う「涅槃」(ニルヴァーナ)の事ではないだろうか。氏の作品にしばしば「テントウムシ」が登場する。「テントウムシ」は「天道虫」と表記されるのだから、川崎氏は、人類を含めた全ての存在が、「タオ」、「ニルヴァーナ」に向かって進んで行く「天道虫」なのだと、絵画を通して表現しているに違いない。だとすれば、「存在とは進化」という私の考えと重なる部分も多い。氏の度重なる放浪は、「タオ」、「涅槃」、「楽園」を追い求める旅であったのだろう。そして異国の地で邂逅した「ニルヴァーナ」を絵にしたため、それを後世に残すことが自分の使命だと得心したと推察される。更に氏は、お年寄りの農民の穏やかな表情に、都会で寄り添いながらひっそり暮らす老夫婦の優しい心の中に、いたいけな幼児の天使の笑みの中に、純真無垢な子犬の優しい眼の中に、何気ない日常のひとときの営みの中にも、「涅槃」が確かに潜んでいる事も知っている。
氏の芸術が、現世で正当に評価されることは困難であろうが、遥か数百年後、21世紀初頭の傑出した芸術家として、美術史を彩る事の方が困難でないのは確かだ。
久保貞次郎研究所2014年11月月報(第56回)
~久保記念観光文化交流館の美術品展示館について~
今月報では、先々週号真岡新聞(12月12日号)の「真岡賛歌その4」で言及したように、久保旧邸の美術品展示館について率直な感想を述べたいと思う。
50年前、真岡市は、久保氏が提唱した「小コレクター運動」、「創造美育運動」の発祥の地であり、多くの文化人、芸術家が集う日本で屈指の現代美術最先端の町であった。その真岡市が久保旧邸を入手し、久保氏の私設藏美術館(久保アトリエ)を利用した、美術展示館を完成させた事、入館無料とした事は、市民として、研究所代表として、至上の喜びであり、市当局、関係者諸兄に心より感謝したい。美術館としては極めて小規模であるが、久保氏ゆかりの作家作品の展示という、明確な展示思想が有り、天井の大正時代の長い梁のごとく、背筋の通った、胸の張れる立派な美術館である。
オープン以来10回程入館したが、何点か気になる所が有ったので、僭越ながら憎まれ役を買って出て、より良き展示館になるため、少しでもご参考になればと敢えて改善点を述べてみたい。
第1点は、お年寄りがゆっくり座って鑑賞出来るように、中央に長いすを二つ設置して頂きたいという事。長いす二つがささやかな休憩所の機能を持ち、お年寄り、幼児にとって、芸術作品に囲まれたやすらぎの場になるかも知れない。
第2点は、展示作品数を増やして頂ければという事。欧米の多くの美術館には、壁一面に出来る限り多くの作品を陳列し、入館者になるべく多くの作品を見てもらうという展示思想がある。それに反し、日本の多くの美術館では、ゆったりと作品を展示する傾向がある。善悪は別にして、当展示館は、小館ゆえ、欧米方式にしない限り、展示数が貧弱であるという誹りを免れない。芸術作品は、鑑賞者がいて初めて芸術作品たり得るという事を再度想起すべきである。
第3点は、将来の補修、改修時の要望になるのだが、入り口の二つめの木製引き戸が、重厚すぎて入館を拒む印章を与えている。遮光、空調の意味も有るのだろうが、百を超える美術館を訪ねて、これほど無機質で寒々しい入り口は、数少ない。何十年も持ちそうな引き戸だから、当分は、可愛らしい展示作品ポスターを一枚作って貼っておくのも一考だと思う。
以上の事は、非難めいた気持ちなど微塵も無く、紛うことなく郷土愛からのご進言であり、僅かでも関係者諸兄のご参考になれば幸いである。
さて、今度は、地域住民が、この展示館を有意義に活用する番である。久保氏が言った、「生活の中に芸術を浸透させる」時である。老若男女、季節折々、展示館を訪れて、様々な作品と触れ合い、少しでも精神が昇華されれば、久保氏の夢見たユートピアへの、微かだが確かな一歩になるに違いない。
久保貞次郎研究所2014年12月月報(第57回)
12月の久保関連蒐集品は、久保氏と親交の深かったアイオーのシルクスクリーン作品24点で、同一作品であり、2015年度「芳賀教育美術展」の副賞にと考えている。副賞の無償提供は2015年度で5年目を迎えるが、ギュスタブ・ドレ版画作品は底をついてしまい、4年間続けたドレ版画作品の副賞提供は無理のようで、アイオーのシルク作品に換えようと思っている。入選数が約650点なので、副賞を揃えるのも1年がかりであるが、児童達の笑顔を思えば全く苦にならない。
今月報では、「第28回芳賀教育美術展の審査を終えて」という拙文を、真岡青年会議所の担当者に手渡したので、その短文を掲載して月報に換えさせて頂きたい。
「以前にも書いた事であるが、純真な子供達が描く児童画に優劣をつける事は、本来かなりの困難さを孕んでいる。しかし賞を決める美術展である以上、この困難さは甘受しなければならない。一般の美術展では、確固としたデッサン力に裏打ちされた完成度の高い作品が上位を占める場合が多いが、芳賀教育美術展では、2名の創造美育運動の重鎮がいらっしゃるので、自由で伸び伸びとした秀作が正当に評価され、喜ばしい限りである。
最終審査に参加させて頂いて4年になるが、やはり他の美術展と同様、抽象画、抽象版画は人気が無い。それは、抽象絵画芸術論がまだ周知されていないが故に、致し方のない事だと思っている。私個人は、長年、抽象版画の大家、恩地孝四郎を研究してきたので、この場をお借りして、簡単だが抽象画の本質に触れたい。
子供が絵を描いていると、多くの大人は、「何を描いているの?」と聞く。抽象絵画芸術論を知るまでは、私もそうであった。「何言ってるの、おじさん」と怪訝な顔をする児童が少なくなかった。児童達は、ただ画用紙に、自分の手から創出された、色、点や線の形を純真に楽しんでいるに過ぎない。何かを描こうとして描いているのではない。この太い道の先に抽象絵画がある。もちろん、自分の心のフィルターを通して、世界を写したり、頭に描いた像を具象化する事も、人間の本来の行為であり、具象芸術も重要である事は言うまでもないが、抽象芸術もそれに劣らず重要である。
最後になったが、出品なさった全ての皆様と御父兄に明記して頂きたい事は、これらの賞は、審査員各位の信条、趣向の結果であり、審査員が替われば結果も変わるという事である。だから、入選しなかったから、もう絵は描かないなどと、ゆめゆめ思わないでほしい。楽しく自由に絵を描く事は、精神を躍動させ、自分を成長させる事なのだから。」
久保貞次郎研究所2015年1月月報(第58回)
新年1月の久保関連蒐集作品は、昨年12月月報で言及したアイオーのシルクスクリーン版画と同一作品で、所有者に、作品は地元の美術展の副賞として無償提供の予定であると伝えると、所有者のご厚意により幸運にも大量に購入出来た。今年度第29回芳賀教育美術展では、入賞者200名全員に、この作品を贈呈させて頂ければと考えている。更に、来年の第30回記念大会では約650名の全入選者、入賞者にこの作品の贈呈をと、無謀にも夢想している。もし実現すれば、多くの人々に数多くの作品をプレゼントした久保氏も、天で、仰天しながらも拍手喝采してくれるであろう。
先日、真岡青年会議所の副理事長と、今年度美術展担当委員長、元委員長の3氏が、新年の挨拶に来宅され、彼らから、第28回まで、少なからぬ運営費は、真岡青年会議所が工面してきた事、第29回で運営費の基金が枯渇してしまう事等を知らされた。第30回からの運営費については、審査会の一層の経費節減について建設的な話し合いをしたが、久保研究所でも副賞無償提供以外の支援が可能かどうか考慮すると彼らに伝えた。30年近く続いた芳賀教育美術展が終焉を迎える事は、芳賀の地の文化の灯火が一つ消える事であり、多くの方々の力をお借りして、なんとか、微力ながらそのまばゆい灯火を守ろうと思っている。過去28年間で、幼少の時天才の様に絵を描き、見事入選、入賞を勝ち取り、小さな宝石の様なその思い出を心の片隅にそっと仕舞われている1万6千人を超える方々の為にも。
1月27日、私の拙本「著作集第5巻」のゲラ摺り第1校を、真岡新聞社の方が届けてくださった。3月末出版の予定だが、3月中旬には発行出来るかも知れない。内容は、真岡新聞掲載文28篇と久保研究所月報24篇、それに渡辺私塾文庫所蔵品目録の3部構成になっている。そして第4巻までと同様に、第5巻の表紙絵も、娘の日洋展入選作品が飾っている。地元にしっかり根付いた新聞社から本を出版出来る自分の恵まれた環境に、いくら感謝してもしすぎる事はないが、もっと密かな喜びは、娘の油彩画を表紙絵にしている事であり、これ以上の贅沢は無い。
話は少し戻るが、娘は芳賀教育美術展で、幸運にも2度久保賞を頂いている。久保賞のメダルを見つめ、幼児の様に自由に絵を描きたいという気持ちに素直になった時、絵を描き出した。芳賀教育美術展が無かったら、今絵を描いていないだろう。娘にとって、もっと幸せな人生が有ったかどうかは別にして、少なくとも「生活の中に芸術が浸透している。」そしてそれこそが久保氏が目指した事、思想に他ならない。その意味で、再度言う。微力ながら、まばゆい灯火を守ろうと思う。
久保貞次郎研究所2015年2月月報(第59回)
~渡辺私塾美術館6月末開館予定~
2月の久保関連蒐集品は「木村利三郎」のシルク作品3点と、久保氏旧蔵作品である「若林元司」のリトグラフ2点であった。木村版画は小品ながら、ニューヨークシティーシリーズの秀作であり、若林版画は久保氏旧蔵品ということで入手した。久保氏と若林氏との関連は不明だが、1988年の作品なので、久保氏がまだ御存命の時であり、例のごとく、作品を買い上げる事で、優れた若い作家を支援したのかも知れない。
2月27日の真岡新聞紙上で既に公表した事であるが、私にとっても、久保研究所にとっても、重大でかつ喜ばしい出来事があった。渡辺私塾駅前教室及び駐車場として入手した所に、綺麗な倉庫が併設されていたので、渡辺私塾美術館として利用する事が決まったのだ。美術館設立は私の40年来の夢であり、嬉しい限りだが、有る程度の手直しも必要なので、6月末の開館を目指している。真岡市「久保記念観光文化交流館」美術品展示館と同様、入場無料とし、当分の間、来館者にはセル画か版画を一人一点贈呈するという蛮行も検討している。また、私が常駐できる日時は限られているので、真岡駅SL館イベントに合わせて当面日曜日午後のみの開館を予定しているが、土曜日、祭日もオープン出来るよう努力するのは言うまでもない。真岡駅イベントに来訪された方々が、そのまま足を運んでくださり、オリジナル作品を手に、喜んで家路について頂けるようになれば、それ以上の幸せは無い。
渡辺私塾文庫、久保研究所の所蔵作品数は、版画を含めれば数千点に達するであろうが、震災でかなりの被害を受け、何点展示可能かは未だ不明である。それでも比較的大きい作品は被害が少なかったので、展示作品は、無名だが実力派作家の大作(10号~120号)を予定している。だが、時には、オリジナル版画ではない廉価なエスタンプ版画であっても、竹久夢二や山下清のような馴染み深い作品展示も考えている。もともと倉庫を利用するワイルドで質素な美術館であるから、今までの常識を覆す型破りの美術館運営を目指すつもりであり、入場無料のお土産プレゼントもその一つだが、入場者が極めて少なくても、型破り美術館なのだから一向に気にしない。純真無垢な児童や、人生を見事に生き抜いたお年寄りが一人二人来館して頂ければそれで充分である。
真岡駅近くに妖しげな美術館があり、恐る恐る入ってみたら、黒い服着た変なおじさんが居て怖かったが、帰りに版画もらっちゃってラッキー、という噂が波紋を呼び、波紋が波紋を呼んで、真岡市は、SLの町であると同時に芸術の町だ、という評判を勝ち取るための、些細な捨て石になれれば幸いである。
久保貞次郎研究所2015年3月月報(第60回)
3月の久保関連蒐集品は皆無であった。1年で一番多忙の時期なので致し方無い事であるが、時間というものは使い方次第で、多少は融通のきくものなので、本業の私塾運営、久保研究所、渡辺私塾文庫、美術館建設、著作集出版に向けて邁進するつもりである。
3月8日、真岡市の久保講堂で開催された「烏山和紙に等身大の絵を描こう」展示会を見に行った。久保講堂では、描いた和紙で大きなテントが作られていて児童達の息遣いが感じられ、和紙によるドレス作品も展示されており有意義な時間を過ごす事が出来た。烏山和紙には縁があって、18年前に、限定稀覯本詩画集「潮に聞け」を、烏山和紙を用いて出版した。翌年には「応援歌~血から知へ果てしなき旅~」を、更に翌年「愛の三行詩第2章」を美しい烏山和紙を用いて出版した。この3冊は、知り合いの古書店主や文化人に贈呈し、今は手元に各1部しか残っていないが、手作り版画を添付したり趣向を凝らしたけれど、烏山和紙の美しさには到底及ばなかった
久保講堂の展示会は、真岡青年会議所主催で開催され、以前にも書いたが、会員諸君は、少なくない年会費を払い、爽やかに密やかにボランティア活動に没頭している。声高に自慢する訳でもなく、賞賛や報酬を求める訳でもなく、誰かに媚びる訳でもなく、会員同士助け合い、肩を震わせながら無私の活動を続けている。私は、かれらの中に、真の人間の繋がりを見る。大げさだが、人類の希望と未来を見る。
3月31日、私の拙本「著作集第5巻」が真岡新聞社より刊行された。久保研究所とは無関係に思えるが、月報が第33回から56回まで所収されていて、月報が著作集の柱の一つになっているのは言うまでもない。月報は、まずホームページに、次に真岡新聞に掲載して頂き、最後に著作集に所収するという3段階の公表システムをとっていて、5年前に久保研究所を立ち上げた時からの私の決意でもある。
先月月報で、渡辺私塾美術館6月末開館予定と書いたが、広い駐車場の整備が3月末で完了し、4月初旬から中2階工事も始まり、4月末には、大きな倉庫を改造しただけのワイルドな美術館が完成予定なので作品搬入に1ヶ月かかるとして、5月末には開館できるかも知れない。当分は、真岡駅SLイベントに合わせて日曜日午後だけの開館であるが、入場無料で、来館者へのオリジナル版画または1点ものセル画プレゼント計画は不変である。美術館建設は私の40年来の夢であり、ここだけの話だが、私は40年かけて、プレゼント用版画・セル画を蒐集してきた。プレゼント進呈が何ヶ月続けられるかは、来館者数によるが、余りの蛮行に、久保氏も天で苦笑しているだろう。それでもこの蛮行が、久保氏が夢見た「芸術を生活の中に浸透させる」事に、私が夢想する「全ての人が芸術家である社会」の実現に向けて、些細な捨て石になれればと願っている。
久保貞次郎研究所2015年4月月報(第61回)
4月の久保関連蒐集品は3月に続いて皆無であったが、渡辺私塾美術館オープンの準備と、仕事始めもあって余儀ない事である。多くの塾生の将来を僅かでも担っている塾の仕事に、例年以上に注力しなければならない事は自明中の自明であると充分自覚している。
美術館開館予定日を5月24日日曜日に設定しているため、睡眠時間を削って毎日1時間ほど時間をさいているが、私一人で作品展示作業をしているので遅々として進まない。それでも40年来の夢の実現なので、至上の喜びに包まれての作業であることは言うまでも無く、連休明けには展示作業を終了する予定だ。
展示作品選択作業で気づいた事は、震災の影響が想像以上であり、カバーガラスの破損、額の損傷、キャンバスの破れ等、約半数の作品が展示不能に陥っていた。私の作品管理の不備が今回の震災で露呈した形だが、真岡市は震度6強の未曾有の揺れであったので、想定外として許されるであろう。
美術館は、倉庫を少し改修しただけの建物で、面積も「美術館」に該当せず、実体は、渡辺私塾併設ギャラリーにすぎないが、私の夢の結晶であり、作品に出会った時の、多くの子供達、お年寄りの笑顔を想像して奮闘している次第だ。一階は常設展として、日本画、洋画、版画を中心に50点程私の好きな絵を飾り、中二階には、特別展として竹下夢二エスタンプ(復刻版画)約60点の展示を予定している。エスタンプ版画に物足りないプロの方々には、受付近くに夢二肉筆の稀少な挿絵原画3点も展示予定なので、不満は無いのではと思うのはやや傲慢か。当面真岡駅SLイベントに合わせて、日曜日正午から5時の開館であるが、来年には土曜日、祭日も開館出来ればと考えている。
以前から何度も公表している通り、入場無料とし、来館してくださった方々には版画を贈呈させて頂く予定であるが、混雑を避けるため、最終告知は今回の月報のみとした。かなりの人が来てくれるよ、と言ってくれる友人もいるが、多分十数名であろうと思っている。
第2回特別展は、山下清エスタンプ展、第3回特別展は、恩地孝四郎展を考えており、恩地孝四郎展は来年か再来年になるであろうが、都会の専門家も来館する内容にしたい。
人は芸術と無縁でも生きていけるが、人生に潤い、優しさ、ゆとり、趣向、目標をもたらす物の一つは芸術であり、音楽、美術、文学等は、私達の心の奥底に確かに届く聖水である。その聖水の通り道は、音楽、美術、文学では異なったルートで心底に届くようで、私にとってもそれらは必須の聖水であるが、私の経験では、どうやら「美術の通り道」の構築が一番困難であると認識している。画集や詩集を求めに行かない今の若者でも、音源を購入する者が多い事から推察出来るように、若者は「音楽の通り道」を既に十二分に構築しているようなので、渡辺私塾美術館で「美術の通り道」を構築する人が新たに一人でも増えていただければ幸いである。真岡駅前に変な美術館が有り、黒服の無気味なおじさんが居て入りずらいが、入場無料で版画のお土産もらえるよ、という噂が口々に伝わり、真岡市を訪れる人が僅かでも増えれば幸甚である。
久保貞次郎研究所2015年5月月報(第62回)
~渡辺私塾美術館5月24日開館~ 代表 渡辺淑寛
去る5月24日(日)、40年来の夢が叶い、美術館開館の運びとなった。前日土曜日の内覧会には、ご招待者30名程が、翌日の開館日には70名程の来館者が有り、予想以上に盛況であった。予想では、内覧会10名、開館日は十数名であったので、数ヶ月に及ぶ一人での苦しくもあり、この上なく楽しい準備が報われた思いである。お土産の、久保氏縁(ゆかり)の画家「アイオー」のオリジナルシルク作品「ラブレターズ」も60名の方に贈呈させて頂いた。(ご家族での来館者にはご家族で1点。またお一人様1回限り贈呈。)
倉庫を改装しただけの粗末でワイルドな美術館だが、今までの美術館にまつわる多くの因習を捨て、入場無料、お土産としてオリジナル版画プレゼント、日曜日のみ開館、内覧会の翌日の開館日には常設展に作品を5点追加、5月31日に更に5点追加等、型破りの美術館にしたつもりだ。因みに5月31日には、常設展85点、竹久夢二特別展70点が展示出来、極小規模の美術館として、どうにか恥ずかしくない美術展になったのかも知れない。来館者のご芳名の記帳も省略させて頂こうと考えたがアイオーのオリジナル作品を誰が所蔵しているか、将来判明出来るように、市町村名とご芳名のみ記帳させて頂いた。
最初は日曜日正午から5時まで開館の予定であったが、日曜日夜仕事があり、体力的にかなり厳しいので、5月31日より午後1時から午後4時までとさせて頂いた。ご了承願いたい。
アイオーのシルク作品は、プレゼント用として900点用意しているので、あと1年は充分補えるであろう。残部作品は、芳賀教育美術展の副賞にと考えている。
館の一角に、「お子様用お絵かきコーナー」を急遽設置した。設置理由は、知り合いの小学生が、私が学生時代に描いた、訳の解らぬ狂気の絵(詩画集「潮に聞け}に所収)を見て、琴線に触れたのだろうか、一心不乱に素晴らしい絵を描き出した為である。宿題でいやいや描くのでなく、どうしても描きたいから、色と形でしか表現できないから、という真の絵画表現を再認識させられたからに他ならない。そう言えば私の「潮に聞け」の絵も、学生運動の陰惨な袋小路の中で、半年間何かに取り憑かれたかのように描き殴った数百枚のペン画であった。蛇足ながら「潮に聞け」の原画の一部と、小学生の絵も展示されている。更に蛇足ながら、私の拙本「著作集」の表紙絵になった娘の油絵も展示されており、ご興味の有る方は来館頂ければ幸いである。
竹久夢二の作品70点は、復刻版画とセノオ楽譜表紙絵が主だが、夢二のアルス児童文庫挿絵原画3点も受付近くに目立たぬように展示されているので、お帰りになられる時是非ご覧になって頂きたい。
なお、パンフレットにあった古沢岩美の艶めかしい油彩画は、やや刺激が強く、鼻血を出してしまう男子高生も出てくるのではと懸念し、展示を割愛させて頂いた。
久保貞次郎研究所2015年6月月報(第63回)
~渡辺私塾美術館6月28日常設展18点追加し103点に。7月5日よりほぼ全作家に略歴・解説書添付。~代表 渡辺淑寛~
美術館を開館して1ヶ月が過ぎた。入場無料で来館者にオリジナル版画プレゼント、日曜日午後1時から4時のみの開館、写真撮影自由、倉庫改装ワイルド美術館、毎週作品追加、お子様お絵かきコーナー設置、展示作品十数点の掲載図録準備等、愚行とも言える型破りな運営だが、多くの喜び溢れる出会いも有った。紙面の都合上、二つの出会いのみ報告したい。
一つ目は、外国人来館者2名との出会いである。思いもかけず、タイの女性とアメリカの男性が自転車で来館された。後から解った事だが、私の教え子の農園にホームステイしている旅行者であった。タイの女性とは英語を通しての会話であったが、色々話しをして楽しい時間を過ごす事が出来、彼女から多くの事を教えられた。
彼女は、ある1枚の油彩画の前に座り込み、長い間じっと見つめていた。その絵は、長い苦しみの時を経て、やっと光明を見いだした時に描かれた「光と私と犬」という、私の娘作の80号作品であった。同じ女性として何か感じるものがあったのだろう。これが本当の絵画鑑賞だと初めて教えられた。日本の美術館で座り込んで展示作品を見ようものなら怖いガードマンに摘まみ出されてしまうだろう。タイでは当たり前なのかもしれないが、彼女は絵と真っ直ぐ向き合い、色と形が創出する絵画芸術宇宙を探遊していた。その後、私が43年前に描いた訳のわからぬ恐ろしいペン画の前で歓声をあげた。14年前の私の拙本「潮に聞け」の原画の一点の前で。もちろんそれらの展示品が、娘の作、私の作などとは、彼女に知らされていなかったのは言うまでもない。また高名な美術教育者にも、私の原画をお世辞混じりに褒めて頂いたので、嬉しくなって、行方不明であった原画9点を、阿修羅のごとく探しだし6月28日、「潮に聞け」全原画24点、嬉々として展示した次第である。
米国の男性は、経済学を修めたエリートで、日本語も流暢であり、知性溢れる好青年であった。様々な事を教えて頂いたお礼に、私の拙本を二人にプレゼントさせて頂いたのだが、後日タイの女性は、そのお返しにタイカレーを持参してくれた。食するのは、正直やや勇気がいったが、家内と二人で、独特の香辛料やココナッツ入りカレーをおいしくいただいた。また米国青年も、手作り梅ジャムを私のプレゼントにと知人に託して帰国された。「義理堅い」とは日本独自の文化だと思っていたが、万国共通であると再確認させられた。もうあの二人と会うことは叶わないであろうが、今や二人は、私の数少ない心の友である。
二つ目の出会いは、男子高生に鼻血を出させる古沢岩美の艶めかしい裸婦油彩画にまつわるものである。(6月28日より展示)鼻血の話と全く無関係に、偶然古沢氏のご遺族から、お手紙を頂いた。私が「渡辺私塾文庫ホームページ」に、古沢芸術の本質は、反戦思想であり、33年間かけて完成させた、中国での悲惨な戦争体験を描いた銅版画集「修羅餓鬼」がその証左である事、古沢氏が営々と描き続けた妖艶な女性群は、人類を救済する女性戦士だと書いた事に対するお礼のお手紙であった。美術館を開館した事、古沢作品は展示を一ヶ月遅れらせた事、家内が41年前、名古屋でお父様に、有り得ないほど美しい似顔絵を描いてもらい、今も大切にしているという縁(えにし)について、お返事を差し上げた所、建築家で舞踏評論家のご子息様が、何と東京から不意に来館してくださった。一流の文化人と歓談できて楽しい一時であった。
入館者から、マニアックな作品もあるので、画家の簡単な解説書があれば良いのですが、というご要望がありましたので、少し厳しい作業でしたが、7月5日よりほぼ全作家に略歴・解説書を添付致しました。また、オリジナル版画プレゼントは当分続行の予定です。初めての方、一度いらっしゃった方のご来館を、心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2015年7月月報(第64回)
~渡辺私塾美術館7月、常設展6点追加し109点に。当分オリジナル版画プレゼント継続実施~代表 渡辺淑寛
美術館を開館して既に2ヶ月が過ぎた。日曜日午後1時から4時のみの開館であるが、多忙の中、また仕事が増えて、大変でしょうと言われるが、全く苦にならない。かえって土曜日あたりから、小学生のように、わくわくした気持ちでいる。開館初日は、正午から5時であったのだが、その後、高3英語という重要な授業があるので、さすがに時間的体力的に無理で、1時から4時開館にさせて頂いた。
7月16日と29日の下野新聞に、2度開館の記事を掲載して頂いたので、芳賀郡内からは言うに及ばず、佐野市、栃木市、宇都宮、千葉、埼玉からの来館者もあった。喜ばしい限りである。また、久保記念館の素敵なレストラン「こころ」のオーナーシェフ様にもお忙しい中、来館して頂き、楽しいお話が出来た。お話の様子から、レストラン内に絵を飾りたいお気持ちが察知出来たので、私に無償で絵を飾らせてほしいと、無理矢理納得して頂き、翌日、シャガールのリトグラフ4点をレストラン内に掛けさせて頂いた。今後季節毎に違った絵を飾らせて頂ければと思っている。関係者の皆様、私の我が儘をお許し願いたい。
当美術館の常設展は、開館当日は75点であったが、少しずつ展示作品を増やし、8月9日には110点にもなった。2ヶ月も経たない内に、常設展展示作品が35点も増える美術館は希有であろうが、倉庫を改装しただけの型破りな美術館なのだから、一向に気にしない。
エアコンを設置したのだが、鉄板屋根なのであまり効果がなく、エアコンをつけたまま、入り口の大きなシャッターを開けているので、かなり暑い。それでも汗をかきながら、竹久夢二の涼しげな版画を見るのも一興だろう。
ある来館者様に、久保研究所と当美術館の関係について尋ねられたが、現在の展示作品は、久保研究所と渡辺私塾文庫の収集作品であるので、当美術館と久保研究所と渡辺私塾文庫は、ほぼ一体である。ここで、久保氏の小コレクター運動について、少し触れてみたい。久保氏は60年前真岡市の久保ギャラリー(現久保記念観光文化交流館)を中心に、一人3点オリジナル作品を所蔵し、「生活の中に芸術を浸透させる」という「小コレクター運動」を展開した。その運動の中で、久保氏は、池田満寿夫、瑛九、アイオー、北川民次、竹田鎮三郎、オノサト・トシノブ、安藤幹衛等の版画を、廉価で販売した。今でも、芳賀郡に彼らの貴重な作品が宝石のようにちりばめられているのは、その運動の賜である。久保氏が、帰天するまで、「国家の無い世界」という思想をはらむエスペラント学会会長であった事を考え合わせると、人間は芸術性を生活の中に取り入れて、個々人が人格的に成長しない限り、人類の進化など有り得ないという思いが、久保氏の確信であったと推察する。その思想を根底に、創造美育運動、大学学長としての教育運動、美術評論、美術品コレクター、美術館館長、芸術家の支援者、版画プロデューサー等の活動があったに違いない。
久保氏の思想とは全く別に、私も、様々な活動の中で、数千年後「全ての人が、詩人、芸術家である社会」を、ここ数十年夢想してきた。そして気恥ずかしい事であり、久保氏の万分の一のスケールであるが、無自覚に久保氏と似たような事をしてきたのは、久保氏と私の思想の根幹がかなり重なり合ったためかも知れない。厚顔無知にも、5年前、久保研究所を、躊躇無く設立出来たのも、その「重なり」が原動力であった。「万分の一のスケール」が「千分の一のスケール」になれるかどうかは、私の努力にかかっているが、地上に生のある限り、少しずつ前に進んでいこうと思っている。
当分の間、来館者様に、アイオーのオリジナル版画プレゼントを実施しています。ご来館、心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2015年8月月報(第65回)
~渡辺私塾美術館8月、常設展7点追加し116点に。当分オリジナル版画プレゼント継続実施~ 代表 渡辺淑寛
大胆にも美術館を開館して、はや3ヶ月。日曜日の開館が、私の日常の中に心地よく根を下ろし、当たり前のように、爽やかに流れている。来館者は多くないが、そんな事はどうでも良い。自らの目と足で所収した絵に囲まれて、たとえ灼熱の盛夏であっても、日曜の午後過ぎゆく数時間は、涼しいそよ風の様で、まさに至福の時である。そしてその数時間は、眼前のそれぞれの作品の辿った数奇な来歴と、私との不思議な縁(えにし)に思いを馳せる、麗しい時でもある。
8月は、常設展作品を7点増やして、計116点になった。竹久夢二特別展70点を加えると計186点展示となり、小美術館として恥ずかしくない展示数であろう。
隙間無く並べる展示方法には違和感を覚える方もいらっしゃると思うが、ターナーの秀作を多く所蔵する英国のテートギャラリーの展覧会場の写真を用意させて頂いたので、一度ご覧になって頂きたい。隙間無く展示している。これは美術品展示思想の違いである。わざわざ来て頂いた方に出来るだけ多くの作品を観てもらいたいという外国美術館の展示思想と、日本での、もったいぶった、ちょびりちょびりみせる展示思想の違いである。そう自分に言い聞かせて、9月6日用に、恩地孝四郎木版画3点(恩地邦郎刷)を、僅かなスペースを見つけて展示し、総計189点になった。幻の版画家、装幀家、詩人恩地孝四郎ファンは一度足を運んで頂ければ幸いである。代表作木版画「萩原朔太郎像」(平井刷)、油彩画「並木のある道」(6号)、木版画「海にいる人物」(邦郎刷)も、既に開館初日から目立たぬように展示している。
以前の月報で触れたが、お子様用お絵かきコーナーを用意し、出来た作品をお見せ頂ければ、ご褒美に、テレビアニメのセル画を差し上げている。また絵画より言語の方が内面の思いを表現し易いお子様には、原稿用紙も用意してあるので、内なる情念を言葉に載せて、思いの丈を発露してほしい。私は、二つの大学で、化学と美学美術史を学んだが、正直言うと、言語表現、音楽表現、肉体表現、美術表現等は対等の表現手法だ思っている。例えば、歓喜で溢れんばかりの幼児の顔の表情は、神々しく、目映く、まさに肉体表現の魁である。かつて遠縁の幼子に、顔より大きいキャンディーをプレゼントした時の、彼の金色の笑顔を今でも忘れない。市内のスーパーでの出来事であったが、周囲の風景は一切消え去り、彼の笑顔だけが、私の視界を覆い尽くし、海より深い感動と喜びを与えてくれた。人間は他者を感動させる様々な力を持ち、その力の発露を芸術と呼ぶのだろう。久保氏は美術表現に重きを置いたが、私は全ての芸術表現を考慮する立場である。もちろん久保氏は全てを理解した上で、まずは美術表現を武器に、「人間の解放」を思索したに違いない。私は「解放」に対して、「進化」という言葉を使うが、本質は同じである。そうそう、私の拙書著作集5冊の副題は「存在とは進化」であった。そして、そうそう私の口癖は、「遙か数千年後、全ての人が芸術家で詩人で哲学者で宗教家で、赤銅色の肉体を持つアスリートである社会」である。
当分の間、来館者様に、アイオーのオリジナル版画プレゼントを実施しています。日曜日午後1時から4時までの開館ですが、ご来館、心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2015年9月月報(第66回)
~渡辺美術館9月、常設展7点追加し123点に。当分オリジナル版画プレゼント継続実施~
~6年連続で、久保研究所より、芳賀教育美術展副賞提供~ 代表 渡辺淑寛
去る9月17日、久保貞次郎ゆかりの久保講堂で第29回芳賀教育美術展の最終審査会に出席した。久保研究所代表審査員として5年連続の参加であり、久保研究所賞を創設させて頂いて4年になるが、各賞、講評については、分をわきまえ、差し控えたい。
関係者の方々に無理を言って、6年前から、久保研究所より副賞を提供させて頂いている。5年間は、各賞に合わせて、油彩画、日本画、版画、本、ノートなどを受け取って頂いたが、今年は趣向を変えて、約700名の入賞者全員に、アイオーのシルクスクリーンオリジナル版画を贈呈させて頂いた。700名の児童に、同じオリジナル版画を副賞として贈呈する美術展など、世界でも希有であろう。
思い起こせば、久保貞次郎氏は、60年前、真岡市で「小コレクター運動」を提唱し、一人一人がオリジナル芸術作品3点を所有し、生活の中に芸術を浸透させる事で、人類の人間的成長、精神の解放を願った。何かの縁(えにし)で、久保研究所を創設した私が、芳賀の地に多くの作品をちりばめる事は、微力だが、久保氏の思いを継ぐ事であると自らに言い聞かせ、今後も一歩一歩地を這うように前進するつもりである。
真岡駅前の渡辺美術館9月の常設展には、執念で、展示スペースを見つけて、7点追加し、123点展示となった。竹久夢二特別展70点と合わせて193点展示となり、建物設備等は三流だが、展示作品数、作品の質は、どうにか二流になったといって良いだろう。以前来館された美術の専門家が、「他の美術館でもそうは見られない作品が、沢山何気なく無造作に置いてあるね」と呟いてくれた事が、心底で心の支えになっている。
大震災で行方不明になっていた、河内成幸作「0次元ニューヨーク・Ⅲ」を、数日前偶然発見したので、恩地孝四郎木版画「人体考察・肩」と一緒に、10月4日用に展示した。これで10月4日は125点の常設展展示となる。河内作品は限定23部の木版画大作で、阿部出版レゾネ本にも掲載され、大英博物館にも所蔵されている代表作であり、一度ご覧になって頂ければ幸いである。恩地作品と同様、河内氏も好きな作家で、大作をあと数点所収していたはずなので、時間を見つけて探してみようと思う。
当美術館の特徴は、入場無料、当分版画プレゼント、お座り頂ける多くの椅子、お子様用お絵かきコーナー、日曜日午後のみ開館、写真撮影自由などであるが、もう1点の特徴は、展示作品の図録、または展示作家の図録が用意されていて、自由に閲覧出来る点である。古い図録を収集することは作品収集に劣らず困難であるが、私は40年来の稀覯本コレクターでもあるので、得意分野で苦にならない。せっかく、分不相応にも美術館を開館できたのであるから、今までの因習に一切囚われる事の無い自由な創造空間を創設出来ればと切に願っている。
日曜日午後1時から4時までの開館ですが、ご来館、心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2015年10月月報(第67回)
~渡辺私塾美術館10月、常設展29点追加し152点に。第2回企画展「山下清版画展」30点展示。第1回企画展「竹久夢二版画展」70点も同時展示~
~久保貞次郎と恩地孝四郎~ 代表 渡辺淑寛
渡辺私塾美術館の常設展10月追加作品数は29点で、大幅追加であった。これで常設展は計152点となり、小規模倉庫美術館としては恥ずかしくない点数であろう。更に、11月1日の開館にあわせて、前日、第2回特別展山下清版画展30点の準備が完了し、第1回特別展竹久夢二版画展70点も同時展示の形をとったので特別展は100点展示で、計252点となった。美術館開館構想中、150点展示出来れば最高だろうと思っていたので、望外の喜びである。
第2回企画展山下清展は来年春頃にと思っていたが、「どうせ、企画展は1回で終わりだよ」という心無い噂が耳に入ったので、一念発起して、11月1日から実施した。山下清版画は全て復刻版画であるが、日本では、30点のみ制作されたと聞いているので、もし事実だとすれば、当美術館でその30点が全て見られるので、ご来館頂ければ幸いである。
第3回企画展は「恩地孝四郎展」を考えているが、かなり大掛かりになるので、来年の初秋を予定している。恩地孝四郎は、日本ではやや馴染みの薄い芸術家であるが、日本抽象版画の先駆者で、詩人で、稀代の装幀家で、未だ謎多き巨人であり、近年研究が進み、海外では棟方志功と並び称される作家である。主に本の装幀で生計を立てていたので、多くの作品を手放す必要もなく、それ故刷り部数も少なく、更に、その数少ない作品は、米国の優れたコレクターが自国に持ち帰ってしまったので、多くの恩地オリジナル作品を鑑賞するためには、米国に行かねばならない。プラグマティズム思想を背景に持つ米国収集家達は、無名作家だろうが芸術性の高い作品は躊躇無く収集し、作品の質よりも作家名に迷い踊る日本の美術関係者は、恩地作品に一瞥も投げなかった。確かな鑑識眼を持つ久保氏でさえ、恩地が、1955年63歳で他界した後、「恩地孝四郎の思い出」の中で「この独創的で詩情豊かなスケールの巨きな作家のもっている真の価値を、かれが生きているあいだに見定めることができなかった、ぼくの能力の低さを軽べつし、あわれんだ」と書き、終生悔恨の念を禁じ得なかった。それでも、1975年の「恩地孝四郎版画集」刊行の折には、資金難の時、久保氏は惜しみない助力を注いだと言われている。私は、久保氏が恩地作品を評価しなかった理由について別な見方をしている。皇室関係者の教育係を務める程の格式高い家に生まれ、裁判所検事を父に持ち、気位の高い孤高の芸術家恩地氏と、他の美術評論家から嫉妬されるほどの大富豪で思想家の久保氏は、何度かの出会いが有っても、お互いが歩み寄る事を、本能的に、水と油のような存在として避け合ったのではないかと、私は考えている。
40年以上も前から恩地芸術に興味を抱いていた私は、18年前、アルス日本児童文庫76冊のうち、54冊の表紙絵恩地肉筆原画と多くの挿絵原画を入手した。オリジナル版画ではないのでそれ程高価ではないが、作品数が極めて少ないと言われている中、54点の表紙絵原画と百点におよぶ挿絵原画、木版画、油彩画、水彩画、多くの木版画入り稀覯本の恩地展覧会は、日本でも希有な催しになるに違いない。そのプレリュードとして、現在恩地油彩画2点、水彩画1点、恩地木版画本から8点、後刷り木版画11点計22点を展示している。
入場無料、アイオーのオリジナル版画プレゼントはまだ継続しています。日曜日午後1時から4時までの開館ですが、ご来館、心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2015年11月月報(第68回)
~渡辺私塾美術館11月、常設展38点追加し190点に。第1回企画展「竹久夢二版画展」70点、第2回「山下清版画展」30点も同時展示。計290点展示~
~新年1月9日、宇都宮大で「久保貞次郎と北川民次を語る」美術シンポジウム開催。代表が語り手として参加予定~ 代表 渡辺淑寛
渡辺私塾美術館11月追加作品は38点を数え、常設展190点になり、夢二作品70点、山下清版画30点と合わせ計290点展示となった。超過密展示であるが、来館してくださった方々にできるだけ多くの作品を観て頂きたいという事が、私の展示思想であり、今後も少しずつ追加していこうと思っている。超過密の言い訳に、英国テートギャラリーの過密展示の写真をそっと置いている事は以前言及した。
追加作品のほとんどが恩地孝四郎作品で、来年初秋開催予定の第3回企画展「恩地孝四郎展」のプレ展として、既に44点展示した。来年の企画展は最終的に恩地作品270点を予定していて、現在、1日数点、アルス日本児童文庫表紙絵原画、挿絵原画の額入れを行っている最中である。来年1月13日から、東京国立近代美術館で「恩地孝四郎展」が開催され、260点余が展示されると聞いたが、点数だけでも同程度の企画展にしようと夢みている。もちろん作品の質、希少性では、月とすっぽん、雲泥の差であるが、アルス児童文庫関連作品は1点物で、当美術館でしか観られないので、その点では、多少胸を張れるかも知れない。来年の夏頃から、全国の恩地研究家に周知し、真岡市に来訪して頂ければと、夢想している。
来年1月9日、宇都宮大学8号館大教室で、フレンドシップ事業美術シンポジウム「久保貞次郎と北川民次を語る」(参加費無料)が開催される運びとなった。第1部の語り手としてご招待に預かったので、久保研究所代表として参加を予定している。真岡市、芳賀郡の皆様も多数ご参加頂ければ幸いです。
何度も言及した事であるが、私は、久保氏の活動を10種に分類していて(①美術評論家②美術品コレクター③ヘンリーミラー絵画の紹介者④多くの芸術家の経済的思想的支援者⑤現代版画のプロデューサー⑥創造美育運動の創設者⑦小コレクター運動の提唱者⑧エスペラント学会の会長⑨跡見学園短大学長(教育者)⑩町田市立国際版画美術館館長)、私の久保研究所創設の主な動機は、正直言えば、⑦の「小コレクター運動」と⑧のエスペラント運動」であった。小コレクター運動とは、各自がオリジナル作品を3点所有し「生活の中に芸術を浸透させる」運動であり、エスペラント運動とは、世界共通語のエスペラント語の普及である。当時エスペランチストは、アナキズムや極左と関係を持つ者もいたが、久保氏は中道主義の立場をとった。戦前の中道主義は、当然反体制でもあり、体制側と左翼の両方から非難される一番厳しい立場であったが、終生中道主義を貫き通した。久保氏は、口に出さずとも、遙か数千年後、全ての人が芸術家である社会、全ての人が、哲学者で、同時に科学者で宗教家で、詩人で、褐色の肉体を持つアスリートである社会、国家も、戦争も、暴力も、差別も、貨幣も無い社会を密かに夢見ていたのではないだろうか。そしてこの夢は、私の40年来の夢でもある。
久保貞治郎研究所2015年12月月報(第69回)
~渡辺私塾美術館12月、常設展33点追加し223点に。第1回企画展「竹久夢二版画展」70点、第2回山下清版画展30点同時展示。計323点展示~
~12月20日名古屋大教授当美術館に来館、翌21日テレビ番組ディレクター来館~
12月追加作品33点のほとんどは、恩地孝四郎作「アルス日本児童文庫挿絵・表紙絵原画」で、残された僅かなスペースに展示した。いつの間にか恩地作品は77点を数え、もう少し追加すれば、小規模の恩地展になりそうだが、既に超過密状態で、今後の追加は困難かも知れない。3月から、少しずつ夢二作品と恩地版画作品を入れ替えて、最終的には、恩地作品300点展示を目論んでいる。第3回企画展「恩地孝四郎展」は10月に開催の予定だが、このようなみすぼらしい倉庫美術館に、恩地作品が300点も展示されようとは、都会の美術愛好家も夢想だにしないだろう。また恩地氏を充分に評価しえなかった事を終生悔やんでいた久保氏も、久保研究所が真岡市で恩地展を開くことになれば、天で、どれほど喜ぶことであろうか。
12月20日、名大大学院教授が来館され、2時間ほど作品を鑑賞しながら、二人で名大美学美術史時代の思い出話に花を咲かせた。私の方が5年ほど先輩で、師は同じ辻佐保子先生であり、兄弟弟子という事になる。一昨年県立美術館で開催された「瑛九展」について、真岡新聞に掲載して頂いた私の拙文が目にとまり、同窓生だと知って、連絡をくださった次第だ。教授のご専門は西洋美術史と博物館学で、エミール・バーノン、フェレックス・ジーム、シャルル・ラポステル、伝フォンタネージ等の西洋古油彩画の展示作品に見入っていた。
翌21日、テレビ番組ディレクターが来館された。東京国立近代美術館で1月13日から開催される「恩地孝四郎展」特集番組制作のための来館であった。恩地研究家は大学で数名、在野で数名しかおらず、私が、恩地作品、恩地稀覯本も蒐集している40年来の研究家である事は、中央では周知の事実であるようで、その事を聞きつけ、わざわざ東京から来訪された。やはり2時間ほど滞館し、「本の文明論」、「抽象絵画」についてお話を聞いて頂き、稀覯本撮影の申し出を快諾した。1月中旬に、収録のため5人で再来訪するとの事である。1月は多忙な月だが、東京国立近代美術館恩地展は過去最大の展覧会なので、なんとしても行かねばならない。
12月の久保氏関連蒐集品は、久しぶりに2点有り、安藤幹衛氏のリトグラフと、久保氏が他界するまで会長を務めていたエスペラント学会関連のガリ版刷り小冊子4冊であった。エスペランティストとしての久保氏については、極めて興味深い研究課題だが、後の機会に譲りたい。
久保貞次郎研究所2016年1月月報(第70回)
~渡辺私塾美術館1月34点追加し常設展257点展示(第3回企画展プレ展として恩地孝四郎作品111点展示)第1回、2回企画展と合わせて計357点展示~
~久保研究所代表、1月9日宇都宮大美術シンポジウムで講演~
~1月13日、NHKテレビ日曜美術館収録のため撮影クルー5名来訪~
~1月22日、ヘンリーミラー協会関連著名画家来館~
1月追加作品34点は、全て恩地孝四郎作品で、木版画15点と挿絵原画19点であった。木版画の中には、かつて米国人に蒐集され、1988年クリスティーズニューヨークオークションで日本人が落札し、再度海を渡って里帰りした「人体考察 肩」(1924年作)も含まれる。1月31日で、恩地作品も111点展示したので、1月31日以降、第3回企画展恩地孝四郎プレ展開催とした。
1月13日から東京国立近代美術館で「恩地孝四郎展」が開催されており、その特集番組制作のためNHK撮影クルー5名が来訪した。中央では、恩地研究家として多少は知られているのだが、何故わざわざ真岡市まで収録に来たかは不明である。著名な女性イラストレーターとの対談と、稀覯本撮影で5時間近くかかり撮影の丁寧さには驚かされた。対談では、女性が主役である事をすっかり忘れ、しゃべりすぎたので、私の出演場面はほとんどカットであろう。2月7日放映「NHK日曜美術館」(朝9時~10時)をご覧頂き、恩地孝四郎に少しでも興味を持って頂ければ、在野の一研究家として嬉しい限りである。
1月9日、宇都宮大学で、フレンドシップ事業シンポジウム「久保貞次郎と北川民次を語る」が開催され、久保研究所代表として、大学の先生方をはじめ150名近くの参加者の前で15分ほど話をさせて頂いた。久保氏の思想を中心に概略は伝えたつもりである。
1月22日、ヘンリーミラー協会関連の著名な画家が、お弟子さんを一人伴って、渡辺私塾美術館に来て下さった。開館日の日曜ではなかったが、東京からの来館であったので、特別に開館し、1時間ほど館内を案内した。やはり、他の絵描きさん同様、40数年前に描いた、私の訳のわからぬ不気味な絵に興味を抱いてくれた。(15年前出版の拙書、詩画集「潮に聞け」の原画24点)こそばゆい限りである。その後、一流の若手シェフが切り盛りする、久保観光記念館のレストラン「こころ」に案内した。地方なのに一級の料理に出会えて、さぞ驚嘆した事であろう。個人的には、その後高3生の面接が有り、更に高2英語の授業があって、忙しい1日であったが、充実した1日でもあった。
倉庫を改装しただけの貧弱な三流美術館であるのに、都会の文化人が少しずつ来館してくださるのは有り難い事なのだが、真岡市民、芳賀郡民の来館が少ないのは残念でならない。生活の中に芸術を浸透させる事が、真の豊かさなのだという久保氏の思想を継ぐ私としては、努力不足だと自戒の念を抱きつつ、皆様のご来館を願うしかない。(日曜日午後1時~4時、入館無料,当分オリジナル版画プレゼント)
久保貞次郎研究所2016年2月月報(第71回)
~渡辺私塾美術館2月21日第3回企画展恩地孝四郎展開催~
~恩地作品182点、第1回企画展竹久夢二展70点、第2回企画展山下清展30点同時展示他計428点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
2月の追加作品は67点であり、恩地企画展を開始したので、全て恩地作品であった。本来であれば、2階の夢二作品、山下清作品を撤去して、恩地作品を展示すべきなのだが、2階に上がったご年配の方々が、「わー、すごい。何か胸がすーとする」と言ってくださった事が何度かあったので、どうしても夢二作品、山下清作品を撤去できないでいる。それ故、1階の狭いスペースに、安売りスーパーのような展示スタイルで恩地作品を展示している。ご了承願いたい。
恩地作品の内訳は木版画63点、リトグラフ2点、油彩画2点、水彩画1点、絵皿1点、アルス日本児童文庫表紙絵原画54点、同挿絵原画59点で、特に表紙絵原画54点と挿絵原画59点は、世界でも当美術館でしか鑑賞出来ない作品なので、ご来館頂ければ幸いである。
恩地家から、入場券を頂いたので、1月13日から2月28日まで開催されていた東京国立近代美術館「恩地孝四郎展」を観に行った。恩地孝四郎は、日本より欧米の方が遙かに高評価である希有な作家であるから致し方ない事であるが、入場者は予想通り少なかった。圧巻は、具象木版画の最高傑作「萩原朔太郎像」の「恩地摺り」、「関野摺り」、「平井摺り」3点の同時展示であろう。恩地芸術を世界に紹介したオリバー・スタットラーは、形象社「恩地孝四郎版画集」の中で、「恩地の手による摺りには、詩が波の高鳴りのように響いている。関野摺りは散文である。平井摺りは学術書の脚注である。」と書いている。私は、渡辺私塾文庫ホームページの中で、「摺りの精緻さは同じでも、芸術性、詩的感動は順に低下していると言う意味に違いないのだろうが、何という鑑識眼の高さだろう。この3作を比較できるスタットラーの境遇、環境に嫉妬すら感じるのは私だけでは無いだろうが、その当時、恩地の近くいた日本人美術評論家諸兄は、スタットラーと比べて、何という見識眼の低さだろう。」と書いた。だがもうスタットラーの境遇に嫉妬する必要はない。目の前で好きなだけ比較鑑賞出来た。そして驚いた事に、スタットラーは、決して大げさではなかった。同じ版木を使いながら、芸術性の深み、高さが全く異なっている。恩地摺りは、朔太郎の苦渋と刻苦を表現しながら、摺りの濃淡によって存在の震え、喜びまで感得出来る。関野摺りは悲嘆と苦渋だけが感じ取られ、平井摺りは、平坦な苦渋のみしか感じられなかった。蛇足だが残念ながら、当美術館所蔵の萩原朔太郎像は平井摺りである。同じ版木でも摺りによってこれ程の差異が生ずるとは、版画は恐ろしい絵画表現である。
幾つかの余儀ない理由で恩地芸術を評価出来なかったため、終生後悔し続けた久保氏が、久保氏の故郷真岡市の久保研究所、当美術館が恩地展を開催し、微力ながら芳賀の地で恩地芸術の普及に携わっている事を知って、天でそっと喝采して下されば、当研究所としても幸甚である。
久保貞次郎研究所2016年3月月報(第72回)
~渡辺私塾美術館第3回企画展恩地孝四郎展200点展示~
~第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点同時展示、他計448点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
3月の追加作品は20点で、恩地作品18点と、アイオーのシルク作品1点、大津英敏リトグラフ1点であった。久しぶりに久保関連作品の、アイオー「虹の色」を追加できた。2月月報でも触れたが、第1回、第2回企画展をそのまま展示しているので、恩地作品200点を超えて展示するスペースはもはや無く、当分、恩地作品は200点でストップしようと思っている。どこかスペースを見つけて恩地稀覯本を50点ほど展示出来ればと思うのだが、それは無い物ねだりなのかもしれない。それでも、関東近辺の恩地孝四郎稀覯本収集家の中で、1月、当美術館が選ばれ、NHK日曜美術館がわざわ取材に来たということは、当美術館所蔵恩地稀覯本に、それだけの希少価値が有るという証左であるのだから、何らかの形で、公開する義務がある事は、重々承知している。
先日、妻の誕生日、久保記念館内のレストラン「こころ」に出かけた。以前にも述べたが、シャガールのリトグラフを数点無理矢理飾らせて頂いている関係上、時々利用させて頂いている。前もって予約を入れて、「お任せ」を注文すると、、若い優れたオーナーシェフが創作料理を提供して下さる。私は、顔に似合わず、生まれつき繊細な味覚を持っていると思い込んでいるので、味にはうるさい方だが、彼の料理には、彼の著名のお師匠さんに劣らず、彼独自の繊細さ・こまやかさが有る。妻の付き合いの関係で、都内の有名レストランに招待に預かり、何度か高級料理を食する機会を得たが、芳賀の大地の旬の素材を用いた彼の料理は、一歩も引けを取らない。
昨年の、久保氏ゆかりの芳賀教育美術展において、アイオーのオリジナル版画「ラブレターズ」を、700点副賞として当研究所から提供させて頂いたが、「ポスター貰いました」と言われる事がまだあるのは、残念である。あの作品は、ポスターでなく、アイオーの初期のシルクスクリーン版画で、画集にも掲載されているオリジナル版画作品なのだが、美術展表彰式時、言及が無かったため周知されなかったのだろう。まだ在庫が有るので、今年、また副賞提供の機会があれば、周知徹底を条件にしたいと横柄に考えている。そうそう、渡辺私塾美術館へ来館された方々に、プレゼントさせて頂いている版画も、勿論、その「ラブレターズ」である事は言うまでも無い。
久保貞次郎研究所2016年4月月報(第73回)
~渡辺私塾美術館第3回企画展恩地孝四郎210点展示~
~第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点同時展示、他計460点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
4月の追加作品は12点で、恩地作品10点と、清希卓油彩画、鹿見喜陌日本画であった。恩地小品があと100点近く有るので、稀覯本も含めて展示したいのだが、もはや満杯で、当分460点の展示で我慢しようと思っている。安売りスーパーのような展示スタイルで、美術館としては貧弱この上ないが、元々倉庫を改装しただけの美術館なので、贅沢は言っていられない。展示内容で勝負するしかない。手前味噌だが、都会の恩地研究家も、恩地作品210点には驚嘆の声をあげるに違いない。
来館者が少ないのは予想通りで、私の努力不足だが、日曜日真岡駅のSLを見に来たついでに来館して頂ければ幸いである。
4月24日、東京の硬派で社会派の出版社の社長兼編集長が、電車を利用してわざわざ来館された。恩地のアルス日本児童文庫表紙絵原画、挿絵原画を鑑賞しにいらっしゃったのだが、もう一つの来訪目的は、私への執筆依頼であった。多分私しか書けない主題なので、快諾したいところであったが、正式な論文である事、多忙である事を考慮し、検討致しますというお返事のみ差し上げた。「なんでも鑑定団」出演依頼、NHK日曜美術館取材等は有っても、正式な論文執筆依頼は初めてであり、嬉しい限りだが、安請け合いは出来ない。
当美術館には久保氏関連作品が15点展示されている。内訳は、川崎満孝アクリル画2点、北川民次木版3点、瑛九エッチング1点、竹田鎮三郎リトグラフ3点、アイオーシルクスクリーン5点、ヘンリー・ミラーリトグラフ1点で、真岡市の久保記念館よりは遙かに少ないが、まだ未展示久保関連作品が多少有るので、第4回企画展として久保関連作家展も考えている。
人類の進化の指標は、経済、物質、軍事の豊かさではなく、生活に対する芸術性の浸透度であると説いたのは久保貞次郎であり、その実践が「小コレクター運動」であった。「小コレクター運動」とは、一人一人がオリジナル芸術作品を3点所蔵し、生活の中に芸術を浸透させる事であり、60年前、真岡の地で始められた運動である。この運動はいまだ朽ち果ててはいない。当美術館来館者に、アイオーのオリジナル版画をプレゼントさせて頂いていることも、この運動のささやかな継承なのだから。
久保貞次郎研究所2016年5月月報(第74回)
~渡辺私塾美術館第3回企画展恩地孝四郎220点展示~
~第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点同時展示、他計470点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
5月の追加作品は10点で、全て恩地孝四郎アルス日本児童文庫挿絵原画であった。もう追加展示出来るスペースは無いと諦めていたが、娘が描いた80号油彩画5点の上に、恩地作品10点を置いて展示した。英国にいる娘も、自分の作品が、世界の恩地作品10点と並んで展示されていると知れば、光栄に思うに違いない。
久保関連作品は、調べてみたら50点ほど有るので、第4回企画展として久保関連作家展を考えていたが、手強い強敵が私の心の中に現れた。昭和7年生まれの謎の型染め作家、神崎温順だ。昭和30年、土佐和紙に魅了された神崎は、高知市に移り住み、魅力的で芸術性の高い型染め絵本を数多く刊行し、その後消息不明になった謎多き作家である。私は、40年前から、その芸術性の高さに惹かれ、作家の詳細について不明のまま、型染め限定本を少しずつ蒐集してきた。(インターネットで、渡辺私塾文庫27番、神崎温順関係本参照)仕事で消耗した時、神崎作品を見つめ、何回となく清らな気持ちに立ち返ることが出来た。来年の第4回企画展を何にするかはまだ決めかねている。
手前味噌になるが、先日東京から来館された方が、「建物は強烈だが、恩地作品220点、他計470点をこんな地方で観られるなんて奇跡だね、それに入館無料で、オリジナル版画のお土産付きなんて、有り得ないよ。館長さん、どうかしちゃったんじゃない?」と冗談をおっしゃった。私は、「強烈というのは、強烈に貧弱だという意味だと思いますが、私も同感です。最後のお尋ねについては、どうかしちゃっていません。至って、頭脳明晰です。私は、久保貞次郎研究所代表もしていますので、久保さんの意志を僅かながら継承する意味で、この形を取っています。それに、偉そうに聞こえるかも知れませんが、私が生まれ育った地元への恩返しになればとも思っています」と本音を吐露した。彼は、「いやー、たいしたもんだ」と言って笑ったが、その笑顔の中には、何の得にもならないのに、全く理解出来ない、という不信の笑みがほんの少し混じっていた。無償の行為が理解されにくい今の時代では、もっともな事なのだが、本音だから仕方が無い。
私は、不定期で、真岡新聞に、「真岡賛歌」を連載していて、5月20日号掲載の真岡賛歌第9回は、「二宮尊徳」であったが、第10回は真岡の花火について書こうと考えている。その時に久保氏が、真岡の地で始めた「小コレクター運動」に触れる予定だが、久保氏の思想、活動は多様であり、未だ全容は闇の中にある。当研究所でも時間をかけて、研究を進めていく所存だ。私個人は、久保氏の思想の中で、「小コレクター運動」を注目していて、遙か数千年後、「全ての人が芸術家である社会」に向けての、人類の第一歩であったのではと思っているのだが、詳しい事は後の機会に譲りたい。
久保貞次郎研究所2016年6月月報(第75回)
~渡辺私塾美術館第3回企画展恩地孝四郎230点展示~
~第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点同時展示、他計480点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
6月の追加作品は、5月と同様、10点で、全て恩地孝四郎アルス日本児童文庫挿絵原画であった。展示スペースは皆無に近かったが、私が15年前に文芸社から出版した「詩画集 潮に聞け」の挿絵原画24点の間に、恩地作品を無理矢理展示した。世界的芸術家恩地孝四郎挿絵原画と、全く無名の田舎のおじさんの、訳のわからぬボールペン原画が一緒に展示されていて、恥ずかしい限りだが、二種の異形な作品群が妙に共鳴していなくもない。「潮に聞け」の原画は、44年前、名大の美学生時、深夜、やむにやまれぬ思いで、数百枚書き殴ったボールペン画の一部で、詩画集に所収した24点以外は全て廃棄してしまったと思う。稚拙だが、マグマの様に噴出した24点の拙作をご覧になりたい方は、是非来館なさって頂ければ幸いである。
当美術館の場所が解りにくいとよく言われるので、簡単に説明させて頂く。真岡駅東口からSL館の方、南に下ってすぐT字路を左折し、日赤、真岡女子高に向かう路を10メートルも行かない右側に、「渡辺私塾真岡駅前校」があり、その奥の倉庫風建物が当美術館で、安売りスーパーのような展示スタイルの極貧の美術館ですので、お解りになると思いますが、発見できない時は、0285-83-3447までご連絡くださいませ。詳しくご案内致します。
久保研究所の現在の活動について触れてみたい。まず第1は、当美術館の運営であり、入場無料で、当分オリジナル版画プレゼントを継続実施の予定である。全ての人が3点のオリジナル芸術作品を蒐集し生活の中に芸術を浸透させ、全ての人が感性的に芸術的に進化するという「小コレクター運動」を提唱し、芸術の普及に一生を捧げた久保氏も喜んでくださるに違いない。
第2は、久保氏の思想の研究と紹介で、原則、月報内で報告していきたい。月報は、ホームページで公表し、真岡新聞に掲載し、最後に渡辺淑寛著作集に所収している。
第3は、久保氏が創設に関わった「芳賀教育美術展」の支援で、副賞を提供させて頂いてから、今年で7年目になる。昨年は入賞者全員に、アイオーのオリジナル版画700点を進呈させて頂いた。今年度も同じ作品700点を既に入手し、昨年同様進呈させて頂く予定である。
第4に、久保研究所代表として、真岡新聞に、「真岡賛歌」を掲載し真岡市を応援する事。現在第10回まで発表出来た。タイトルのみ、列記すると、?神の魚の住む川、②井頭公園の薔薇の園、③いちごてれびと真岡新聞、④久保記念観光文化交流館、⑤SLの走る町真岡、⑥真岡木綿小論、⑦フルーツの町真岡、⑧桜咲き、菜の花香る町真岡、⑨二宮尊徳の生きた町真岡、⑩花火が夜空を彩る町真岡。(お問い合わせは、久保研究所℡0285-83-3447まで)今後粘り強く、地を這うように継続していきたいと思っている。
久保貞次郎研究所2016年7月月報(第76回)
~渡辺私塾美術館第3回企画展恩地孝四郎232点展示~
~第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点同時展示、計482点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~(8月14日はお盆休みで休館) 代表 渡辺淑寛
7月の追加作品は2点で、展示スペースが皆無に近い中、何とかアルス日本児童文庫挿絵原画2点を展示出来た。あと18点展示して、恩地作品250点、展示作品数計500点で、恩地作品が丁度半分になり、渡辺私塾美術館のサブタイトルを恩地孝四郎美術館にすることも考えているが、展示スペースをどう創るか思案中である。
去る7月29日号真岡新聞に、久保研究所代表、美術館館長として、「真岡賛歌その11」を掲載させて頂いた。「祭りの町 真岡」というタイトルで、大衆の側からの祭り論を少し書かせて頂いた。大衆と権威が対立する場面の多い現代社会において、宗教における「神の元での平等」と同様、「祭りの元での平等」の無礼講の中で、祭りこそが、大衆と権威の利害を超える希有な創造的空間なのだ、という趣旨なのだが、一読して頂ければ幸いである。
久保研究所との関連性は薄いが、渡辺私塾文庫所蔵の江戸木版本85冊揃い「集古十種」について重要な事実が判明した。当文庫のホームページを見て、元弘前市図書館館長の方から、「集古十種」の多くのページに押印されている「奥文庫」の印は、弘前藩(津軽藩)第九代藩主津軽寧親の印章であると、お知らせ頂いた。18年前購入時、「奥文庫」について気になり、何人かの研究者にお尋ねしたのだが、皆目わからず、そのままになっていた。さすが地元の知識人、「奥文庫」の印章を見て、すぐに弘前藩主の旧蔵品であると看破なさった。「集古十種」の来歴が判明し、稀覯本コレクターとして嬉しい限りである。近く、青森県の新聞社が、取材に来るという。「集古十種」については、以前テレビ局から取材を受けた事があるので、当文庫の蔵品の中では、出世頭であろう。透き通るような美しい木版画本85冊で、入手するのに25年を要したいわく付きの稀覯本である。詳しくは、「渡辺私塾文庫」ホームページ?「集古十種」を見て頂ければ幸甚である。数年後当美術館で、企画展として江戸和本展の開催も考えており、実現すれば、その時展示したい。
久保氏が江戸本・和本を蒐集していたという資料は無いようだが、もし「集古十種」を一瞥していたら、その資金力で、江戸和本の一大コレクターになっていたかも知れない。
久保氏の多くの活動の中で、研究が進んでいない分野は、「エスペラント活動」と、「晩年の精神世界」であるが、急がず着実に研究していこうと考えている。
久保貞次郎研究所2016年8月月報(第77回)
~8月6日久保氏の取材で読売新聞記者来宅、同日「集古十種」の取材で青森県陸奥新報記者来宅~
~8月20日「集古十種」の調査研究で、弘前市の専門家来宅~
~渡辺私塾美術館恩地孝四郎作品250点展示、他計500点展示~
~入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施、日曜日午後1時~4時開館~ 代表 渡辺淑寛
8月は久し振りに久保氏関連本を入手出来た。「ヘンリー・ミラー協会会報」第5号と第7号で、5号には久保氏の小論「ついにジョン・マリンが日本に到着した」と「「ヘンリー・ミラーの素直さ」の2編が、7号には「ホイットマンのこと」が所収されている。大文豪ヘンリー・ミラーの絵を世界に紹介したのは、久保氏の功績の一つである事は周知の事実である。ヘンリー・ミラーは、文章表現に行き詰まると、ほとばしるように絵を描いたと言われている。当美術館には、ピカソの「犬を連れた少年」、マチスの「ダンス」、ミラーの「ブルックリン子」のリトグラフが3点並んで展示されているが、ミラーの作品は、両天才の傑作に一歩も引けを取らないと、私見だが確信している。一度来館なさり、自らの目で確かめて頂ければ幸いである。
8月6日、青森県陸奥新報社東京支社の記者が、「集古十種」の取材で来宅された。7月月報で言及したが、当文庫所蔵の「集古十種」85冊全揃いが、弘前藩第九代藩主津軽寧親の旧蔵品であると判明し、わざわざ来訪された。陸奥新報創立90周年記念号に掲載なさるとの事で、恐縮しながらも喜びに浸っている。専門家の調査では当文庫の「集古十種」は、日本でも希有な最古の版の全揃い本のようで、「奥文庫」の押印で、津軽藩主旧蔵本であると判明した。44年前名大の美学美術史生であった時、どこかの博物館で「集古十種」と邂逅し、江戸木版画本としての芸術性の高さに感動し圧倒され、それ以来26年の歳月を要し、18年前東京神田神保町において、多くの幸運と強運で、奇跡的に入手出来た。この「集古十種」が、津軽藩主旧贈品という由緒ある稀覯本であると解ったのは、何と18年も経った本年7月6日の事である。ホームページに掲載した「奥文庫」の押印を見た弘前市元図書館長の方から,、喜びと驚きに満ちた熱いメール、お手紙、お電話を頂いた事が、嬉しい騒動の端緒であった。元図書館長の思い入れは相当なもので、8月20日、はるばる弘前市から来宅された。私も熱い思いにほだされ、できる限りのおもてなしをさせて頂いたのは言うまでも無い。「集古十種」顛末記については後日に譲りたい。
同日、久保氏の取材で、読売新聞記者が来宅された。翌日久保観光記念館を二人で訪問し、読売新聞8月14日号23面で大きく掲載して頂いた。一読して頂ければ幸甚である。その記者は、知性と教養に溢れ、哲学や文化についても語り合い、楽しい時を過ごす事が出来た。
パズルを解くように、展示スペースを見つけ、恩地孝四郎作品を追加して250点展示とし、第1回企画展竹久夢二70点、第2回企画展山下清30点他150点計500点が展示出来たので、それを記念し、当美術館のサブ名称を「恩地孝四郎ミュウジアム」とした。来館者は少ないが、北関東の外れに、恩地作品250点を展示した入場無料の美術館があったという事は、後世長く語り継がれることであろう。
久保貞次郎研究所2016年9月月報(第78回)
~久保氏没後20周年を記念し、渡辺私塾美術館29日(土)・30日(日)連続開館(午後1時~4時)。入場無料、当分オリジナル版画プレゼント継続実施。アイオーのオリジナル版画を以前差し上げた、29日・30日来館者様には、別作家のオリジナル版画プレゼント~
~渡辺私塾美術館恩地孝四郎作品251点展示(世界有数の恩地コレクション)他計502点展示
~当美術館、真岡市街角美術館に認定~ 代表 渡辺淑寛
今月10月31日は、久保氏没後20周年記念日にあたり、久保研究所・当美術館でもささやかな記念行事として、29日(土)・30日(日)連続して開館する。更に、以前アイオーのオリジナル版画を差し上げた来館者様には、29日・30日、別な作家のオリジナル版画をプレゼントさせて頂く予定。些細な行事ですが、一人一人がオリジナル芸術作品を3点以上蒐集し、生活の中に芸術を浸透させるという、60年前に久保氏が提唱した「小コレクター運動」の思想を、僅かでも後世に伝えてゆきたいという、微力な私に、今出来るささやかな一歩です。
9月の久保氏関連新蒐集品は、久保氏献呈サイン入り書籍「私の出会った芸術家達」と、竹田鎮三郎水彩画「メキシコ風景」で、竹田氏の水彩画は大作で、かなり希少であるため、展示作品番号502番として、早速当美術館に展示した。
9月20日第30回芳賀教育美術展最終審査会に審査員として出席した。今回は、創造美育関連の審査員は少なかったが、大学の先生方が数名参加し、新鮮な審査会であった。創美関連審査員が少なくなったと言っても、ほとんどの審査員は創美理論を感覚的に習得しており、今までと変わらない創造性に富んだ作品が入選を果たした。他界なさったり、ご高齢で出席出来なかった二人の長老がいても、知事賞は同じ作品になったであろう。久保研究所で副賞を提供させて頂いて7年目になるが、今年も、昨年と同作品のアイオーのオリジナル版画を620点用意させて頂いた。更に、昨年同版画を受け取っている2年連続入賞者の方には、別な作家のオリジナル石版画89点が準備出来た。これも久保氏の「小コレクター運動」の意志を継ぐささやかの一歩である事は言うまでも無い。
当美術館展示作品数がいつの間にか500点を超え、狭く乱雑すぎて、私でも何処に何が展示されてあるか解らなくなってしまったので、全作品に展示番号表を添付した。また数日前から、正確な展示作品目録を作り始めたが、かなりの作業で数ヶ月かかるかも知れない。絵画の額入れ、展示など全て私一人の手作業なので、稚拙な美術館になってしまったが、かえって自慢でもある。自慢ついでに、恩地作品251点を、世界有数の恩地コレクションと書いたが、誇張では無いと思う。恩地作品251点を常設展示している所は、多分希有であろう。本年2月7日放映のNHK日曜美術館「恩地孝四郎特集」番組で、都会の美術館や有名恩地コレクターを尻目に、5人の撮影クルーが、地方の当美術館までわざわざ足を運んだという事実は、その証左であるのかも知れない。
当美術館が真岡市の街角美術館に認定された。真岡市に、少しでもお役に立って頂ければ幸いである。9月29日読売新聞記事の見出しは「真岡 美術館のまちに」であった。心底芸術を愛する日本国民の数は想像を遙かに超えて少ないのが現実だから、「美術館のまち」になるのは多少時間が必要だが、真岡市には世界屈指の「瑛九コレクション」が有る。くじけること無く地道に啓蒙普及・PRを続ければ、真岡市は、必ずやSLのまち、美術のまちになるに違いない。
久保貞次郎研究所2016年10月月報(第79回)
~久保氏没後20周年記念日10月31日、久保記念館で座談会が開催される~
~渡辺私塾美術館、恩地作品258点他計512点展示、入場無料、日曜日午後1時~4時開館、当分オリジナル版画プレゼント継続実施(以前アイオーの版画を差し上げた来館者様には別作家のオリジナル版画プレゼント)~
~10月の久保氏関連蒐集品は6点~ 代表 渡辺淑寛
去る10月31日久保氏没後20周年記念日に久保記念館で座談会が開催され、座長として参加させて頂いた。出席者は、久保氏御令嬢3名、創造美育協会会長、久保氏最後の弟子の洋画家、元県立美術館学芸課長、文星芸術大学教授、創美理論を実践している幼稚園園長並びに理事、宇佐見氏御遺族、真岡青年会議所現理事長、来期理事長、新聞記者2名他計30名ほどが参加し、豪華な顔ぶれで有意義な座談会であった。その後、出席者による久保家のお墓参りが予定されていたので、ありきたりの座談会では、久保氏に顔向け出来ないと考え、久保氏の業績、小コレクター運動とエスペラント活動の思想的関連、人類の遙か1万年後の未来についてなど、座長としてやや僭越であったが、話をさせて頂いた。帰り際に、大学教授が、「地方で、このようなレベルの高い座談会が開かれるなんて信じられません」とお話になっているのを耳にし、久保氏もさぞ喜んでいらっしゃるのではと思いを馳せた。また、私もなんとか責任を果たせのではとの思いで安堵した。その後、前述した方々の多くが、当美術館の見学を希望なさったので、開館日ではなかったが、来館して頂き、ご案内させて頂いた。
久保氏没20周年記念として、「公刊月映1号」と「月に吠える」から、木版画を切り離し、当美術館に7作品を展示した。木版画を切り離すという事は、その稀覯本の商品価値を激減させる事になるので、愛書家として相当の決断を要としたが、秘蔵しておくより、多くの方に観てもらう事を優先した。特に「月映」は、今後古書市場に現れる事も無いだろうし、再度の入手も叶わないだろう。
あれだけの狭い貧弱な美術館に展示作品数512点とは奇跡に近いが、恩地作品も258点を数えるに至った。今年1月の東京国立近代美術館「恩地孝四郎展」では、世界中から集めた400点余が展示されたが、地方の極貧弱小美術館で恩地作品が258点も常設されていようとは、都会の美術関係者は到底信じられないであろう。恩地作品の常設展示数からすれば世界屈指と言っても決して過言ではないと思う。
10月29日、30日のみ、以前アイオーのオリジナル版画を差し上げた来館者様には別作家の版画をプレゼント、とお知らせしたが、当分の間、今後の日曜日の開館時にも、このプレゼントの継続を決定致した。ご来館心待ちにしております。
10月の久保氏関連蒐集品は6点で、久し振りに盛況であった。真岡市の版画家浅香公紀氏から、ご存命中直接頂いた木版画本1点は所蔵していたが、今月浅香氏の他の木版画本を、なんと2点も新蒐出来た。一目見て浅香氏の作品と解る綺麗で純朴な木版画がちりばめられた稀覯本は、私の宝物で、疲れた時は3冊をそっとひもといて、心の潤いを取り戻している。他の2点は、竹田鎮三郎氏の木版画と水彩画で、水彩画は希少だが、私には、木版画の方が迫力があり、芸術性が高いと思えてならない。他1点は、久保氏献呈署名入り本1冊で、最後の1点は、1997年日本経済新聞社刊「瑛九作品集」である。瑛九、アイオー、難波田龍起、細江英公の4作品入り限定100部の超豪華本で、19年前定価33万円であったので、とても手が出なかった。そして19年間辛抱強く待った甲斐があってか、ついに運良く10分の1の値段で購入できた。果報は寝て待てという格言は、どうも本当らしい。
久保貞次郎研究所2016年11月月報(第80回)
~11月14日、久保研究所代表、ラジオ栃木放送出演~
~渡辺私塾美術館、11月20日より新キャンペーンスタート、1度目、2度目、3度目来館でそれぞれ別なオリジナル版画プレゼント,恩地作品261点他計 522点展示、入場無料、日曜日午後1時~4時開館、~
~11月久保関連蒐集品は2点~ 代表 渡辺淑寛
去る11月14日午後1時、ラジオ栃木放送のリポーターが渡辺私塾美術館を訪れ、10分間ほど生放送の形で、久保研究所代表、美術館館長としてインタビューに応じた。その中で、久保氏の業績についてもほんの少し触れることができた。久保氏の業績について、私は10項目に分類しているが、全てを詳細に解説するには数時間を要するであろうから、小コレクター運動について少し触れ、当美術館開設理由との関連を述べるにとどまった。久保氏の業績と思想については、今後一層の研究が進み、将来正当に評価される時が、必ずや来るであろう。当研究所がその一助になれば幸いである。
当美術館で11月20日から、新キャンペーンがスタートした。初めての来館者様には、アイオーのオリジナル版画をプレゼントさせて頂き、2度目の来館時には別作家のオリジナル版画をプレゼント、3度目の来館時にも別作品のオリジナル版画をプレゼントをさせて頂くという新キャンペーンである。入場無料で、惜しげもなくオリジナル版画をプレゼントとは、館長、ついに錯乱か、と思われる方もいらっしゃるかも知れないが、いたって正気である。昨年5月24日の開館時から温めていた思いを実現させただけである。入場無料の美術館開設は、40年来の夢であったが、オリジナル版画3点のプレゼントは開館時からの夢であり、プレゼント作品を多数揃える必要から、4,5年はかかるだろうと思っていた。しかし不思議なもので、私利私欲の活動でない、利他的な無償の行為には、天も味方をしてくれるようで、同じ作家の同一作品を多数入手出来た。限定150部の版画を100部蒐集する事は、奇跡に近いが、現に、その奇跡が何度も起こっている。私の経済状況を心配して下さる友人も居なくは無いが、美術商に、多数の版画を廉価で入手する名人ですね、と何度となく言われたことがあるくらいだから、大丈夫である。私の私費で充分やり繰り出来ているし、そうでなくては継続困難だと、重々承知しており、ここ数十年遊興費零で、しっかり覚悟も決めている。
版画3点のプレゼントは、もちろん、久保氏の小コレクター運動のささやかな継承を意図したものである。久保氏は、一人一人がオリジナル作品3点以上を蒐集し、生活の中に芸術を浸透させ、精神生活を豊かに潤い有るものにし、それが人類の進化に繋がるという趣旨の「小コレクター運動」を展開したが、私も、オリジナル版画3点プレゼントという形で、僭越だが久保氏の思いを継承しようと思っている。この新キャンペーンは、現在の版画の在庫から考えて、2,3年は続けられそうだし、何とか続けなければならない。今後もきっと天が味方してくれるであろう。
11月の久保関連蒐集品は刀根山光人の版画2点で、秀作なので、スペースを見つけて当美術館に、何とか展示した。利根山氏も、久保氏が支援した作家の一人で、茨城県結城市のご出身であり、10月31日久保氏没20周年記念の座談会に出席なさった結城市の幼稚園関係者が熱心に研究なさっている作家である。
蛇足ながら、当美術館は、台町本校高等部塾生の面接にも利用していて、版画プレゼントは、分け隔てなく一般の来館者様と全く同様の扱いであり、まだ面接をしていない高等部塾生は、どんどん来館して、版画を受け取って頂きたい。
久保貞次郎研究所2016年12月月報(第81回)
~渡辺代表著作集第6巻,真岡新聞社より刊行~
~渡辺代表、株式会社ミツトヨ清原生産部で講演~
~渡辺私塾美術館、恩地孝四郎作品274点他計543点展示、来館者様に版画プレゼント継続実施(日曜日午後1時~4時開館)~ 代表 渡辺淑寛
2016年末、拙本第6巻著作集を真岡新聞社より出版させて頂き、高3生卒業式で、卒業生に第1巻から6巻までの計6冊を全員に贈呈できた。第6巻は卒業式前日完成という離れ業だが、間に合ってほっとしている。今は一顧だにされない著作集だが、百年後には、何人かの研究者が現れて、正当に評価して下さるのではと内心密かに期待している。この世に生ある限り、許されるのであれば、後巻の出版継続を固く決意している。第6巻のお勧めは、真岡賛歌7篇と恩地孝四郎賛歌8篇だが、前者は比較的平易な文章表現を心がけた。恩地賛歌8篇は難解で、今の日本でご理解頂ける方はほとんどいないであろう。1巻から5巻までと同様、娘の油彩画が表紙絵になっていて、私個人としては贅沢の限りである。仰々しく著作集などと銘打って刊行出来る今の自分の恵まれた境遇を、天に、心底より感謝致したい。
1月8日渡辺私塾美術館来館者様先着10名様に、オリジナル版画と一緒に第6巻をプレゼントさせて頂いた。機会があれば、何かの記念日に、今回と同様、著作集プレゼントを企画したい。
去る12月13日、株式会社ミツトヨ清原生産部で講演を依頼され、無償という条件でお引き受けし、久保研究所代表として講演させて頂いた。受験について、来世の可能性について、久保氏の思想について、1万年後の人類の夢である、全ての人が芸術家である社会について、簡単に説明させて頂いた。突拍子もない演題で、百名を超える参加者の多くが、最初は目を丸くしていたが、最後には私の真意が多少なりとも伝わったのか、心のこもった拍手を頂いた。私のような訳のわからぬ者に講演を依頼し、訳のわからぬ話に熱心に耳を傾けるミツトヨという会社の懐の深さ、柔軟性、潜在能力、将来性に、逆に私の方が感銘を受けたというのが、偽らざる心境である。誠実な担当の方々、またその上司の方々と、またお会いできる事を楽しみにしている。
12月中、展示作品がまた増えて、21点追加展示され、計543点の展示となった。内訳は、恩地作品13点、私の学生時代のペン画3点、栃木県出身で日本画壇の重鎮であった米陀寛の作品2点、竹田鎮三郞のリトグラフ大作、神崎温順の型染作品、大貫松三の油彩画である。大貫作品は2005年、平塚市美術館で開催された「大貫松三展」の渡辺私塾文庫出品作で、8号の小品だが、異彩をを放つ少女像の名品である。2階に展示されているので是非足を運んで頂けたら幸いである。あの狭い空間に543点展示とは狂気の沙汰だが、狂気ついでに新年1月中にあと10点ほど追加展示しようと考えている。今になって決めたことだが、当美術館は、一旦展示した作品はそのまま展示し、少しずつ追加展示の形をとろうと思っている。入場無料、来館者様全員に版画プレゼント、日曜日午後1時~4時のみ開館と異例ずくめなのだから、展示スタイルも異例であって、何ら不思議では無いと自分に言い聞かせている。
新年は1月8日から開館で、塾生の面接希望者も来館して面接を受けることが出来る。多くの美術品に囲まれて、自分の将来について話し合うのもなかなか風流ではないだろうか。
久保貞次郎研究所2017年1月月報(第82回)
~渡辺私塾美術館、恩地孝四郎作品302点他計583点展示、来館者様に版画プレゼント継続実施(日曜日午後1時~4時開館)~
~久保貞次郎研究所に版画100点展示~ 代表 渡辺淑寛
1月1日は休館にさせて頂いたので、お正月休みを利用し、40点追加して展示作品数は583点となった。40点のうち28点は恩地作品で、念願の300点展示を実現する事が出来た。恩地作品300点の常設展示は、世界でも希有であり、極貧の美術館だが、21世紀初頭、北関東の小都市に、恩地作品300点を常設展示する極小の美術館があったという事は、後世、驚きを持って語り継がれるであろう。
残りの12点の内1点は、テオドール・ルソーの鉛筆画「森の中の村」で、1977年サザビーズの証明書付きだが、名前だけの粗末な作品であるという誹りは免れないと自分でも思っている。他の1点は、私が、学生時代の45年前に描いた「宇宙の全ての事物達」という、1972年作の訳のわからぬボールペン画であるが、ほんの一部の人に、不思議にも熱狂的に人気がある。他は吉原英雄リトグラフ3点、米陀寛の日本画、畦地梅太郎の木版画、草間彌生のリトグラフで、残り4点は、久保関連作品であり、竹田愼三郎リトグラフ2点、アイオーの版画小品、安藤幹衛のリトグラフである。安藤油彩画大作7点は真岡市に寄付させて頂いたので、安藤作品は初展示であるが、竹田作品は全7点の展示で、大作秀作も多く、是非来館なさって鑑賞して頂ければ幸いである。
1日で583点全てを鑑賞する事はやや困難に違いないので、今日は誰々の作品を観るのだと決めて、来館なさるのも一方法なのかも知れない。1度目の来館者様、2度目の来館者様、3度目の来館者様にそれぞれ異なった版画のプレゼントは、愚かにも、まだ継続実施中である。
また、お正月休み中に、先の震災で破損した数百点の作品の修理を始めた。その中で比較的状態の良い版画作品100点を選んで修復し、口ノ町公園近くの久保貞次郎研究所に展示してみた。時間を見つけて週に3,4度訪れ、額縁の中の新たな世界に見とれながら、たった一人の鑑賞者として至福の時を過ごしているのだが、数年後の公開も考えている。久保研究所には、約2000点の芸術関連洋書も置かれているので、将来は真岡市の隠れた文化研究所も兼ねれば、と夢見ても居る。
久保氏が稀覯本のコレクターであった事はあまり知られていないが、高名な美術評論家であったので、贈呈本も多く、羨ましい稀覯本蒐集家であった。久保氏帰天後、K氏コレクションという名で、10数年前東京で数回稀覯本オークションが開催され、私も可能な限り参加し、その時に入手出来たのが、当研究所所蔵の約百点の久保旧蔵本である事は言うまでも無い。
久保貞次郎研究所2017年2月月報(第83回)
~渡辺私塾美術館 恩地孝四郎312点他計604点展示、来館者様にオリジナル版画プレゼント継続実施(入場無料、日曜日午後1時~4時開館)~
~久保貞次郎研究所に版画200点展示~(再来年公開予定) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
1月末より21点増えて全部で604点の展示となった。あれだけの狭いスペースに604点とは、常軌を逸しているが、来館者様に出来るだけ多くの作品を観てもらいたいという私の展示思想のなれの果てだと、一笑に付して頂ければ幸いである。新展示作品21点のうち4点は、真岡市出身の優れた木版画家浅香公紀氏の木版挿絵本3点「四季」、「木の実草の実」、「旬」と、木版画「ロンドン・ビッグベン」で、浅香氏の木版画を目にすると、心の奥の奥まで染み渡り、文字通り自己存在丸ごと洗われる思いがしてならない。浅香氏から直接贈呈して頂いた木版画98点を、3年前真岡市に寄贈させて頂いたので、当美術館には浅香氏の作品は無かったが、数十年前木版挿絵本3点も頂いたことを思い出し、必死に捜して、同時に見つけた1点と共に展示した。好きな作家の作品展示は嬉しい限りだ。
他に、笹島喜平水彩画「こけし」、草間彌生水彩画「幻の花」、1950年ムルロー工房作、ロートレックのリトグラフ「ドイツのバビロン」、更に、恩地孝四郎の弟子の関野準一郎の木版画4点、最後に「アルス日本児童文庫第53巻挿絵原画」10点である。1月月報でも触れたが、恩地作品312点を常設展示している所は世界でも希有であろうから、恩地研究家のご来館を期待したい。
恩地氏存命中、久保氏が、恩地作品を高評価しなかった事について、終生強い悔恨の念を抱いていたという事は何度か触れたが、恩地作品312点常設展示を天から見て、「頑張ったね」と褒めてくれるであろう。しかも、入場無料で、3回来館の度に、計3点のオリジナル版画がプレゼントされるのをご覧になって、3点以上の作品を手にし、生活の中に芸術を浸透させるという「小コレクター運動」を提唱なさった久保氏であるから、天で拍手なさっているに違いない。
1月月報で、久保研究所に版画100点を展示した旨、お知らせしたが、休みを利用して、破損箇所を修理し、ガラスの汚れをしぶとく落として、計200点展示した。超廉価の版画作品のみで、資産価値は零に近いが、、全作品、作者一人一人の熱い思いに溢れ、何度見ても飽きる事はない。無名作家の作品ばかりだが、有名、無名などどうでも良い。我々には不可視の色、形、世界を、我らの眼前に表出させる事が、芸術家の仕事であり、その作品が芸術作品なのである。未だ、この200点の鑑賞者は、私と友人の二人のみであるが、震災で破損した作品を粘り強く修理し、久保研究所の展示作品数も少しずつ増やしていこうと考えている。駐車場が2台分しかないので、どのような公開方法が可能なのか考慮中であるが、再来年をめどに、何とか公開したい。
久保貞次郎研究所2017年3月月報(第84回)
~渡辺私塾美術館計627点展示(恩地孝四郎作品315点)、来館者様にオリジナル版画プレゼント継続実施(入場無料、日曜日午後1時~4時開館)~
~久保氏関連本3月に4点入手~ 久保研究所代表 渡辺私塾館館長 渡辺淑寛
当美術館の展示数が、2月末より23点増えて計627点の展示となった。あれだけのスペースに627点とは、もう狂気の沙汰だが、狂気が狂気を呼んで、もはや留まるところを知らない。狂気ついでに、このまま突き進んでみようと思っている。新展示作品は、恩地氏のお弟子さんの関野準一郎木版画7点、竹久夢二版画4点、生野一樹銅版画2点、恩地木版画3点、入江酉一郎日本画、北村巌油彩画、角浩石版画、笠井正博シルク、森義利合羽摺、最後に草間彌生作品2点である。
60年前、草間氏が全くの無名画家であったとき、東京銀座の求龍堂画廊での個展で草間作品を購入したのは、作家の川端康成と久保貞次郎だけであった、という話もあるが、私も20数年前草間作品がまだ廉価であった時、気に入って4点購入していた。それらが当美術館で現在展示されている4点である。
恩地木版画3点は、1点は後刷り作品だが、2点は1924年発行の「詩と版画」から切り取ったオリジナル作品で、昨年開催東京国立近代美術館の恩地展でも未出品木版であり、希少作品である。稀覯本「詩と版画」は30年前に1冊入手し、最近もう1冊所蔵出来たので、手を震わせながら細心の注意を払って2点の添付木版画を切り取り、額に入れて展示した次第だ。恩地作品315点常設展示は、世界でも希有だ、と言っても決して吹聴の誹りを受けないであろう。
3月中に、久保氏関連本を4点入手した。1点は、1970年発行「工作美術館第6巻・ファミリー工作」(久保貞次郎監修)で、久保氏の児童美術教育の範疇に、立体造形美術も含まれていたことがうかがい知れる。2点目は、当美術館に何度も来館されている知人から頂いた「真岡小学校PTA新聞こだま復刻版第1巻」(平成3年)で、久保氏の奥様加世子氏がPTA副会長をなさっていた関係上、昭和30年開催「久保コレクション世界名画展」等の記事が掲載されている。3点目は、久保氏最後の弟子、洋画家川崎満孝氏の個人雑誌「黙想」1巻~6巻、9巻で、氏の思想性に満ちあふれた雑誌であり、今度会った時に、欠号を譲って頂こうと思う。4点目は、久保氏が支援した森義利氏の「合羽版作品集」である。この作品集には、当美術館で展示中の、1973年作「機や」が掲載されていて、この合羽摺り作品は、30数年前入手したもので、限定70部であり、いまや希少作品なのかも知れない。
日曜日午後1時~4時のみの開館ですが、世界中捜しても当美術館でしか観られない作品が多数有りますので、御来館をお待ちしております。
久保貞次郎研究所2017年4月月報(第85回)
~渡辺私塾美術館計650点展示(恩地孝四郎作品326点)、来館者様にオリジナル版画プレゼント継続実施(入場無料、日曜日午後1時~4時開館)~
~平日(月~土)午後1時~4時、3名以上入場の場合、電話予約で臨時開館、入場無料・版画プレゼントは同じ。電話090 5559 2434(全日午後1時~6時受付)~
~久保氏の芸術新潮編集長宛書簡入手~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
知人から、1週間で日曜日午後3時間のみの開館では、行きたくても時間が取れない、せめて午後6時まで延長してほしい、という正直で有り難いご忠告を頂いた。だが日曜夜には仕事が入っており、時間的に厳しいので、入館者3人以上で、電話予約による平日臨時開館をふと思いついた。日曜日以外は、時間を指定して頂ければ、御相談の上、午後1時~4時の時間で、都合の良い時間に臨時開館致します。ご利用頂ければ幸いです。
4月は、23点追加して、計650点の展示作品数となった。中小美術館の展示数を優に超える展示数であろう。狭くて貧弱な美術館だが、展示作品内容では、地方の小美術館に、それ程引けをとらないと自負している。特に恩地孝四郎作品326点常設展示は、世界でも希有であり、東京の某テレビ局から熱心な出演依頼が何度かあった事、NHKの恩地特集番組制作時、番組制作者が、わざわざ当館まで来訪された事などを考え合わせると、後世、関東の片隅の不思議な美術館の存在が、研究者の間で語り継げられるのではと、密かに思っている。
追加23点の内訳は、恩地作品11点、竹久夢二版画5点、関野準一郎木版2点、、笠井正博シルク小品2点、城景都銅販1点、最後に若山為三8号油彩画2点である。3年前の開館時から、若山油彩画「少年読書」が展示されていて、昭和12年第15回春陽会出品作12号の傑作である。そう言えば、東京から来館された美術関係者が「いやー、ここに有ったのか」と呟きながら熱心に鑑賞なさっていた。また「少年読書」が掲載されている第15回春陽会会報誌も同時に展示されている。今回展示した若山油彩画2点は、震災で破損紛失したものと諦めていたが、他の破損作品の修理中、偶然発見し、修復して「少年読書」の隣に2点展示した。
先日、芸術新潮編集長宛、1964年6月15日付けの久保氏の書簡を入手した。1964年と言えば、久保氏が芸術新潮6月号に「滝川製ヨーロッパ絵画」という、身を切るような辛い論文を発表した年ある。著名な美術評論家が、40数点の贋作を購入したという事実を、自ら詳細に公表すると言う事は、真の勇気と真義を持ち合わせた久保氏ならではの行動であろう。手紙の内容は、編集長からの励ましの手紙に対する御礼と、「狩野亨吉論」の執筆依頼に対する返事、最後に瑛九についてであった。久保氏は、「狩野亨吉論」を、同年同誌12月号に発表している。
この書簡は、芸術新潮6月号刊行直後のようで、かなりの反響が有り、贋作者滝川氏からも葉書が来たとも記されていて、当時の生々しい状況が読み取れる貴重な書簡である。
久保貞次郎研究所2017年5月月報(第86回)
~渡辺私塾美術館計686点展示(恩地孝四郎作品326点)、来館者様にオリジナル版画プレゼント継続実施(入場無料、日曜日午後1時~4時開館)~
~平日(月~土)午後1時~4時、3名以上入館の場合、電話予約で臨時開館、入場無料・版画プレゼントは同じ。電話090 5559 2434(全日正午~午後6時受付)~
~新居広治氏について~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
5月初旬、東京六本木国立新美術館と森アーツセンターに美術展を観に行った。当紙6月2日号に展評を掲載させて頂いたので、一読して頂ければ幸いである。
5月は36点追加して計686点展示となった。あの狭いスペースに686点展示とは、もはや狂気を通り越して妖気であるが、そろそろ物理的にも限界であろう。中二階を拡張すれば、と助言してくださる方もいらっしゃったが、改築の予算があれば、プレゼント用版画の購入に充てたいので、当分今のままで頑張ろうと思う。ここ7年間ほど、芳賀教育美術展の副賞として毎年700点の版画も寄贈させて頂いているので、美術館来館者様用プレゼント版画(2度目、3度目の来館時にはそれぞれ別の版画を用意)を合わせると、年間千数百点のオリジナル版画が必要である。自分でもほとほと困った道楽だと思っているのだが、7年前に久保研究所を創設した以上、久保氏の「小コレクター運動」の意志を継いで、この世に生ある限り、この道楽を継続しようと固く心に決めている。
先月19日(金)の4月月報で、電話予約による臨時開館についてお知らせしたところ、翌日20日山梨県からの来訪者からお電話があり、1時間ほど臨時開館出来た。お母様と二人のお嬢様計3名様の来館で、真岡市出身のお母様は、何と、私の亡き母に洋裁を習ったとの事であった。不思議な縁(えにし)であり、5,6人の少女達に洋裁を教えている母の姿がありありと蘇り、懐かしい思い出に浸ることの出来た良き日であった。
先日、久保氏の支援の元、真岡市に一時期在住していた新居広治氏に関して、二人の来館者様と話し合うことが出来た。新居氏は、1911年東京生まれ、1974年63歳で他界した実力派の版画家であり、「ニイ ヒロハル」が正式な読み方であるが、「ニイイ ヒロハル」と記載されている書籍もある。渡辺私塾文庫内で、新居氏関連書籍を調べた所、「でえだらぼう」(斎藤隆介作、新居広治画、1972年、福音館書店)、「花岡ものがたり」(新居広治・滝平二郎画、1995年、御茶の水書房)の2冊が見つかった。また、当美術館開館時、寄託の形でお預かりした新居木版画「水郷連作2」を追加作品36点のうちの1点として展示した。新居氏は政治活動家でもあったため、真岡市民とはあまり交流が無く、真岡市に一時期在住と記された書籍は皆無で、真岡市に何年ほど住んでいたのか、久保氏との詳しい関係など現在調査中である。
最後に、36点の追加作品の内訳は、恩地氏の高弟関野準一郎木版画5点、藤田嗣治版画3点、小杉放庵作品4点、古沢岩美作品2点、金子保作品2点、油彩画として鈴木亜夫、首藤ユリ子、榎本順一、北村巌、
日本画として、石川義、片岡宣久、版画作品は、竹久夢二、長瀬義郎、小作青史、田中正秋、加藤晨明、浅香公紀、川西英、長谷川潔、川瀬巴水、横田稔、ルノアール、ジャンセン、ブレイク、それに前述した新居広治である。後気軽にご来館して頂ければ幸甚です。
久保貞次郎研究所2017年6月月報(第87回)
~6月10日、当美術館が「認定まちかど美術館」に認定される.(日曜日午後1時~4時開館、平日3名以上で臨時開館、℡090 5559 2434) 入場無料~
~4度目までのご来館時、毎回異なったオリジナル版画プレゼント、5度目以降は、お好きな洋書(英・独・仏・露)を毎回1冊プレゼント~
~6月25日で、当美術館705点展示(恩地孝四郎作品326点)~
~久保氏関連作家、木村利三郎作品展示~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
去る6月10日、「認定まちかど美術館めぐり」が開催され、30名を超える方々に御来館頂き、その時「認定まちかど美術館」認定証を真岡市から拝受した。その記念として、4度目の来館者様にもオリジナル版画をプレゼントし、5度目以降は毎回、常備している数百冊の洋書(英・独・仏・露)から、お好きな洋書を1冊をプレゼントさせて頂くことにした。早速、25日御来館なさった方が、時間をかけ1冊選んでお帰りになった。50年かけて蒐集した洋書が数千冊有るので、向こう10年ほどは在庫切れになることは無いであろう。50年前、大学1年の時、古書店で初めて洋書に触れた折り、少ない知性にそっと触れられるような、言いしれぬ喜びを感じた事を良く覚えている。同じ喜びを共有なさる方がいらっしゃれば幸いである。また、高校2年英語クラスの授業の一部で、「言語と芸術」がスタートした。第1回は米国詩人ラングストン・ヒューズの「The Negro Speaks of Rivers」を解説した。人類の始まりは有色人種からであり、我らは有色人種である事を誇りにすべきだ、という主題の秀作である。久保研究所、美術館開設、版画、洋書プレゼント、言語と芸術など、私のささやかな活動に対して、天にいらっしゃる久保氏から、ほんの少し「ほほえみ」を頂けるかも知れない。
何年か前、私の教え子が、タイの女性英語教師と共に来館してくださり、楽しい時を過ごす事が出来たが、その教え子が、今度は建築学徒であるタイの女性を伴って来館してくれた。今回も前回同様、別な来館者と一緒になって、有意義で素晴らしい時が流れた。
その1週間後、茨城県在住の著名な翻訳家が、英国文人「トバイアス・スモレット」の大著「フランス・イタリア紀行」(2016年鳥影社)を携えて来館なさった。翻訳に十数年を要した労作で、頭の下がる思いである。私の拙文中に、ゲーテの「イタリア紀行」の引用があるので、わざわざ足を運んでくださったに違いない。その労作を有り難く拝受した。その方は美術にも造形が深く、展示されている「伝アントニオ・フォンタネージ」20号油彩画の所で目を止めた。以前来館された、西洋美術専門で、私の後輩に当たる名大教授にも観てもらったが、「フォンタネージにしては少し新しい気がする」が3人の共通意見のようである。正確な鑑定は日本では無理であろうから、イタリアまで行って鑑定してもらうしかないが、そんな費用も情熱も私には無い。画家名の前に「伝」をつけて、「真作なら数百万、贋作なら数千円」とぶつぶつ言いながら、一人悦に入っている。
6月は19点追加して計705点の展示となった。あの狭い空間に705点展示とは、もう形容する言葉も無いし、追加展示を止めるブレーキも無い。内訳は、川上澄生木版画4点、他に版画6点、私の不気味なペン画2点、娘の少しまともなミクストメディア2点、鹿見喜陌日本画、佐藤吉伸フレスコ画、難波田史夫水彩画2点(図録掲載作品)、最後に、久保氏関連画家木村利三郎シルク「City NO196」で、絵の修理中に、歓喜の中で再発見した作品であり、当然展示すべき作品である。
久保貞次郎研究所2017年7月月報(第88回)
~渡辺私塾美術館計725点展示(恩地孝四郎作品326点) 日曜日午後1時~4時開館、平日3名以上で臨時開館(午後1時~4時)(お問い合わせは℡090 5559 2434)
~入場無料、4度目までのご来館で毎回異なったオリジナル版画プレゼント、5度目以降はお好きな洋書(英・独・仏・露)を毎回1冊プレゼント~
~8月13日(日)は当美術館お盆休み~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月は20点追加して計725点の展示となった。館内に展示するスペースが無くなったので、屋外に立て掛けて展示した。来館された美術関係者が、ミロのリトグラフ大作2点が無造作に屋外に立て掛けてあるのを見て、「これだけの作品を外に立て掛けるとは」とため息をついておられた。ごもっともである。2階に展示してある山下清と竹久夢二の作品111点と入れ替えれば良いのだが、お年寄りの方々が、2階から降りてきて「良かったね、胸がスーとしたね」と言ってくれるので、それが本当の絵画鑑賞だと解っている以上、どうしても入れ換える事が出来ない。際限なく追加展示するだけである。昔のはやり歌の文句ではないが、もうどうにも止まらない。
追加作品の内訳は、三上隆彦、岩月虎雄、北村巌、駒込繁芳、藤本東一良、山崎堅司、渡辺章人、狩野寿一の各油彩画、スリランカ臈纈染2点、ビュッフェリトグラフ2点、デラ・コスタ染色50号、吉原秀雄パステル、ラファエロ、ドガ、ルノアール、竹久夢二各リトグラフ、最後に前述のミロリトグラフ2点の計20点である。
6月から始めた洋書プレゼントは大好評であった。立派な方々が、1冊1冊手にとって子供のような笑顔を浮かべお帰りになるのを見ると、高校生の時初めて洋書を手にした時の言い知れぬ喜びを思い出した。
先日、真岡青年会議所の理事長他4名の方々が来宅され、今年度の芳賀教育美術展についてお話を伺った。お話を伺い、今年度も全副賞を提供させて頂くと即答した。今年度で8年目になるが、芳賀の子供達に何点の作品を受け取って頂いたのであろうか。数千点になるに違いない。久保研究所として、多くの芸術作品を贈呈できる今の自分の恵まれた立場を、久保氏に、多くの方々に、そして天に、いくら感謝しても感謝しすぎることは無いと、心底思っている。
7月28日号の真岡新聞に、「真岡賛歌その15」として、親鸞聖人が創建した、真岡市高田の本寺専修寺(ほんじせんじゅじ)について書かせて頂いた。凡庸な拙文だが一読して頂ければ幸いである。
6月月報で、教え子がタイの建築学生を伴って来館され、楽しい時を過ごした、と書いたが、2週間後、今度はフランスの学生二人を連れて来館された。タイの女性が来館された時居会わせたお客さんが、偶然、その時も来館されていて、5人で少しだけ、英語による日仏の文化交流が出来て嬉しい限りである。余り知られていないが、久保氏は、他界するまでエスペラント学会会長の職にあり、世界共通語としてのエスペラント語の普及に心血を注いだ。そして公言はしていなかったが、久保氏は、世界中の人々がエスペラント語を口にし、世界共通言語のもとで、いつの日か戦争の無い世界の到来を夢見ていた。しかしやや言いずらい事だが、タイの女性、フランスの二人に対して、英語を通してしかコミュニケーションが取れなかったのも事実である。エスペラントの復活と世界的普及には、今後相当な困難を伴うであろう事は創造に難くないが、私の知人の中に、エスペラント語を話し、エスペラントの復活と世界的普及を強く確信している有能な人が一人いるのも事実だ。
久保貞次郎研究所2017年8月月報(第89回)
~8月7日、もおかテレビ「行ってみっぺ真岡」収録~
~8月21日、北九州市立大外国語学部米国人教師来館~
~久保氏関連稀覯本3点蒐集~
~渡辺私塾美術館計740点展示(恩地孝四郎作品331点)~
~入場無料、日曜日午後1時~4時開館、平日3名以上で臨時開館(Tel 090 5559 2434まで)、4度目の来館まで毎回版画プレゼント、5度目以降毎回洋書プレゼント~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月7日、当美術館で、もおかテレビ「行ってみっぺ真岡」の収録をして頂いた。昨年のNHK「日曜美術館」の収録では生意気な事、難解な事を言い過ぎてほとんどカットであったが、今回も懲りずにやや難しい事を言わせて頂いた。それでもスタッフが素晴らしい方々で、楽しい時を過ごす事が出来た。9月第2週から放映とのことで、もおかテレビでご覧頂ければ幸いである。
8月21日、北九州市立大外国語学部米国人教師が来館された。ヘンリー・ミラーの研究家で、真岡市が所蔵している、ヘンリー・ミラーから久保氏宛の多数の手紙の閲覧の為にはるばる九州から来訪され、そのついでに当美術館に立ち寄ったのだ。手紙の閲覧は、個人情報との兼ね合いで慎重を期する事項だが、純粋に学術的研究の為なので、真岡市が許可したのであろう。世界的大文豪であるヘンリー・ミラーの研究は、まだ道半ばであり、画家としてのヘンリー・ミラーを含めたトータルな研究にとって、真岡市所蔵の手紙は、今後重要な位置を占めるに違いない。その意味で、今回の真岡市による閲覧許可の判断は、後世高く評価されるであろうし、個人的にも真岡市に心より拍手喝采をお送りしたい。
その研究家は日本語が堪能で、学問的な事まで話し合う事が出来た。当美術館では、ヘンリー・ミラーの「ブルックリン子」(久保エディション)、マチスの「ダンス」、ピカソの「犬を連れた少年」の3点のリトグラフを並べて展示しているが、(マチス、ピカソの原画はどちらもロシア・エルミタージュ美術館蔵)、ヘンリ・ミラーの作品は、マチス、ピカソの作品に、生命感、存在感、芸術性において決して引けをとらないと、彼に伝えた。ミラーは、デッサン等美術の訓練は皆無であるが、文章が書けない時、ほとばしるように絵を描き、絵が描けなくなると文章に没頭した事、止むにやまれずほとばしるように色と形にする事が本当の純粋な美術表現である事も彼に伝えた。更に、久保氏が他界するまでエスペラント学会会長を務め、人類は数万年後、暴力、差別、戦争も無い世界で、全ての人が芸術家である社会を夢見ていたのではないか、とも伝えた。全ての人が芸術家で、同時に哲学者で、詩人で、科学者で、宗教家で、赤銅色の輝く肉体を持つアスリートである時代になった時、初めて人類の本史が始まり、今はまだまだ前史であるとも熱く語った。ミラーの絵を見に訪れたら、黒い服と帽子を被った変なおじさんが、文明論を語り出したので、さぞびっくりなさったであろうが、彼は、その様な人類の夢を受け入れるだけの知性を充分持ち合わせた人物であった。私の教え子で、九州大教授をしている者が二人いて、九州と縁が無いわけでも無いので、一般の来館者と同様、アイオーの版画を贈呈し、彼が未所蔵の、久保氏美術の世界8「ヘンリー・ミラー」をプレゼントさせて頂いた。
8月は、久保氏関連稀覯本を3点入手出来た。1点は、「木内克デッサン集」(1966,美術出版社、限定500部)久保編集で、6ページの久保氏木内論が掲載されている。2点目は、「利根山光人素描集」(1979,総合美術社、限定50部、利根山氏のミクストメディア1点入り)、3点目は池田満寿夫「ふじやまげいしゃ」(1985,吾八、限定100部、金守世士夫木版3点入り)
当美術館8月の追加作品は15点で、内訳は、恩地孝四郎木版5点(博物譜より)、私の訳のわからない絵2点、川上澄生カット木版2点、生野一樹、川瀬巴水、マーティロ・マヌキャン版画各1点、清水練德、北村巌、渋谷英治油彩画各1点。震災で破損した絵の修理中なのだが、震災を生き延びた作品でどうしても展示したい作品は、美術館に持ってきてしまって、今や足の踏み場も無い。7月月報でも書いたが、もうどうにも止まらないので、勢いに任せようと思う。
恩地作品常設展示数が331点になった。大げさでも自慢でも無く世界屈指の恩地作品美術館であろう。みすぼらしい美術館だが一度ご来館頂ければ幸甚である。
久保貞次郎研究所2017年9月月報(第90回)
~渡辺美術館9月は25点追加し、計765点展示~
~入場無料、日曜日午後1時~4時開館、平日3名以上で臨時開館(℡090 5559 2434まで)、4度目の来館まで毎回版画プレゼント、5度目以降毎回洋書プレゼント~
~第31回芳賀教育美術展に久保研究所から副賞の版画700点提供~
~久保氏関連書籍2点、絵画1点蒐集~
~親鸞聖人「教行信証」閲覧に御婦人来館~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
本紙7月28日号掲載拙文、真岡賛歌その15~親鸞聖人が7年間過ごした町 真岡~で、親鸞聖人の聖典「教行信証」江戸初期本2種が閲覧可能であると記した。350年前の江戸本など誰も興味を示さないだろうと思っていた所、8月27日、上品な立ち振る舞いの御婦人が、展示作品を鑑賞した後、「教行信証」の閲覧をお申し出になった。閲覧者皆無だと思い込んでいたので、持参しておらず、少し待ってもらい、慌てて自宅に取りに行き、何とかご覧頂けた。「さわっても宜しいですか」と言って、目映い宝石にそっと触れるように、静かに何度も何度も手にとって、2種の江戸本を心底慈(いつく)しんで頂いた。愛書家を自認している私でも、このように心を込めて書籍に接したことは、久しく無かった。前世で「教行信証」と深い御縁があったのかも知れないこの御婦人に、手にとって喜んで頂き本当に嬉しかった。今思い出してもすがすがしい気持ちになる。
9月19日、久保講堂で芳賀教育美術展の最終審査会があり、7年連続で審査員として参加させて頂いた。翌日、アイオーのシルクスクリーン版画700点余を、今年度も副賞として提供出来た。副賞提供は今年度で8回目となり、版画だけでも4000点を超えるかもしれない。久保氏は長年にわたって芳賀の地に版画作品を浸透させたが、久保研究所も、点数だけ見れば、肩を並べたであろう。久保氏の財力からすれば、私など万分の一にも及ばないのに、自分でも良く頑張っていると思うのだが、これも真岡青年会議所の気持ちの良い若者達の支えがあっての事だと重々承知している。最終審査会の帰り、大学の先生と真岡青年会議所関係者計3名の方が来館なされた。建築に造形の深い方は、ロシア語の建築関係書を見つけ、「すごい本を見つけた。本当に頂戴してよいのですか?」と言って、嬉々としてお帰りになった。5度目以降は、英仏独露の洋書の中から好きな本を1冊プレゼントさせて頂くのだが、かなりの掘り出し物であったらしい。価値の解る方に持って頂いた方が、本にとっても幸せであろうし、私も幸せである。
9月は、25点追加し、計765点の展示となった。外に立て掛けたり、空いているスペースに直接横にして置いたりして展示スペースをつくったのだが、狂気、妖気を通り超して、もう黙狂という言葉しか見当たらない。追加作品は、林武版画2点、ミリポルスキー版画、46年前私の初めての絵画購入作品(銅版画)、横田稔版画、真岡高卒秋山静木版画、城景都版画、加藤栄三素描、松本哲男素描、小寺健吉水彩画、アルド・ラディガラス絵、中国画家油彩画2点、西洋油彩画2点、清水錬德、利根川光人、北村巌、ベル・串田、足立一夫、青木義照、金子保、渋谷英治、林湖山、仲田好江油彩画各1点。今回は、著名ではないが優れた油彩画を多く展示してみた。
9月中旬、名古屋地区の大学教授から、小杉放庵作、春陽堂昭和7年発行「奥の細道画冊」についてのお問い合わせが有り、その日のうちに調査結果をメールにてお知らせした。「奥の細道画冊」は、放庵の木版画43点入りで、幻の稀覯本と呼ばれ、現存している完本は希有であり、研究家のお役に立てれば望外の喜びである。
8月月報でお知らせした九州市立大学のヘンリー・ミラー研究家から、お礼のお手紙を頂いた。来年夏、また真岡にいらっしゃり、来館なさるとの事である。
今月の久保関連蒐集品は画集泉繁(1978,限定620部)、第8回東京ビエンナーレ版画展(1972年)、他に前述の利根山光人6号油彩画「ジェスチャー」で、小品だが生命感に満ちた秀作である。
来館者の中に、当美術館の場所が解りにくかった、とおっしゃる方が多いので、再度言及させて頂く。真岡駅東口から少し南下して、T字路で真岡女子高、芳賀日赤方向に左折し、10メートルほど行った右側奥で、渡辺私塾駅前校右奥に位置している。来館頂ければ幸いである。
久保貞次郎研究所2017年10月月報(第91回)
~渡辺美術館10月は18点追加し全783点展示(恩地作品333点)、入場無料、日曜日午後1時~4時開館、来館者様に版画または洋書プレゼント~
~10月当研究所で久保氏関連作品20点蒐集~
~10月9日芳賀教育美術展表彰式で久保氏の児童美術教育について簡単に説明~
~真岡新聞10月27日号に「美術と私と黒豚の夢」掲載~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
10月の久保氏関連蒐集作品は20点で、いつになく多かった。内容は、瑛九直筆ドゥローイング18点で、子供の落書きのような作品群だが、妙な迫力がある。次の1点は、1979年瑛九展図録(エッチング「屋上」入り、限定150部)、最後に、アイオーのシルクスクリーン版画「マグリット」(1977年、アイオー版画全作品集NO329)。「マグリット」は、展示作品番号777番として当美術館に展示した。
10月9日、芳賀教育美術展に、久保研究所賞のプレゼンターとして出席し、式の最後に副賞の解説の時間を頂いたので、副賞の解説及び久保氏の児童美術教育思想について、僭越ながら簡単にお話をさせて頂いた。話の内容については、荒町教室の弟が毎日書いているブログの10月9日号を参照して頂ければ幸いである。お歴々の方々の前で、偉そうに語っているあの黒い服の変なおじさんは、一体何なんだ、と思われた方もいらっしゃるであろうが、昨年も、同様に時間を割いて頂き、献身的裏方の真岡青年会議所の方々にも、昨年同様了解を得ているので、御無礼はなにとぞご容赦願いたい。
真岡新聞10月27日に「美術と私と黒豚の夢」と題する随筆を掲載して頂いた。いつもは難解な文章なのに、今回はとても読みやすく、心に染み入りました、と何人かの友人に言われ、気をよ良くしている。美術と私の関わりについての、幼少時からの懐古文だが、一読して頂ければ更に幸いである。
10月22日、29日とも台風接近で大雨になり、入り口から雨が吹き込んで、22日は、1時間ほどで来館者が無いまま閉館にした。27日も同様に1時間を経過したので閉館にしようとしたところ、いつもいらっさる方が来館なされ、新展示作品を鑑賞された後、台風の中お帰りになった。頭が下がる思いである。この方は月に2度は来館なされ、生活の中に芸術を取り入れている。久保氏が言う、生活の中に芸術を浸透させるという「小コレクター運動」の神髄を無意識に実践しており、人類の精神的進化の道を、少しずつ目立たぬように歩んでいる。
今年6月から、5度目以降の来館者様には洋書プレゼントを実施しているが、来館する高校生は、版画より洋書の方がお気に入りのようで、版画の代わりに洋書を頂けますかと何度も尋ねられた。版画の方が高価なので、当然、洋書を選んでもらっている。それ故、一般の来館者様も同様に版画と洋書をお選び頂けますので、来館時お申し出ください。
10月の追加作品は18点で、内訳は、まず恩地孝四郎木版画2点であり、恩地作品は全部で333点になった。この2作品は、1935年恩地詩画集「季節標」(限定50部特装本)からのオリジナル版画で、11月からこの「季節標」原本も常設の予定である。世界中の恩地関連美術館で「季節標」特装本を展示している所は果たして何カ所有るであろうか。多分片手で足りるであろう。次に北村巌、清川泰次、小絲源太郎、清希卓、フェドーソフの各油彩画5点、、ルノアール、ビュッフェ、小杉小二郎、藤波理恵子、生野一樹、城景都、多賀新、アイオーの各版画8点、更に、横尾忠則大判ポスター、楢原健三陶板画、尾山幟日本画で計18点の追加展示作品である。文字通り足の踏み場も無いほど乱雑で狭苦しい美術館であるが、芸術の大衆化の名の下、意図的にスーパーマーケットのように展示している。作品のレベル、希少性からすれば、一見の価値は充分有るかも知れない。ご来館を心待ちしております。
久保貞次郎研究所2017年11月月報(第92回)
~渡辺美術館11月は25点追加し全808点展示(恩地作品342点)、入場無料、日曜日午後1時~4時開館、来館者様に版画または洋書プレゼント~
~久保氏関連版画3点蒐集展示~
~12月31日(日)は休館~
~来館者様プレゼント用に、CD付き英会話本を追加~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館11月の追加展示作品は25点で、内訳は恩地木版9点、油彩画9点、版画5点、小磯良平絵皿、大内青圃テラコッタ彫刻の計25点である。恩地木版9点は全て後刷り作品であるが、オリジナル作品の多くは米国に渡っていて、今や後刷りでもかなり希少である。今回で恩地作品は342点の常設展示となった。点数だけなら世界でも屈指の恩地美術館だと言っても大言壮語にならないであろう。油彩画は、田中義昭、林湖山、清希卓、頓宮隆輔、田中たかし、石崎侑一、磯貝秀雄、宮本三郎、山口薫の9点である。最後の2名はビッグネームであり、真贋不明なので作品紹介蘭に「伝」と付記したが、相当迫力のある作品である。版画のうち1点は、私にとって2番目の購入作品で、46年前名古屋のデパートで買い求めたワイズバッシュの大作版画で、かなり色焼けしているが展示してみた。もう1点は古沢岩美の銅版画小品で、残りの3点は、久保氏と関係の深い竹田鎮三郎木口木版画1点と、アイオーのシルク版画2点である。更に、小磯良平絵皿については、ビッグネームだが、絵皿になると極端に廉価になり、それ程珍しくない。最後は、大内青圃のテラコッタ作品で、「宝光馬」というタイトルの小品だが、今にも走り出しそうで存在感がある。この作品の隣には、大内青坡の30号油彩画「裸婦群像」が以前から展示されている。大内青圃は青坡の実弟で、兄弟の作品を一緒に展示している美術館はさほど多くないだろう。青坡の油彩画はほとんどは焼失していて、地方の極小美術館に30号代表作が展示されている事は奇跡に近い。11月で全展示作品が808点になった。正真正銘足の踏み場も無いほどの乱雑さだが、出来るだけ多くの作品を展示したいという、私の40年来の決意だから仕方が無い。このまま突き進もうと思う。
11月5日、6名の方々が団体で来館された。ご丁寧に電話予約もして頂き、熱心に鑑賞なさっていたので、気をよくして、版画の他に私の拙本もプレゼントさせて頂いた。団体様大歓迎である。
11月25日土曜日、埼玉県からいらっしゃった男性から、一人だが開館して頂けるかという、丁寧な電話があった。遠来の来館者様なので5分で美術館に駆けつけ、臨時開館し、版画もプレゼント出来た。電車の時間が迫っていたので、長くは居られなかったようだが、沢山写真を撮って帰られた。平日は3名以上で臨時開館なのだが、私がフリーの時は、人数に関わらず便宜を図りますので、午後1時以降、090 5559 2434までお電話頂ければ幸いです。
来館時、版画より洋書を希望する高校生が多いと前回お知らせしたが、洋書とCD付き英会話本はどちらが良いかと尋ねると、少し考えて、英会話本と答えた高校生が数名居たので、11月26日から、英会話本も選択できるように用意した。一般の方も同様に選択できますので、来館時ご希望をおっしゃって下さい。
展示作品808点のうち、久保氏関連作品もいつの間にか41点になった。内訳はアイオー9点、竹田鎮三郎8点、北川民次3点、草間彌生4点、浅香公紀5点、利根山光人3点、川崎満孝3点、瑛九、安藤幹衛、ヘンリー・ミラー、森義利、木村利三郎、新居広治各1点である。今をときめく草間氏と久保氏の関係については、未だ研究者の間でも結論に達していないが、草間氏が全く無名の時、閑散とした初めての個展で、草間氏の絵を購入したのは、かの川端康成氏と久保氏のみであったという逸話はつとに有名である。私も数年後、その逸話を知る以前、独特な作風が気になって、相変わらず不人気で廉価な草間作品を5点購入した。20数年前、東京のオークション会場で、多くの画商さんやコレクターに、何故こんな変な作品を5点も購入するのかと冷笑された事、彼らの軽蔑の眼差しを今でも覚えている。私が、大学で美学美術史を学び、爪に火をともすようにして蓄えた小銭と、いつの日か地元に小さな美術館を開設するという夢と、誰にも負けぬ熱い思いの三つを携えて、はるばる東京まで出向いている筋金入りのコレクターである事も知らず、「どしろうとの田舎者が」という罵声が聞こえてきそうな眼差しであった。有名無名に関わらず、気に入った作品を購入する事が美術品収集の王道である事を、彼らはすっかり忘れているのだ。値上がりを期待して、評価の定まった売れ筋の絵しか買えない彼らの方が、悲しいほどしろうとなのだ。草間作品1点が震災でゆき方知れずになり、現在捜索中である。発見したら即刻展示する予定だ。
久保貞次郎研究所2017年12月月報(第93回)
~京都大博士課程の学生から久保氏について問い合わせ~
~久保記念館内レストラン「こころ」にシャガール計19点展示させて頂く~
~12月1日と15日、団体役員が来館~
~当美術館12月は19点追加し計827点展示(恩地作品344点) 入場無料、日曜日午後1時~4時開館、来館者様に版画または洋書プレゼント~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
11月末日、京大博士課程の女子学生から、久保氏に関する問い合わせが有った。1938年久保氏が日本の児童画を持って訪米し、米国の小学生の児童画と交換した際、交換先の小学校名の問い合わせであった。思い当たる節も無くその場で即答出来なかったので、1日だけ時間を頂いて、10数冊の久保氏の著作を簡単に読み直しだが、小学校名は発見出来なかった。数時間の後、久保貞次郎美術の世界③「私の出会った芸術家たち」1959年叢文社)閉じ込み付録に、関連箇所をようやくにして見つけた。美術評論家今泉篤男氏との対談の中での久保氏の発言である。「アメリカでも児童美術の研究者に会いました。それは北川民次さんの紹介です。・・・帰りには向こうの児童画を30枚ほどもって来て日本で展覧会をしました。」(原出典は1954年美術手帳5月号) 翌日、私は彼女に自分の推測もまじえて、その本を紹介し次のように話した。特定の米国小学校を正式に訪問して児童画を交換したのではなく、芸術家やエスペラント関連の知人を通して児童画を交換したのではないだろうかと。それにしても西のアカデニズムの頂点で、久保氏を研究しているうら若き研究者が居ると知って、心底嬉しかった。
12月初旬、久保貞次郎記念館内レストラン「こころ」にシャガールの版画4点を展示させて頂いた。この4点で計19点のシャガール展示となり、素晴らしい人柄と凄腕の若きオーナーシェフ様にはいつもご迷惑をおかけしているが、多くの皆様に、シャガールを鑑賞しながら素晴らしいお食事を満喫して頂ければと、「こころ」の一ファンとして切に願っている。
同日、NPO法人の役員の方が来館なされ、絵を観ながら2時間に渡って様々な事を話し合った。彼から好意的な提案がなされたが、ここでは差し控えたい。
12月15日、妻の紹介で、有力な団体の女性役員2名が来館なされた。展示作品を鑑賞しながら、妻も同席して楽しい時を過ごす事が出来た。さすが、指導的立場にいる方々、人格的に素晴らしい人達であった。
12月の当美術館追加作品は19点で、計827点の展示となった。昔のはやり歌、「もうどうにも止まらない」という曲が聞こえてきそうだ。今月は、久保関連作品が7点も見つかり全作品展示した。ヘンリー・ミラー版画3点と北川民次、木内克、木村光祐版画各1点、最後に政治家藤山愛一郎氏の12号油彩画である。藤山氏と久保氏には浅からぬ因縁が有って、久保氏が、稀代の贋作者滝川太郎氏から購入したルノアールの「少女」を、1956年銀座の大手画廊を通して、贋作とは知らず藤山氏に売却した事がある。そのルノアール作品が展覧会中盗難に遭って大きな話題になり、詳細は省くが、波紋が波紋を呼んだ贋作盗難事件で、その被害者が、時の有力政治家藤山愛一郎氏であったのだ。藤山氏の「浅い春」油彩12号に話を戻そう。作品の芸術性は、政治家の余技のレベルを遙かに超えた秀作である。調べてみると藤山愛一郎画集という大冊の画集も出版されている。政治で無く画業に没頭していたら、日本美術史上に名を残した人かも知れない。
次に恩地孝四郎木版「桜」と「湯上がり」の2点で、1946年富岳本社「日本女俗選」から額装した作品である。オリジナルといえばオリジナルだが、恩地自刻自摺りによる少部数の純粋なオリジナル作品とは言えない。その様な恩地作品はもはや日本にはほとんど無く、多くは米国に渡り、愛好家に秘蔵されていて、美術館以外では目に触れる事も少ないだろう。
他は、大沼映夫、吉原英雄、青木大乗、多賀谷伊得、難波田龍起の版画で、最後の難波田氏は、当美術館で肉筆画2点を展示している難波田史夫氏のお父さんである。私見だが、現代日本抽象絵画の巨頭であるお父さんより、早熟早逝のご子息の方が才能に溢れているように思えてならない。一緒に展示してあるので、鑑賞して頂ければ幸いである。他は、ベッチン布への吹きつけ画8号で、独特の味わいがある作品だ。残りの4点は全て油彩画で、広田進8号、ミシェル・サルマン15号、大貫松三10号、妹尾正彦20号である。以前有名大学に進学した才色兼備の卒業生に、当美術館で一番好きな作品は何かと尋ねたら、ためらわず大貫松三の8号油彩画「無題(少女)」ですと言ってくれた。今の若者の審美眼、それほど捨てた物では無いと思わず腕組みした事を覚えている。自分に同じ質問をすれば、「無題(少女)」は5指に入るであろう。独特な点描画の大貫松三の10号油彩画「牡丹」も展示できて少し悦に入っている。最後の妹尾正彦20号油彩画は、「鯰とひょうたん」というタイトルで、独立十人の会出品作であり、氏の代表作でもある。自分に対するクリスマスプレゼント、お年玉としても余り有る作品だ。人と動植物を同一画面に展開し、事物の根底を流れる共通の生命感を表現する、私の大好きな画家である。
ご来館をお待ちしております。
久保貞次郎研究所2018年1月月報(第94回)
~当研究所で久保氏関連書籍3点入手~
~渡辺美術館1月は22点追加し849点(恩地孝四郎作品345点)展示~
~日曜日午後1時~4時開館、入場無料、来館者様に版画または洋書プレゼント~
~3人以上で平日午後1時~4時臨時開館(℡090 5559 2434)~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新年1月、久保氏関連書籍3点を入手した。1点は、1999年東京都現代美術館草間彌生展図録(淡交社)で、草間氏が久保関連作家であるかどうかについて議論の余地がある事は承知している。残りは、1938年6月、久保氏を北川民次氏に紹介した小熊秀雄氏の書籍2点で、昭和28年「小熊秀雄詩集」(筑摩書房)と昭和49年「小熊秀雄 詩と絵と画論」(三彩社)の2点である。久保貞次郎美術の世界3「私の出会った芸術家たち」(叢文社)231ページに、北川氏に紹介してもらう少し前、久保氏が小熊氏からデッサン画を7点購入した記述がある。私見だが、小熊氏は画家というより優れた詩人であろう。
当美術館1月の追加作品は22点で、内訳は、関野準一郎木版2点、笠井正博シルク3点、生嶋順理リト2点、小杉小次郎リト、横尾忠則リト、北川民次エッチング、木村光佑シルク各1点計11点で、最後の2点が久保関連作品である。また、吉原英雄パステル画10号、油彩画では、佐々亮暎30号、小林丙6号、恵後原好一20号、吉川華憂8号、小川博10号の5点で、日本画は酒井三良10号、尾山幟10号、秋葉長生10号、田中案山子10号で、最後に恩地孝四郎稀覯本「蟲・魚・介」(昭和18年、アオイ書房)計22点である。「蟲・魚・介」は、恩地オリジナル木版10点入りの豪華本であるが、1点ずつ額装しようと額まで用意したところ、1冊の稀覯本という名の素晴らしい芸術作品だと気づかされ、額装10点にせず、恩地作品1点として展示した。なお、経済的理由のため、849点のうち約500点は、私の拙い額装である。
1月という時期もあり、教え子4名の来館があった。大貫松三の「無題(少女)」が一番好きです、と言ってくれた才色兼備の子が、大貫松三の「牡丹」を観に、わざわざ東京から足を運んでくれた。前日鎌倉の庭園で牡丹をながめてきたが、油彩画「牡丹」10号の方が素晴らしいとつぶやき、帰りがけに再度二階に上がって鑑賞していった。大貫氏の点描油彩画は出色であると、私もつくづく思う。
同日、20数年前の当塾卒業生が御夫婦で来館された。名前を聞いてすぐ思い出した。栃木県の高校英語教師になることが目標であった教え子で、相当な学力の持ち主であったが、ランクをかなり下げて、英語教師になりやすい大学学科に進学した子であった。目標を達成し、立派な人生だと思う。私が40年前に作成した英語秘密兵器プリント「基礎構文」を教師になっても長年愛用しているとも言ってくれた。
14日、4年前旧帝大文学部に進学した教え子が、高校英語採用試験合格の報告も兼ねて来館された。高校時は、おとなしい子であったが、4年経って溌剌(はつらつ)とした立派な好青年になった。さぞや、有意義な大学生活を送ったのであろう。
28日、30年近く前の教え子が突然来館された。現在、仕事の傍ら、独学で絵を描いていて、2月に宇都宮で個展を開くという。数点の絵を携帯で見せて頂いたが、私好みの面白い半抽象画で、個展を開いても恥ずかしくないレベルだから、胸を張って個展の準備をするようにと、私も胸を張って伝えた。
14日、県央の版画団体の会長さんと会員の方が来館なされた。さすが専門家だけあって800点余の作品を詳細に鑑賞されていたが、不思議にも、お二人共、46年前の私の不気味なペン画に興味を示された。お一人は、「ぼくのイエルニカはこんな顔」に、お一人は、猫のペン画「プルートゥ」に。そう言えばプロの画家が来館されると、多くが、訳のわからぬ私のペン画に興味を示される。嬉しい事だが不思議でならない。先の版画団体の方々は、この2点を版画に起こしてもいいですか、とまで言ってくれた。社交辞令であろうが、内心喜んでいる。これらの不気味なペン画31点は、17年前に文芸社から出版して頂いた拙書詩画集「潮に聞け」の原画で、46年前1年間、何かに取り憑かれたように、ノートに書き殴ったボールペン画で、200点近く有ったと記憶しているが、31点以外は全て廃棄してしまった。不気味で不条理なペン画31点をご覧になりたい鷹揚(おうよう)な方々は是非来館なさって下さい。
久保氏の業績には、遙か足下にも及ばないが、当研究所、当美術館を中心に、芸術のかすかな波が、ほんの少しずつ拡散し、僅かながら波紋が波紋を呼んでいると感じるのは気のせいだろうか。
久保貞次郎研究所2018年2月月報(第95回)
~京都大博士課程研究員2月20日来館~
~渡辺美術館2月は13点追加し計862点(恩地孝四郎作品352点)展示~
~久保氏関連作品計57点展示~
~日曜日午後1時~4時開館、入場無料、当面来館者様に毎回版画または洋書プレゼント~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
2月20日、はるばる京都から電車を乗り継いで、京都大博士課程の院生が単身来館された。既に日本学術振興会特別研究員である彼女は、知性と行動力に満ちあふれた、すがすがしい、うら若き女性であった。当美術館で久保氏関連展示作品を鑑賞し、私と懇談してから、市内の旅館に一泊し、翌日は真岡市所有の数千点の児童画と、久保記念美術館、北川民次と久保氏の関連資料を調査して、京都への帰途についた。黒い服を着た、田舎の変なおじさんの話を、嫌がりもせずメモをとりながら聞き入ってくれ、今時珍しい、礼節をわきまえた若者である。2時間近く楽しい時を共有した後、かなりの時間と出費も顧みず遠方から真岡市まで足を運んでくれたお礼として、彼女が捜していた久保氏関連本8冊と、私の拙本2冊、それにアイオーの版画をお土産としてプレゼントした。お荷物になって迷惑になりませんか、と尋ねると、とんでもありません、と言って、嬉々としてリックを背負い、徒歩で旅館に向かった。久保氏並びに真岡市の学術的普及という点において、彼女は真岡市の至宝になるかも知れない。
2月の追加作品は13点で、内訳は、恩地孝四郎オリジナル木版画7点、草間彌生肉筆画、アイオーシルク版画、小西治男油彩画2点、小泉倫之助油彩画、小泉守邦油彩画である。恩地作品7点は、オリジナルとは言っても、全て1920年代の版画雑誌から切り取った木版画で、真の意味の「オリジナル作品」と言えるかどうかは微妙だが、発行部数も少なく、90年以上前の発刊誌なので、この7点も、今では極めて貴重である。恩地作品もいつの間にか352点になった。恩地作品352点常設展示は、世界でも当美術館だけだと、敢えて言い切ったとしても、真摯な恩地研究家であれば、羨望の眼差しで、悔しそうに少しはうなずくであろう。
震災で行方知らずとなっていた5点目の草間作品をついに発見し、展示した。「風雨」というタイトルのミクストメディア作品で、妙な抽象画であるが、今や引く手あまたの作品になっている。アイオーのシルクスクリーン版画は、1974年の有名な「グラスシリーズ」(2点合装)の作品であり、これも貴重である。小泉倫之助油彩画は「ホノルル郊外」というタイトルの20号作品で、1974年第51回春陽展出品であり、氏の代表作であると、入手後知った。小西治男氏は、昭和29年東京芸大(梅原・林教室)卒のエリート洋画家であるが、2点の油彩画とも、風情に欠けるありふれた平凡な風景を描いている絵である。凡庸を芸術まで高めるにはかなりの技量と情熱が必要だが、その困難に立ち向かう苦渋と熱意にほだされて、熟慮の結果入手した。何故このような風景を油絵にするのか、と腕を組んでしまうが、一定の芸術的レベルには達していると思う。
市内荒町の久保記念館で、第15回企画展「デモクラート~久保貞次郎が交流した芸術家たち~」という素晴らしい展覧会が3月26日まで開催中で、ポスターに記されている出品作家の中に吉原英雄が含まれていた。当美術館では、失念していて昨年までは、久保関連画家に含めなかったが、今年1月から関連作家とした。吉原氏は1955年、具体美術協会を退会し、瑛九が主宰し、久保氏が支援したデモクラート美術家協会に移籍している。当美術館でも6点展示しており、目映い真紅のパステル画2点は出色の作品で、来館なされたら是非ご覧頂きたい作品である。
草間作品を捜している時、ヘンリー・ミラー「母、中国、そして世界の果て」という本を見つけた。2004年、エディション・イレーヌ出版、限定500部の小冊子で、京都大名誉教授であった著名な文化人のご子息の翻訳で、その翻訳者から、直接頂いた貴重本である。ヘンリー・ミラーが他界する4年前の1976年作の短編で、10年ぶりに精読してみた。ミラーが、現世で忌み嫌っていた実母と、来世で再会する話であるが、あの世、黄泉国の描写が極めて精緻であるのには驚かされた。久保氏も晩年精神世界について深く研究していたので、久保氏の影響が多少有るのだろうか。
最近、上三川、清原にお住まいの来館者が多くなり、喜ばしい限りだ。この美術館の事は何処でお知りになったのですか、と尋ねると、真岡新聞の久保研究所月報を読んだので、と言ってくれる。そう言えば、真岡新聞は、上三川の一部と、清原にも全戸配布されているので、私としては、月報執筆の労苦が多少なりとも報われた事になり、一番嬉しい浸透、波及の形である。真岡新聞関係者諸兄に心より感謝したい。
久保貞次郎研究所2018年3月月報(第96回)
~久保氏蔵印日本画(瑛九・小野里利信)2点入手~
~田町街角美術館「ヘンリー・ミラー展」、「上野洋子展」を観て~
~渡辺美術館3月は9点追加し871点展示(恩地孝四郎作品352点)~
~日曜日午後1時~4時開館、入場無料、当面来館者様にオリジナル版画または洋書プレゼント~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
3月の久保氏関連作品は、瑛九の日本画「月竹蛇」と、小野里利信の日本画「山水」で、二人の日本画は極めて珍しく、久保氏蔵印が有るので、久保氏が座興で描いてもらったのかも知れない。座興の席画にしては、しっかりした書き込みで、来歴を調べてみようと思う。いずれにしろ珍品である。当美術館では日本画まくりは展示していないので、別な形の公開を模索中である。
3月11日、田町街角美術館に、2階「ヘンリー・ミラー展」、3階「上野洋子展」を観に行った。2階には、ヘンリー・ミラーのホキ得田宛ラブレターが2点、セリグラフ版画1点、水彩・ガッシュ作品13点が展示されていた。渡辺美術館でも4点のヘンリー・ミラー版画を展示していて、久保エディションの記載が有り、内心自慢に思っていたが、田町街角美術館には、それらの版画の水彩原画が展示されていて驚いた。久保氏はその原画を元にして久保エディション版画を制作したのであろう。長野のヘンリー・ミラー美術館が閉館されて9年になり、2010年ミラー作品のほとんどが韓国の釜山市立美術館に寄贈されたので、日本で、ミラーの良質な作品を一番多く所蔵している機関は、真岡市なのかも知れない。30分ほど、立ち振る舞いの上品な学芸員の方とお話をして、3階の「上野洋子展」を観に階段を上がった。展示室に入った時、すぐに気がついた。全ての油彩画から、穏やかで優しい波動が流れ出ていた。この安らぎは、キャンバスの背後のいずこから来ているのだろうかと思い、辺りをふと見ると、入り口近くに素敵な紳士がお座りになっていた。お尋ねすると、洋子氏のご主人であると紹介された。油彩画から流れいずる安らぎは、上野氏ご夫妻の、日々の生活の中に満ちあふれる安らぎだったのだ。お二人に、これらの油彩画は、洋子氏が描いた作品だが、お二人の精神的合作ですね、と僭越にもお伝えした。話を進めていくと、洋子氏は,、今英国に居る娘が通っていた、益子の優秀な画塾で共に学ばれていたと聞いて、不思議な縁(えにし)を感じた。3人で1時間ほど歓談出来、楽しい有意義な時を過ごす事が出来た。
渡辺美術館に、3月18日は、熊本県と埼玉県からの来館者もあった。熊本市の方は、横浜に用事が有り、そのついでに立ち寄ったとの事であった。デザイン関連のお仕事をしていて、特に352点の恩地孝四郎作品に見入っていた。埼玉県川越市からの来館者は、夏以来の来館で、季節によって作品が違って見えると、鋭い意見を伝えてくださった。堅牢な建物の中にまばらに展示された作品では、その様な感想は生まれないであろう。芸術の大衆化の名の下、芸術作品を一般の方々に近づけるため、50点ほどの作品を外に立て掛けて展示しているが、それがかえって、野外彫刻のように、地域環境と繋がりを持ち、季節感が生まれるのかも知れない。私にとっては、極めて嬉しい感想であった。そう言えば、最近英国の世界的美術館テートギャラリーを訪れた知人が、テートギャラリーでも、当美術館と同様、作品を壁に隙間無く展示している、と報告してくれた。来て下さったお客様に出来るだけ多くの作品を観て頂きたい、という展示思想なのである。しかも、何と、テートギャラリーでは、常設展は入場無料であり、写真、模写自由との事であった。多くの日本の大美術館のお偉い方々に、猛省とは言わないまでも、、少し内省して頂きたいと言ったら、言い過ぎであろうか。
3月の追加作品は9点で,油彩画6点、日本画2点、それに、アイズピリのリトグラフ代表作「花・チューリップの花束」である。油彩画の内訳は、吉野正明4号、神戸文子4号、栃木県出身の洋画家杉山吉伸「高原山」10号、グリゴリエワ「冬の日」15号で、「冬の日」は、1975年三越本店現代ソビエト絵画展出品作であり、月光荘シールの添付されたロシア絵画の重要作である。次は、角卓「月に満ちて」30号で、私の好きな作家、角浩氏のご子息にあたる。油彩画の最後は、真岡市久下田出身の、久下塚青蘭「樹陰」6号で、画集掲載作品である。久下塚氏の師匠は東郷青児氏で、東郷作品の二番煎じだと、揶揄する向きも有るが、私は、決してそうは思わない。久下塚氏の作品には、悲しいほど鋭い女性憧憬、母性憧憬が秘められており、風景画にも同じ悲しみが流れている。久下塚氏は、師の装飾的美しさを遙かに凌ぐ画家であると、数十年後、正当に評価されるに違いない。
日本画は、篠崎之男「田沢緑畑」12号、小川芋銭「収穫」10号で、芋銭の作は、落款からすれば間違いのない作品なのだろうが、私見ながら、芋銭の高弟、酒井三良の手が入っているようにも思える。
日曜日午後1時から4時までの開館であるが、ご来館頂ければ幸いである。
久保貞次郎研究所2018年4月月報(第97回)
~久保氏関連画集2点蒐集~ ~渡辺美術館4月は5点追加し876点展示(恩地孝四郎作品352点)~ ~日曜日午後1時~4時開館、当面版画または洋書プレゼント~
~4月19日、丸の内三菱一号館で、「ルドン展」、上野国立西洋美術館で「プラド美術館展」、東京都美術館で「プーシキン美術館展」を観に行く~
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
4月の久保氏関連品は、木村光佑版画集「ザ シンホニー」1982年、朝日放送、限定200部と、「木下繁彫刻集」1988年、六芸書房、限定200部であった。「木下繁彫刻集」には、久保氏の小論「木下君を葬送ることば」が掲載されているが、1997年「久保貞次郎を語る」(文化書房博友社)の「久保貞次郎執筆編集年譜」には未掲載の論文である。同書年譜は、精緻を極めているとの評判なので、未掲載論文は珍しい。
4月8日、真岡青年会議所の現理事長と元理事長、大学の先生ご夫妻が来館なされた。現理事長と暫し歓談した後、大学の先生から、「日本美術教育研究論集51」を拝領した。同書には、その先生と元理事長の素晴らしい共同論文「真岡における美術教育運動」が掲載されており、芳賀教育美術展と、久保氏の創造美育運動、子どもが絵を審査する「子ども審査会」についての論文で、極めてユニークな内容であった。更に同書には、各論文に対して、他の学者による論評が巻末に掲載されていて、「真岡における美術教育運動」の「論評」を読んで、正直不快感を禁じえなかった。「これを読むと、・・・真岡には美術教育という概念が根付いているのではないかという錯覚?に陥るが」などの軽薄な論調は看過出来るとしても、子どもが審査員である「子ども審査会」の思想的、時代的意義について、浅学である事には閉口した。それ故、真岡新聞5月4日号に「児童の絵を観る力~美術展の審査員が全て子ども達である社会~」という拙文を、急遽掲載した次第だ。一読して頂ければ幸いである。蛇足ながら、この大人げない私の不快感は、芳賀教育美術展開催に向けて、真岡青年会議所会員諸君の、献身的で涙ぐましい奉仕活動を、10年にも渡って目の当たりにしてきたからだ。会員諸君は、少なからぬ会費を納め、何の利益にもならないのに、困難な使命を団結して遂行し、声高に自慢する訳でも無く、ただひたすら他者の為に活動している。私は、彼ら彼女らの中に日本の未来を見る。
4月8日と22日、清原の会社に単身赴任している方が来館なされた。この方は、昨年度から月に2度ほど来館なさり、いつもノートと筆記用具を持参し、質問事項、自分の考えを前もって書き込んで来て、意義深い話をしてくださる。更に時には、メモをとりながら私の話を聞く時もあるほどで、その立ち振る舞い、人間性には頭が下がる思いだ。以前その方に、益子に世界的彫刻美術館ナンドール美術館が有るとお伝えすると、22日は、ナンドール美術館の帰りに、わざわざ立ち寄って下さり、最近ご無沙汰しているナンドール美術館の様子を聞く事が出来た。
4月の追加作品は5点で、ダラ・コスタのシルク版画「待ち伏せ」と、油彩画4点である。油彩画の内訳は、松井正「南の風」20号、出村章「ボトルのある風景」20号、Volk・F「樹」15号(オランダの画家)、宇治政次郎「帽子と草花」20号(1926年第13回二科会出品作)である。追加作品は徐々に減ってきているが、展示スペースが少ない以上、致し方ない事である。
4月19日、妻と二人て、三菱一号館美術館に「ルドン展」(5月20日まで)、国立西洋美術館に「プラド美術館展」(5月27日まで)、都美術館に「プーシキン美術館展」(7月8日まで)を観に行った。目当てはもちろん「ルドン展」である。真岡新聞平成24年12月14日号に、ルドンの「グランブーケ」について、私の拙文を掲載して頂いたが、再度簡単に解説したい。
「グラン・ブーケ(大きな花束)」は、1901年ルドン作で、フランスのブルゴーニュにあるドムシー男爵城に2010年まで秘蔵されていた装飾画大作全16点の中心作である。「グラン・ブーケ」以外の15点は、油彩に似たデトランプという手法で描かれていて、以前からオルセー美術館蔵であったが、世界最大級のパステル画「グラン・ブーケ」は、2010年8月三菱グループが密かに購入していた。これは、1987年、安田火災海上が、ゴッホの「ひまわり」を購入して以来の大英断であり快挙であろう。全16点同時公開は、2011年、パリ、グラン・パレの「ルドン=夢想の王者展」以来2度目であり、今後、かなりの期間実現は困難であると予想される。ただ、歴史的美術展なのだから、もっと明るい所で作品を鑑賞したいと思ったのは私だけだろうか。
次に国立西洋美術館の「プラド美術館展」を訪れた。スペイン、マドリードのプラド美術館は、国民的画家のベラスケスやゴヤの作品を数多く所蔵しているが、今回の美術展では、ベラスケスの重要作7点が展示されていた。国民的画家ベラスケスの作品を、国外に同時に7点出品する事は例外的な事であり、「王太子バルタサール・カルロス騎馬像」、「東方三博士の礼拝」の代表作も展示されていて立派な美術展であった。プラド美術館の至宝、ベラスケスの「ラス・メニーナス」が無かったのは残念であるが、ルドン展よりは来館者も少なく、照明も明るかったので、落ち着いて鑑賞出来た。
最後に、エルミタージュ美術館に次いで、世界第2位の所蔵品数を誇るモスクワのプーシキン美術館から、フランス風景画65点を展示する「プーシキン美術館展」を訪れた。バルビゾン派、印章派を中心に、初来日のモネ「草上の昼食」、モネ「白い睡蓮」、ルノアール「庭にて、ムーラン・ド・ラ・ギャレットの木陰」、アンリ・ルソー「馬を襲うジャガー」など有名作品も観る事が出来た。ただ、一番印象的だったのは、フェレックス・ジエムの「ボスポラス海峡」であった。バルビゾン派に分類されているが、黄金色に輝く40号の油彩画は、むしろターナーの海景画に近い。それにしても「フェレックス・ジエム」という名は、どこかで聞いたことがある。はっと思い当たった。渡辺美術館で所蔵している20号油彩画「牧場の森」の作者、「フェレックス・ジーム」ではと思い、心躍らせて家路についた。やはりそうであった。12年前、重厚な風景画であったので、廉価で購入した油彩画の作者だ。4月19日以来、今でも心が躍っている。
久保貞次郎研究所2018年5月月報(第98回)
~渡辺美術館5月は8点追加し884点展示(恩地孝四郎作品352点展示)~ ~日曜日午後1時~4時開館、入場無料、当面版画または洋書プレゼント~、
~京都国立博物館及び広島大4年生から問い合わせ~ ~久保氏関連作品57点展示~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
渡辺美術館、5月の追加作品は8点で、油彩画3点は、塚本張夫「富士かくる」15号、佐藤真一「川沿いの家」20号、松井叔生「花とレモン」20号、日本画は2点で、池田憲二「冬樹林の彼方」30号、入江酉一郎「ゴザの人」15号、他の3点は土屋ジョー作品で、水彩画「コンポジッションⅠ」、「コンポジッションⅡ」、鉛筆画「無題」であり、いずれも30号である。土屋ジョーについては、詳細不明の画家であるが、芸術性の高い,、迫力に満ちた3作品である。入り口左に展示しているので、一度ご覧になって頂ければ幸いである。
5月6日、3月月報で紹介させて頂いた上野洋子ご夫妻が初めて来館された。作品の多さに驚きながらも、画家の優れた鑑賞眼で、楽しそうに鑑賞なさっていた。教養溢れるご主人も、奥様に劣らぬ鑑賞眼で、お気に入りの絵に見入っていた。またのご来館をお待ちしております。
5月初旬、広島大4年生から、アルス日本児童文庫の付録である1926年発行「アルス月報」について、書簡で問い合わせがあった。「アルス月報」は、1920年代アルス社が、自社発行の全集本に挟み込んだ、宣伝を兼ねた小冊子で、現在全揃いは極めて少なく、全部で何冊発行されたかも定かではない。渡辺私塾文庫、当美術館でも3分の1ほどの冊数しか所蔵しておらず、諦めかけたが、卒論に利用するとの事なので、4時間ほど必死で捜して、奇跡的にお尋ねの「アルス月報12月号」を発見し、その日のうちにコピーして、郵送させて頂いた。ここ数十年、百回近く、大学教授であろうが学生であろうが、分け隔て無く、問い合わせ、資料請求には無償で対応できた事は、私のささやかな自負である。
翌日、天下の京都国立博物館の著名な考古学者から、当文庫所蔵の「埴輪集成図録集帖」(昭和6年)について、お電話で問い合わせがあった。1時間ほどで捜すことが出来たが、お探しの本は、第11回本で、当文庫所蔵本は第1回本であったので、残念ながらお力になれなかった。それでも、上品な物言い、物腰の低さ、さすが一流の学者は違うと感心させられた。考えてみれば、日本1,2の国立博物館に所蔵していない稀覯本を、地方の弱小文庫・美術館が所蔵している訳はないと、誰も居ないところで一人含み笑をしてしまった。
5月13日、月に1度ほど来館してくださる市内の方が、写真を1枚持参してくれた。館外の建物に立て掛けて展示している作品と、その建物の風景とが精妙にマッチしている芸術的写真であった。更に、この方は、真岡新聞昨年6月30日号掲載の、私の拙文、「真岡賛歌その14、詩篇?、都会で瞳を濡らしたら、真岡に帰ってくればいい」について素晴らしい感想を語ってくれた。涙をこらえながら、何度も何度も読み返しました、とさえ言ってくれた。この「詩篇?」は全く無反応、無反響で、昨年来、もう詩篇を発表するのは止めようと思っていたので、心底うれしかった。現在構想中の「真岡賛歌その16」の後、詩篇?も考え始めた。ひとえに、この方の御陰である。
5月20日は、地元の方々以外に、千葉県のご家族3名と、小山市の御婦人2名が来館なされた。ほんの少し、当美術館の波紋が、波紋を呼び始めたのだろうか。いや、まだ小さな石を投げて、かすかな波紋が出来始めたにすぎないだろう。
5月の久保関連作品蒐集は皆無であった。来館者様用プレゼント版画が底をつき始めたので、現在多数のプレゼント用洋書を購入しており、単に経済的理由である。そもそも、大資産家であった久保氏の万分の一の財力も無いのに、毎年の芳賀教育美術展への副賞版画700点提供、入場無料で版画プレゼントの美術館運営、当文庫・美術館の資料提供一切無料など、宙に浮きそうになるほど背伸びをしている事は、私も重々承知しているが、お、また歌の文句が出てきそうだ、「もうどうにも止まらない」
ご来館を心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2018年6月月報(第99回)
渡辺美術館6月は5点追加し889点展示(恩地孝四郎352点展示、久保氏関連作品57点展示)
7月は日曜日午後1時~4時開館、入場無料、当面版画または洋書プレゼント
8月以降年内は、電話予約で開館(月曜から土曜日午後1時から5時まで、℡090-5559-2434、来館予定時間の15分前に開館予定) 入場無料・版画・洋書プレゼントは同じで、一名の予約でも開館 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
6月18日、二宮町文化財絵はがき3セットを入手した。浅香公紀木版画が印刷された絵はがきで、「桜町陣屋跡」、「横田円蔵の家」、「河野守弘の墓」、「高田山専修寺」、「長沼八幡宮」の5点で1セットになっている。浅香氏は、作品を見ればすぐ浅香作と解る優れた木版画家であるが、久保氏が支援した画家のなかで、唯一世に出なかった作家だと揶揄する者もいる。しかし実際は、意図的に世に出ようとしなかっただけなのである。ご存命中、美しい木版画本、綺麗な花の木版カレンダーを何度も贈呈して頂いたが、いつも趣味で作っています、とおっしゃっていた。本来、芸術活動とは、全ての人が、日常的に、趣味で実践する行為だと確信なさっていたのかも知れない。この絵はがきセットは、当美術館の2階にある浅香コーナーに展示してあるので1度ご覧頂ければ幸いである。
6月の追加作品は5点で、内訳は、久下塚青蘭「雲と木」4号、、関伸郎「雪幻譜」12号の2点の油彩画、石踊達哉「私の風景」日本画30号、ヨルク・シュマイサー木版画2点である。久下塚氏は、1936年真岡市二宮町生まれで、真岡市出身の数少ない著名な洋画家である.。渡辺私塾文庫HPで、私は次のように書いている。「中学1年時上京し宮本三郎、東郷青児に師事。東郷作品に似ていると評されるが、私には、氏独自の世界が感じられてならない。氏の作品には、氷のように冷たいけれど、細い針のような鮮烈で悲痛な女性憧憬がある。澄み切った風景画にもその悲しみが貫かれており、50年後洋画史の中で高く評価されるに違いない」 当館では、他に「ポーズする女性」10号、「樹陰」6号も展示していて、小品だが計3点の展示は希有であろう。石踊氏の「私の風景」は、氏が1970年東京芸大大学院を修了した翌年の作で、困窮していたのか、額も貧弱で、絵の具も良いものではないが、後に日本画壇の重鎮になる力量を暗示する秀作である。ヨルク・シュマイサー氏は、1942年ポーランド生まれで、1968年に、京都市立美大に留学した経歴を持つ世界的版画家で、2点の木版画を同時に入手出来て幸運であった。
6月22日金曜日、東京と宇都宮の女性から前もって電話予約を受けたので、特別に開館した。平日は3人以上で特別開館という決まりなので、電話予約時、大変申し訳なさそうであった。お二人とも、芸術に関係するお仕事をしていて、恩地孝四郎についてもかなりの知識をお持ちになっていたので、楽しいひとときであった。
開館時間が、日曜日の1時から4時のみで、時間も短いし、日曜日の午後は家族の用事も多いので、来館するのは容易でない、という事を以前から耳にしてきたので、8月から12月末まで、実験的に、電話予約で、月曜日から土曜日、午後1時~5時開館としてみた。1名でも可で、電話予約時、私のスケジュールもあるので、ご相談のうえ、おおよその来館時間を決めて頂き、15分前には開館しておく予定だ。前日までにお電話頂ければ幸いである。(℡090-5559-2434、正午から午後6時受付、日曜日は原則休み) このシステムより、日曜日午後1時~4時開館の方が来館者数が多いようであれば、来年1月には再度元に戻そうと思っている。版画・洋書プレゼントは、現行通りであるが、芳賀教育美術展副賞用版画700点が必要なので、版画はそろそろ底が尽きそうである。現在英・独・仏・露・伊の洋書を多数入手しているところだが、道楽も過ぎる、とおしかりを受けそうであるけれど、財力、体力、気力が続く限り継続しようと思う。お、先月同様、また、山本リンダの昔の歌の文句が聞こえてきたぞ、「もうどうにも止まらない」
久保貞次郎研究所2018年7月月報(第100回)
久保研究所の8年間の活動及び芳賀教育美術展について
渡辺美術館7月は1点のみ追加し、890点展示、(恩地孝四郎352点、久保氏関連作品57点展示)
8月Ⅰ日以降年内は、月曜日から土曜日午後1時~5時電話予約で開館。日曜日は原則休み。1名でも可。前日までに℡090-5559-2434に来館時間をお知らせ下さい。(℡受付全日正午~18時。来館時間の15分前に開館致します。) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
久保研究所月報も今回で第100回を迎えた。久保研究所設立日は2010年4月Ⅰ日であったので、8年と4ヶ月前であり、丁度100回の月報になる。この月報は、ホームページで公表し、真岡新聞社様のご好意で掲載して頂き、拙書渡辺淑寛著作集にも漏れなく所収している。
久保研究所代表としてこの8年間、様々な活動をしてきた。思い出すままに列挙してみると、?,7年間芳賀教育美術展最終審査員、?,8年間同美術展に副賞提供、?,講演依頼(宇都宮大シンポジウム、株式会社ミツトヨ、真岡青年会議所他)、?,真岡市「久保貞次郎氏を語り合う」座談会座長、?,美術館開設(2015年)、?、久保氏について、学者、研究者、学生からの問い合わせに対する無償対応、?,月報の発表、?,久保氏関連作品の収集、?,久保氏と恩地孝四郎との関係についての研究、?,真岡新聞、下野新聞、私の拙書等による久保氏の思想、業績の周知及び普及、?,晩年の久保氏と精神世界との関わりについての研究、?,美術評論、芸術論、随筆、真岡賛歌などを真岡新聞に掲載、などが列挙できる。今振り返れば自分なりに良くやって来たと思う。?の副賞提供は700名分であるので経済的にはハードであるが、財力の続く限り継続しようと思っている。今年度も700点のオリジナル版画(靉嘔のシルクスクリーン版画「ラブレターズ」)を何とか用意出来た。?で、久保氏は、恩地存命中恩地氏を高く評価せず、恩地作品を収集しなかった事を終生深く後悔していた。それでも、真岡市に当美術館が出来、恩地作品352点が常設されている事を天から見て、胸をなで下ろし、微笑んでいらっしゃることだろう。
芳賀教育美術展は今年度で32年目を迎え、久保氏が提唱した創造美育思想が色濃く反映された、日本で唯一の大美術展である。毎年芳賀郡全域の園児から中学生まで7000点を超える作品が搬入され、約700点の個人賞、学校奨励賞が選ばれ、その中から特別賞が再度選ばれる。特筆すべきは、2年前の30回から、児童自らが審査員になって、作品を審査する「子ども審査会」であろう。私は以前から子どもの絵を観る力は大人以上であると確信しており、本年5月4日真岡新聞に「児童の絵を見る力~美術展の審査員が全て子ども達である社会~」と題する拙文を掲載して頂いた。この「子ども審査会」は世界でも希有であり、今後予想を超える反響と賞賛の嵐が各地から巻き起こるに違いない。更に忘れてならない事は、芳賀教育美術展の主催は、三団体から成っているが、実際の運営は、後援団体の末席に名を連ねている真岡青年会議所が行っているという点である。会員各位の、創造を絶する献身的な刻苦を10年間目の当たりにしてきて、少なからぬ会費を納め、声高に自慢するわけでも無く、ひたすら無私の精神で助け合いながら活動する若者達に、ただただ頭が下がる思いだと、そっと伝えたい。君達の苦渋は、誰かがきっと見ているよ、と密かに伝えたい。青年会議所は、1年で職責が全て変わるので、1年だけだから、この使命、重責を何が何でも遂行しようという強い意志、あるいは1年交代制の優れたシステムが、この刻苦の克服を可能にしているのかも知れない。
北関東の7月の大地は、歴史的猛暑で、来館者も少なく、追加作品は、穐月明「籠の紅白牡丹」日本画10号のわずか1点であった。書き込みの少ない淡彩画であるが、日本画特有の「粋」な作品である。
久保関連作品も、久保氏監修「徳間文庫 日本の美術館」1冊であるが、久保氏の短文「序 美の旅人へ」が、巻頭に掲載されている。
6月月報で言及したように、8月から、実験的に、月曜日から土曜日午後1時~5時予約開館にしてみた。前日までに(℡090-5559-2434)来館時間をお知らせ頂ければ幸いである。(℡受付全日正午~18時)(入場無料、版画、洋書プレゼントは同じ、1名でも可)、変更後の方が私の負担は増えるが、これで来館者が増えれば満足である。もし来館者数が少なくなるようであれば、来年1月から、また元に戻そうと考えている。
久保貞次郎研究所2018年8月月報(第101回)
渡辺美術館8月は14点追加し904点展示(恩地孝四郎352点、久保氏関連作品57点展示)
神崎温順の芸術~型絵染絵本13点追加~
久保氏関連本、木内克ローマ蝋型作品集入手
月曜日から土曜日午後1時~5時電話予約で開館、1名でも可、日曜日は原則休み、前日までに℡090-5559-2434に来館時間をお知らせ下さい、℡受付全日正午~18時
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月は酷暑のため、閑散とした月であった。来館者は市職員の方々4名と、私の教え子4人の8名にすぎなかった。3年前の開館以来最少来館者数である。開館時間変更も影響しているのかも知れない。もう少し様子を見て、日曜日定期開館に戻すことも検討したい。
久保氏関連新蒐本は、木内克「ローマ蝋型作品集」で1975年、限定500部、リトグラフ「裸婦立像」入りである。木内氏は著名な彫刻家であったが、久保氏は、版画家を中心に、画家、彫刻家、陶芸家、写真家も支援した事は周知の事実であろう。
8月の追加作品は14点で、1点は浜田泰介の6号油彩画、残りの13点は、神崎温順の型絵染絵本である。神崎氏は、昭和7年生まれで、昭和30年に土佐和紙に惹かれ、高知市に移住し、多くの型絵染作品、型絵染絵本を発表したが、世に知られることも無く、詳細不明の謎の芸術家である。私は、稀覯本蒐集家として50年前、神崎氏の型絵染絵本と出会い、その芸術性の深さに魅了され、いつの間にか、神崎絵本の有力な蒐集家になっていた。当美術館でも、神崎額入り型染め作品を10点展示しているが、神崎芸術の神髄である型絵染絵本を初めて13点展示した。全く無名だが、全国に少数の熱狂的愛好者のいる神崎芸術、古来からの染色技法を基盤にした孤高の神崎芸術に邂逅なさりたい方は、来館頂ければ幸いである。
8月28日、上野の東京都美術館で「藤田嗣治展」(10月8日まで)を観に行った。日本、世界各地から集められた126点の秀作が展示された素晴らしい美術展であった。藤田は、戦争画を描き、戦争責任を追及され日本を去り、フランス人になったが、画家に戦争責任を問うのは本末転倒である。もっと大きな力、ほとんど止めようも無い軍隊という名の組織について、哲学的に群衆心理学的に組織論を徹底して研究する事の方が遙かに重要である。それでも、藤田は幸せであった。フランスで十二分に評価されたからである。ゴッホを例に挙げるまでも無く、画家が生前に評価されることは例外的な事だとよく言われるが、神崎氏が画壇から評価される事はついぞ無かった。餓死したという噂も有るが詳細は未だ謎である。それでも、北関東の外れの小さな美術館で、23点の作品が展示されていると知ったら、天に居る彼も、少しは喜んでくれるであろう。
最後に、渡辺私塾文庫27「神崎温順」に記した私の拙文を抜粋して、8月月報の終尾としたい。
「神崎氏については、銀花49号(昭和57年)で、寿岳文章氏によって17頁にわたってされ紹介され、少数ではあっても全国に熱烈な愛好家が居て、彼の型染め作品を清らな眼で鑑賞しているのでしょうが、その芸術性の高さからからすれば、悲しいくらい評価の低い芸術家です。型染め絵を通して表出した芸術性、精神性の深さは、日本美術史上希有であると、私は確信しています。
抽象画、抽象版画は、世界美術史上正当な評価を受けてきませんでしたが、その鬱積したエネルギーが、文様、装飾芸術、型染芸術のなかで、見事に開花しています。・・・・・幼児の純真な絵の多くは抽象画であると言われています。物を写す具象作業も人間の本能的活動でしょうが、内面のやむにやまれぬ思いを非具象の「形」と「色」で表現することも、やはり人間本来の本能的活動の一つでしょう。私達大人は、子どもの絵を観て「何を描いているの」と思わず尋ねてしまいますが、精神の強い思いを、ただ「形」と「色」で表現したにすぎないのです。この延長上にある、強くて太い芸術表現が「抽象芸術」であると確信します。神崎型染め芸術は、その道で宝石のように輝く結晶の一つではないでしょうか」
久保貞次郎研究所2018年9月月報(第102回)
渡辺美術館9月は1点追加し905点展示(恩地孝四郎352点、久保氏関連作品58点)
久保氏関連版画集「瑛九銅版画ScaleⅤ」(銅版画63点入り)入手
元大学教授(日本美術教育連合理事)が来館
真岡市まちかど美術館、久保記念美術展示館について
芳賀教育美術展の子ども審査会、最終審査、表彰式に代表が参加
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
長年捜していた瑛九銅版画ScaleⅤを入手出来た。今までに何度か目にしたが高額すぎて二の足を踏んでいて購入できなかったのだ。だが瑛九の銅版画63点入り(昭和58年、林グラフィックス)の豪華版画集なので、清水の舞台から飛び降りる気持ちで、勇気を奮い起こし購入した。瑛九作品の評価は、年々うなぎ登りで、やっと時代が瑛九に追いつき始めて来たのだろう。瑛九を見出し世に送り出した久保氏も、天で喜んでいるに違いない。この版画集が905番目の展示品である。
9月の来館者数は、灼熱の8月ほどでもないが、やはり少なかった。来年1月からは、土曜日の正午から午後4時まで開館することも考えている。来館者様は、常連の方々と、元大学教授で、美術教育では著名な文化人が初めて来て下さった。真岡市の学芸員の方とご一緒に来館され、恩地作品や有名画家の作品が無造作に置かれているのに驚いた様子であった。また恩地作品は世界でも屈指であろうとおっしゃって頂き、嬉しい限りである。その方は画家でもいらっしゃて、お帰りになる時、私の似顔絵を描いて下さり、拝受致した。
真岡市まちかど美術館と久保記念美術展示館を同じ日に観に行った。まちかど美術館では「久保貞次郎と世界の児童画」(7月26日~10月29日)が開催されていて、左奥のネコちゃんの絵に魅了され、暫時見入ってしまった。学芸員の方もこのネコちゃんの絵が一番好きだと言って下さり、意気投合して、暫し児童画の話題で花が咲いた。
久保記念美術展示館では「創造美育運動と作家たち」が開催されていた。(8月2日~9月17日)北川民次、泉茂、オノサト・トシノブ、アイオー、瑛九、木水育男、藤本よし子、池田満寿夫の作品が展示されていた。出色であったのは、瑛九の油彩画3点である。3点とも大きな瑛九展でも開催されない限り目にすることが出来ない傑作で、これらの作品を入場無料で展示している真岡市に拍手喝采を贈りたい。そう言えばまちかど美術館も入場無料であり、当美術館も含めて、街角美術館は全て入場無料である。80年前、完成したばかりの久保講堂で、著名な知識人を集めて「児童画審査会」を始めたのは久保氏であったが、小コレクター運動も、創造美育運動も真岡市が原点の地である事を忘れてはならない。その意味でも、一切入場無料にしている真岡市は、50年後、100年後、美術の町として高く評価され、理想的な自治体であったと尊敬の念を持って、長く語り継がれるであろう。
9月14日、久保講堂での「児童審査会」に初めて参加させて頂いた。子どもが絵を審査して賞を決めるという画期的な試みであり、多分世界でも類をみないであろう。3年前、当時の真岡青年会議所理事長と大学の先生が中心となり、芳賀教育美術展の一環として始められた。この「子ども審査会」については、反響が乏しいが、まだ未知の研究分野であり致し方無いのかも知れない。私個人としては数十年前から、子どもの絵を観る力には気付いており、本紙5月4日号で「児童の絵を観る力~美術展の審査員が全て子ども達である社会~」という拙文を書かせて頂いた。更に、9月30日、表彰式の最後で、直接何点かの絵を示しながら、子どもの絵を見る力について説明させて頂いた。別な機会に、ゆっくり時間をかけて解説したいと考えている。創造美育思想を柱に、児童美術表現論はあまた有るが、児童美術認識論は皆無に近い。解っていることは、子どもの絵を観る力は、純粋で直裁で鋭く本質を突いているという点だ。子どもは大人より宇宙から表出してきたばかりなので、宇宙の美、秩序、神秘を、赤き血潮の中に記憶しているからなのだろうか。そうそう、17年前に文芸社から出版した私の不気味な詩画集のタイトルは「潮に聞け」であった。
久保貞次郎研究所2018年10月11月報(第103回)
渡辺美術館来年1月より土曜日午後1時~4時定期開館 全913点展示(恩地孝四郎352点、久保関連作品63点) 真岡小2年生7名見学に来館 久保氏の元秘書他計4名来館 吉原英雄パステル画2点田町「まちかど美術館」に貸し出し
11月26日拙書著作集第7巻真岡新聞社より刊行 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館、2019年1月より毎週土曜日午後1時より4時まで定期開館することにした。以前は日曜日定期開館、その後不定期で電話予約であったが、来館者は、ほとんど常連の方々なので、今回は土曜日午後1時~4時定期開館とした。入場無料、来館者様全員に版画または洋書プレゼントは継続実施中である。
さる10月4日真岡小2年の児童7名と引率の先生方が来館された。町たんけん見学学習の一環としての来訪であった。全員礼儀正しい児童で、質問もしてくださり、全員に、オリジナル版画と、アニメの原画(セル画)を受け取って頂いた。美術館が珍しかったのか、少し経って、別のグループ7名の児童も飛び入りで来館された。プレゼントの用意をしていなかったので申し訳無かったが、皆様喜んでお帰りになり、楽しい1日であった。後日、先生が全員の手書きのお礼状が掲載されている手作り冊子を届けて下さり、思いもよらぬ嬉しい贈り物に、深夜不覚にも目頭を熱くした。
10月27日久保氏の元秘書他計4名の方々が来館なさった。4名の皆様は、跡見学園時代の久保氏の教え子で、ほれぼれするほどの、知性溢れた聡明な女性達であった。久保氏に関する貴重な資料を沢山拝受し、お土産に靉嘔の版画と、私の拙書「著作集第6巻」、「潮に聞け」をお一人ずつ受け取って頂いた。1時間ほど展示作品をご覧頂き、有意義な時を過ごす事が出来た。
10月31日、真岡市まちかど美術館「ヘンリーミラーの版画展」(11月Ⅰ日~12月28日)展示のため、吉原英雄パステル画2点を貸し出した。「ミラー・オブ・ザ・ミラー」(10号)と「赤いスッパッツのっ女性」(15号)の2点である。後日まちかど美術館を訪問した時、2階入り口近くで2点が並んで展示されており、一際異彩を放っていた。この2点を敢えて選んで展示した真岡市学芸員の鑑識眼は一流である。まちかど美術館3階では、「第1回しもつけ富士の会」写真展(11月7日~12日)が開催されていた。霊峰富士を様々な視点角度から活写し、鮮烈な色彩も表出されていた。写真芸術は全くもって侮れない。その後荒町の「久保記念美術品展示館」を訪れた。「久保貞次郎エディション展」(前期10月11日~12月10日・後期12月13日~2月11日)が行われていた。靉嘔、池田満寿夫、瑛九、泉茂、桂ゆき、北川民次、木内克、福沢一郎、竹田鎮三郎、山口薫、脇田和の久保エディション版画が展示されていたが、やはり瑛九作品が出色であった。それにしてもこれだけの作品群を無料で鑑賞出来る真岡市は、何と素晴らしい芸術の町なのだろうか。市当局関係者の皆様に心より感謝致したい。また、多くの方々にご利用頂き、波紋が波紋をを呼んで、日本各地から多くの人々が真岡市を訪れる事を願っている。
11月初旬、真岡市内の知人が、久保家土地部と書かれた書類をわざわざ届けて下さった。久保氏研究の貴重な資料であり、有り難く拝受した。
10月11月の当美術館追加作品は8点で、全て久保関連作品である。内訳は、久保貞次郎特装本版画入り3点、瑛九版画入り特装本3点、浅香公紀木版、新居広治木版である。現在入手困難な作品であり、来館なさって鑑賞して頂ければ幸いである。
8月月報でお知らせした神崎温順型絵染本閲覧のため、10月中旬、常連の方が来館なされた。13冊の型絵染め本を観ている最中、その方は、心震わせ合掌しながら鑑賞なさっていた。神崎作品には、命ある物の生と死に関わる厳粛な作品も多く、苦難を重ねたその方の合掌するお姿を目の当たりし、心の中で涙を禁じ得なかった。本当の芸術鑑賞のあり方を再認識させられ、美術館を開いて良かったとつくずく思った。
11月26日、著作集第7巻が完成し、真岡新聞社から刊行された。まさか第7巻まで出版出来るとは思ってもいなかったが、もうここまで来たら、最低第10巻までは出そうと思っている。時代を先取りしたやや難解な内容を含んでおり、評価されるのは50年後か100年後であろうが、そんなことはどうでも良い。18年前、文芸社から詩画集「潮に聞け」を出版した折、北の県のうら若き女性から、感想と賞賛の文が届いた事がある。書いた本人よりも深く思索をしていて、感心させられたが、その様な方が一人でも居れば良いのである。2019年1月5日土曜日来館なされる方全員に第7巻を贈呈させて頂く予定だ。
久保貞次郎研究所2018年12月月報(第104回)
渡辺美術館本年1月より土曜日午後1時~4時定期開館 全927点展示(恩地孝四郎353点、久保氏関連作品66点)
当美術館12月14点追加(恩地未完木版画集「海の表情}、プレス・ビブリオマーヌ限定稀覯本異装6種13冊)
真岡市田町まちかど美術館で「滝川太郎の贋作展」(1月5日~3月4日)開催(午前9時~午後5時、火曜日定休)、当美術館で3点貸し出し
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館は、本年より土曜日午後1時~4時開館で、版画、洋書プレゼントは今まで通り実施致します。版画の在庫が少なくなってきましたので、無くなりましたら拙書著作集プレゼントに切り替わるかも知れません。
12月の追加作品は、恩地孝四郎木版画集「海の表情」で、未完の木版画をご子息の邦郎氏が1987年に版木から摺り起こした17点入り、限定20部の稀覯本です。多くが、大美術館や米国の愛好家の手に渡り、入手困難である限定本ですが、当美術館は、貧弱ですが世界有数の恩地美術館でもありますので、2部所蔵しており、1部を当美術館で展示することに致しました。
他の追加作品は、プレス・ビブリオマーヌ限定稀覯本異装6種13冊です。異装とは、同じ内容の本が別装幀されている事をさします。例えば、1974年「流線形物語」(佐々木桔梗著)では、A版は限定455部本で、軽症者用版は、限定205部、重症者用版は、限定53部で、何と53部本は、振ると機関車の音がするという優れ本です。軽症、重症は機関車に魅入られている度合いを表すのでしょう。
著者の佐々木桔梗氏は、機関車に魅了されており、今回の展示品の中には、「荷風ふらんす鉄道物語」、「探偵小説と鉄道」、「機関車のある風景」が含まれています。機関車のある真岡市には極めてふさわしい稀覯本でしょう。また今回のプレスビブリオマーヌ本の中には「異端の花」超特装ダイアモンド一部本も展示されていますので、是非一度来館なさって手にとって頂ければ幸いです。
1月5日から3月4日まで、田町の真岡市まちかど美術館で、「久保貞次郎と、滝川太郎の贋作展」が開催されている。滝川太郎(1903~1971)は、一水会所属の画家であると同時に、稀代の贋作者で、久保氏は彼から47点の贋作を購入したと言われている。滝川の贋作はあまりの出来栄え故、鑑定家でも真偽判定が困難で、1956年神奈川近代美術館の「ほんもの・にせもの展」でも、滝川製にせものと本物の作品が展示された時、後にそのほんものも、滝川製贋作と判明したほどであった。西欧の秀作油彩画を日本に移入しようとしていた久保氏が、資産家でかつ美術評論家であった故、かえって47点の贋作を購入してしまう結果になったのかも知れない。更に、久保氏から大手画廊を通して、ルノアールの「少女」を購入した大物大臣藤山愛一郎氏が、1962年川崎の百貨店で開催された「西洋美術展」にその「少女」を出品した時、世を騒がす事件が起きた。その「少女」が盗難にあい、なんとか戻った作品を、藤山氏は国立西洋美術館に寄贈したのだが、その「少女」も滝川製贋作と判明した事件である。1947年、最初に疑義を表明したのは、画家の硲伊之助であったが、多くの作品が贋作であると判明したのは、久保氏自身による「芸術新潮」誌上での告発があったからである。
驚くべき事は、久保氏が、滝川はコロー以外どんな画家の贋作も作れると書くと、半身不随になっていた滝川は、左手で、コローの模写絵を描き、久保氏に送りつけた事である。私がそのコローの絵の裏に書かれた文章を読んだ時、虐げられた力ある無名の画家と、安住の地に居座っている一部の有名画家が混在する日本洋画界の持つ矛盾に対する、どす黒い怨念を感じた。そのコロー模写画もこの展覧会で展示されている。
この展覧会には、久保氏油彩画4点、滝川贋作9点と当美術館貸し出し作品3点の計16点が展示されている。特に出色なのは、贋作モディリアーニの「女の顔」で、贋作とは思えない迫力である。滝川は、1969年のインタビューで、「俺の贋作には命がこもっている。原作以上の迫真力がある。」、「黒田、安井、梅原にしても本場のコピーじゃないか。本場の本格派の精神まで写す俺のコピーの方が、はるかに価値が有る」と言い放ったが、あながち、単なる強がりとは思えない出来栄えである。
当美術館の貸し出し作品は、マチスの「ダンス」のリトと、ピカソの「犬を連れた少年」のリト、それに藤山愛一郎の希少な油彩画である。藤山氏は政治家になっていなければ、日本洋画史に名を残した画家になっていたかも知れない。
真岡市には久保氏購入滝川贋作が24点あり、滝川太郎贋作展は真岡市だけが実現可能な展覧会であるので、必見である。この美術展は、後々語り継がれ、日本美術史上に名を残すに違いない。真岡市の英断に惜しみない喝采を送りたい。
久保貞次郎研究所2019年1月月報(第105回)
渡辺美術館1月より毎週土曜日午後1時から4時開館 2月中来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈
当美術館1月5点追加 稀覯本4冊とフランスの水彩画1点で計932点(恩地孝四郎353点、久保氏関連作品66点)展示
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館は、本年1月から土曜日午後1時~4時開館に改めたが、1月の来館者数は、日曜開館とほとんど同じであった。。あまり頻繁に開館日を変えるのも一貫性がないので、本年中は土曜日開館とし、来年1月からはまた検討したいと思っている。版画、洋書プレゼントは当面継続する予定である。
1月の追加作品は、フランスの画家Paul Aley Deschmacker(1889~1973)の水彩画「花々」(15号)と、書票集(エクスリブリス)限定稀覯本4冊(吾八書房刊)であった。この限定本4冊には私の書票が入っていて、全国の稀覯本コレクターにとって、吾八書房の書票集に自分の書票が添付されることは小さな夢であったのだが、私は20年前に偶然と幸運が重なってその小さな夢を実現出来た。解りにくい内容なので、是非来館なさって私から説明させて頂ければ幸いである。
1月は、まちかど美術館や、知人のお店などに貸し出しをしている作品が10点近くあるが、雨や雪の日以外は屋外に50点ほど展示していて、よく絵の販売店と間違われる。だが極めて貧弱だが美術館の端くれなので、絵の売買は一切していない。また、久保記念館の素敵なイタリアンレストラン「こころ」に、シャガールの版画19点を展示させて頂いているので、上品なお食事を満喫しながら、鑑賞なさって頂ければ幸甚である。
1月の来館者様で、真岡市田町まちかど美術館の「滝川太郎の贋作展」(1月5日~3月4日)も観てきた何人かの方が、素晴らしい美術展であったと、口々に感想を述べてくれた。更に、モジリアーニの「女の顔」のあの澄み切った眼を見た時、とても贋作であるとは思えないと話してくれた。全く同感である。もしモジリアーニ展が開催されて、この「女の顔」が出品されていたら、その展覧会で出色の作品となっていたであろう。滝川太郎は、贋作を描きながら、溢れ出ずる才能を無意識に表出させてしまったのだろか。私も、贋作者の烙印を押された滝川太郎の比類なき才能を惜しむ一人である。3月4日まで開催されているので、是非、かの澄み切った眼を、贋作者の悲しみを、、当時の洋画壇への憤りを、自らの目で観て頂きたい。
当美術館には、油彩画を描いている娘(英国在住)の絵が8点展示されているが、拙宅にある他の作品を写真に撮ってメールしてほしい旨の連絡があったので、探し出して写真を撮りメールを送った。親馬鹿なのかも知れないが、水準に達している作品が20数点あったので、帰国したら、当美術館か、まちかど美術館での個展開催を勧めてみようと思っている。
久保貞次郎研究所2019年2月月報(第106回)
渡辺美術館本年1月より毎週土曜日午後1時から4時開館 3月中来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントは継続中
当美術館2月は14点追加し計946点(恩地365点、久保関連作品67点)展示 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館2月14点追加の内訳は、恩地孝四郎木版10点石版2点と,、竹田愼三郎木版、塙賢三水彩画である。恩地石版2点は、児童書からの切り取り版画で、児童書の詳細は現在調査中。木版10点の内6点は、日本版画協会昭和11年、12年、15年、16年、17年、18年カレンダーからの木版画6点で、極めて珍しい作品である。この6点のうち3点が、形象社恩地孝四郎版画集補遺に掲載されていて、この作品の写真を撮るため、わざわざ外国のコレクターの所まで足を運び、写真を撮るだけなのに、かなりの謝礼を支払ったと聞いている。2016年に開催された東京国立近代美術館の恩地孝四郎展は過去最大の恩地展と言われたが、勿論、このカレンダー版画は展示されなかった。この6点を常設展示している所は当美術館だけかも知れない。御興味のある方は、是非来館して頂きたい。もう1点は、「高見沢本社版」という印の入った木版画で、これも現在調査中である。残りの3点の木版画は、昭和54年平凡社「新東京百景」特装本添付の米田後刷り作品で、これは、よく見かけるありふれ木版であろう。
塙賢三は、お気に入り画家の一人で、当美術館でも3点目の水彩画であり、竹田愼三郎は言わずと知れた久保氏関連画家で、当美術館で8点目の作品となる。
久保氏と恩地との関わりについては、以前にも何度かふれたが、1955年恩地没後、久保氏は、恩地を評価出来ず、それ故作品を多く収集しなかった事を終生後悔した。しかし大富豪の美術評論家と、天皇家と関わりが有る名家の出で、気位が非常に高い貧乏芸術家とでは、水と油で、お互い心を開く事が無かったのではないかと、私は推測している。それでも、恩地他界20年後、形象社恩地孝四郎版画集出版の折、資金不足になった時、久保氏が援助したと言われていて、この版画集は版画レゾネとみなされ、恩地研究には欠かせない貴重本になっている。恩地と久保氏の関わりについては、いまだ未研究の分野だが、不遜ながら当研究所の重要な課題の一つであろう。
2月Ⅰ日真岡新聞に「真高の春の七草粥とK先生の思い出」を掲載して頂いたところ、いつになく好評だったようで、黒い帽子を被り黒ずくめの不審者が自転車に乗っていると、「楽しく読んだよ」、とか「七種粥、私も食べたよ」と何人かの人に声をかけて頂き、嬉しい限りであった。後日K先生の御子息御夫妻が当美術館に来館してくださった。奥様は、絵を描いておられ、作品が展示されているお店「自然派カフェサロンらそす」で多くの作品を鑑賞出来た。全ての作品から醸し出される生命感に、自分の精神が心地よく揺れ動くのを自覚出来た。芸術性豊かな水彩画大作も展示されており、額の中に我らには未知の新たな世界を創り出せる本当の芸術家が、また一人、真岡市に現れたと確信した。
久保貞次郎研究所2019年3月月報(第107回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館 4月来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントは継続中
当美術館3月は5点追加し計951点(恩地369点、久保氏関連作品67点)展示
久保記念美術館「深沢史朗展」(~4月15日)、真岡市まちかど美術館「浅香公紀展」(~5月6日)について
3月16日、真岡市田町まちかど美術館に「浅香公紀展」、荒町久保記念美術館「深沢史朗展」を観に行った。浅香氏は言わずと知れた真岡市出身の優れた木版画家で全国に愛好家蒐集家が少なくない。9年前の平成22年、真岡市主催の「浅香公紀氏を偲んで」展が「金鈴荘」で開催され、展評を真岡新聞平成22年10月22日号に掲載させて頂いた事があった。
今回の浅香公紀展では、計28点の木版画が展示されており、優しい眼差しで自然を捉え、心温まる色彩と形状で自然を表現する氏独自の感性が、我らの精神の内奥まで染み渡って来て、気が付くと静かな展示室で我を忘れている。特に印象的であった作品は、「城山公園」木版画で、我ら腕白小僧が遊びに遊んだ昔の城山公園が描かれていて目頭が熱くなった。現在の整備された城山公園の写真も展示されており、学芸員諸氏のタイムリーヒットであろう。
第19回企画展「没後40年深沢史朗展」には、深沢作品13点、島州一2点、木村利三郎2点、愛嘔2点、吉原英雄2点、池田満寿夫4点計25点が展示されており、壮観であった。深沢氏の名を世に知らしめた「Sharaku and I」も展示されており、素敵な美術展であった。それにしても、真岡市でしか観られない貴重な美術展を、無料で同日に二展観覧出来るとは信じられない事である。市当局並びに関係者の皆様に心より感謝したい。そしてこれらの歴史に残る素晴らしい文化事業について、胸を張ってもっと声高にアナウンスすべきだと思う。
当美術館3月の追加作品は5点で、著名な日本画家山本倉丘の御長男で京都画壇の重鎮であった山本知克氏の初期作品「畦道」20号が1点。残りの4点は恩地孝四郎木版画「上野動物園」、「温室」、「日の出」、「藤沢薬品木版カレンダー」(恩地木版3点入り)であった。「温室」、「日の出」も希少であるが、特に「藤沢薬品木版カレンダー」は極めて貴重で、日本の美術館ではほとんど蒐集されておらず、調査の結果、1989年大英博物館が、浮世絵研究家ロバート・ベルゲス氏から購入したという記録があった。また日本では、江戸時代から続く京都西陣老舗「帯屋捨松」製造部が所蔵しているだけのようである。恩地作品は「1月2月京の雪」、「5月6月内海にのる」、「9月10月銀座のたそがれどき」の綺麗な木版画3点が所収されている。1978年刊行形象社恩地孝四郎版画集補遺ではNO18,NO19,NO20で、「京の雪」が「舞妓」になっていて、他は失題でとなっており、3点とも前述のロバート・ベルゲスコレクション所蔵と記されている。推測だが、形象社関係者がベルゲス氏を訪問し、謝礼を払い写真のみ撮って帰ってきたのだろう。もし詳しくこの木版カレンダーを調査出来ていたら、題名間違いや失題にはならなかっただろうから。
芸術作品の普及は、美術館、百貨店、画商、古書店などが担ってきたが、優良企業がカレンダーという形で、若手の実力画家を登用し、無償で一般大衆に提供する事も、隠れた有力な普及方法であったのかも知れない。そう言えば、私も浅香氏から素晴らしい木版カレンダーを何度も頂いた。もしかしたら浅香氏は、芸術普及思想の根底を熟知して、有名画家になろうとする努力よりも、木版カレンダー制作無償配布の方に情熱を傾注していたのではないのだろうか。
当美術館では、この貴重な藤沢薬品木版カレンダーが間近に鑑賞出来ますので、是非来館なさって下さい。
以前、芳賀教育美術展の副賞700点用愛嘔シルクスクリーン版画は、在庫切れで本年限りとお伝えしたが、3月中に幸運にも更に700点購入出来たので、来年も副賞として提供出来ることになった。2010年から久保研究所で副賞を提供させて頂き、2014年までの5年間はギュスタブ・ドレ鋼板画を贈呈させて頂いた。2015年からは愛嘔のシルク作品を提供し、今年で5年目になる。来年も提供できれば、何と4200点の同一版画を芳賀郡の少年少女に受け取って頂いた事になり、歴史的にも美術史的にも希有であろう。乞う御期待。
久保貞次郎研究所2019年4月月報(第108回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館 5月来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館4月は9点追加し計960点(恩地371点、久保氏関連74点)展示
久保記念美術品展示館の年間展覧会決定 6月15日土曜日渡辺美術館臨時休館 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館4月の追加作品は9点で、久保氏関連作品7点、恩地稀覯本2点である。久保氏関連7点の内訳は、浅香公紀木版画1点、木版画本一冊、長倉翠子資料、久保氏関連本3冊、7点目は、「みずゑ」昭和26年2月号(544号)。「みずゑ」は、当時、メジャーな美術雑誌であったが、この544号は、久保氏が、自らの児童美術教育論文で全ページ埋め尽くし話題になった号である。どれ程費用を要したかは定かでないが、確かな事は、児童美術教育に対する久保氏の計り知れない決意と覚悟がそうさせた、という事である。昭和26年と言えば、くしくも、創造美育協会設立の前年である。日本における児童美術教育の金字塔になったこの小冊子を手にとって頂き、久保氏の鋼(はがね)のような信念に思いを馳せて頂ければ幸いである。
恩地2点は、木版「のこるこころ」入り形象社恩地版画集と、昭和9年版画莊刊行「飛行官能」で、前者はよく見かけるが、後者は、スーパー稀覯本で、20年かけて、10数年前幸運にも入手できた版画本である。版画と写真と詩をちりばめた飛行機賛歌の本であるが、昭和9年当時、全く注目されず、ほとんど破棄され、現在確認されている完本は僅かである。この本の古書価格が急騰したのはここ10年で、8年ほど前、渡辺私塾文庫所蔵作品としてホームページに掲載した所、有名古書店から買取依頼があり、その価格は、心が揺れ動くほどの高額であった。
先程、飛行機賛歌の本であると表現したが、恩地孝四郎は、飛行機や機関車などを、人類進化の勝利の象徴、一里塚と捕らえる柔軟な歴史観を持った芸術家であった。恩地は、現在でも「抽象版画の祖」と称されるのみであるが、実際は、版画家、装幀家、詩人、作曲家、写真家、文明批評家であり、久保氏と同様、研究が進む連れて、歴史上光り輝く巨人となるに違いない。
市内荒町の久保記念美術品展示館の年間展覧会予定が公示された。第20回企画展「没後30年 北川民次展」(5月16日~7月15日)、第21回企画展「アニマルワールド」(7月18日~9月16日)、「芳賀教育美術展歴代の知事賞展」(9月19日~10月7日)、第33回真岡市美術展(10月10日~10月14日)、第22回企画展「写真X版画」(10月17日~2020年1月20日)、栃木県立美術館展「野沢一郎が愛した美術」(2020年1月23日~2月3日)、第23回企画展「四季折々展」(2020年2月6日~3月30日)。企画展は真岡市所蔵の久保コレクション、宇佐美コレクションからの出品で、真岡市でしか開催できない貴重な美術展である。真岡市田町のまちかど美術館の年間展覧会については、5月月報で掲載予定。
真岡市には入場無料の美術館が4箇所あるのをご存じであろうか。久保記念美術館、まちかど美術館、趣味の美術館(認定まちかど美術館)、渡辺美術館(認定まちかど美術館)で、それぞれ独自の視点、思想を持って作品を展示している。日本で、小美術館ながら4箇所も美術館のある市は希有であろう。久保氏は、「芸術を生活の中に浸透させる」事が、人類の進化の証であると考えたが、多くの人達は、花火、お花見、お祭り、音楽、映画、読書等で、立派に自分たちの生活の中に「潤い」を取り入れている。だが、日本では、美術館に行って、額縁の中に潜んでいる、「色」、「形」、「未知の世界」に心を奮わせる習慣はまだ悲しいほど根付いていない。60数年前、久保氏による「創造美育運動」、「小コレクター運動」を核として、真岡市が、美術教育において、日本の、いや世界の最先端都市であった事を想起すれば、日本の停滞した美術の現状をお祭りのようにおおらかに打破するのは、真岡市に他ならないと、私は、鋼のように強く夢想している、
なお、6月15日土曜日は、当美術館余儀ない理由で臨時休館致します。申し訳ありません。
久保貞次郎研究所2019年5月月報(第109回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(6月15日は臨時休館) 入場無料 6月来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館5月は3点追加し計963点(恩地373点、久保氏関連74点)展示 「公刊月映Ⅳ号」を展示
当美術館所蔵藤田嗣治版画2点、真岡市田町まちかど美術館に貸し出し 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館5月追加作品は3点で、いつになく少ないが、3点とも重量級で、1点は、大正4年(1915年)発行の幻の稀覯本「公刊月映Ⅳ号」である。 3年前、NHK番組日曜美術館「恩地孝四郎」制作のための来訪目的の1つが、この「月映Ⅳ号」の撮影であった。「月映」は、国立図書館や国立西洋美術館等には所蔵されているのだろうが、手続きが煩雑で、撮影時の光量など細かい規制が有り、5人の制作スタッフで真岡までわざわざ訪問したのは、「月映Ⅳ号」を、心ゆくまで自由に撮影したかったためなのだろう。当美術館には「公刊月映Ⅰ号」の恩地木版4点が既に展示されているが、恩地木版6点が含まれているⅣ号を間近に鑑賞して頂ければ幸いである。このⅣ号には、17歳で永逝した妹芳子の死の悲しみを昇華結晶させた、藤森静雄の傑作木版7点が収録されている。特に第1作「亡びゆく肉」は、鬼気迫る作品で、機械的に作業をしていたNHKスタッフもこの作品に出会った時、息をのみ無言で数十分予定外の撮影を続けていた。その7年後、文学の世界では、宮澤賢治が、24歳で妹トシが永眠した時、「永訣の朝」、「松の針」、「無声慟哭」の歴史的作品三部作を書き上げた事と、不思議な芸術的共鳴を感じざろうえない。
全くの私見だが、日本近代版画史上の最高傑作版画は、この藤森静雄「亡びゆく肉」と、恩地孝四郎「萩原朔太郎像」だと思っている。朔太郎晩年の悲嘆と苦渋の中、屹立する人間の強さを表現した「萩原朔太郎像」は、「抽象版画家恩地孝四郎」とは無縁で、それ故、「抽象版画の祖」のみで、恩地を括るのは誤謬である。蛇足ながら、前述の宮澤賢治三部作と、萩原朔太郎の「竹」、「帰郷」の資料も当美術館に用意されているので、来館時お申し出頂ければ贈呈致します。思い起こせば、4年前美術館開館時から、お子様お絵かきコーナーを設け、絵が苦手なお子様には、原稿用紙を用意し言葉で自分を表現する事を奨励していた。極めて貧弱な施設だが、当美術館の最終目標は、総合芸術館であろうと思っている。久保氏も天国で微笑んでくださっているに違いない。
追加作品もう1点は、妹尾正彦油彩画8号「鷹」で、当美術館は、傑作「鯰とひょうたん」油彩画20号も所蔵しているので、妹尾作品2点を寄り添うように並べて展示している。妹尾氏は私の好きな画家の一人で、動植物、子どもを好んで描き、動植物と人間の生命の繋がりを表現する数少ない画家である。
最後の1点は、「山田耕作童謡百曲集」(百冊全揃)、(昭和2年~4年)(全冊恩地装幀)である。恩地装幀なので、かなり以前収集したのだが、現在百冊全揃いは極めて貴重で、山田耕作研究家から問い合わせが有り、20点ほどの楽譜のコピーを贈らせて頂いた事があった。
真岡市田町まちかど美術館で、「北川民次絵本原画展」(前期、「ジャングル」、5月9日~7月8日、後期、「うさぎのみみはなぜながい」、7月11日~9月2日)が開催されている。この美術展も真岡市所蔵久保コレクションからの出品で、真岡市しか開催出来ない必見の展覧会である。この美術展開催前、市から、当美術館所蔵の藤田嗣治版画2点の貸し出し依頼があり、前期で、「母子像」、後期で「夢」を喜んで貸し出す事が出来た。メキシコの大地に根ざした北川民次と、西洋美術を背景に独自の世界を創り上げた洋画家藤田嗣治とは、不思議なとりあわせであるが、二人は長年にわたって深い交流があり、互いの芸術を理解し尊敬しあう間柄であった事は、美術史的には、良く知られた事実である。
4月末、フランスを訪問した恩義のある知人に、お土産は何が良いだろうかと相談を受け、当美術館重複所蔵の夢二木版画2点を、旅の餞別として受け取って頂いた。芸術の本場フランスでも、夢二版画は大好評で、訪問先の方々も、うっとりしながら早速、居間に飾ったとのことであった。竹久夢二は、日本のアカデミズムでは、ほとんど評価されていないが、大衆的人気画家としては、10指に入るであろう。もしフランスで夢二が周知されれば、日本人画家として5指に入る可能性もある。当美術館でも、二階に夢二版画80点、挿絵原画3点が展示されている。来館を心よりお待ちしております。
久保貞次郎研究所2019年6月月報(第110回)
li 渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2人以上の来館者様で随時開館、℡090 5559 2434まで)
入場無料、7月来館者様全員に拙書著作集第7巻贈呈、版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館6月は5点追加し計968点展示(恩地孝四郎作品373点、久保貞次郎関連作品75点)
真岡市田町まちかど美術館年間スケジュール決定 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
真岡市田町まちかど美術館2階常設展示室の年間スケジュールが発表された。「北川民次絵本原画展」(前期2019年5月9日~7月8日、後期7月11日~9月2日)、「メキシコに生きる画家 竹田鎮三郎」(9月5日~11月4日)、「靄嘔 虹のはじまりを探して」(11月7日~2020年1月6日)、「花を愛でる 花を描く」(前期2020年1月9日~3月9日、後期3月12日~5月11日)。全て、真岡市所蔵の久保コレクションを中心とした美術展で、真岡市でしか開催出来ない貴重な展覧会であり、入場無料である事、火曜日以外全日開館している事など、必見の美術展である。真岡市の、地道だが歴史に残る文化事業に心より敬意を表したい。久保氏が住んだ真岡市には、小さいながらも入場無料の4つの美術館があり、市当局が、久保氏の思いを受け継ぎ、連綿と文化事業を継続しているという事は、後世驚きをもって高く評価されるであろう。
当美術館6月の追加作品は5点で、油彩画3点と竹久夢二木版画及び木版画集の計5点である。油彩画3点は、久保氏関連作家安藤幹衛「岩場」10号、古沢岩美美術館旧蔵古沢作品「ミモザ」パステル12号、3点目は、昭和28年リスボン世界観光ポスターコンクール最優秀作品油彩原画栗谷川健一「ムックリを鳴らすアイヌ娘」30号である。栗谷川氏の最優秀作品ポスターは、つとに有名で、北海道のいくつかの美術館に展示されているが、そのポスター作品には、30号の油彩原画が有ることは余り知られていない。栗谷川氏の出身地である北海道岩見沢市市役所に、最優秀作品ポスターには,30号の油彩原画が有る事、その原画を、遥か栃木県の小美術館で展示中である事を、お知らせした。大変驚かれていたが、感謝されたのは言うまでも無い。この油彩画は、11年前東京の中規模の絵画オークションで落札した作品である。そのオークションの参加者の多くが画商さんで、作品の質など眼中に無く、値上がりが期待できる名の通った画家の作品にしか入札出来ず 結局、この傑作油彩画に入札したのは私一人で、最安値で入手出来た。自分の眼を信じ、気に入った作品を入手するという本道からかけ離れた日本の絵画市場は、芸術の道から遠く離れ、利潤追求主義に毒されて、根底から歪んでいる。
傑作「ミモザ」が、閉鎖した古沢岩美美術館から、流れ流れて北関東の外れの小美術館にたどり着いたのも奇縁である。女体を好んで描くエロ画家と揶揄された古沢岩美氏に対して、私は全く異なった見解を持っており、反戦画家であると同時に、女性や母性に人類の救い、光明を見出す希有な洋画家だと確信している。その旨をホームページに掲載したところ、古沢氏の御子息が、東京からわざわざ来館なさり、感謝のお言葉を頂いた事は、以前月報で述べた通りである。
安藤幹衛油彩画は、以前二科会出品大作7点を真岡市に寄贈させて頂いたので、当美術館では版画を除いて未展示であったが、10号の油彩画をやっと展示できた。岩の質感が独特で良い作品である。これで久保氏関連展示作品は75点になった。
夢二作品2点は、どちらも加藤版画研究所作品で、俗に「加藤版」と呼ばれ、「高見沢版」などに比べてかなり高額であったが、やっと落ち着いた値段になり、所蔵できた。肉筆挿絵原画3点も加えて夢二作品は、いつの間にか85点の展示となった。恩地作品常設展示373点は希有中の希有だが、夢二作品85点常設展示も希有であろう。
2度目の来館者様に贈呈させて頂いた新井苑子リトグラフ「The Green」(限定150部のうち100部用意)も、昨年末に底が突き、何人かの来館者様にご迷惑をおかけしたが、ポール・ギャマンリトグラフ「黄昏の馬」、同一作品30点が入手出来たので、2度目の来館時、新井作品の代わりに「黄昏の馬」をプレゼントさせて頂く予定である。「2度目の来館時、品切れだった」、「2回目の来館です」とお申し出下さい。残り27部ですので、すぐ無くなるでしょうから、現在何十部かの同一版画作品を探している最中です。
絵を飾るスペースがもう皆無で、100点ほど外に立てかけて展示していますので、雨の日は外に出せず、展示作品数が少なくなる事をご容赦下さい。また、絵を館内に戻すのに30分ほど時間を要しますので、午後3時30分を過ぎて来館者様がいない時は、午後4時を待たず、早めに閉館する場合もある事を、お許し下さい。
久保貞次郎研究所2019年7月月報(第111回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で随時開館 Tel090 5559 2434まで)
入場無料 8月来館者様に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館7月は5点追加し計973点展示(恩地孝四郎373点、久保貞次郎関連79点)
田町まちかど美術館に、藤田嗣治版画「夢」貸し出し 8月17日はお盆休みで休館 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月10日、真岡市田町まちかど美術館「北川民次絵本原画展」(後期7月11日~9月2日)展示のため、藤田嗣治石版画「夢」を借り受けに、市職員2名が来館された。北川氏と藤田氏の関係は、5月月報で言及した通りである。
美術品は、国民、市民の財産でもあるという主旨のもと、当美術館では、貸し出し依頼に対して、一切無償で対応させて頂いている。資料請求依頼を含めれば、100件を超えるであろうが、少しでもお役に立てればという思いの中で、その対応は、不思議にも純粋な喜びである。
7月8日、久保記念観光文化交流館内レストラン「こころ」で、私の誕生日を、妻と二人でささやかに祝った。いつものようにシェフお任せコースで、素敵な夕べであった。「こころ」はお店の改装で少し狭くなったようだが、無理を言って展示させて戴いているシャガール版画19点は、店内の壁面を綺麗に飾っている。シャガール版画19点が鑑賞できるレストランは、そうは無いであろうから、真岡市の隠れた名所に違いない。
7月4日、真岡青年会議所の役員4名の方々が、久保氏が創設に関わった第33回芳賀教育美術展の審査及び支援依頼のため来宅された。今年度の青年会議所理事長は10年来の気心の知れた友人であるので、全ての依頼を快諾した。美術展の副賞を提供させて頂いて今年で10年目、最終審査員を務めて9年目になる。今年と来年の副賞1400点は、靄嘔の「ラブレターズ」を鬼の形相で収集したので、一安心であるが、再来年はどうしようかと考え始めている。今年度も、表彰式閉幕時、黒い服を着た変なおじさんが副賞の解説を兼ねて、10分ほどお話をする許可を得た。過去、「綺麗な言葉を使いましょう」、「子供は褒めて育てましょう」、「子供の絵を観る力は素晴らしい」であったように記憶しているが、さて、今年は何を話そうか。
7月20日、鹿沼、宇都宮、益子から7名の美術関係者が来館された。当美術館に、第1回川上澄生版画展準大賞出品作品高久茂作「スカーフ」が展示されているのを観て、鹿沼からいらっしゃた方が驚かれていた。高久氏木版大作は、あと2点所蔵しているので、機会があれば展示したい。
7月の追加作品は5点で、4点は久保氏関連本、他の1点は、私のお気に入りの型染め作家、神崎温順の「木霊之譜」である。久保関連本は、古川龍生木版画全集「田園叙情」(久保編)、古川龍生スケッチ帖(直筆ペン画、16ページ)、「瑛九展」(エッチング「屋上」入り、久保論文「瑛九のひとと芸術」所収)、木内克「エーゲ海に捧ぐ」(リト1点入り、久保小論「人間解放の書」所収)の4冊である。古川龍生直筆スケッチ帖は珍しいかも知れない。
「木霊之譜」は、10部限定型染大判16図の大作で、27日に来館された清原の方と、息をのみながら一緒に鑑賞した。神崎氏は、没年等詳細不明であるが、全国に少数ながらも熱狂的なファンを持ち、芸術性の極めて高い型染め作家である。天理図書館に多くの作品が所蔵されていると言われているが、当美術館、当文庫には天理図書館に劣らぬ数の作品が所蔵されており、大作では「火焔之譜」のみ、未だ未所蔵である。私が生存中、「火焔之譜」にはたして邂逅出来るだろうか。
昨年の8月31日から12月21日にかけて、「遥か数万年後、全ての人が芸術家である社会について」と題する4回シリーズの拙文を当紙に掲載させて頂いたが、時代を飛び越えた内容であり、読んでくれた方は数名であろうと思っていた。しかし今年に入って、芸術関係者、学者、宗教家、政治家の方々から、4回全文まとめて読みたいので送ってほしいという問い合わせが有り、嬉々として対応させて戴いた。中には、話が聞きたいと、中央の新進気鋭若手政治家も来訪して下さり、恐縮した次第である。時代を先走り、難解な内容だからと、一時執筆を思いとどまったが、やはり、書きたいときに書いておき、公表しておくべきだと再確認した。当美術館でも15部用意し、まだ7部残っている。「4回シリーズ有りますか」と言って頂ければ贈呈致します。それにしても当紙真岡新聞は、購読無料の週刊新聞だが、市内全戸及び芳賀郡、清原、上三川町一部配布、6万2千を超える発行部数を誇り、意外にも底知れぬ浸透力を持ち、ありがたい事だが、全く侮れない地元密着型地方新聞である。真岡新聞とは、「高校への5科教室」から始まって、かれこれ40数年のお付き合いになる。真岡新聞関係者の皆様に心底より感謝したい。
久保貞次郎研究所2019年8月月報(第112回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜以外電話予約で随時開館 ℡090 5559 2434まで)
入場無料 9月来館者様に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館8月は9点追加し計982点展示(恩地孝四郎373点、久保貞次郎関連83点)
久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月31日、下都賀在住の方が、当美術館に浅香公紀木版カレンダー10年分を寄贈してくださった。御礼に、私の訳の解らない拙書著作集1巻から7巻までの7冊と、平成の奇書「潮に聞け」の8冊を贈呈させて頂いた。100年後に人気の出る本ですから、と言ってお渡ししたせいか、笑いながら喜んで受け取って頂いた。木版カレンダーは、1968年度から1979年度の間の10年分で、貴重な初期の作品である。浅香氏後期の華麗な花の作品と違って、土着性の強い作風で、この時期の作品はほとんど残存していないと思われる。私が浅香氏から,直接頂戴し、真岡市に寄贈させて頂いた木版カレンダーは、確か後期の作品であったと記憶している。この希少な初期木版カレンダーは、展示作品979番として、2階の浅香公紀コーナーに有り難く展示した。
8月追加9点の内、額入り作品は1点のみで、神崎温順型染め「日本海岸」である。神崎氏については以前何度か言及したので今回は割愛する。額入り作品を展示するスペースが皆無のため、今後は版画入り稀覯本中心の追加をと考えている。 残り7点のうち4点は渡辺文庫洋書部から洋書初版本4冊を展示した。内訳は、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」(1869年)、「鏡の国のアリス」(1872年)と、チャールズ・ディケンズ「デビッド・コッパーフィールド」(1850年)、「荒涼館」(1853年)の4点である。「不思議の国のアリス」は厳密には第2版なのだが、1860年代発行のアリス本は通常初版本とみなされている。「鏡の国のアリス」は、誤植のある初版中の初版で、両書とも端麗な多数の木口木版挿絵で飾られており、この稀覯本2冊を所蔵している所は、日本でも多くないであろう。チャールズ・ディケンズの2冊は、木口木版挿絵でなく、鋼版画挿絵で、鋼版特有の鉄染みが目立つが、2冊の初版本は貴重であろう。特に「デビッド・コッパーフィールド」1850年初版本は、日本に何冊あるのであろうか。1世紀半前の有名初版本を手にとって鑑賞して頂ければ幸いである。
他の3点は、全て久保貞次郎関連本で、北川民次書票付き久保氏旧蔵本2冊(「ベルト・モリゾ」(仏文)と「スペイン絵画史」第4巻1933年)が1点(2冊まとめて展示番号980番とした)。書票とは、エクスリブリスと呼ばれ、自分の本である事を明示するため、本の表紙裏に添付する綺麗な札で、高級な書票の場合、有名画家の版画を添付する場合が多い。久保氏は、主に北川民次氏の版画書票を重用し、この2冊とも、同一の北川書票が使われている。北川書票添付の久保氏愛用書を手に取り、半世紀前の文化の香りを味わうのも一興であろう。
残りの2点は、久保氏旧蔵本「飯野農夫也版画集」(1974年)、「飯野農夫也作品集」(1976年)で、前者の版画集は、並装本と特装本を展示した。並装本には、飯野氏手書きの久保氏献呈書き込みが有り、特装本は限定40部の木版画入りである。後者の作品集は久保貞次郎編で、木版3点入り、限定80部の稀覯本だ。飯野農夫也氏(1913~2006)は、茨城県真壁郡(現筑西市)生まれで、真岡中(現真岡高)卒である事は余り知られていないが、真岡市とは関係の深い芸術家である。久保氏、新居広治氏と親交があり、35歳時、真岡高、真女高合同講習会を行い、受講生の中に、後に版画家となる秋山静氏がいたと言われている。晩年、81歳の時、名古屋日動画廊で、故北川民次と二人展を開催しており、中央ではよく知られた木版画家であった。34歳時、新版画懇話会結成に関わり、恩地孝四郎、小野忠重、北村文雄等とも知己を得ている。前述の二つの版画集は、飯野氏の代表的作品集なので、貴重な特装本2冊を同時に鑑賞して頂ければ幸甚である。
8月24日、東京から美術関係者3名、矢板から2名の女性が来館してくださった。当美術館について、波紋が波紋を呼ぶように、日本中にほんの少しずつ浸透はしているのであろうが、地元真岡市、芳賀郡の方々の来館者が少ないのは残念である。当美術館は2015年5月に開館し、最初、開館日は日曜日のみであったが、次に日曜日以外全日予約開館、現在は土曜日と日曜日以外予約開館にしている。来館者数が多いのは、現在の開館形態であるので、当分この形式でやっていこうと思っている。以前、ある来館者様が、「ちょっと敷居が高くて」とおっしゃっていた。まちかど美術館巡りをして、ぶらっと立ち寄って頂ければ、私としてはこれ以上の喜びは無い。解説を求められればお答えさせて頂くが、静かな鑑賞がお望みであれば自由に観て頂ければ良く、写真撮影、模写も自由である。日常色に染まった時、額縁の中のまだ見ぬ新しい世界、色、形に、思わずはっとして、心を震わせるのも決して悪いことでは無いだろう。
久保貞次郎研究所2019年9月月報(第113回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜以外電話予約で随時開館 ℡090 5559 2434まで)
入場無料 10月来館者様に拙書著作集第7巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館9月は2点追加し計984点展示(恩地孝四郎373点、久保貞次郎関連作品83点展示)
第33回芳賀教育美術展に最終審査員、表彰式プレゼンターとして参加 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
久保氏が創設に関わった第33回芳賀教育美術展に、9月13日子供審査会、19日最終審査、29日表彰式プレゼンターとして参加した。久保研究所で副賞を提供して本年度で10年目を迎え、最終審査員としての参加から9年が経った。最古参の一人になったが、煩雑を極める美術展運営において、真岡青年会議所メンバーの身を切るような献身的努力を目の当たりにして、なるべく僭越、横柄にならないよう留意している。
副賞は、最初の5年間は、ギュスタブ・ドレの鉄版画を用意したが、直近5年は毎年入選者700名全員に、靄嘔のシルクスクリーン版画「ラブレターズ」(1974年作)を贈呈している。今年で5年目なので、計3500点の「ラブレターズ」を提供した事になり、来年度の700点も蒐集しているので、来年で計4200点、芳賀の子供達に受け取って頂くことになる。このシルク版画は、久保氏のアドバイスで、11111点も刷り上げ、話題になった作品だ。久保氏は、一人一人が3点以上のオリジナル作品を身近に置き、生活の中に芸術を浸透させる、という「小コレクター運動」を提唱したが、その思想を背景に、多くの人が所有鑑賞できるよう1万点以上を制作するよう靄嘔氏を鼓舞したのだろう。40年経って、真岡市の久保研究所が5千点もの「ラブレターズ」を蒐集し、芳賀の子等に提供出来るとは、数奇な縁、運命を感じざろう得ない。百年、2百年後、「何故、この靄嘔作品が、芳賀の大地に宝石のように散りばめられているのだろうか」と口々に語り継がれる時代が必ずや来るであろう。
13日の、子供が子供の絵を評価する子供審査会で感じた事を率直に言わせて頂けければ、多くの関係者がまだ、子供の絵を見る力は、本質的に大人の評価能力より優れているという確信が不足してるように思えた事である。大人のプロの画家の絵を評価する審査員も子供であるべきだという確信は、21世紀初頭では困難な確信なのだろうか。
最終審査会でいつも感じる事だが、入選、入賞の決定は、審査員の主観、好みで大きく左右されるという事である。審査員が替われば受賞者も入れ替わるであろうから、賞に漏れたからといって、作品を創るのを決して止めないでほしい、と強く言いたい。芳賀教育美術展で、一度も授賞しなかった子でも、将来優れた芸術家になる可能性は充分有るという事を、一体誰が否定できようか。
表彰式では、毎年久保貞次郎研究所賞の授与と、副賞の紹介をさせて頂いているが、ついでに、題名を決めて、短いお話をするのを許してもらっている。3年前は「綺麗な言葉を使いましょう」、2年前は「子供は褒めて育てましょう」、昨年は、「子供の絵を観る力は素晴らしい」であった。今年は「女性を大切に致しましょう」にした。易しくない話であるのに、お子様、御父兄、来賓の方々も、熱心に聞き入って頂き、汗顔の至りである。
9月の追加作品は2点のみであるが、どちらも重量級であった。1点は「書窓版画帖十連聚全9冊」、アオイ書房、昭和16年~18年、全冊ナンバー148番である。戦前の刊行で、同じナンバーの全冊揃いなので、希少であり、全冊鑑賞出来る所は日本でも数少ないに違いない。出版順に「文明開化往来(川上澄生)」、「港都情景(川西英)」、「都会生活(織田一麿)」、「宇宙説(武井武雄)」、「新野外小品(前川千帆)」、「東京の窓(関野潤一郎)」、「水韻譜(逸見亮)」、「蟲・魚・人(恩地孝四郎)」、「伊豆一周畫詞(平塚運一)」の全9冊。なお恩地孝四郎の「蟲・魚・人」は、当美術館では以前から展示している。
もう1点は小杉放庵「奥の細道画冊」で、春陽堂昭和7年版(木版43点)、龍星閣昭和30年版(小本)、春陽堂47年版(印刷画43点)の3冊セットを展示した。特に、綺麗な木版43点入りの春陽堂昭和7年版は希少で、幻の稀覯本と言われている。日光の小杉放庵美術館に問い合わせた所、昭和7年版は未所蔵との事であった。世界最高の放庵関連美術館でも観られない原本なので、是非来館して頂き、間近で鑑賞して頂ければ幸いである。更に驚くべき事は、45年に及ぶ私の稀覯本蒐集の中で、この幻の稀覯本を3点所蔵している点である。43点の木版画をばらして額に入れ、販売されているの何度も見聞きした時、妙な正義感で、散逸を防ぐため蒐集しておこうと思い立ち、いつの間にか3点所蔵していた、というのが実情である。そして更に恐ろしい事だが、木版43点のうちの1点「永平寺」の肉筆原画を当美術館で、美術館設立時から所蔵展示している。真作かどうかは不明だが、掛け軸から額装し直した作品で、掛け軸の共箱、共書きも付いている。この幻の稀覯本一冊は、小杉放庵美術館に寄贈すべきだ、という考えも頭をよぎるが、まだ勇気も時間も不足していて、その決心には至っていない。
久保貞次郎研究所2019年10月月報(第114回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜以外電話予約で随時開館 ℡090 5559 2434まで)
入場無料 11月来館者様に著作集第7巻贈呈、版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館10月は1点追加し、計985点展示(恩地孝四郎374点、久保貞次郎関連83点展示)
真岡市で、久保氏関連本無料配布(10月10日から来年3月30日まで)
真岡小2年生9名が町中探検で来館 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館10月の追加作品は1点のみであったが、9月に続いて重量級の作品を追加できた。恩地孝四郎作昭和10年、アオイ書房「季節標」特装本(限定50部、恩地木版3点入り)、仮装本(特装本に付いている版画無し本)、並装本(限定200部、恩地木版1点入り)の3点セットである。この3点を同時に鑑賞出来る所も極めて少ないが、並装本に、何と、恩地孝四郎肉筆画が描かれている。そしてドイツ語で、肉筆画のタイトル「春の喜び」と「ヘルン・スダ氏へ、1936,4月」という献呈署名が記されていて、この並装本は、特装本を遥かに凌ぐ、1点物のスーパー稀覯本である。ヘルン・スダ氏に、恩地自ら恩地独自の抽象画を描き、贈呈したのであろう。入手出来たのは、計り知れない程の幸運であった。市内、郡内、県内の一般の方々、都会の恩地研究家も是非来館して鑑賞して頂ければ幸いである。
真岡市は、10月10日から来年3月30日まで、久保氏関連本の無料配布を始めた。久保氏関連本は、古書業界でもやや高額なので、俗な言い方だが、真岡市の「太っ腹」には驚きである。それでも久保氏の思想の普及には、著作の普及が一番効果的であるので、市当局の英断には惜しみない拍手を送りたい。当美術館でも、田町まちかど美術館で、早速制限冊数一杯、大変有り難く頂戴いたした。10月18日金曜日、横浜在住で、創造美育運動の研究家であるご夫婦が来館なされた。お話を聞くと、やはり、真岡市から久保氏関連本を頂いた帰りであると言う。また、後日、大学の先生からご連絡があり、久保氏関連本を真岡市に頂きに来訪なさったとの事であった。このように、遠方から久保氏関連本を求めて多くの方がいらっしゃるのであるから、少なくても真岡市民は、この機会に最低一冊は久保氏の本を入手し、久保氏が創設した思想・文化の香りに触れてみるのも一興ではないだろうか。更に、田町まちかど美術館で関連本を頂いた時、「真岡市ゆかりの美術評論家 久保貞次郎」(久保記念観光文化交流館 開館5周年記念)という小冊子も一緒に拝受した。僅か16ページの冊子だが、久保氏の思想、経歴、諸活動がカラー写真入りで網羅されており、素晴らしい冊子である。2019年真岡市教育委員会発行とあるが、教育委員、学芸員、市関係者の並々ならぬ御努力が垣間見る事が出来て、頭の下がる思いであった。久保研究所代表をしている私でさえ、これほど久保氏を全的に捉えた本は初めてであり、この小冊子は、久保氏研究史上長く歴史に残るであろう。
10月3日、真岡小学校2年生9名と引率者3名の方々が、町中探検で来館された。今年で2回目になる。礼儀正しく、好奇心に満ちて、きらきら光る宝石のような児童達との出会いは、私の精神を喜びで満たし、自分の生き方を自省する機会を与えてくれる。
最初の挨拶で、帰りに、一番気に入った絵を私に教えてほしいと、9名の児童にお願いした。開館して5年近くになるが、いつも気付く事は、子どもの方が、大人より一つの作品を観る時間が長く、子どもは、感想、印象をその場で体で表現したり、歓声を上げたりして反応するという事である。もし、都会の美術館で、大人が体で表現したり大声で歓声を上げたりしたら、怖い警備員につまみ出されてしまうだろう。さて、私は問いたい。美術館で静に鑑賞する方法と、子どものように大声を出し楽しく鑑賞する鑑賞法では、どちらが本当の絵の見方であろうかと。答は言わずもがなだ。子どもの絵の見方は、無用な先入観、無意味な知識とは無縁で、直截で本質を見抜く力を所有する。だから瞬時の反応が多種多様で豊かで、歓声を上げたり、躍り上がったりするのだ。
一番好きな絵に話を戻そう。子供たちは、高額廉価、有名無名、洋画日本画、美術史、技法などに無頓着で、ある意味健全である。子供たちにとっては、楽しいか、おもしろいか、綺麗か、はっとするか、思わず見入ってしまうか、などが問題なのだ。当然一番好きな絵も多様であったが、最後の男の子が、不動の信念を込めて力強く指差した作品には驚かされた。1929年、アルス日本児童文庫第62巻口絵、恩地孝四郎肉筆原画「都会と田舎」であった。今までに来館された千数百名の来館者全員が気にも留めなかった水彩小品を、この子はためらわず選んだ。そう言えば、恩地は、子どもが読む児童書の表紙絵、挿絵、口絵原画を作成する時は、高額な水彩絵の具を使い、全霊をを込めて描いたと言われている。この子は、その恩地の執念を、しっかり感じ取ったのだろうか。いずれにしても、子どもの絵をみる力は、大人に引けを取らないという提言は、あながち否定できないと、私は思う。
久保貞次郎研究所2019年11月月報(第115回)
渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜日以外電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434まで)
入場無料 12月来館者様に拙書著作集第8巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
当美術館11月は2点追加し、計987点展示(恩地孝四郎375点、久保貞次郎関連83点展示)
12月初旬、拙書著作集第8巻、真岡新聞社より出版 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月初旬、渡辺淑寛著作集第8巻が真岡新聞社から出版の予定で、最終校正も終わり、現在製本中である。第8巻は来年末の予定であったが、「遥か数万年後、全ての人が芸術家である社会について」4回シリーズをまとめて読みたいという方々、(第7巻では、その1のみ所収)、真岡賛歌16編を一緒に読みたいという方々(第5巻~第7巻で所収)が少なからずいらっしゃったので、急遽1年前倒しで出版の運びとなった。第8巻には他に、未所収随筆2編、未所収久保研究所月報14編、当美術館展示作品目録985点を掲載した。久保研究所月報は、ホームページにアップし、真岡新聞に掲載し、著作集に所収するという念の入れようだが、それだけ久保研究所及び月報を重視しているという事である。第8巻が出版できた暁には、もちろん土曜日来館なさった方々全員に贈呈の予定である。著作集は、この地上に生有る限り出版し続けるつもりだが、果たして第何巻まで発行出来るだろうか。
当美術館11月の追加作品は2点で、1点は、アルス日本児童文庫第47巻[山の科学」恩地孝四郎表紙絵原画である。当美術館では、既にアルス日本児童文庫表紙絵原画全76点のうち54点展示していて、他の22点はもう市場に出てくる事は無いであろうと諦めていたが、全国から送られてくる古書目録で目ざとく発見し、すぐ電話をして購入した。絵画市場では、恩地は既に巨星であり驚くほど高額であるが、古書業界ではそれほどの評価で無く、別作家13点のおまけ付きで廉価で入手出来た。これでアルス日本児童文庫表紙絵原画は55点となり、私の生存中、残り21点のうち1点でも入手出来れば僥倖であろう。
もう1点は、若山八十氏孔版画絵本、「妖しい空間」、「白秋」、「天才の祭」、「炉端」、「双面」の5冊である。孔版画とは、昔のガリ版刷りのことであり、やや貧弱な作品を連想するが、とんでもない。キラキラした宝石のような5点で、素晴らしい版画稀覯本である。これらの素敵な限定本を是非手にとって鑑賞して頂ければ幸いである。
大震災後、未だ未整理の渡辺私塾文庫所蔵品を調べていたら、「佐竹本三十六歌仙絵巻」関連本を沢山再発見した。「佐竹本三十六歌仙絵巻」は鎌倉時代に制作された上下2巻の肉筆絵巻で、1919年の売り立て時、一人で購入するには余りに高価過ぎたため37分割されて掛軸装の形で販売され、話題になった絵巻である。それぞれ1点は、現在の金額で、3千万から4億円の金額で売買されたようで、現在ほとんどが重要文化財になっている。もちろんこの原画を入手することなど、逆立ちしても不可能だが、1901年土屋秀禾作木版画三十六歌仙絵巻全2巻と1917年土屋秀禾木版画三十六歌仙絵巻全2冊を、当文庫で所蔵していた。この2点の稀覯本でも小さな展覧会開催が可能だが、他に10点ほど関連本があるので、数年後当美術館で特別展が開ければと思っている。そう言えば、当文庫には、青森県の日刊紙「陸奥新報」2016年9月5日号の1面を飾った「集古十種」全85冊が所蔵されている。希少性では、「集古十種」の方が上位であろうから、集古十種特別展が先なのか、などとにやにやしながら夢想出来るのも、酒タバコはもちろん車も持たぬ50年に及ぶ蒐集歴のお陰なのかも知れない。
最近でも、今日持ってきた作品購入して頂けないかとか、この展示作品おいくらですかとか聞かれる事がある。倉庫改装の貧弱な建物でも、当美術館は美術館の端くれであるから、美術館として作品の売買は一切しないのは自明中の自明である。恩地作品以外は、個人的に購入は控え、現在、大震災後の作品整理に集中している現状なので、その点をお汲み頂ければ幸甚である。
11月になり寒さが増すにつれ、来館者様の足も遠のいている.狭い所に、987点が混在する、普通の美術館とは異質の美術館であるが、久保関連作品も83点展示し、久保氏も目指した「芸術の大衆化」の名のもと、意図的に行っている展示スタイルなので、眉をひそめず、是非来館して頂きたい。日常も大切だが、日常色に染まりすぎ、生きる意味を忘れ、人を愛することも忘れた時は、この不気味な美術館に足を運んで、987種の様々な色彩と形態の世界に触れてみるのも一興だろう。
なお蛇足ながら、久保貞次郎研究所の現在の主な活動は、当美術館運営、芳賀教育美術展の支援、恩地と久保氏の関連性の思索、久保氏の晩年の精神世界についての研究であるのだが、後半の2項目については、この月報の中で少しずつ触れていく予定である。
久保貞次郎研究所2019年12月月報(第116回)
◎渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜日以外電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎入場無料 1月来館者様に拙書著作集第8巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
◎渡辺淑寛著作集第8巻12月9日真岡新聞社より出版
◎当美術館12月は3点追加し、計990点展示(恩地孝四郎376点 久保貞次郎関連84点)
◎久保記念美術品展示館と田町まちかど美術館の企画展について 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月11日、田町まちかど美術館の「靉嘔展」、久保記念館「写真x版画-融合する2つの表現」を観に行った。「靉嘔展」には、20点の靉嘔作品が展示されていて、特に18番から20番のシルク作品「久保さんのイス」と同作品「ペン画下絵」、「久保氏像」が圧巻で、他の美術展ではなかなか目にする事が少ない3作品である。久保記念館の「写真x版画 融合する2つの表現」では28点展示されていて、そのうち7点が瑛九作品であった。瑛九は、インクの換わりに光を利用し、光量、光の入射角、発光体などを変化させながら、フォットデッサンという新たな版画形態を確立した。この企画展には、瑛九が使用した7点のフォットデッサン型紙も展示されていて、真岡市ならではの貴重な美術展になっている。そう言えば、この7点の型紙と23番展示作品「瑛九展ポスター」は、6年ほど前、私が市に寄贈した作品で、手前みそになるが、その希少性を見抜き展示作品とした市学芸員、市当局の見識の高さに称賛の意を送りたい。これだけの美術展を入場無料で開催し、久保関連本を無償提供している真岡市は、後世必ずや高く評価され、日本美術史に名を刻むであろう。
12月当美術館追加作品は3点で、No988は、吉原英雄リトグラフ「赤い花」(久保氏関連作品84点目)、No989は、アンリ・マティスリトグラフ「馬、女曲芸師、道化師」で、1947年美術誌「ジャズ」からの版画であり、マティスの版画は、有名な「ダンス」に続いて2点目である。No990は、恩地孝四郎木版「抒情 私は信ずる」で、この作品は、昭和7年版芸術創刊号添付木版画である。「版芸術創刊号」は限定500部だが、87年間のうちに焼失、紛失、廃棄を経て、今では入手困難な稀覯本になってしまった。2016年東京国立近代美術館「恩地孝四郎展」では、世界中から400点余を集め史上最大の「恩地展」が開催されたが、この木版「抒情 私は信ずる」は出品されていなかった。大美術館でさえ、重要作品であることは解っていても入手出来なかったのかも知れない。大震災で散乱散逸した稀覯本を整理していて、版芸術創刊号を2冊見つけ出した。40数年前、まだ極めて廉価であった時、文庫用と、遠い将来の美術館開設展示用に2冊購入した記憶がある。金額も現在の市場価格の20分の1ぐらいであったと思う。「抒情 私は信ずる」は極めて希少な作品なので、来館なさって鑑賞頂ければ幸いである。それにしても、作品数が極めて少ない恩地作品を、地方の弱小貧弱美術館が376点も常設展示しているとは、都会の専門家も信じられないであろうが、自分でも喜ばしいと同時に不思議な気持ちでもある。
拙書著作集第8巻が12月9日、真岡新聞社より出版された。関係者の皆様に心より感謝の意を表したい。私にとっては13冊目の本になるが、今までと同様、一顧だにされることも無く埋もれてしまうであろう事は重々解っている。内容も難解で、時代より遥かに先行しているからなのだろうが、数百年後、何人かの研究家が現れ、正当に評価される可能性は零ではないと、密かに自負している。1巻から6巻までは、娘の油彩画を表紙絵にしたが、7巻と8巻は、私が47年前に描き殴った不気味なペン画を、表紙絵、裏表紙絵にしたため、一層訳の解らぬ恐ろしい本になってしまった。しかし私個人は、この表紙絵、裏表紙絵をいたく気に入っていて、本の内容より、この不気味なペン画の方が、早く高評価を得るのではと夢想している。因みに、表紙絵は、黒猫「プルートゥ」(1972年,6月1日作)、裏表紙絵は「犬だってCR病院へ」(1972年、6月27日作)である。これらのペン画は、2001年文芸社刊行詩画集「潮に聞け」掲載作品で、「潮に聞け」は予想通りほとんど売れなかったが、文芸社内に物好きな方が何人かいて、2007年7月第14回東京国際ブックフェア」にこの「潮に聞け」を出品した。世界30カ国から770の出版社、並びに全国各地の書店、図書館、学校関係者、海外出版社が集い、書籍の受発注、著作権取り引き、セミナー、サイン会などのイベントが多数開催される大がかりなブックフェアーであったが、仕事が詰まっていて参加出来なかった。作家然と、うら若き乙女達にサインして、妖しげな目つきで握手も出来たであろうが、黒い服を着たi田舎の変なおじさんでは、相手にされなかったかも知れない。いずれにしてもその「潮に聞け」掲載作品の原画が当美術館に全て展示されているので、来館されご覧頂ければ幸甚である。来館時、詩画集「潮に聞け」を見たいのですが、といって頂ければ、冬の優しい日差しと相談して、こっそり贈呈させて頂くことも有るやも知れません。
久保貞次郎研究所2020年1月月報(第117回)
◎渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜日以外電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎入場無料 2月来館者様に拙書著作集第8巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
◎当美術館1月は10点追加し、計1000点展示(恩地孝四郎376点、久保貞次郎関連85点)
◎各月新展示作品コーナーを新設 ◎日下田博藍染額2点展示 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
2020年1月で、当美術館展示作品がついに1000点に達した。この狭い美術館で1000点展示とは、狂気の沙汰だが、思い起こせば、5年前に開館した時から入場無料、版画プレゼント、私の拙書贈呈など、そもそもの初めから狂気の中で美術館を開館した訳だから驚くに当たらない。芳賀教育美術展での入賞者700名への副賞提供も今年で11年目を迎え、お金がいくらあっても足りないのでは、と心配してくれる友人もいるが、大丈夫。酒たばこ賭け事はもちろん、運転免許も持たず、ただひたすら倹約を重ね、美術館、久保研究所の運営費にしている。自分では、この上なく贅沢で高尚な道楽だと悦に入っている次第だ。
新年1月から、入り口シャッター左に、新展示作品コーナーを新設した。シャッターに立て掛ける形式の粗末な展示スタイルだが、少し見やすくなったかも知れない。1月の追加点数は10点であった。No991はフィリピンの洋画家、エドガルド・サルミエント「パラソアイン教会」30号で、日本ではフィリピンの画家というだけで相手にされないが、マニラまで行かずとも「パラソアイン教会」の荘厳さが感得出来る素晴らしい作品である。
No992,No993は、益子町日下田藍染工房八代目(先代)日下田博作藍染額「渓流」、「西明寺」で、木々や山々の丸みのある輪郭が何とも言えない味を出している。数十年前、廉価で購入した記憶があるが、その芸術性の高さからすれば秀逸な買い物であった。日下田藍染工房は、江戸時代寛政元年(1789年)創業で、益子町城内坂に位置し、八代目博氏、当代九代目正氏とも栃木県無形文化財に指定されている。人間独自の、自然な進化発展能力故、「染色」も益子焼と同様、「用」の中に「美」を取り入れ、久保氏が主張した「生活の中に芸術を浸透させる」事を見事に美しく実践している。平成8年、住居が県指定建造物有形文化財に、作業場が県指定有形民俗文化財に指定された、純粋伝統の地、日下田藍染工房を、近隣の多くの方々が足繁く訪れる事を、天にいらっしゃる久保氏も願っているのではないだろうか。
No994は、浮世絵と近代版画の橋渡しをした小林清親の木版「両国花火之図」、「五本松雨月」(明治13年)2点合装作品である。No995は、私の好きな作家、角浩リトグラフ「ドンキホーテと狩人達」。No996は、川西英の代表作木版「アイヌの女」。No997は、小村定吉「奥義曼荼羅」(昭和46年)著者肉筆蛇皮装限定2部本で、昭和時代、一番贅沢な本の装幀は蛇皮装であった。見事な蛇皮装で、勇気のある方には一見の価値があると思われる。No998は、子供たちに人気のある畦地梅太郎「雷鳥と山男」1978年木版作品。
No999は、横田稔限定本「谷間の博物誌」、「続谷間の博物誌」、「続々谷間の博物誌」の3部作で、各冊、石版画15点、銅版画15点入りのキラキラ光る宝石のような稀覯本である。来館なされた女流画家にこの3冊をお見せした所、何かに魅入られたかのように、愛(いと)おしく手にとって感嘆されていた。私にしても、挿入作品の一つ銅版画「櫻」を初めて目にした時、思わず落涙した事をはっきり覚えている。鑑賞者の感受性によって受け取り方は異なるのであろうが、この稀覯本のように、芸術作品には、一定程度の「客観的美」が存在すると、私は確信している。ただ「感受性の差」も確かに有って、長時間長蛇の列の中で辟易したためか、ダビンチ「モナリザ」を観た時、感じるものは少なかった。芸術作品とどのように触れあうかも感受性に少なからぬ影響を与えるのだろう。
記念すべきNo1000は、戦後自民党の重鎮であった藤山愛一郎氏の3号油彩画「春」、「苺図」2点で、久保氏と藤山氏との関係は、2018年12月月報で言及したのでここでは割愛する。藤山氏は、日本政治史に名を残した政治家でありながら絵をたしなみ、大判の画集も出版していて、画廊で個展も何度か開催している。当美術館で展示しているNo822の油彩12号「浅い春」も1966年資生堂ギャラリー個展出品作であった。3号油彩画2点と同時に、藤山氏に関する資料も入手したので、藤山愛一郎研究家がいらっしゃり、ご連絡頂ければ、資料提供を惜しまない
久保貞次郎研究所2020年2月月報(第118回)
◎渡辺美術館毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で日曜日以外電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎入場無料 3月来館者様に拙書著作集第8巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
◎当美術館2月は10点追加し、計1010点展示(恩地孝四郎376点、久保貞次郎関連85点)
◎日下田藍染工房訪問 ◎久保記念館レストラン「こころ」にシャガール版画20点目展示 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
去る2月2日日曜日、家内と二人で益子町の日下田藍染工房を訪れた。真岡新聞2月14日号1月月報で、日下田藍染工房に言及させて頂く御報告と、20年ぶりの工房見学が目的であった。藍染工房当代九代目日下田正氏がご丁寧に応対してくださり、色々ご教示頂いて、恐縮しながらも楽しい一日であった。正氏と面会する前、素敵な作品が置かれている販売所で、家内と私が同時に強く心惹かれる作品に出会った。晩冬の優しい日差しを浴びて、宝石のようにキラキラ光る柘榴(ざくろ)染めスカーフである。恐る恐る値札を見ると思っていたより遥かに廉価であり、はやる気持ちを抑え、嬉しさをひた隠しにしてすぐ購入した。「用」と「美」の秤(はかり)の中で、「美」に限りなく近いこの優美華麗な黄金色のスカーフを、余りに美し過ぎて、家内は、身につける事を未だにためらっている。
2月22日、知的で上品な年配の女性とその娘様が来館なされた。展示作品をゆっくり鑑賞しながら、「心が震えるようです」と感想を述べて頂き、私の拙文と、母渡辺通枝の随筆の愛読者であるとも言って頂き、心に染みるお言葉であった。美術館を開設して本当に良かったと思いながら、お帰りになる時、失礼ながら、思わず、お住まいとお歳を尋ねてしまった。凛とした眼差しの81歳のお母様と、教養のあるお嬢様で、市内在住の方であった。そう言えば、日下田正氏にも私の拙文の愛読者であると言って頂いた。また、真岡新聞月報の切り抜きを持参して質問なさった来館者もいらっしゃった。やや横柄な文体なので、読者は数名であろうと卑下していたが、どうもそうではないらしい。ただただ嬉しい限りである。
同日、小山市から御夫妻が来館され、入り口に貼ってある、青森県陸奥新報一面に掲載された「集古十種」の記事を、奥様が熱心に読まれていた。その後、急に津軽訛りで、ご主人に話しかけていた。事情を伺うと、奥様は、弘前市のご出身で、故郷を懐かしみ、いつの間にか津軽訛りが出ていたと言う。不思議な事だが、素晴らしい事でもある。
2月末、久保記念館レストラン「こころ」に、20点目のシャガール版画を展示させて頂いた。20点のシャガール版画を愛でながら、一流若手シェフの美味しい料理を満喫し、久保記念館を散策するのも高尚で贅沢な時の移ろいではないだろうか。
2月の追加展示作品は、1月と同様10点であった。現在、在庫絵画作品を別な建物に移している最中で、震災で所在不明であった作品が続々再発見出来、3月、4月も10点ずつ追加展示の予定である。10点の内訳は、恩地孝四郎高弟関野準一郎木版2点、「土山」と「軽井沢」で、似た構図の森林描写であり、2点同時展示は趣がある。恩地氏と同様、関野氏も日本より米国の方が高評価の画家で、特に東海道53次シリーズ「土山」は代表作である。
1月新展示した、工房八代目日下田博藍染絵額が4点も見つかり、今月4点全て展示した。「登り窯」、「椿」、「山水図」、「春」で、1月分と合わせて計6点の展示であり、6点同時展示は圧巻である。他は、大津鋭敏の代表的リトグラフ「遠い記憶」、子供に人気の畦地梅太郎木版「傷つく小鳥」、現代一流風景画家鳥居雅隆「ソームー城」油彩6号、坂本繁二郎リトグラフ「馬」である。坂本繁二郎はビッグネームだが、「馬」はよく見かける作品である。とは言っても、中央の馬の鋭き眼光は、看過できない。どなたか来館なさって、この馬とにらめっこをしてもらいたい。完敗するのは必定だ。
久保貞次郎研究所月報と言いながら、美術館中心の内容になっているが、久保研究所の現在の主な活動は美術館運営と、芳賀教育術展支援であるので、ご容赦のほど宜しくお願いしたい。
久保貞次郎研究所2020年3月月報(第119回)
◎開館5周年記念として、ロダン「バルザック像」展示(ブロンズ最終直前習作、107㎝67㎏、国立西洋美術館蔵、パリ ロダン美術館蔵、フィラデルフィアロダン美術館蔵と同作品)
◎当美術館、当面平常通り開館(毎週土曜日午後1時から4時開館)、茂木町の英断に拍手
◎入場無料、4月来館者様に拙書著作集第8巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中(2名以上の来館者様で電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎当美術館3月は11点追加し、計1021点展示(久保貞次郎関連85点、恩地孝四郎376点) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新型コロナウイルス対策での,政府によるイベント中止要請の報道を受け、当美術館でも3月は休館とすべきか迷っていた。ところが3月5日、茂木町が、休校要請の意に反して、休校撤回を発表しニュースで大々的に取り上げられた。地方自治体が中央政府の要請に背を向ける事がどれ程大変な事なのかを知る私は、正直驚いた。だが、落ち着いて考えてみれば、共働き家庭の多い茂木町では多くが学童保育を利用し、通常授業より児童間の接触が増す事、栄養の面で良質な給食が途絶える事、児童の精神衛生問題、休校中都会に出かけ万が一にもウイルスを持ち帰る危険性等を考慮すれば、いつも通り同じ児童が同じ学校に通う方がよほど安全だと容易に推察できる。各地域によって、様々な事情を勘案し地域独自の政策を採る事が、真の意味の地方自治地方分権であろうから、中央政府も各地域の特殊事情を重々理解し、茂木町の英断を内心評価しているのではないだろうか。それ故何ら逡巡せず、胸を張って町政に邁進して頂ければ幸いである。そういう訳で、当美術館も、茂木町の勇気をほんの少し頂いて、当面、通常通り開館する事に決定した。
今年で開館5周年を迎え、5周年記念として、ロダン「バルザック像」(ブロンズ最終直前習作、107㎝67㎏)を3月14日に展示した。この作品は、1891年フランス文芸家協会から依頼され、7年間も心血を注いだ労作(石膏像)であったが、同協会から引き取りを拒否され、怒ったロダンは、前受金を突き返したと言われ、この石膏像は40年間ロダンの自宅に秘蔵され、ロダン生前一度もブロンズ鋳造される事が無かった曰く付きの作品である。ロダンは、ル・マタン誌1908年7月13日号で「この作品は、私の全人生の成果であり、私の美学の軸そのものである。」と述べており、ロダンにとっては最高傑作のはずであったが、生前評価される事はついぞ無かった。胸像も含めていくつかの習作が存在するが、全身習作は2種のようで、当美術館と国立西洋美術館蔵、パリ ロダン美術館蔵、フィラデルフィアロダン美術館蔵の作品が最終直前習作、メナード美術館蔵が最終習作で5体とも107㎝である。270㎝の完成ブロンズ作品は、国内では、箱根彫刻の森美術館、東京芸大美術館、久留米市にある。因みに、やや専門的になるが部屋着(ガウン)の袖の反りかえりの違いで、最終直前習作と最終習作の区別が出来る。本来であれば立派な大理石の台座に設置すべき作品であるが、現時点では経済的に到底無理なので、木製台座をと考えている。
今、久保氏旧蔵稀覯本「ロダン その人と作品」1908年、フランス女流作家ジュディット・クラデル著、限定25部)掲載のバルザック石膏像を見ているのだが、ロダンに造詣の深かった久保氏も、真岡市に数少ないバルザック像が展示されていて、天で心底喜んでいらっしゃるに違いない。
3月新展示作品残りの10点は、2月に続いて、関野準一郎版画5点、「赤坂」、「柳河」、「NHK愛宕山」、「蝋燭」、「オレゴンの海」の木版作品である。寡作であった師恩地孝四郎と違って、関野準一郎は相当数の作品を制作し、比較的入手し易い。恩地ほど作品に深みを持たせていないが、米国では高評価で、浮世絵の伝統が感じられる独自の世界を持った版画家である。残りの5点のうち3点は、生野一樹のエッチング、「円覚寺」、「山門(道)」、「桜」3点で、寂しさ、荒涼感の漂う銅版風景画のなかに、大地の生命感、強靱さが確かに感得出来る。残り2点は、ヨルク・シュマイサーの木版2点「二女神と魚」、「流るる女神」で、当美術館でも既に「馬と女性」、「孔雀の女性」の木版画2点を展示している。4点同時にシュマイサー木版画を鑑賞出来る所は多くないであろう。シュマイサーは、ドイツ生まれで、現在オーストラリア在住の世界的画家であるが、日本にも4年間留学し、一般には東西両文化の融合芸術であると言われている。しかし私見だが、一見日本近代版画の影響を受けた風に見えても、シュマイサー芸術の根底を流れる潮流は、デューラーやキルヒナーと同じく、ドイツ文化風土に深く根ざした表現だと思っている。
話は戻るが、当美術館でも、ウイルス対策として、薄ゴム手袋、殺菌ウェットティシュ、赤ちゃんお尻拭きティッシュ等を用意しているが、利用した来館者様は今の所皆無である。物に触れる事もなく、ただ見て回るだけであり、来館者も極めて少ないので、そもそもの初めから、コロナウイルス対策は完璧である。入場無料、拙本版画プレゼント、ウイルス対策万全の当美術館を、訪問され、一度バルザック像と対峙してみては如何だろうか。
久保貞次郎研究所2020年4月月報(第120回)
◎緊急事態宣言のため4月18日から5月30日まで渡辺美術館休館 6月より通常開館(毎週土曜日午後1時から4時開館)
◎当美術館4月は5点追加し、計1026点展示(久保貞次郎関連85点、恩地孝四郎376点)
◎入場無料、6月来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第8巻贈呈、版画・洋書プレゼントも継続中(2名以上の来館者様で電話予約で相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎ロダン「バルザック像」台座完成
◎新コロナパンデミック小論~文明史の中で~今こそ、家庭和楽で免疫力を高めよ~ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
3月月報で、4月も通常開館の予定だと書いたが、国、県の非常事態宣言、市の真岡市街角美術館休館要請を受け、5月末日まで休館とさせて頂きます。御容赦願いたい。
4月初旬、ロダン「バルザック像」の台座を、費用をかけず、自ら根性で完成させた。不用の机と布を用い会心の作である。「バルザック像」は仰視するのがベストのようで、カバーの緑と、床の人工芝の緑がマッチして、仰ぎ見ると格段に存在感を増す。貧弱な倉庫美術館だが、展示作品は、量と質において一般の美術館に決して劣らないと密かに自負し、誰も居ない所で胸を張ったりもしている。
当美術館4月の新展示作品は5点で、No.1022は、ターナー「今のイタリア」(銅版、1870年)、No.1023は、池田幹雄の秀作「海辺の華」(日本画10号)、No.1024からNo.1026は、芹沢銈介型染め作品3点である。人間国宝芹沢銈介氏は、真岡市とは無縁でない。御子息の東北大名誉教授芹沢長介氏は、真岡市東大島の後期旧石器時代礒山遺跡を1961年と1962年に発掘調査し、1977年、六一書房から、「真岡市礒山旧石器時代出土資料 礒山」という学術書を著している。以前にも書いたが、真岡市には、歴史的に貴重な、「後期旧石器時代礒山遺跡」という秘宝、秘密兵器が有る。(詳しくは、真岡新聞平成30年6月8日号、または拙書著作集第8巻掲載「真岡賛歌その16」を参照)
この場をお借りして、新コロナパンデミックと文明との関わりについて、少し書かせて頂きたい。人類史は、感染症との戦いの歴史でもあった。推定死亡者数、10万人以上の主な感染症を列挙すると、紀元前430年ギリシャ(アテノの疫病、推定死亡者数、10万人)、西暦165~180年、ローマ(アントニヌスの疫病、500万人)、西暦195~220年、中国(建安の疫病、1000万人以上)、西暦541~542年、地中海(ユスティニアヌスのペスト、2500万人)、西暦1347~1352年、アジア、欧州(黒死病、7500万人以上)、西暦1518~1568年、メキシコ(天然痘、腸チフス、1700万人)、西暦1556~1560年、欧州(インフルエンザ、2500万人)、西暦1665年、イギリス(ロンドンの大疫病、10万人)、西暦1775~1782年、北アメリカ(天然痘、13万人)、西暦1852~1860年、ロシア(コレラ、100万人)、西暦1855~1896年、アジア(ペスト、1000万人)、西暦1918~1920年、世界(スペイン風邪、5000万~1億人)、西暦1968~1969年、世界(香港風邪、75万人)である。そして人類は、2020年世界中でパンデミック化した新コロナウイルス感染症と、今の今、正に対峙している。
アベノマスクなどと品の無い表現で揶揄されながらも国家、自治体が最善を尽くそうと苦闘しているさなか、今度は我々個々人が自らと家族を守るため、出来うる全てをしなければならない。新コロナウイルスの感染形態は飛沫感染、接触感染、エアロゾル感染の3種のようで、飛沫感染は、マスクをつけ、他者と距離をとれば多少は防げる。乗り物のつり革、ドアノブ、各種スイッチ、小包等に最新の注意を払うことで接触感染の危険性は減少する。長時間の密閉空間を避ければ、エアロゾル感染はかなり防げる。また、個々人、外出を極力控え、三密を回避し、食事、快眠、うがい、手洗い、歯磨き、洗顔、入浴、清掃等に気を配り、必要以上に不安がらず、前向きに生きる事も大切である。
その人の人格、人間力は、危機に瀕した時の振る舞い方、行動で決まると言われている。家族が一緒に居る時間が多くなった今こそ、感染者、医療従事者の、想像を絶する悲嘆と苦渋に、家族全員で思いを馳せ、家族の夢を語らい、笑顔を絶やさず、笑い声が響き渡る家庭を築き上げ、まさに今こそ、家庭和楽で免疫力を高める時である。過去のパンデミックに比べて、医療環境は格段に進歩しているが、人の移動も遥かに増加している故、21世紀初頭の方が有利かどうかは不明だ。我々人類は,1980年WHOから根絶宣言を受けた天然痘のように、新コロナウイルスを絶滅させるか、軽いインフルエンザレベルまでウイルスを弱毒化し共存するかの何れかであろうが、私は後者を予感する。また、高度な医療を有し、知的レベルが高く、欧州と違って島国である日本が、荒廃した世界の救世主になる可能性も無くは無いという予感も有る。
今後経済も一層停滞するであろうが、悪い事だけではない。この危機で、ロボット工学が一層進み、在宅勤務制度も飛躍的に前進するであろう。そしてこのパンデミックは、科学技術にあぐらをかき増長した人類に対する、生命体地球からの警鐘であり、食物連鎖の頂点にあるはずの人類も、生物の一種にすぎないという自明な命題を再想起させる、天の恩寵であると捉えるべきだ。そしてこの恩寵は、パンデミックと言う名の世界共通の敵を再度授かった人類にとっての絶好の好機、つまり世界の全ての国々が一致団結し、不可視の敵に立ち向かう最大の好機をも含んでいる。大空を滑空する翼、獣肉を切り裂く犬歯、大海を遊泳する尾ひれを持たないけれど、比類無き精神を所有する人類は、断じて、地球を庇護し、自然環境と美しく調和しながら進化してゆく存在である。夜明けはそれ程遠くない。
ウイルスで逝った人々の悲しみの歌よ、朗々と天まで届く勝利の歌となれ。
日本の喜劇王の死の淵での悲しみの笑みよ、朗々と天まで届く喜びの笑声となれ。(4月30日記)
久保貞次郎研究所2020年5月月報(第121回)
◎新コロナ対策で5月は休館させて頂きました。6月より通常開館(毎週土曜日午後1時から4時開館)
◎入場無料、今年来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第8巻贈呈、版画・洋書プレゼントも継続中(2名以上の来館者様で電話予約相談の上随時開館 ℡090 5559 2434)
◎当美術館5月は8点追加し計1034点展示(久保貞次郎関連87点、恩地孝四郎377点)
◎久保貞次郎氏との秘話 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
市当局から、条件付きながら、5月11日から開館可能である旨のご連絡を頂いたが、その条件の一つに、真岡市民のみ入館可というのがあった。当美術館では来館者様の3分の1は市民、3分の1は市民以外の県内の方々、3分の1は県外からの来館者であり、遠くは九州、青森から来館なさる方もいる。県外来館者様の半数は、不意の来館で、そのような方々に、真岡市民でないため入館出来ませんとは到底言えないので、5月末まで休館とした。ご了承願いたい。
5月は全休ながらも、知らんぷりをして8点追加した。NO.1027は、日下田博藍染額「四季図」で、益子町日下田藍染工房八代目博氏の藍染額は7点目となる。博氏作品7点を同時に鑑賞出来る所は多くないであろう。日下田藍染工房ファンの方々の来館をお待ちしております。NO.1028は、児童に大人気の畦地梅太郎木版「残雪の宴」、NO.1029は、川上澄生木版小品「勲章」、NO.1030は、長谷川利行水墨額「にんにくの芽」。長谷川利行はビッグネームだが、作品自体は、幼児の殴り書きのような水墨画である。それでも妙な躍動感生命感に魅入られて30年ほど前購入した作品で、利行の会鑑定書のついたきちんとした作品である。NO.1031は、栃木市出身の洋画家清水登之の6号水彩画「陸路洲本にて」、NO.1032は大浦信之リトグラフ「Work」、NO..1033は吉原英雄リトグラフ「ランチタイム」。両氏とも久保氏と親交の深かった画家で、この2点で、久保氏関連展示作品は87点になった。大浦氏は、私のお気に入り画家の一人で、大判リトグラフシートを何点か所蔵している。
最後のNO.1034は、恩地孝四郎木版「ヒヤシンス」。木版と言っても、昭和2年雑誌「婦人クラブ」の表紙絵である。文庫館を整理していたら2冊出てきたので1冊額装してみた。「ヒヤシンス」は、93年前の作品だが、時代を超越した精妙な女性像が高く評価され、表紙絵といえども、恩地の代表作の一つになっている。恩地作品の多くは、戦前戦後を通じて、高い鑑識眼を持った西洋の研究家、コレクターによって海を渡ってしまい、日本には、大きな公立美術館を除いて、恩地オリジナル作品はほとんど残っていない。我々一般人が入手出来るのは、表紙絵や稀覯本添付木版作品だけである。幸い当美術館、文庫館には恩地が無名であった時代から蒐集した恩地稀覯本コレクションが有り、作品点数だけであれば日本でも屈指かも知れない。先日、6月追加作品として、恩地木版年賀状7点の額装が完了したので、6月には384点の恩地作品を展示出来る。日本より国外の方が高評価な一流画家の「すきま作品」をしぶとく展示していく事こそ、地方の弱小美術館の使命だと思っている。日本では、芸術作品の価値は、芸術性の高さ、質でなく「画家の名前」で決まる悪習がまだ残っているが、欧米では日本ほどその悪習に染まっておらず、多くの大小美術館が、恩地作品の小品も地道に蒐集している。特に、名だたる大英博物館が、当美術館でも展示中の恩地木版カレンダー、木版パンフレットなどを積極的に購入していて、その鑑識眼の高さには驚かされる。
今月もスペースに余裕が有るので、先月の「新コロナパンデミック小論」に続いて「久保貞次郎氏との秘話」と題して少し書いてみたい。久保氏は真岡市では高貴なお方で、雲の上の存在であった。母が足利銀行真岡支店に勤務していた時、久保氏が来店すると、その場の全員が一斉に起立し、深々とお辞儀をしたと、何度も母に聞かされた。芸術家を除けば、真岡市で久保氏と親交を持てた人はごく僅かであったろう。私のように粗野な平民と久保氏の関わりなど有ろうはずもないのだが、たった1度接触があった。40年近く前、真岡新聞に「高校への5科教室」を連載している時、中3生でも解る「特殊相対性理論」の特集記事を書かせて頂いた。掲載日の夕方、4名の方々から、質問、励ましのお電話を頂いたが、その中のお一人が、久保と名乗り、「近づく場合と、遠ざかる場合の時間のずれはどうなのか」などの鋭い質問をしてくれた。たじたじとなりながらも、「静止している物体に対して、運動している物体の時間が遅くなるのであり、運動の方向は関係ありません」とやっとの思いでお答えしたのを覚えている。また、何故相対論を学んでいるのか、と問われ、私は精神世界についても研究しており、宇宙の秘密に迫りたいから、と生意気にお答えした事も記憶している。晩年、久保氏が精神世界について造詣を深めていた事は余り知られていないが、万が一、私との電話での微かなやり取りが、その端緒になったとすれば、これ以上名誉な事はない。
久保貞次郎研究所2020年6月月報(第122回)
◎渡辺美術館6月より通常開館
◎毎週土曜日午後1時から4時開館(2名以上の来館者様で電話予約相談の上、随時開館、℡090 5559 2434)
◎入場無料 今年度来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎当美術館6月は9点追加し計1043点展示(恩地孝四郎384点、久保貞次郎関連87点) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館、5月は新コロナ対策で全休にさせて頂いたが、6月からは通常開館とし、平常通り館内に900点余、屋外に100点余を陳列している。それでも先の見えない、不気味な新コロナウイルス騒動に辟易し、来館者は皆無であろうと覚悟はしていたが、毎土曜日、何人かの来館者がいらっしゃり、嬉しい誤算であった。特に20日には、2月月報で言及させて頂いた知的で上品な年配の女性とそのお嬢様が、再来館して下さり、綺麗な包装紙に包まれたお土産も御持参なさった。お土産に託されたお二人のお心遣いに、心中で手を合わせながら、有り難く拝受し、そのお土産は、拙宅の夕食(ゆうげ)となった。家内と、たまたま来宅していた孫娘二人計4人で美味しく完食し、食事中3人は、鼻高々の私の表情を嬉しそうに眺めていた。
同日、常連の来館者様が、亡き母の文章が掲載されている小冊子をお持ちくださった。17年前の「寿ニュース」3点で、80歳をすぎた母の静寂な短文が載っていて、久しぶりに母の文章に触れ、月並みな表現だが心が洗われた。そして敢えて言わせて頂ければ、その日に来館なされた前述の方々こそ、当美術館の展示作品を遥かに凌ぐ、本当のお宝なのだろう。
27日、県外から3名の方々がいらっしゃった。新コロナ対策で県外の来館者様には慎重にとの事なので、研究者でなく偶然立ち寄った方々である事を確かめてから、距離をとって、それとなく事情を説明し、屋外の作品を観てもらって、気持ちよくお帰り頂いた。正式な来館者にはならなかったが、コロナ騒動が終わったらまたゆっくり来てみますね、と笑顔で言って頂き、気持ちの良い人達であった。
6月8日、田町まちかど美術館で9月3日から11月3日まで開催予定の渡辺美術館展用パンフレット写真撮影のため、市の職員が、作品5点を借り受けに来館した。新コロナ第2波、第3波の可能性も零では無いので、渡辺美術館展の実現を願うばかりである。それにしても私にとっては有り難いお話で、市当局に心より感謝したい。展示作品は16点で、最終的には市が展示作品を決定したのだが、私のお気に入りの作品ばかりで、市関係者の鑑識眼の高さには、ただただ脱帽するばかりである。
6月の追加作品は9点で、NO.1035からNO.1041の7点は、恩地孝四郎1931年木版年賀状6点と1932年木版年賀状1点である。たかが年賀状ではないか、と思われる方もいらっしゃるであろうが、1931年賀状6点は、1978年発行「恩地孝四郎版画集補遺」に所収されていて、6点の図録製作のため、英国ロバート・ヴェルジェスコレクションまで行って、少なくない謝礼を支払い、やっと写真を撮らせてもらったという話もあるくらいだ。1978年には、既にこれらの賀状7点を所蔵していたので、私に一言声を掛けてくれていたら、他の恩地コレクションと一緒に、にんまりしながら無償で写真撮影を認めたのに、と偉そうにしている昨今である。因みに、ロバート・ヴェルジェスコレクションの多くが大英博物館に収蔵され、当美術館で展示している「1949年藤沢薬品工業木版カレンダー」(「京の雪」、「内海にのる」、「銀座のたそがれどき」)も、ロバート・ヴェルジェスコレクションから大英博物館に移ったようだ。日本の有名美術館には、カレンダーや賀状など、恩地の埋もれた傑作を蒐集する意欲も嗅覚も持ち合わせていないのかも知れない。
NO.1042は、竹久夢二アルス日本児童文庫挿絵原画「ほら男爵の旅」(1927年、第19巻世界童話集55ページ)で、夢二肉筆原画は4点の展示となった。4点共2階の夢二コーナーに並んで陳列されている。夢二専門美術館を除けば、夢二版画82点に加えて肉筆作品4点を展示している美術館はそれ程多くはないであろう。
NO.1043は、川瀬巴水木版「塩原畑下」で、巴水代表作の一つである。当美術館には、既に「日光神橋の雪」、「京都清水寺」の有名作品2点が展示されていて、3点まとめて階段昇り口左に展示した。一度来館なさり3点一緒に鑑賞なさって、精妙静寂な川瀬巴水木版画の真髄に触れて頂ければ幸いである。
久保貞次郎研究所2020年7月月報(第123回)
◎渡辺美術館8月以降毎週土曜日通常開館(お盆休みも開館)
◎毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約相談の上、随時開館、℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎武井武雄刊本作品71点、重本節子「花かごシリーズ」4点追加展示 ◎7月25日の花火について ◎第34回真岡市美術展について
◎当美術館7月は10点追加し計1053点展示(恩地孝四郎384点、久保貞次郎関連88点) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月25日夜、雨上がりの夜空に花火が打ち上げられた。毎年恒例の真岡市花火大会は中止になったが、関係者の心意気なのだろうか、我々市民の沈みがちな心の中に、彩りと勇気を与えてくれる素晴らしい贈り物であった。一咲一咲の花火が、「コロナに負けるな」、「人類は必ずコロナに打ち勝つ」、「感染症などに負けてたまるか」と言っているようで、歳のせいか、思わず目頭を熱くした。関係者の皆様に、心底より感謝したい。
第34回真岡市美術展「我が家の秘蔵展~静物画と小さな工芸品~」が、10月8日から19日まで、荒町の久保記念美術展示館で開催される。金鈴莊開催時、何度か足を運んだ事があり、掛け軸作品が多く展示されていたと記憶している。真岡市は、苺のまち、SLのまち、神社仏閣のまち、後期旧石器時代礒山遺跡のまちなど、幾つかの顔を持つ市であるが、久保氏が礎(いしずえ)となった美術のまちでもある。34年間も継続しているとは驚きであるが、美術のまちとしての真岡市の底力なのだろう。そう言えば、芳賀教育美術展も今年で34回を迎える予定だが、果たしてコロナに打ち勝てるであろうか。
当美術館7月は10点追加し、1053点展示となった。もはや狂気の沙汰であり、芸術の大衆化などという言い訳は通用せず、美術品の倉庫と化しているが、このまま突っ走るしか道はないようだ。
NO.1044は、竹久夢二木版「小春」(1986年、松永版)、NO.1045は、竹田鎮三郞リトグラフ「結婚式の帰り」。この竹田
作品で、久保貞次郎関連作品は88点になった。NO.1046は、武井武雄木版「おもちゃ絵諸国巡り 三重」、NO.1047は、武井武雄木版「洋燈」で、「洋燈」には額裏に「吾八書房シール」が添付されている。日本で、美術作品を大衆へ橋渡しする重要な役割を担ってきたのは、画廊、画商、百貨店が主であったが、有力古書店の役割も大きかった。特に神田神保町の吾八書房は、版画入り限定本の出版では関東の雄で、版画の普及と同時に、多くの貧しい画家を経済的に支えてもきた。吾八書房が無くなってから久しいが、今でも残念でならない。そう言えば、久保氏も、多くの貧しい画家に版画製作を鼓舞し、思想的にも経済的にも多数の芸術家を支え続けたが、日本美術史上、久保氏は例外であり、希有なのだろう。
NO.1048は武井武雄刊本作品71点である。武井武雄は、国外は別にして、国内では恩地孝四郎より著名であり、宝石のような刊本作品139点は特に有名で、長野県岡谷市に武井武雄イルフ童画館という立派な美術館もある。一方、きちんとした恩地孝四郎美術館は存在しない。それでも、厚かましくも強いて挙げれば当美術館である。武井武雄刊本作品について語るスペースは無いが、71点を同時に手にとって鑑賞出来る所を私は知らない。ご興味の有る方は、限定稀覯本という武井総合芸術の真髄に触れて頂ければ幸いである。
NO.1049は、竹久夢二木版豆本「猫」(昭和41年、加藤版画研究所)である。武井刊本を整理している時発見した稀覯本で、幾つかの古書店で現在の価格を調べてみたら、40数年前の購入価格の20倍ほどの値段であり、夢二人気の息の長さには驚きである。
NO.1050からNO.1053の4点は、重本節子「秋のはなかご」(2005年、限定3部)、「冬のはなかご」(2006年、限定5部)、「春のはなかご」(2006年、限定5部)、「夏のはなかご」(2006年、限定4部)である。2枚重ねの化粧巻紙に肉筆で創作詩が書かれていて、華麗な総合芸術作品だ。重本氏は、以前真岡市に住んでいて、後に愛知県に移住した詩人である。審査委員長を任された21年前の真岡新聞渡辺私塾文藝賞からのお付き合いで、1度もお目にかかったことは無かったが、5.6年お手紙のやり取りを続け、この4点は、その時に愛知県から送って頂いた作品でる。美術館を創ったら、何時かは展示しようと思っていたが、やっと実現した。重本氏には、御礼に拙書著作集などをお贈りさせて頂いたが、ある時、突然音信不通になった。その後しばらくして、ご病気で夭逝なさったという、悲しい知らせが舞い込んだ。この4点は、重本氏の貴重な遺作に違いない。真岡市在住時、氏と御面識のあった方々は、目映いばかりの4作品を是非ご覧になり、氏を偲ばれ、思い出話に花を咲かせてみては如何だろうか。
久保貞次郎研究所2020年8月月報(第124回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜以外2名以上の来館者様で電話予約相談の上随時開館)(℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎当美術館8月は21点追加し計1074点展示(恩地孝四郎384点、久保貞次郎関連88点)
◎田町まちかど美術館での「渡辺私塾美術館コレクション展」(9月3日~11月3日)について 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月13日、探しものをしていて、「市内一老女性」という差出人の、2008年7月30日付けのお手紙を12年ぶりに見つけ、再拝読した。2008年7月25日真岡新聞掲載の私の拙文「全ての女性への応援歌~姫百合の花~」へのご感想と激励のお手紙であった。著作集第1巻所収の文章であったので、再読してみた。自画自賛だが、悪くない内容であり、深夜、一老女性に手をあわせて感謝した。停滞した人類史を前進させる、人類に残された最後の手段は、女性のみが所有する母性であるという考えが根底にある文章だが、何かの機会に、当紙に再掲載して頂ければと願っている。そう言えば久保貞次郎氏も、女性の能力、可能性を重視し、跡見学園短大の学長を8年間務め、独自の芸術教育を展開した。当時、青山学院短大、学習院短大と並んで、女子短大御三家と称された跡見学園短大には、全国から優秀な女性が集い、入試倍率も10倍を優に超え、久保氏の薫陶を受けた多くの女性が、卒業後様々な分野で活躍した。市内でも、久保氏の教え子で、絵を描き、芸術を生活の中に浸透させている女性と出会ったりする。久保氏の教えは、多くの女性達によって、今後も脈々と語り継がれるであろう。
8月15日(金)朝、電話があって、要件は、私の教え子の姉妹が家族と7人で、美術館を訪問したいという主旨であった。30年近く前の教え子であったが、旧姓をフルネームで言って頂いたので、すぐ思い出した。目に浮かんだのは、うら若き女子高生二人であった。入試と真っ直ぐ向き合い、地道に努力出来る素直な姉妹で、二人とも難関大に進学した。約束の時間に、二家族が車で来館された。そうだ、二人とも素晴らしいお母さんになっていたのだ。ご主人達とお子様達が絵を見ている間、思い出話に花が咲いたのは言うまでも無い。良き日であった。
灼熱の8月、来館者様は激減するであろうと思っていたら、意外と多くの来館者があり、市内、上三川町、群馬県、埼玉県、東京都、オーストラリア出身の方などの来館があった。
当美術館8月の追加作品は21点で、NO.1054からNO.1074まで、武井武雄アルス日本児童文庫挿絵原画である。武井氏の直筆原画21点を手にとって鑑賞出来る美術館は少ないであろう。また、追加点数には入らないが、7月に展示した武井武雄刊本作品71点に加えて、刊本作品6点を追加し計77点となった。受付の所に鎮座しているので、これも手にとって鑑賞出来る。
田町まちかど美術館で、9月3日から11月3日まで、「渡辺私塾美術館コレクション展」が開催されている。出品点数は16点で、NO1は、草間彌生「湖」(ミクストメディア)、NO2、恩地孝四郎「並木のある道(中国風景)」(油彩)、NO3、恩地孝四郎「萩原朔太郎像」(木版)、NO4、恩地孝四郎「アルス日本児童文庫第47巻表紙絵原画」(水彩)、NO5,南都麗「ぼくのイエルニカはこんな顔」(ペン)、NO6、安倍舞「SpaceⅠ」(ミクストメディア)、NO7、J・J・ティソ「春」(ドライポイント)、NO8,J・J・ティソ「お姉さん」(ドライポイント)、NO9、川上澄生「ヨコハマ」(木版)、NO10,橋下関雪「緑樹白壁」(日本画)、NO11,入江酉一郎「きつね」(日本画)、NO12,佐々木裕久「星夜」(日本画)、NO13,古沢岩美「ミモザ」(パステル)、NO14,栗谷川健一「ムックリを鳴らすアイヌ娘」(油彩)、NO15,安藤幹衛「岩場」(油彩)、NO16,川崎満孝「上高地の紅葉」(アクリル」の計16点である。
NO5、南都麗は、私のペンネームで、「ぼくのイエルニカはこんな顔」は、48年前にノートに書き殴った、訳の解らぬ落書きだが、2001年文芸社から出版した「詩画集 潮に聞け」に掲載した作品の原画だ。ほとんどの人は、「何だこれ、きもい-」と言いうが、プロの絵描きさん達は、何故か褒めてくれる。「潮に聞け」出版時、詩を添えたのだが、蛇足ながら最後にその詩を書き添えて終わりとしたい。
「え!? 美人だとおっしゃるのですか? ふふ、私はそうは思いません。 彼女は、数千年ごとに沈黙と饒舌をくりかえし、今は沈黙の時。 え!? 口がないですって? ふふ、彼女は、食う食われるの食物連鎖を超越し、言葉は心で語ります。 とにかく待ちましょう、今は静寂の時、彼女が宇宙の秘密をほとばしるように語るまで。」
久保貞次郎研究所2020年9月月報(第125回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜以外2名以上の来館者様で電話予約相談の上随時開館)(℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書著作集贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)◎9月は1点追加し計1075点展示(恩地孝四郎384点、久保氏関連88点)
◎「全ての女性への応援歌~姫百合の花~」(2008年7月25日真岡新聞掲載文、著作集第1巻所収) 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館9月は1点のみの追加であるが、稀覯本「版芸術」(白と黒社、昭和7年~11年)全58冊のうち38冊を入り口左に展示した。入手困難なNo1~No5も揃っていて、38冊を手にして鑑賞出来る所は日本でも希有であろう。
今月報では、8月月報で紹介した2008年真岡新聞掲載の拙文「全ての女性への応援歌~姫百合の花~」を掲載させて頂く事にした。女性の可能性を信じていた久保氏も、天で喜んでいらっしゃるに違いない。
昔、日の国では、南の島で、夕暮れ色の姫百合の花が散るように、岸壁から身を投げる少女達がいた。
昔、東洋では、「美」の名のもと、少女の足を弱める「纏足(てんそく)」という悲しい風習があった。
昔、アフリカでは、「美」の名のもと、女性の首に幾重にも鉄輪を重ね、脊髄を痛める恐ろしい風習があった。
昔、西洋では、女性の優れた能力を恐れる余り、魔女狩りという悲惨な歴史があった。
今、日の国、南の島では、夕暮れ色の姫百合の花が、少女の数だけ咲いている。舞い落ちる花びらを天まで届けた姫百合風が、「全て、一部の男達の罠ですよ」と、泣くように吹いている。
世の女性達よ、一部の男達の言いなりになってはいけない。「美」の名のもと、やせ細ってはならない。「聖戦」の名のもと、一部の男達が起こした戦争を止めなければならない。
世の母達よ、如何なる理由があっても、二度と、夫を、愛する子を、戦場に送ってはならない。
世の少女達よ、男の子より数倍学べ。人類の悲しみの歴史を学べ。飢餓の地があるのに、何故飽食の地があるのか、政治を学べ、地理学、文化人類学を学べ。人類史が何故戦争史なのか、国際関係論を学べ、宗教学、語学、社会工学を学べ。一人一人は善人なのに、人は集団になると何故暴徒化するのか、組織論を学べ、集団心理学を学べ。宇宙の秘密、生と死の秘密を知るために、宇宙物理学を学べ、リーマン幾何学、相対論を学べ。遥か数千年後、全ての人が芸術家である社会に向けて、芸術学を学べ、文学、哲学、論理学、医学を学べ。
戦いで、はかなく散っていく者は名も無き男性兵士なのだから、男達も、歴史を変えるには女性の力が必要だと薄々気づき始めている。女性のしなやかな感性、海のような母性を密かに求め始めている。
世の女性達よ、子を授かり、人類を永続させる事は換え難き必須の使命だが、直情に走る男性を母性で包み、地球の消滅を阻止する事も不可避の使命だと銘記せよ。女性に頼りすぎだとは誰にも言わせない。悠久の人類史で、幾とせも地底深く封印された女性の神秘の力を、今の今、女性自身で開封せよ。
この地球を、血球から知球に変えるため。存在とは、紛れもなく進化であるために。
明日、日の国、南の島では、朝焼け色の姫百合の花が、少女の数だけ歓喜の中で咲くだろう。朝焼けに染まる姫百合風が、「人類を救うのは女性達ですよ」と微笑むように吹くだろう。
久保貞次郎研究所2020年10月月報(第126回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館)(℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎10月は6点追加し計1081点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連作品88点)
◎渡辺美術館コレクション展、第34回真岡市美術展について 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館9月は1点のみの追加であったが、10月は6点の追加作品を展示出来た。No1076、No1077は、世界的に人気のる英国稀覯本ケルムスコットプレス刊本で、50年前、全53点を蒐集しようと意気込んだが、とんでもない。余りに高額で、結局2点しか入手出来なかった。No1076は「クリストファー王子と美女ゴウルディリンド」全2冊(ウイリアム・モリス、1895年、刊本35番)、No1077は「サンダリングフラッド」(ウイリアム・モリス、1898年、刊本51番)。この希少本を手にとって、19世紀英国文化の香りに触れて頂ければ幸いである。
No1078は、ギュスターブ・ドレ「ドレギャラリー」全2巻(1870年、ロンドン)で、10点のドレ版画本から秀作を選び1冊にまとめた木版フルページ250点のアンソロジー大冊である。以前、ドレ版画本から1枚1枚切り取って芳賀教育美術展の副賞として提供させて戴いた作品も含まれている。30年以上前のバブル期、とあるオークションで、同様に切り取られたドレ版画が額装され、数十万円の価格で飛ぶように売れていた場面を目撃した。児童のように純真な心で芸術作品を鑑賞すれば、芸術には精神の浄化、成長機能が有ると論じたのは久保氏であったが、現在の美術市場は、その芸術の本道から遠く離れ、資本の論理に屈服していると危惧しているのは私だけだろうか。
No1079は、「ジョスパー・ジョーンズリトグラフポスター」で、1986年ニューヨーク近代美術館が、展覧会用に1976年のジョーンズ作品をリトグラフで制作した由緒ある作品である。日本ではポスターと名が付けば極端に商品価値が下落する不思議な商慣習が有り、この額入りリト大作をいわゆるワンコインで落札した。これは美術愛好者にとっては有り難い美術市場の歪みかも知れない。
No1080は、「版画誌 陸奥駒」全20冊(青森夢人社、昭和8年~10年、限定25部~50部)で、大学、美術館、博物館研究者からの問い合わせ数第1位の所蔵品である。戦前の少部数発行であるため、全20冊揃いはかなり希少で、資料請求のたびに、コピーして無償で送らせて頂いている。
No1081は、恩地孝四郎「淸岳高邁」(昭和18年、形象社恩地版画集No230)で、久しぶりの恩地オリジナル木版作品である。恩地作品は、摺りが少部数で、日本より欧米の方が高評価であるため、かなりの作品が海を渡ってしまいオリジナル作品と巡り会うことは稀である。たまに邂逅出来ても高額で、資金と勇気不足で尻込みする場合が多い。実を言うと、古書店で見つけた木版秀作に、今の今、尻込み中である。そして今の今の今、、勇気を振り絞って注文の電話をいれてみたら、なんと売り切れであった。落胆4割、安堵感6割の複雑な気持ちであるが、やはり日本でも、その芸術性の高さから恩地人気は、地を這うように浸透しているのだろう。その意味で、手前味噌、自画自賛だが、恩地作品365点常設展示は、世界でも希有で、少し胸を張れると自負している。
「渡辺美術館コレクション展」(9月3日~11月3日、真岡市田町まちかど美術館)、「第34回真岡市美術展」(10月8日~10月19日、真岡市荒町久保記念美術品展示館)が滞りなく終了した。当美術館展示作品から、渡辺美術館コレクション展には16点、真岡市美術展には5点出品させて頂いた。
今回で34年目を迎えた真岡市美術展は、芸術による人類の進化を夢見た久保氏の芸術理論が、真岡市で未だ立派に息づいていると実感出来る素晴らしい美術展であった。一方、私個人は、「芸術の大衆化」の名のもと、意図的に、狭い場所にスーパーや八百屋さんのように作品を雑然と展示しているのだが、綺麗な美術館に美しく整然と展示された当美術館の愛おしい作品群を見て、やはり、芸術作品は、華麗な建物に、美しく展示されるべきだと思わざろう得なかった。作品達も、私の方を向いて、「そうだ、そうだ」とうなずいていた。しかし、もう後戻りは決して出来ない。「芸術の大衆化」に向けて、コロナ禍など何のその、来館者数などに目もくれず、北関東の大地で、たとえ展示作品数が2千を超えようとも、この形式でしぶとく美術館を継続しようと、岩よりも固く決意している。
久保貞次郎研究所2020年11月月報(第127回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館)(℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎11月は5点追加し計1086点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連作品88点)
◎久保記念美術品展示館第26回企画展、真岡市田町まちかど美術館常設企画展について 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館11月の追加作品は5点で、No1082は、横田稔「草原叢書」全10冊(版画60点入り)である。横田挿画本はNo999「谷間の博物誌」シリーズ全3冊を既に展示しているが、画家やコレクターの来館者様に極めて高評価であったので、今回横田氏代表作「草原叢書」全10点を展示してみた。きらきら光る宝石のような美書を手にとって心を震わせてみては如何だろうか。
No1083は、昭和2年発行「俳画講座」全6冊(木版49点入り)で、当時の著名な日本画家の美しい木版画が鑑賞できる。
No1084は、大正12年発行肉筆画帳「俳味大鑑」で、6名の日本画家と6名の俳人による12面の書画帖である。この俳味大鑑は数10部刊行されていて、調べたところ、全冊異なった絵、書のようで、その意味で1点物である。
No1085は、1860年刊「ウイリアムホガース全作品」(鋼版画151点入り)で、鋼版画は鉄版画とも言われ、鉄染みが出る欠点は有るが、繊細な線描が可能で、英国では19世紀後半まで多用された。
最後のNo1086は、1880年刊「ターナーギャラリー」全3巻(鋼版画120点入り)で、10月追加作品「ドレギャラリー」と同様、多くのターナー版画本から秀作を選び3巻にまとめたアンソロジー大作だ。
皆様お気付きのように、11月は、5点全て稀覯本になっているが、絵を展示するスペースが無いためであるのは言を待たない。
コロナ禍で、来館者が少ない中、10月14日、11名の方々が、突然同時に来館なされた。真岡女子高生、市の職員、新聞記者の皆様で、話を聞くと、市の魅力を高校生が発信する「真岡すきすきシェアクラブ」の活動の一環で、偶然立ち寄ったとの事であった。今後この「すきすきシェアクラブ」活動が定着し、更なる発展を祈願して止まない。11名の皆様にも規則通り、アイオー版画と拙書著作集を受け取って頂いた。
11月25日、小雨の中、久保記念美術品展示館第26回企画展「魔法の版画 リトグラフ」、真岡市まちかど美術館常設企画展「幻想の銅版画~内なる情熱を刻む~」を観に行った。久保記念館では、瑛九作品13点、オノサトトシノブ作品3点、アイオー作品2点、利根山光人作品2点、泉茂作品2点計22点が展示されていた。比較的大きい瑛九作品13点が立ち並び壮観であった。田町まちかど美術館には、瑛九作品11点、泉茂作品6点、藤本よし子作品2点、木村茂作品11点、久保卓治作品4点計34点が展示されていた。銅版画であるため比較的小品が多く、田町まちかど美術館にしてはいつになく多数の作品展示であり、楽しく鑑賞出来た。久保記念館の瑛九展示作品は全て真岡市蔵宇佐美コレクションで、まちかど美術館の瑛九展示作品は全て真岡市蔵久保コレクションであり、真岡市蔵の瑛九作品数は、世界でも屈指である。瑛九芸術の評価は世界中で年々高まり、オリジナル作品は高額で入手困難で、多数の真岡市蔵瑛九作品はとてつもなく高価で希少である事を、真岡市民も知っていて損は無いであろう。
11月25日は雨交じりの平日午後であったので、コロナ禍も相まって、両館とも入館者は多くなかったが、私は、入館者数と地域の文化的レベルが比例するとは思わない。21世紀初頭、日本中で、美術館が生活の中に浸透し定着していないだけなのである。人類進化の尺度の一つは、日常生活への芸術の浸透度であると主張したのは、久保氏であったが、人類は、美術館とは異なった、様々な形で芸術を生活の中に浸透させている。例えば、真岡市民、芳賀郡民は、夏の広大な夜空に展開する短命な花火芸術に、何十万と集い、生活の中に芸術を見事に浸透させている。しかし、久保氏が活躍し、久保記念館も建立した真岡市は、年に一度の短命な花火芸術に加えて、小さな額縁の世界だが芸術の主流の一つである長命な絵画芸術を普及させる義務がある。そして真岡市は、入場無料の二つの美術館、二つの認定美術館を展開し、自治体として限界に近い形で、その義務を立派に果たしている。
二つの美術館を訪れて感じた事が3点有った。一つは、都会の大美術館を除けば、これだけの瑛九作品が観られる所は他には無いのではないかという事。2点目は、少ないスタッフで、毎回の事だが、これだけの企画展を準備するのは、相当大変な事だろうという点。3点目は、このような真岡市の美術施策は、後世になればなるほど、必ずや高く評価されるであろうという事だ。感謝の気持ちを胸一杯吸いこんで、今言うぞ、真岡市万歳!
久保貞次郎研究所2020年12月月報(第128回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館(土曜以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館)(℡090 5559 2434)
◎入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎12月は4点追加し計1090点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連作品88点)
◎入試に臨む芳賀の大地の少年少女に告ぐ 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
当美術館12月の追加作品は4点で、No1087は、モーリス・ドニ「ポエム」(1939年、パリ、ボラール刊)である。挿絵も含めて、ドニのリトグラフ69点が鑑賞出来る入手困難な稀覯本で、版画芸術(阿部出版)第63号にも紹介されている.。No1088は、ギュスターブ・ドレ鋼版画フルページ40点入り「ペロー童話集」(1880年、パリ)で、No1078ドレギャラリー全2巻に続いて2点目の展示作品である。No1089も同じくドレ稀覯本「王の牧歌(アーサー王物語)」(1867年、ロンドン、4分冊を全2巻に改装)で、アルフレッド・テニソンの詩と、フルページ36点のドレ鋼版画が競い輝き合った超稀覯本であり、日本で手にとって鑑賞出来る所は少ないであろう。版画芸術第69号で11ページに渡って詳細に紹介されている。No1090は、マティスの復刻版「ジャズ」(2004年、パリ、マンテーズ社)で、リトグラフ20点入りである。1947年限定270部の原本「ジャズ」は、世界中の大美術館に収蔵されていて我々には高嶺の花だが、この復刻版も良質な出来映えで、一瞥に値する作品である。
歴史的コロナ禍で、来館者様も減少し、せっかく足を運ばれても、クラスター対策で、お名前、住所、連絡先をお願いします、と伝えると、外から見るだけで失礼します、と言ってお帰りになる方も多い。それでも、土曜日だけは美術館に冬の日差しが差しこむ事を喜びとし、1月2日(土)も開館した。
入試の時期を迎え、スペースに余裕が有るので、以前当紙に掲載させて頂いた「全ての受検生への檄文」から12項目抜粋して、「入試に臨む芳賀の大地の少年少女に告ぐ」と題して、拙文を書く僭越さを切に許されたい。
「入試に臨む芳賀の大地の少年少女に告ぐ」
①合否は、たった今からの君達の勇気と決意で決まる。そして、多くの者が不安に駆られている今こそが最大のチャンスだと知れ。
②学べる事、入試を経験出来る事に感謝し、真っ直ぐ前を向き、出来うる最高の答案をしたためよ。
③生まれて初めて、身も心も研ぎ澄ませ。
④入試の結果は神聖で崇高。如何なる結果も甘受せよ。そしてその結果を、今後の君のかけがえのない糧とせよ。
⑤天は、木の葉一枚の行く末も知るという。だとしたら、天は、君の努力をどうして見捨てようか。
⑥勝利の女神は、人知れず努力し、他者を思いやる爽やかな若者に、そっと優しく忍び寄る。
⑦何をするにも勇気は必要だが、勉強の継続には真の勇気が必要だと君達は既に知っている。だが苦渋の中で獲得したその勇気は、君の将来の確かな不動の武器になると、今の今銘記せよ。
⑧絶えず苛立ち、自分の努力不足を誰かのせいにする受験生に合格者は少ない。
⑨これから入試に臨む君が家族の中心になるのであるから、笑みを絶やさず、穏やかな心で、周囲の人に、優しい言葉をかけよ。
⑩不安にならない入試など無いのだから、多少の不安は、勉強の原動力になる。それでも入試間近不安に駆られたら、私は一人で戦っているのではない、家族と、愛する友と、まだ見ぬ同胞と共に戦っていると、呪文のように繰り返せ。
⑪周囲に言われるから勉強してやってるなどとうそぶく受験生は、皆無だと思うが、万が一居たら恥を知れ。
⑫もう避けては通れない。だとしたら、胸を張り、勇気に満ちて、君の誇れる答案を書いてこい。
久保貞次郎研究所2021年1月月報(第129回)
◎渡辺美術館 栃木県新コロナウイルス非常事態宣言を受け、1月15日から2月21日まで臨時休館。
◎毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎1月は4点追加し計1094点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連作品88点)(連絡先℡090 5559 2434)
◎真岡女子高 渡辺通枝奨学金について 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
栃木県新コロナウイルス非常事態宣言を受け、真岡市の他の美術館と同様、1月15日から2月21日まで臨時休館させて頂きます。ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
1月の当美術館追加作品は4点で、内訳は、No.1091が、ギュスターブ・ドレ木版136点入り「ダンテ神曲」全3巻(1903年、ロンドン)である。昨年12月追加作品、ドレ版画稀覯本「ペロー童話集」、「王の牧歌」に続いての大冊追加作品で、今後もドレ版画入り稀覯本の追加を予定しているので、今夏までには、日本で屈指のドレ版画本展示美術館になるかも知れない。
No.1092は、大内青圃テラコッタ作品「摩尼羅末の神」で、No.808「宝光馬」に続いての大内テラコッタ作品である。2点とも小品だが、実兄の大内青坡No.253油彩30号「裸婦群像」の隣りに展示した。大内兄弟の作品3点を同時に鑑賞出来る美術館は多くないであろう。
NO.1093,No1094は、藤井浩祐ブロンズ作品2点で、女性像「寒山」と、小品「煙草入れ」である。2点とも2014年小平市平櫛田中美術館「藤井浩祐展」の出品作品であり、図録にも掲載されている。7年前、2作品返却時、学芸員から金銭入りの封筒を渡され、一切無償でやっておりますから、とお返しし、何度かのやり取りの後、気持ちよくお返し出来た事を、鮮明に記憶している。そして当方を信頼して下さったのか、現在でも、田中美術館の展覧会図録を送って下さり、有難い限りだ。
今月月報もスペースに余裕が有るので、「真岡女子高 渡辺通枝奨学金」と題して、拙文を書かせて頂く事、切に許されたい。
「真岡女子髙 渡辺通枝奨学金について」
亡き母渡辺通枝(旧姓小峰通枝)は、1939年、県立真岡高等女学校(現在の真岡女子高)を卒業し、早逝した両親に変わって家計を支えるため、大学進学を諦め、足利銀行に入行した。足銀時代の思い出話には、名士で富豪の久保貞次郎氏がよく登場した。久保氏が来行すると、その場の行員は全員起立して深々とお辞儀をしたという話、久保氏は密かに多くの芸術家を支援していたという話を、小さい頃から母に聞かされた。
古希を迎える2年前、渡辺私塾事務長として多忙の中、母が数十年前に書いたPTA会誌の短文が偶然見つかり、心のこもった文であったので、子供達が冷やかし半分に褒めちぎったら、それで火が付いたのか、堰を切ったように文学書を読み文章を書きだした。そして70歳の時、私たちの後押しで、恥じらいながらも1993年度日本随筆家協会賞に応募し、3千数百名の中から、見事最高賞を受賞した。翌年、真岡女子高に、渡辺通枝奨学金の創設を申し出、快諾して頂き、今年で28年目を迎える。本を1冊出版して随筆家人生が終わる歴代受賞者も多い中、母は、5冊の随筆集を刊行し、日本随筆家協会理事、日本ペンクラブ会員にも推挙され、著書が日本図書館協会選定図書,、全国学校図書館協議会選定図書にも選ばれた。日本では芥川賞、直木賞以外文学関連報道は少ないが、70歳になって随筆家デビューした地方の一女性としては、異例の活躍であったろう。その証左に、日本ペンクラブ電子文芸館にアクセスすると、北原白秋、寺田寅彦、芥川龍之介、尾崎紅葉、坂口安吾等の珠玉の随筆作品135篇に混じって、母の作品5篇が全文掲載されていて、5篇掲載は現在母一人だけである。「初夢」、「道なかばにして」、「野の菊」、「五行の神」、「八十路生きていく」の5篇で、文字通り80歳を過ぎても、事故で片目を失いながら、心に染み入る作品を書き続け、2013年冬、90歳の天寿を全うした。母の後ろ姿を追って、私も、一顧だにされないが13冊の拙本を書き、弟は現在、真岡随筆クラブの会長を務めている。
真岡女子高在校生の皆様がこの拙文に目を留め、70歳にして随筆家になった卒業生が居た事、隻眼の身で90歳までエッセイを書き続けた同窓生が居た事を、心の片隅にそっと置き、何時の日か苦渋の時、その記憶をささやかな力に変えて頂ければ、渡辺通枝奨学金を残した母にとって至上の喜びであろう。
久保貞次郎研究所2021年2月月報(第130回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎2月は4点追加し計1098点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連作品88点)(℡090 5559 2434)
◎「久保貞次郎氏の業績と、女性解放運動の文明論的小考察」 久保研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
1月15日から2月21日まで真岡市の他の美術館に倣って休館にしたため、2月はほとんど開館出来なかったが、追加作品は4点とした。No..1095は、私の好きな画家、林湖山の「終演」6号で、湖山得意の、もの悲しくも優しいピエロの油彩画である。No.1096からNo.1098は、ギュスターブ・ドレ挿絵稀覯本で、「ラ・フォンテーヌ寓話」(1866年、パリ)、「ドレ ロンドン巡礼」(1872年、ロンドン)、「ドン・キホーテ」全2巻(1869年、パリ)であり、3点とも150年ほど前の、重厚な大冊だ。今月で、ドレ挿絵稀覯本展示は7点になったが、まだ8点ほど所蔵しているので、夏までには全て展示したいと思っている。半世紀に渡って少しずつ蒐集したドレコレクションだが、全15点展示が実現出来れば、日本でも有数のドレ挿絵本展示館になるに違いない。
今月報もスペースに余裕があるので、「久保貞次郎氏の業績と、女性解放運動の文明論的小考察」と題して、拙文を書かせて頂きたい。
「久保貞次郎氏の業績と、女性解放運動の文明論的小考察」
久保氏の業績を、①美術評論家、②美術品コレクター、③ヘンリー・ミラー絵画の紹介者、④多くの芸術家の経済的思想的支援者、⑤現代版画のプロデューサー、⑥創造美育運動の提唱者、⑦小コレクター運動の創設者、⑧エスペラント学会会長、⑨町田美術館館長、⑩教育者の10項目に私は分類している。⑩教育者について補足すると、久保氏は50歳から78歳まで28年間、跡見学園女子短大で、教鞭を執り、8年間学長を務めている。久保氏は、既に半世紀前に、女性の活躍が人類の未来を左右すると確信し、うら若き女子大生に、斬新で夢のような芸術教育を実践した。例えば、授業の一環で、美術館や画廊を訪問し、学生に作品の感想を自由に発表させ、ほとんどの場合、その場で乙女達の純粋な感性を称賛した。また、芸術作品を3点以上所有し、生活の中に芸術を浸透させるという「小コレクタ-運動」の主旨のもと、自らプロデユースしたオリジナル版画を廉価で乙女達に譲った事もあった。生徒に絵を売るとは何事か、という非難も有ったが、耳を傾ける事は無かった。僅かだが身銭を切って、気に入った作品を購入する事も「小コレクター運動」の主旨の一つである。代金のほとんどは版画作家に渡り、貧しい作家達の経済的支援の一助にもなった。蛇足だが、その版画作品を今も所持していれば、数十倍、数百倍の価値になっている作品もある。
1960代後半に米国で起こったウーマンリブ(女性解放)運動は、日本にも波及し、1970年11月、東京で第1回ウーマンリブ大会が開催されたが、久保氏は、その11年前、1959年4月、跡見学園女子短大で、「児童美術」、「美術鑑賞」の講座を担当し、美術を通した女性解放運動を、既に見事に実践していたのである。
多くの生物は、種の保存の宿命を背負う女性が優性であり、人類も女性の方が寿命が長い。女性の優位を無意識に感知している男性達は、腕力、暴力を背景に、営々と男性社会を築き、営々と戦争を繰り返してきた。おそらく西洋の悲惨な魔女狩りや、「美」の名のもと、女性の足を弱める東洋の「纏足」という風習、女性の首に幾重にも鉄輪を重ね脊髄を痛めるアフリカの風習も、女性に対する男性の恐怖の裏返しなのだろう。
以前、愛犬が花火の音に驚いて失踪した事があった。家族で一晩中探し回り、私はもう見つからないと諦めた。しかし妻は、愛犬の首輪の匂いを嗅いで涙を流し、愛おしさの余り、愛犬の排泄物まで捜し始めた。しかし茫然自失の中、突然奮い立ち、インターネットで愛犬と同犬種の写真をプリントアウトし、人の集まるお店に貼らして頂いて、警察にも連絡した。その甲斐あってか、何と1週間後、奇跡的に愛犬と再会出来た。この時の妻の底知れぬ情の深さ、本質に突き進む行動力を目の当たりにして、妻には、いや女性にはとても適わない、足元にも及ばないと心底痛感した。
これからの人類の進化には、このような情の深さ、行動力、女性の非暴力性、破滅に対する本能的回避能力、生物学的強靱さが何としても必要である。世界の指導者の半数が女性になり、猪突猛進型の男性指導者を母性で優しく包み、重大な場面で女性の決断を尊重すれば、近い将来、戦争、差別、暴力、貧困も激減するに違いない。時代が女性の感性を要請している只中、女性の意見をどれだけ取り入れるかが極めて肝要であるのに、先の五輪組織委会長の「女性はおしゃべりで会議が長くなる」という言は論外なのだ。21世紀初頭、文明論的には、人類の目映い未来は女性の今後の活躍に拠る、という確固たる認識を全ての人が持たねばならぬ時代なのである。
久保貞次郎研究所2021年3月月報(第131回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、今年度来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎3月は5点追加し計1103点展示(恩地孝四郎385点、久保貞次郎関連88点)、2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「児童教育小論~子どもは褒めて育てよう~」 久保研究所代表、渡辺美術館館長 渡辺淑寛
去る3月13日(土)は強い雨風で、来館者様は皆無であろうと思っていたら2名の方が来館され、お一人の御婦人はタクシーで来て、タクシーでお帰りになった。熱心に写真をとられ、感性豊かな御感想も述べられた。お見送りの時、気がつくと、無意識に私は深くこうべを垂れていた。
当美術館3月は5点追加し1103点展示となった。5点ともギュスターブ・ドレ木版挿絵稀覯本で、No1099は、「ラブレー論」全2冊(1928年、パリ、ガーニエ社)。No1100は、「失楽園」(1800年代中期)で、No1101は、「ほら男爵の冒険」(1880年)。No1102は、「新約・旧約聖書」(1866年)で、最後のNo1103は、「クロテミテーヌの伝説」(1870年)であり、後の4点は、ロンドン、カッセル社刊である。今月で、ドレ挿絵稀覯本は12点展示となり、机の上に重ねて展示しているので、ご興味をお持ちの方は是非来館なさって100年以上も前のドレ版画を紐解き、1世紀半前の英仏に思いを馳せて頂ければ幸いである。
今月報も、スペースに余裕が有るので、「児童教育小論」と題して拙文を書くこと、切に許されたい。児童美術教育の権威であった久保氏も、天で喜んでいらっしゃるであろう。
「児童教育小論~子供は褒めて育てよう~」
私塾という名の、本音が一番ぶつかり合う教育現場で、45年間子供たちと向き会ってきたが、不動の確信を持って言える事が一つ有る。それは、子供は、褒められることで成長するという事だ。肉体的栄養は主に食べ物であり、精神的栄養は「学び」であると良く言われるが、それでは不充分だと思う。他者から認められること、褒められることが精神的成長の必須の触媒となるのだ。この「称賛」という触媒は、肉体にも好影響をもたらす事は言うまでも無い。「今日、塾の先生に褒められたよ」と家族に伝える弾む声を想像するまでもなく、褒められた子の、喜びに溢れた輝かしい表情、帰って行く時の誇らしげな足取りを見ればすぐ解る。子供の成長にとって不可欠な要素は「褒め言葉」なのだ。
40年近く前、中学1年生で、成績は思わしくないが、ノートを綺麗にとるおとなしい男の子がいた。「うわー、ノート綺麗だね、君、絶対伸びるよ。ご褒美に、一つ良いことを教えてあげるね。後で見直すためにノートをとるのだから、君はすごい武器を持っているという事だよ」と私はその子の目を見て伝えた。案の定、その子は、家でノートを見返し、復習の習慣を身につけたのか、1年後には学校で上位になり、高校を首席で合格し、現役で東大に進学した。
褒める点が容易に見つからない時、私は容姿について褒める事もしてきた。これも30数年前の事だが、3兄弟で上二人は在塾していて、三男の方の入塾手続き時、御父兄は、本人の前で、3兄弟のなかで一番出来が悪いと話した。その子の顔を見た時、何百回と言われ続けたのだろう、その言葉を否応なく受け容れていたが、一瞬、悲しい目をした。私は、すかさず言った。「お父さん、3人の中で一番賢そうな顔をしてますよ。伸びると思います。」 その子の顔が一瞬明るく輝くのを、私は見逃さなかった。しかしその子が本当に力をつけたのは高3生になった5年後のことである。その5年間、3兄弟で一番成績が悪いと言われた時、必ず「塾長が、一番頭良さそうだって言ってくれたもん」と、自分に言い聞かせるように反論したという。大学合格報告時に御父兄からそっと、そう教えて頂いた。3兄弟とも見事に国立大に進学したが、一番難易度の高い第一希望に合格したのは、何と、その子であった。
面談時、中島みゆきの歌が好きだという事で、その感性を褒めると、受験勉強に集中し、希望の教育学部国語専修に合格した女子高生。「君には、努力を持続出来る素晴らしい才能がある」と褒めると、その通り努力し、現在国立大医学部で研鑽している好青年。授業中、宮澤賢治の「永訣の朝」を解説すると、素晴らしい感想を述べ、その感受性を称賛され、現在県立高の国語教師をしている教え子。英単語予習を完璧にしてくるので、「お姉さんと同じ大学に行けるかも知れないよ」と、お世辞まじりで褒めると、本当に、最難関女子大に進学した女子高生。それほどの成績ではなかったが、どっしりゆっくり勉強するので、「君、なんか、ゆっくりでいいね。覚醒するかも知れないよ」と褒めると、本当に覚醒して、旧帝大歯学部に進学した純朴な男子高生。一見弱々しく見えるが笑顔を絶やさずいつもにこにこしているので、その事を称賛すると、一層の笑顔で努力し、現在立派な医師をしている小柄な青年。例を挙げたらきりがないが、一つ確かな事は、私のなにげない褒め言葉が、塾生達にとって大きな心の支えになった可能性は零ではないという事だ。
もしかしたら、子供ばかりでなく、大人も「褒め言葉」で精神的に成長するのではないか、あるいは全ての生き物も同じではないか、と思いを馳せているのだが、この問題は、後の機会に譲りたい。
いずれにしても今回の結論は明白である。「子供は褒めて育てよう!」
久保貞次郎研究所2021年4月月報(第132回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎4月は6点追加し計1109点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連88点)、2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「芳賀の大地の少年少女へ~綺麗な言葉を使いましょう~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
4月18日(日)、宇都宮市と群馬県の方から御連絡があり、日曜日であったが特別に開館の運びとなった。お一人の方が、気品漂う聡明美麗なご婦人であったので、説明に力が入り、午後2時から4時過ぎまでご案内させて頂いた。版画、著作集も受け取って頂き、楽しい午後の一時であった。
4月初旬、久保観光記念館レストラン「こころ」に20点目のシャガール版画を持参し、美味しいランチを楽しんだ。20点の版画作品の多くは、フランスの著名な版画誌「デリエール・レ・ミロワール」掲載のリトグラフから私が額装した
作品で、由緒正しきオリジナル作品である。色彩豊かなシャガール版画を楽しみながら、前菜がサラダバーのランチを満喫するのも一興だろう。
当美術館4月は6点追加し1109点の展示となった。No1104は、恩地孝四郎木版「朝」(1930年「線」創刊号より)。1975年形象社「恩地孝四郎版画集」には未掲載だが、2016年東京国立近代美術館「恩地孝四郎展」では、ハワイホノルル美術館からわざわざ借り受けて展示された作品である。No1105,No1106は、ギュスターブ・ドレ木版稀覯本で、ドレ挿絵本は計14点の展示となった。No1107,No1108は、私の好きな版画家永瀬義郎の「少女」、「蝶」の2点である。No1109は恩地孝四郎木版「青空」(1921年「国粋」1月号より)で、前述のレゾネ本2冊には未掲載作品であり、この作品が展示されている所は当美術館だけの可能性もある。これで恩地作品は387点展示となり、常設展示作品数だけなら世界でも屈指であろう。
「芳賀の大地の少年少女へ~綺麗な言葉を使いましょう~」
初めての料理に出会った時、見た目と匂いで食するかどうか判断するが、初対面の人に対しては、見た目とその人の話す言葉で判断評価する。容姿端麗、紳士然としているが、話し出すと、品の無い話し方で、落胆する時が希に有る。
綺麗な言葉とは、標準語という訳ではない。宮澤賢治「無声慟哭」の中で、賢治の妹の、死の淵での「それでもからだくさえがべ?」(それでも私の体臭いでしょう?)という末期の言葉が、岩手県花巻の方言で書かれている。この方言に初めて触れた時、私は胸を突かれ涙を禁じえなかった。綺麗な言葉とは、相手を思いやりながら、自分の気持ちを素直に表現する言葉である。相手を傷つける言葉は、必ずといってよい程自分に跳ね返ってくる。例えば、「うるせー」などという言葉は、一番汚い言葉であり、「死ね」などの雑言は、論外中の論外だ。そのような事を口にする者は、歳を重ねた時、同じ言葉を子どもに言われ、死ぬ程辛い悲しみを味わうかも知れない。
日本神道には、人の発する言葉には魂が宿どり、言霊となって他者を動かすエネルギーを持つという考えが有る。相手を傷つける汚い言葉は、自分の心も傷つけ汚すのだ。それとは逆に、絶えず相手を思いやる綺麗な言葉を使えば、どんな経験、学びより人間的成長の糧となる。例えば、家庭内で諍いが生じ、険悪な空気が流れた時、「お父さん、お母さん、夫婦喧嘩してる時じゃないよ」という非難の言葉をぐっと飲み込んで、「家族みんなで力を合わせて頑張ろうね、私も勉強頑張るからね」と優しい声で笑顔で言えば、その険悪な空気は尻尾を巻いて退散し、皆の顔に笑みが戻るであろう。
芳賀の大地の少年少女よ、二度と再び「うるせー」、「死ね」などと口にするな。二度と再び、父母祖父母兄弟姉妹を悲しませるな。家庭で、学校で、回りの人に優しい言葉をかけよ。友の優しい一言で、肩に背負った悲しみが喜びに変わる時が有るのだから、孤立して苦しんでいる人に、自分は味方だと、そっと言葉にして伝えよ。
家庭、学校、社会での君達の最強の武器は、何と、君達の発する言葉なのだ。だから、汚い言葉を使って自分を弱めるな。綺麗な言葉を使って自分を高めよ。芳賀の大地の少年少女よ、もう一度言う。胸を張り、真っ直ぐ前を向いて、綺麗な言葉を使おう。
今月報の、横柄で尊大な物言い、切に切に御容赦願いたい。
久保貞次郎研究所2021年5月月報(第133回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎5月は6点追加し計1115点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連89点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「大人にも動植物にも褒め言葉を」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
渡辺美術館は、2015年5月24日に設立されたので、本年5月24日で6年目を迎えた事になる。名古屋大美学美術史の学生時夢見た入場無料、版画贈呈、スーパーマーケットのごとく大衆化された美術館建設に40数年の歳月を要したが、その夢が実現して早6年。幸運が幸運を呼んで、多くの皆様の御協力も有り、展示作品数も1115点を数え、恩地作品387点常設展示は世界にも胸の張れる重要な作品群となった。関係者の皆様、街角美術館に認定してくださった市当局、学芸員の皆様、来館者の皆様に、心より感謝の意を表したい。
当美術館、5月は6点追加し計1115点展示となった。No.1110,No.1111は、1880年と1888年カッセル社版ギュスターヴ・ドレ木版挿絵稀覯本2冊で、今回でドレ挿絵稀覯本は計16冊となった。No.1112は、河内成幸木版「飛べⅢ」(1889年)で小品だが有名作品である。No.1113は、真岡市の版画家浅香公紀木版「長命寺(滋賀)」(1984年)で、浅香氏は、久保氏が支援した優れた画家の一人であった。No.1114,No.1115は、益子町日下田藍染工房八代目当主日下田博藍染額「湖」、「池畔」であり、この2点で、日下田博藍染額は9点の展示となった。本場の藍染工房に劣らぬ展示作品数になったかも知れない。藍染絵独特の円みのある風景描写に心惹かれる美術愛好家は私だけではないであろう。
「大人にも動植物にも褒め言葉を」
3月月報で、「児童教育小論~子供は褒めて育てよう~」という拙文を書かせて頂いたが、その末尾で「もしかしたら子供ばかりでなく、大人も褒め言葉で精神的に成長するのではないか、あるいは全ての生き物も同じではないか、と思いを馳せているのだが、この問題は、後の機会に譲りたい」と書いた。この場をお借りして、その機会としたい。
1月月報の「渡辺通枝奨学金について」で言及したが、母渡辺通枝が70歳にして随筆家デビュー出来たきっかけは、私と弟による、母への好意的だが意図的なお世辞であった。母は、自らにも厳しかったが家族にも厳しく、その厳格さを和らげる為、弟と作戦を練って、30年前のPTA会報に載った母の短文を褒めちぎる事にした。実際、その短文は、子の成長を純粋に願う飾り気のない素晴らしい文章であったので、褒め言葉にリアリティーが有り、「文章うまいね」、「沢山書くといいよ」、「文芸誌に投稿するといいね」、「作家になれるかも知れないよ」と、お世辞もエスカレートしていった。母は、世辞とは解っていても、何十回となく褒められるので、内心嬉しかったのだろう、70歳を前にして文学書を紐解き、随筆を書き出した。母の小言はめっきり減って、私達の作戦は大成功であったが、素晴らしい副産物をもたらした。書き上がった随筆を何篇か読ませてもらうと、何の虚飾も無い純真な心情が吐露された清らな作品で、私も弟も「月刊随筆」への投稿を勧めた。母は、恐る恐る「黄泉の国の花」という一篇を投稿した。何十回投稿しても掲載されない者が多い中、何と奇跡的に即掲載され、その後、数千名の中から70歳で日本随筆家協会賞を受賞し、瞬く間に日本ペンクラブ会員、日本随筆家協会理事にまで駆け登り、地方の一女性としては異例の活躍であった。ふと振り返ると、そう、母の随筆家人生を創ったのは、私たちの「褒め言葉」なのである。
植物に目を向けよう。幾つかの国で、同じ植物を2鉢用意し、一方には日々罵詈雑言を、他方には褒め言葉を言い続ける実験をしている。かなりの確率で雑言を浴びた方は枯れてしまい、褒められた植物はすくすく育つという結果が報告されている。植物には脳が無くそれ故意識も無いので、偶然だと主張する学者もいるが、それは、傲慢な人間の立場からの脳、意識感であって、人間には未知の、異種の意識がある可能性もある。後にノーベル賞受賞者になった大学教授が、生きた海老を沸騰水に入れると、衝立ごしに置かれている数点のサボテンに微かな電流が流れる実験をテレビ番組で行っていた。サボテンには、人間には未知の、異種の意識があるのかも知れないのだ。
動物の話もしよう。以前プラトンという愛犬がいて、散歩の途中、藪から突然出てきた野良猫に、きれいに猫パンチを受けた。当然反撃しようとしたが、リード(手綱)が有ったため追う事が出来ず殴られ損になった。するとプラトンはへたりこんで、尾崎豊の名曲「I
Love you,」のように、「ウー、ウー、ウー」と悲しそうに泣き始めた。喧嘩に負けて戻ってきた子供のように犬も泣くのだと驚きながらも、余りの哀れさに、全身で抱きしめ「大丈夫、負けるが勝ちだよ、良く我慢したね、偉(えら)い、偉い、負けるが勝ち、プラちゃん、偉い」と褒めてあげた。すると、悲しい瞳で私を見ていたプラトンは、褒め言葉に力を得たのか、立ち上がりまた歩き出す事が出来た。この時、動物も褒め言葉に敏感に反応し、喜び和み、心を開き、愛と勇気を受け取るのだと確信した。
異なる経験をし、違う意見をお持ちの方もいらっしゃるであろうが、私は、自分の経験で物を書くように努めているので、今回も不動の確信を持って言い放つ事を許されたい、「大人にも動植物にも褒め言葉を」と。
久保貞次郎研究所2021年6月月報(第134回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第8巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎6月は5点追加し計1120点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連89点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「芳賀の大地の少年少女よ、数学を楽しく学ぼう~数学は宇宙を知る一つ道~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
人類と新コロナウイルスとの熾烈な戦いも2年目を迎え、勝ち負けはいまだわからない。最悪の場合、人類の消滅という結果だが、天は地球を守るため、人類をこの地上に遣わしたと仮定すれば、人類の絶滅など決して有り得ないと確信している。当美術館でも、入館時、住所、氏名、電話番号を書いて頂きます、と言うと、大半の人が中に入らず、外の展示作品を見てお帰りになる。それでも、足を運んで頂いただけ有難い事だと思っている。
6月の追加作品は5点で、No.1116は、日下田藍染工房八代目当主日下田博藍染絵「山水」である。この作品は、No1007藍染絵「山水図」と左右対称の図柄で、興味深い藍染額だ。今回で当美術館日下田博作品は計10点になり、少し胸を張っている。No1117からNo1120は、中村忠二ミニチュア水彩額27点セット(忠二自作額)、忠二手作り一部本「滝の白糸行記」、同「井の頭行小記」、肉筆原画入り本「蟲たちと共に」の4点である。中村忠二(1898~1975)は、それ程著名な画家ではないが、その数奇な画家人生も相まって、日本中に密かな愛好家のいる作家である。晩年武蔵野の荒小屋に一人住み、拾い集めた紙に、蟲や草花の水彩小品を1万点以上描き残し、美しくも哀しい詩を書き添えた孤高の画家である。数十年前、地を這うように蟲や草花と共生した画家からしか生み出されない水彩小品に感銘を受け、忠二作品を少しずつ蒐集してきたが、当美術館でももっと早く展示すべきであったかも知れない。特に、忠二手作り一部本2点は超稀覯本で、全国の忠二フアンにとっては垂涎の的であろう。7月の追加作品も、忠二作品を予定している。
「芳賀の大地の少年少女よ、数学を楽しく学ぼう~数学は宇宙を知る一つ道~」
数学が大嫌いで、数学を棄て、私立文系希望になる高校生が後を絶たないが、今回は、数学の不思議、楽しさについて書いてみたい。数学の本質に触れ、楽しく数学を学ぶ少年少女が一人でも増えれば幸いである。
まず、小中生の皆様、3分の1は、0・333・・・で、3分の1を3倍したら1になります。0・333・・・を3倍したら、0・999・・・。あれ、1と0・999・・・は同じになってしまいました。不思議ですね。種明かしをすると、数学の世界では、1と0・999・・・は同じとみなすのです。次に、数直線上で、0から2分の1の間に幾つの分数が有ると思いますか。勿論無数に有ります。4分の1,8分の1、16分の1と半分にしていけば無数に有る事はすぐ分かります。3分の1、9分の1、27分の1と3等分しても無数に有ります。5分の1、7分の1についても同様です。僅か0・5の狭い範囲に、無数達がせめぎ合っていて、やはり不思議ですね。
以前、宇宙人とあだ名され、現役で東大に上位合格した秀才が、教科書を読んでも弧度法(ラジアン)が分かりません、と言って来ました。分度器の度数の替わりに、弧長が半径の何倍になっているかで、角を決める方法で、ラジアン(radian)は倍と読むと良いよ、ラジアンとは本来「倍」の意味だよ、と伝えました。するとその少年は目を輝かせ、「目からうろことはこういう事なのですね」と口にしました。公式をただ暗記して使うのではなく、公式の裏に有る本質を学ぶのが数学の本道だと、その時、彼は心奥で得心したのでしょう。
高3理系の皆様、正弦、余弦曲線で0から2分のπまでの面積が1である事は知ってますよね。自然対数関数の1からeまでの面積も何と1なのです。サイクロイドの面積は円3個分で、回転体(ラグビーボ^ル形)は円柱の8分の5倍、アステロイド(星形、ヒトデ形)の面積は円の8分の3倍で、数学の神様、或いは宇宙は、いつも綺麗な数字で答えを用意しています。因みに5対8は黄金比の近似比です。大学初級になりますが、まだまだ有ります。カージオイド(心臓形)の面積は円の1・5倍、正葉曲線(ローズカーブ、四葉形)の面積は円の半分。また、サイクロイド、アステロイド、カージオイドの弧長は、順に、8a,,6a、8aで、宇宙は驚くほど綺麗な答えを用意しています。人類が、数学という手段で宇宙を解析しようとすると、待っていましたとばかりに、綺麗な姿を現します。私には、アインシュタインが言うように、人類の知性を遥かに超えた意志が、宇宙をデザインしているのではと思えてなりません。何れにしても、数学は美しく、純朴で可愛らしくて素晴らしい学問です。そして宇宙を知る一つ道でもあります。皆様を苦しめている入試数学は、数学のパズル部門にしかすぎません。そのパズルも解けるように作られていますので、パズルも嫌がらず楽しく解いてみましょう。今回の結論も自明ですね。そう、芳賀の大地の少年少女よ、数学を楽しく学びましょう。
久保貞次郎研究所2021年7月月報(第135回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(7月31日著作集第9巻、真岡新聞社より新刊)、(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎7月は6点追加し計1126点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連89点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「芳賀の大地の少年少女よ、英語を楽しく学ぼう~第2言語を学ぶ事は人類進化の一過程~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月末日、拙書渡辺淑寛著作集第9巻が真岡新聞社より刊行された。第1巻から第6巻までは、表紙絵に娘の油彩画を用いて高評価であったが、私は、何を錯乱したのか第7巻、第8巻の表裏表紙絵に、私の50年前の不気味なペン画を使ってしまった。案の定、プロの画家以外はすこぶる不評で、第9巻には娘の油彩画を使おうとも思ったが、錯乱ついでに、再度意味不明のペン画を使用した。3冊の表裏表紙絵計6点は全て、20年前に請われて出版した、文芸社「詩画集 潮に聞け」の掲載作品である。南都 麗というペンネームのこの不気味な詩画集は、20年経っても一向に見向きもされず、一定程度評価されるのはあと百年はかかると、一人強がっている。
7月の追加作品は6点で、No1121からNo1124は、中村忠二限定本「秋冬集」、「白黒篇」、「春夏集」、「花と蟲」(1972年~1974年)である。6月忠二追加作品「蟲たちと共に」と合わせてこれらの限定本5冊が忠二の限定本代表作であり、画家であった奥様と3度離婚2度復縁の一因となった忠二の異常な倹約振りは、この5冊の出版の為だと後に判明した。そしてほとんどは友人に無償で贈呈したらしい。家庭を犠牲にした作品完成、画集出版への執念は、優れた画家にはよく有る事だが、忠二の場合、その情念は、我々の想像の遥か彼方に有る。今月の忠二作品展示で、当美術館の柱がもう1柱増えた。来館なさり、忠二作品を見たいと言って頂ければ案内致します。
「芳賀の大地の少年少女よ、英語を楽しく学ぼう~第2言語を学ぶ事は人類進化の一過程~」
皆様の中には、授業に英語が有るから、入試科目だからと、いやいや英語を勉強している方もおられるであろうが、英語学習には三つの重要な意義があると私は思っている。
第1点は、勿論コミュニケーションの手段獲得としての英語学習である。今や英語は世界共通語の性格を帯びつつある。英語圏の人達との会話に使うばかりではない。以前当美術館を訪れたタイやフランスの女性の方々とも英語で意思疎通が出来た。そして今までの経験で感じた事は、通訳などの専門職でなければ、学校で学ぶ単語力、構文力で、外国人との会話にはそれ程不自由しないという事である。肝心な点は、学校の英語をしっかり学び、易しい英語を沢山聞いて、英語で話す段になったら、中1程度の文で、単語を並べればそれで意思疎通可能だという事である。ただ正直言えば、国が目指している、英語での読む、書く、聞く、話すを必要とする人は、将来に渡って百人に一人もいないだろうと以前から感じていた。案の定、大学入試における4つの能力の評価はあっという間に頓挫してしまった。実用英語偏重主義の矛盾が露呈したのだろう。しかし、だからと言って、英語学習をおろそかにして良いという事にはならない。以下の第2点、第3点の意義に注目して頂きたい。
例えば、英文を読む時、第2言語としての英語自体を学びながら、書かれている内容も同時に学ぶことが出来る。そしてセンター英語で7割程度得点出来る高校生であれば、辞書を片手に、ヘミングウェイの「老人と海」、ラフカデオハーンの「試論」、アインシュタインの「私は信じる」、マザーテレサの「上智大講演録」などを原文で、感動しながら読むことが出来る。つまり、受験英語を経験しながら、英語圏の文化の真髄を垣間見る事が出来るのである。これが第2の意義だ。
一つ目の大学で独語を、二つ目の大学で仏語をかじった私は、以前にも書いたが、学生時代シェイクスピア劇を原文で読んだ時、英国と争う事など個人的には有り得ないと思った。ヘルマンヘッセの「青春は美し」を独語で読んだ時、ドイツ人とは戦えないと思った。アルチュールランボーの「地獄の季節」を仏語で読んだ時、フランスと戦う事は無理だと感じた。何も文学に限った事では無い。韓国ドラマ「チャングムの誓い」や「ホジュン~宮廷医官への道~」を食い入るように観たとき、これだけの作品を創る韓国の民と争う事など、到底出来ないと思った。他民族の文化、風土、伝統、芸術の本質に触れる時、私達は無意識にでも、他民族への尊敬、畏敬の念を心奥に沈潜させるに違いないのだ。他国の言語学習を通して、他国の文化、芸術を理解する事は、お互いが核武装しあう事に劣らず戦争抑止力になると言ったら言い過ぎであろうか。終わりの無い軍事力競争に明け暮れるより、近い将来、世界中の人々が、他国の言語学習を通して、お互いを尊敬し、慈しみあう方が、余程世界平和への近道ではないのか。世界中の多くの人々が第2言語を学習する事は、人類が戦争で絶滅すること無く生存し進化していくための、数少ない道であり、人類進化の不可避で必須の一過程であると確信する。これが第3の意義だ。だから芳賀の大地の少年少女よ、英語を楽しく学ぼう。
久保貞次郎研究所2021年8月月報(第136回)
◎県の緊急事態宣言を受けて、8月20日から9月12日まで休館とさせて頂きました
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(7月31日著作集第9巻、真岡新聞社より出版)、(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎8月は4点追加し計1130点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「お年寄りの皆様へ~日々の生活の中で運動を致しましょう~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
真岡市の他の街角美術館と同様、県の緊急事態宣言を受けて8月20日から9月12日まで休館とさせて頂きました。申し訳ありません。
当美術館8月の追加作品は4点で、計1130点展示となった。No1127は、田中岑25号油彩画「金精山」(1959年)。私の好きな画家の一人で、No788、8号油彩画「竜巻」に続いて2点目の展示作品である。No1128は、清水錬徳30号油彩画「横浜港」で、当美術館では4点目の展示作品となった。No1129は、真岡市出身で、久保氏と関係の深かった浅香公紀木版「堤の仏」(1999年)で、小品だが素晴らしい作品である。浅香作品は、10点目の展示である。最後のNo1130は、日下田博藍染絵「空」で、当美術館では11点目の作品であり、11点展示美術館は稀有であろう。
最近、車で来館され、下車せず外の展示作品だけ観てそのままお帰りになる方が散見されるが、新コロナの時代、致し方のない事だ。それで、晴れた土曜日は、外に沢山展示して、ドライブスルー屋外美術館にする事も考えている。受付不要で、乗車したまま50点程の大作を観てそのままお帰りになれば良いので、プレゼント贈呈は無理だが、来館者様は増えるかも知れない。10月から始める事も考えている。
8月14日大雨の土曜日、お二人来館されたが、その内のお一人は、元大学教授の学者で、真岡新聞掲載の私の拙文を熱心に読んでくださっているとの事であった。その時、その先生から嬉しいお言葉を頂いた。「何か運動をなさっているでしょう、あのような文章は、心身とも健康でないと書けないでしょうから」という身に余るお言葉であった。前から少し考えていたのだが、「8月月報で、お年寄りの皆様へ~日々の生活の中で運動を致しましょう~、という文章を書く予定です」と思わず言ってしまった。その事もあり、今までは、教育論、女性論、数学論、文学論などであったが、今回は趣向が異なる事、お許し願いたい。
「お年寄りの皆様へ~日々の生活の中で運動を致しましょう~」
私はスポーツ医学には無知ですので、以下の文章は全て私の体験談です。普遍性の有無は不明ですが、少しでも御参考になれば幸いです。
数十年前、年中無休の超多忙の中、1か月ほど意識的に足の屈伸運動をしていない事にふと気が付きました。それでゆっくり膝を曲げてみると、自分の足が木でできているような妙な感じで、やや恐怖心に駆られ、それ以来、就寝起床時一日2回数秒間、足の屈伸運動をしています。そのお陰なのか両膝とも好調で、同年代の友人にも褒められます。また過労と心労のためか、お腹の具合が悪く、同時期、いつの間にか就寝前寝床で1分間ほど、お腹を円を描くようにマッサージをするようになっていました。勿論今も続けています。更に、5年程前から1日数回、肩、腰、首の運動も加え、直近3年は、顔のマッサージも追加しています。顔のマッサージと言っても、ただ指で、目の下、こめかみ、顎、喉などを10回程度押すだけですが、意外に効果的で心身ともすっきりします。全部の運動でも3分程度で終わり、お腹のマッサージ以外は、何処でも出来ますので、私はトイレ内、スーパーのレジで並んでいる時でも、憚らず堂々とやります。今はソウシャルデスタンスですので、充分可能です。若い時の不摂生が祟り、私は二つの重大な持病を持っていますが、いつの間にか、近親者の男性の中では最年長を今生きています。家族、優秀なお医者さん方のお陰もあるでしょうが、私は、この秘密の運動もほんの少し寄与しているのではないかと密かに思っています。ですから、ほとんど運動をなさっていないお年寄りの皆様、日々の生活の中で、まずは足の屈伸運動から始め、数十秒間でも体を動かしてみては如何でしょうか。日々ラジオ体操をなさっている方は、それがベストです。この素晴らしき地上で1日でも長く生きられるよう、どんどん体を使って、肉体も精神も活性化させ、仕事から解放された、これからの本当の人生を満喫なさっては如何でしょうか。
1637年、デカルトは「方法序説」の中で、「我思う故に我あり」と書き、精神の優位性を説きましたが、西暦100年頃、古代ローマのユウエナリスは「諷刺詩集」で、「健全な精神は健全な肉体に宿る」と肉体の重要性を主張しました。この二律背反を止揚する鍵は、仏教の「色心不二」の概念だと私は思っています。色(肉体)と心は別なものでなく、同じもの一体であるという概念です。私達は、この概念を既に経験しています。心労のあまり胃が痛くなったり、恥ずかしさで赤面するのは、心から色への影響であり、落ち込んでいる時、鏡を見て無理やり作り笑いをすると元気が出るのは、色から心への影響なのでしょう。別に作り笑いをしなくても、楽しくスポーツをした後は、すっきりした気分になる事は誰でも経験しています。ですから、健全な精神を持つ為にも、私達お年寄りは健康でなくてはならず、日々の生活の中で些細な運動が必要です。繰り返します。お年寄りの皆様、日々の生活の中で運動を致しましょう。
久保貞次郎研究所2021年9月月報(第137回)
◎県の緊急事態宣言を受けて、9月30日まで休館とさせて頂きました
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、入場無料、拙書著作集第9巻贈呈(7月31日第9巻、真岡新聞社より出版)
◎9月は1点追加し計1131点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「特殊相対論と量子論」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
県の緊急事態宣言より、結果として8月20日から9月30日まで休館となってしまった。心よりお詫び致します。
9月は全休であり、当美術館9月追加作品も1点のみであったが、重量級にした。ルノアールが他界した年、1919年パリの美術豪商ヴォラールが採算を度外視して出版した「ルノアールの作品と生涯」である。多数のルノアールオリジナル版画入りなので、版画のみ切り取られ、額入りで最近でも高額で取引されている。版画入り完本は世界中で極めて希少で、日本でも数点しか残っていないであろう。40年前、神田神保町洋書専門店で偶然目にし、余りに廉価であったので、素知らぬふりをして購買した事を覚えている。手に取って鑑賞出来る所は、多分日本では当美術館だけであろうから、一瞥していただければ幸いである。
9月15日、芳賀教育美術展の最終審査に参加した。園児から中3生までの作品だが、芳賀郡のレベルは極めて高い。久保氏が主導した創造美育運動の成果の一つなのかも知れない。例年通り久保研究所賞3名を独断で選ばせて頂いた。
今月報は、スペースに余裕が有るので、「特殊相対論と量子論」と題して数式を使わず書かせて頂きたい。
「特殊相対論と量子論」
⑴「特殊相対論」
40年近く前、真岡新聞掲載「高校への5科教室」で、中3生対象に、「特殊相対論」を数式を交えて掲載した事があった。大学の相対論研究者からお電話が有り、「中学生対象の相対論、見たことがない、素晴らしい」とお褒めのお言葉を頂いたのを覚えている。今回は、文章のみで、「光速不変の原理」と「時間の遅れ」の2大原理に絞って書いてみたい。
車を並走させると、お互い止まっているようで、「やあ、今日は」と挨拶出来る。ところが、秒速30万㎞の光は、同じ速度で並走して、「やあ、今日は」と言っても、光君、無視を決め込み何も言わず、秒速30万㎞であっという間に前に進んでしまう。人間には理解困難だが、1887年、二人の米国人マイケルソン、モーリーの実験以来、同じ実験結果で動かしがたい事実である。これが光速は観測者に無関係に不変であるという「光速不変の原理」である。(実際には光速での並走は不可能)
今、電車に乗っていない人と、電車に乗っている人が、リンゴを下に落としてみる。1mを毎秒1mで落とすと、二人とも1秒で床に落ちるように思える。ところが、電車の外の人にとって、電車内のリンゴは進んでる方向に斜めに落ちているように見えるので、距離が2mになったとすると、リンゴが床に落ちるのに2秒かかる。この例では、同じ現象が終了するのに、運動している方は、2倍時間がかかり、外の人に対して時間が遅れる。この「時間の遅れ」も多くの実験で証明された事実である。浦島太郎が地上に戻った時、とびきり若かったのは、宇宙人に招待され光速に近いロケットに乗って旅をしたからだ、と言う識者もいて、「浦島効果」とよばれ、世界でも似た話が幾つか有る。、
⑵量子論
光子、電子、陽子、中性子、コォークなどの素粒子は、粒子と波の両方の性質を持ち、まとめて量子と呼ばれている。「粒子と波の両方性質」と言われても、人間にはやはり理解困難である。ボールが飛んでくるのが粒子だが、地震の時、地面が飛んで来る訳ではない。波として、地面が振動してエネルギーを伝えているに過ぎない。量子は他に不思議な現象を引き起こす。20世紀で一番美しい実験と言われた「二重スリット実験」で、2つの細長い切り込み(スリット)の有る衝立と、その奥にスクリーンを用意する。その衝立に電子1個を照射すると、波の性質である干渉(波の重なり合いと消し合い)が起こる。私は波ですよ、と言っているようである。それで、電子はどちらのスリットを通ったのか調べようと観察すると、何と、干渉縞が消えて、粒子の性質しか示さなくなる。人間が観察すると(知ると)、量子の現象に影響を与えるのである。更に、ここでは触れないが、2つの量子はもっと不思議な現象を引き起こす。(量子エンタングルメント)。我々人間は、量子は、雲のように、もやっとした状態で確率的に存在していて、時には波、時には粒子として振る舞うのだ、と理解するしかない。
⑶結論
私個人は、「光速不変の原理」や「波と粒子の二重性」について、矛盾を感じる事なく、合点がいっている。円柱を真上から見たら円であり、真横から見たら長方形である。そしてどちらも正しい。つまり、人類は、例えとしての円柱を完全な姿で理解する能力が未だ欠如しているのだ。これを人類の「科学的未開性」と呼ぶと、「政治的未開性」は、有史以来の戦争の存在。「経済的未開性」は世界中での貧困の存在。「精神的未開性」は、我々の精神の片隅に宿っている暴力性の存在。「医療的未開性」は、コロナも含めて世界中に蔓延する疾病の存在。未開性を挙げたら切りが無いが、裏を返せば、人類にはこれから進化出来る領域が山ほど有るという事だ。人類の今までの歴史は前史であり、真の歴史(本史)はこれから始まるのだ。人類の輝く未来に、美しき本史に祝福あれ。
久保貞次郎研究所2021年10月月報(第138回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後Ⅰ時から4時まで開館、入場無料、来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(7月31日第9巻真岡新聞社より刊行)
◎10月は4点追加し計1135点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎古沢岩美小論~古沢芸術の本質は反戦思想と母性崇拝~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
10月2日から40日ぶりに開館できたが、来館者様は極めて少なく、1日数名である。それでも、車や自転車でいらっしゃって外に展示した作品だけ観てすぐお帰りになる方々もおられるので、ドライブスルー美術館も考えているがまだ決断出来ないでいる。やや離れた所まで作品を移動するのに、かなりの時間と労力を要するからだ。もう少し考える時間を頂きたい。
10月の追加作品は4点で、No1132からNo1134は、初山滋木版3点である。初山滋(1897~1973)は、一般には童画画家と言われているが、その芸術性の高さ故、多くの収集家から、一流の木版画家と見なされている。特にNo1132の木版「こども」(1948年作)は、童画の持つ純朴さに加えて幻想性に溢れた秀作である。No1135は、古沢岩美銅版画集「修羅餓鬼」(1993年、限定50部、銅版30点入り)だ。この銅版画集は、氏が1960年から1993年まで33年間かけて制作した30点の銅版画からなる版画集で、余りに高額であり、50部という少ない限定部数のため、美術界でも余り知られていない。以下「古沢岩美小論」に続く。今回は久しぶりに専門の美術評論が掲載出来て少し満足している。
◎「古沢岩美小論~古沢芸術の本質は反戦思想と母性崇拝~」
古沢岩美(1912~2000)は、妖艶な女体画で有名であったが、エロ画家と揶揄されたこともあり、美術評論家諸氏や他の有名画家からも不評であった。「似たり寄ったりのグロテスクな気味悪さ」とか「低俗な興味で人目をひくが、いい意味のエロティシズムをも殺している」などの論評に対して、私は以前から違和感を覚えていた。氏の圧倒するような女体画の中に、女性、母性、女神崇拝が感知出来たからだ。氏は、人類救済の可能性を、生物学的に優位な女性だけが持つ母性の中に見出そうとしているのではないかと私は推測していた。そして氏が33年間かけて制作した銅版画集「修羅餓鬼」を手に取った時、私の推測が的外れではないと確信した。加害者と同時に被害者でもあった、中国での3年間の地獄の戦争体験による苦渋と慚愧の中から生み出された30枚の銅版画は、戦争という大きな流れの中で、個の無力さ、悲しみ、残虐さを見事に具現化し、強烈な反戦芸術作品になっている。そして「最も惨鼻を極めた湘桂作戦で日本軍24万人の内、行軍と栄養失調で8万までが干からびて死んでいった修羅のなかでふてぶてしく生き続けた」(古沢氏、みずゑ525号、昭和24年8月号)のは、女性達だと、氏は述べている。そのような想像を絶する人間の残虐さ、存在の過酷さの中で、人類を救う唯一の光明は、残酷な現実を超越出来る艶めかしい女性達の持つ母性であると、本能的に思ったのかも知れない。だとすれば、氏が「修羅餓鬼」を制作している傍ら、隠微で無敵の女神のごとき女性を、何故営々と描き続けたのか説明がつく。
そう、古沢芸術の本質は反戦思想と母性崇拝だと言って過言ではない。そして銅版画集「修羅餓鬼」は、後世、ゴヤの版画集「惨禍」と並び称される反戦芸術作品となるであろう。
10数年前から、ホームページ渡辺私塾文庫「28」古沢岩美関係本の冒頭で、上述の趣旨を掲載していたのだが、その拙文を目にした氏の御子息が、東京からわざわざ当美術館を訪問された事があった。反戦芸術家で母性崇拝画家と捉えてくれるのは、渡辺館長くらいで、父の芸術の本質を鋭く突いてくれて本当に嬉しい、と言って頂いた。古沢岩美氏は、日本のシュールレアリスム、前衛芸術の草分けとして「日本のダリ」と称された事もあったが、終生異端の画家であった。そして御子息も、建築家であると同時に、暗黒舞踏評論家であると聞かされて驚いた。御父の異端の血は、御子息にも脈々と流れているのである。
当美術館には古沢作品が既に5点展示されている。No265,「夕焼けのパリ」油彩20号、No653,「裸婦Ⅱ」子羊皮デッサン4号、No664,「女」手彩エッチング、No803、「姦」銅版、No965,「ミモザ」パステル12号(古沢岩美美術館旧蔵作品)で、今回の「修羅餓鬼」で6点目の展示作品となった。30点の銅版画をばらして額に入れ高額で販売されているの何度か目にして、散逸を防ぐ思いから、当美術館では3セット所蔵している。その旨、御子息に伝えると絶句していたが、私の古沢芸術に対する深い思い入れが伝わったのか、喜んで下さった。大美術館や公立図書館でも1点所蔵していれば良い方であり、完本3セット所蔵は多分当美術館だけであろう。おや、今、心なしか胸を張っている自分が居る。 来館なさり、反戦への思いと母性願望という古沢芸術の本質にそっと触れて頂ければ幸いである。
久保貞次郎研究所2021年11月月報(第139回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時まで開館、 入場無料、来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(7月31日第9巻真岡新聞社より刊行)
◎11月は2点追加し計1137点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「一般相対論と量子論その2」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
11月に入って来館者数が少し増えてきた。嬉しい限りである。7日日曜日は開館日ではなかったが、遠方から前日御予約が有り、3名の方が来館され特別開館の運びとなった。
11月は2点のみの追加であるが、1点は、9月追加の「ルノアールの作品と生涯」に劣らぬ、世界的希少本「ルドン銅版画集 悪の華」である。1891年、ベルギーで刊行された限定100部、ルドンオリジナル銅版9点入り本で、多分日本には有っても数点であろう。「みずえ」1963年2月号で、詩人安東次男が13頁に渡ってこの希少本を紹介している。手に取って鑑賞できる所は、此処だけかも知れない。もう1点はやはりルドンの石版画「女神」(聖アントワープの誘惑Ⅲより、1896年)で、この作品は日本各地で散見出来る。
本年9月月報で「特殊相対論と量子論」と題し、拙文を掲載させて頂いたが、多くの方から、「難解だけど、面白かった」と言って頂いたので、今月報で「一般相対論と量子論その2」と題して、数式を使わず書かせて頂く事、許されたい。
「一般相対論と量子論その2」
⑴一般相対論
前回の特殊相対論では、光速不変の原理と時間の遅れについて述べたが、一般相対論は、重力と時空の歪みと宇宙論が主である。アインシュタインは1905年に特殊相対論を発表した10年後、重力による時空の歪みを表す一般相対論を公表した。質量を持つ物体の周りでは空間が歪むという考えは、やや解りにくい。トランポリンや、厚い座布団の上に重い鉄球を置くと鉄球は深く沈むであろう。沈んだ縁にビー玉を置くと、ビー玉は鉄球の所に落ちていく。極端な例はブラックホールで、超重量星が歪んだ空間の遙か底に有って、近くを通る物質も、光までも奈落の底に落ちていく。我々凡人はそうイメージするしかない。そして何故時空が歪むのかの定説は無く、仮説の重力子(グラビトン)も未だ未発見である。
アインシュタインは、翌1916年、一般相対論を宇宙に当てはめたアインシュタイン方程式を発表した。しかしこの宇宙は定常宇宙だと確信していた彼は、この方程式の解では宇宙が収縮してしまうと解り、翌1917年、反重力(斥力)を表す宇宙項を追加した。この時期になっても、彼の一般相対論は難しすぎて低評価であったが、1919年、アーサー・エディントンが、日蝕時、太陽の近くで光が曲がる事を観察し、アインシュタインは、一躍時の人となった。しかし1929年、エドウイン・ハップルが赤方偏移を利用し、宇宙が膨張している事を証明したため、宇宙項を削除した。その後ジッター宇宙モデル、フリードマンモデル、ルメートルモデルなどが提唱され、現在は、アインシュタインが削除した宇宙項が見直されて、様々な宇宙モデルが発表されている。そして宇宙が膨張していれば、膨張の始まりが有るはずだという議論になり、138億年前ビッグバンで宇宙が始まり、それ以来宇宙は膨張を続けていると言う理論が定説になった。1964年、宇宙背景放射が確認され、ビッグバン理論が定着した時、旧約聖書「創世記第Ⅰ章3に、「神は、光あれ、と言われた。すると光があった」と書かれているので、ローマ教皇庁は歓喜したと言われている。
現在、宇宙膨張の原因を、反重量(斥力)を生み出すマイナス質量のダークエネルギーに求め、探求中であるが、「マイナスの質量」などSF小説並みで、UFOのような反重力飛行も夢ではなくなり興味は尽きない。
⑵量子論その2
前回、二重スリット実験で、量子は奇妙な振る舞いをすると書いた。粒子と思われていた電子は、二重スリットを通り、干渉を起こし波の性質を示す。そしてどらちのスリットを通ったのかを観察すると、干渉縞が消え、粒子の性質のみ示す。更に観察結果を知る前に観察カメラのスイッチを切ると、また干渉縞が現れる(量子消しゴム)。量子が、人間の意図を読み取るのではと、スイッチを切るかどうかは、他の偶然性に委ねても(例えば野球で巨人が勝ったらスイッチオン、負けたらオフ)、結果を人間が知ったら、粒子、知らなければ干渉縞が現れ波として振る舞う(遅延選択実験)。量子は全てお見通しなのか、謎が謎を呼び定説は無い。
更に、一つの量子から、二つの量子を作り、片方のスピンが上向きであると解ると、もう一方がどれ程離れていても一瞬で下向きスピンになる。(スピンとは、自転の向き、NS極、エネルギーの偏り等で難解)
これは量子もつれ(量子エンタングルメント)と呼ばれ、量子コンピューター、量子暗号通信、量子テレポーテーションへの研究が各国でなされている。
⑶結論
結論は前回と全く同じである。人間はこの宇宙を僅かしか知らない。そして戦争の存在、貧困の存在、社会に潜む暴力、差別の存在、蔓延する疾病の存在、いずれも人類の未開性に他ならない。しかし裏を返せば、人類の進化の余地は計り知れないのだ。人類にとって今までが前史で、近い将来本当の歴史(本史)が始まるのだ。
相対論と量子論は、フランスの詩人アルチュール・ランボーの「地獄の季節・別れ」の一節で幕とする。(渡辺かなり改訳)
まだまだ前夜だ 我等は流れ入る全ての精気と情愛をこの身に受け入れよう 暁の時、我等は燃え上がる忍耐の鎧を着て、背中から血を流し光り輝く街中を走り続けよう 次の時代、本史が見えるまで
久保貞次郎研究所2021年12月月報(第140回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(本年7月真岡新聞社より刊行)
◎12月は3点追加し計1140点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎フランス美術誌「ヴェルブ」全26冊について 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月の追加作品は3点で、No1138は、私の最初の著作「愛の三行詩」(ペンネーム南都麗、1997年)で、限定1000部のうちスーパー特装Ⅰ番本である。私が25年前に制作した訳のわからぬ版画が9点添付されている。物好きの方がいらっしゃったら一度手に取って頂けたら幸いである。No1139は、永瀬義郎「孔雀の女王」で、ナガセプリントと言われる独特の版画手法を用いた作品であり、永瀬作品は4点目になった。
No1140は年末を飾るビッグな展示作品で、仏美術誌「ヴェルブ」全26冊、全38巻である。世界的希少本である本年9月の追加作品「ルノアールの作品と生涯」(1919年)、11月の「ルドン銅版画集 悪の華」(1891年)を凌ぐ世界的珍品だ。版画を切り離し額装して販売する画商が多く、全26冊完本で所蔵している所は数少ないであろう。更にヴェルブの解説書である「アルバムヴェルブ」4冊も同時に展示した。吉井画廊刊の並装本と、ルオーリトグラフ入り特装本、ニューヨーク英語版、パリ仏語版の4冊で、この4冊付き「ヴェルブ」完全セットを手に取って鑑賞できる所は世界でも希有に違いない。以下で「ヴェルブ」全26冊について解説したい。
フランス美術誌「ヴェルブ」全26冊について
世界で一番美しい美術誌と言われる「ヴェルブ」は、フランスの美術文芸評論家で画商のテリアードが、米国の富豪の資金援助で、採算を度外視して1937年~1960年の24年間で全26冊全36巻刊行した歴史的美術誌である。オリジナルリトグラフが惜しみなく豪奢に添付されていて、世界中の美術品コレクターの垂涎の的であり、世界的コレクターの久保貞次郎氏も全冊揃い完全セットは未蒐集だったと聞いた事がある。特に、第13号以降の個人特集号は人気が有り、具体的には、第13号マティス、第17~18号ボナール、第19号~20号ピカソ、第21号~22号マチス、第24号シャガール、第25号~26号ピカソ、第29号~30号ピカソ、第31号~32号ブラック、第33号~34号シャガール、第35号~36号マティス、第37号~38号シャガール特集である。とりわけ3冊のシャガール特集号には計52点のオリジナルリトグラフが入っていて、切り取って額装し、現在でも高額で取引されている。一般に書籍から切り取った版画は、画帳崩しと呼ばれ、低価格になるのだが、「ヴェルブ」からの作品は逆に高評価になる。間違いない真作のオリジナル作品である事、「ヴェルブ」の希少性が相まっての事であろう。
19世紀末のルドン、クリムト、ミュシャ、ビアズレー等の幻想的・象徴的・退廃的世紀末芸術に代わって、20世紀初頭、色彩革命のフォービズム(野獣派)と形態革命のキュビズム(立体派)が台頭した。フォービズムの代表はマティスで、キュビズムの代表はピカソとブラックであるが、シャガールはその両方の探求者だと、私見だが私は確信している。そしてもう明白であるが、「ヴェルブ」は20世紀芸術を飾る象徴であり金字塔であるのだ。名大の美学美術史学徒時、「ヴェルブ」が、贅を極めたまばゆい美術誌であるばかりか、西洋美術史の中の重要な一里塚(マイルストーン)であると知った時、何時の日か「ヴェルブ」全26冊を何としても入手しようと夢想した。更に強欲にも、繊細で精緻で極美の江戸木版画本「集古十種」全85冊も同様に夢想した。そしてその後25年間脇目も振らず働きに働いて、神田の古書店ともお付き合いが出来るようになり、バブルも弾けた25年前、夢のごとく全26冊を入手した。相当な重さであったので、洋書専門店主は、郵送します、と言ってくれたのだが、万が一の紛失を恐れ、両手に提げ、汗にまみれながら真岡まで持参した。疲労困憊であったが喜びに満ちた初秋の一日を今でも良く覚えている。蛇足ながら、翌年夢のまた夢の「集古十種」全85冊も奇跡的に入手出来た。はかない夢のようにみえても、強く強く希求しそれに向かって努力すれば、どうやら夢は実現するらしい。「集古十種」全85冊は、2022年末に当美術館で展示しようと思っている。
「ヴェルブ」全26冊と「アルバムヴェルブ」4冊は、2階奥の特設コーナーに置いてあるので、来館なさり「ヴェルブ」を見たいと言って頂ければご案内致します。既に12月11日、毎週のように来館して下さる英文学者と私で、シャガール特集号2冊とマティス特集号1冊を紐解きながら、いの一番に堪能させて頂いた。
18歳の時、ギリシャ・レスボス島から法律家を目指しパリに来たテリアードよ、フランス芸術に魅了され、「熱情」という意の「ヴェルブ」を刊行したテリアードよ、君は知っているか、君がピカソやマティス、シャガール等の才有る若き芸術家を世に知らしめたように、久保氏も池田満寿夫やヘンリー・ミラーや多くの芸術家を世に知らしめた事を。美術誌「ヴェルブ」の名は知っていても、君の名を知る者は少ないが、そんなことはどうでも良い。他の誰でも無く、正に君こそが、西洋美術史の中で燦然と輝く「ヴェルブ」という名の一里塚を打ち立てたのだから。
久保貞次郎研究所2022年1月月報(第141回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)
◎1月は4点追加し計1144点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連90点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(Tel090 5559 2434)
◎久保記念美術品展示館展、まちかど美術館展について
◎第2回渡辺美術館コレクション展について 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新年1月追加作品は4点で、No1141は、日下田博藍染額「山水その2」であり、益子日下田藍染工房先代当主、日下田博藍染額は12点目の展示となった。No1077「山水図」、No1116「山水」と似た図柄だが、よく見ると雲の切れ目など僅かに異なっていて別作品である。詳細は不明だが、決して同一作品は作らないという芸術家の矜持が感じられる作品である。No1142は、塚本張夫15号油彩画「海上の日出」(1940年作)で、塚本油彩画はNo877、15号油彩画「富士かくる」に続いての2点目の展示作品だ。No1143とNo1144は鬼塚金華油彩25号「旭化成田子浦工場」(1958年作)と油彩25号「旭化成延岡工場」(1955年作)で、2点とも「鬼塚金華画集」(平成元年、三彩社)の掲載作品であり代表作である。塚本油彩画、鬼塚金華油彩画は3点とも静寂な風景画で、若い頃は地味過ぎて面白味が無いと思っていたが、年を重ねた昨今、大地の静かな息吹が感じられ、お気に入りの油彩画になった。
年末捜し物をしていて、50年前開催、名古屋の百貨店での国際版画展図録が見つかり、作者、タイトル不詳であった私の最初の絵画購入作品(No754)が図録に掲載されていて、作者が判明した。深沢幸雄「青の少女」(1971年作リトグラフ)で、深沢幸雄は実力派の版画家であり、半抽象的重厚な肖像画秀作である。その当時その百貨店に勤務していた妻の社員割引を利用して購入したとはいえ、なけなしのお金で購入した自分の鑑識眼を少し褒めたい気分でもある。この話にはおまけが有って、その図録の表紙裏に、手描きの美麗な似顔絵が描かれている。妻に聞くと、昨年10月月報で言及した古沢岩美氏が、その版画展に来ていて、妻が選ばれ似顔絵を描いてくれたとの事であった。今とは余りにかけ離れているので、「別人ではないの」と言うと、「50年前は少しは綺麗だったのよ」と言う。端麗な似顔絵と比べると、50年前でもやや無理があるので、二人で大笑いした。
真岡市荒町久保記念美術品展示館では、2月10日から5月15日まで、第32回企画展「油絵の魅力」が開催されている。久保氏旧蔵の真岡市収蔵作品を中心に、真岡市でしか見られない重厚な油彩画が展示されていて必見である。田町まちかど美術館では、第21回常設企画展「栃木の魅力を再発見 郷土ゆかりの作家たち」後期が開催中である。(1月6日から2月28日まで)やはり久保氏旧蔵真岡市収蔵作品が中心だ。入場無料であり、パンフレット等も一切無料である。以前、入館時、コロナ禍で住所氏名連絡先を記載する事が必要であったが、現在はその必要もなく、気楽に入館し真岡市でしか見られない珍しい作品をゆっくり鑑賞出来る。このような素晴らしい芸術環境を創設している自治体は、真岡市以外日本でも希有であろう。日本自治体史の中で、真岡市の芸術政策は、将来高く評価されるに違いない。人類の進化の指標の一つは、「生活の中に芸術を何れだけ浸透させるかだ」と言ったのは久保氏であったし、その延長上で、「一人一人が、オリジナル芸術作品を3点以上持とう」という「小コレクター運動」を真岡市から始めたのも久保氏であった。日本では、ぶらりと美術館を訪れ、額縁の中に有る、新鮮な色と形の新しい世界を鑑賞する習慣は全く定着していないが、その定着化の可能性が一番有る自治体は、真岡市なのだ。そしてその定着化は、久保氏の夢でもあり、私の夢でもある。渡辺美術館でも、薄暗い堅固な建物に展示作品を横柄に飾るのでなく、スーパーや八百屋さんのようにありふれた物として作品を並べて、「芸術の大衆化」を図っているのだが、まだまだ成功とは言えない。コロナ禍も有って、来館者が極めて少ないからなのだが、遙か数千年後全ての人が芸術家である社会に向けて、微かな一歩として、方向、目的は間違っていないと、私は密かに確信している。
一昨年9月3日から11月3日まで、田町まちかど美術館で、渡辺美術館コレクション展を開催して頂いたが、本年3月3日から5月5日まで、真岡市教育委員会主催で第2回渡辺美術館コレクション展を開催させて頂く事になった。オミクロンが猛威を振るっているので、開催出来ない可能性も有るが、前回と同様、16点を展示する予定だ。恩地孝四郎のアルス日本児童文庫表紙絵原画を始めとして、油彩画5点、日本画6点、版画4点の予定だが、実際に足を運ばれて、心震える一作品に邂逅して頂ければ、それ以上の倖せは無い。
私見ながら、新コロナ禍は、宇宙の人類に対する警鐘であり試練であると思っている。人類は、多くの犠牲を払いながらも、必ずやこの見えない敵を駆逐し、更なる医学の進化を獲得するであろう。そうそう、私の著作集の副題は「存在とは進化」であった。だからこそ再度言う。人類はこの試練を必ずや克服するであろう、存在とは進化なのだから。
久保貞次郎研究所2022年2月月報(第142回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)
◎2月は7点追加し計1151点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連92点)、土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「金柑ジャムを作って」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
2月追加作品は7点で、No1145は、泉田勝次郎油彩10号「秋のパリ」で、素敵なパリ風景画だ。No1146は、城景都エッチング「少女」で、多くはないが私を含めて熱狂的愛好家を持つ画家で、当美術館では9点目の展示作品である。No1147,1148は、久保氏が応援した、真岡市出身浅香公紀の木版画2点で、当美術館では、12点目、13点目の展示作品であり、久保貞次郎関連作品では91点目、92点目の作品となる。No1149は、フランス美術誌「デリエール・レ・ミロワールNo.246」で、昨年12月月報で紹介した「ヴェルブ」ほど希少ではないが、シャガールオリジナルリトグラフが14点入っている人気稀覯本である。No1150と1151はその稀覯本の中のシャガール有名作「黄昏時の二人」と「青い背景の画家」だ。シャガール額入り作品は、当美術館では、この2点が初展示である。真岡市荒町久保記念館内レストラン「心」にシャガール版画を20点展示させて頂いているので、当美術館でのシャガール作品展示は後回しになった次第である。
エッセイ「金柑ジャムを作って」
十数年前、近くのホームセンターで、背丈50センチ程の金柑の苗を衝動買いして玄関先に植えた。土質が悪いので、育ちは悪いだろうと思っていたが、7年ほど前から小さな白い花が咲き、50粒ほどの金色の実を付け始めた。その時一粒摘んで口に含んだら、口が曲がるほど酸味が強かったので、これは食用でなく、白い花と黄金の実を愛でる観賞用だと決めつけてしまった。その後、3年ほどたって、2メートル程の高さになった時、実の数が急に増え出し、5百粒近い数になった。だが年を越して寒さで小さく縮んでしまっても、全く気に止めなかった。
昨年12月、東北在住の親類の女性が来宅された時、帰り際に、たわわに実った金柑を見て、「このままにしたらもったいないね。ジャムにすると美味しいわよ」と言って帰られた。私には、「このままにしたら可哀想じゃない」と続けて言ったようにも感じられたので、私は、はっとし、その日の内に、金柑ジャムを作る事を心に決めた。
すぐ、木から半分ほど金柑を摘んだ。中くらいのサラダボール3個が一杯になるほどの量であった。次に、インターネットで、金柑ジャムの作り方を調べた。よく洗い、苦みを取るため下ゆでをすると書かれていたが、完全無農薬故、よく洗った振りをして、さっと洗い、苦みを残したかったので下ゆでを省いた。酸味と苦みが、ジャムの命だという一人合点のこだわりが有ったからだ。その後、金柑を半分に切って、皮付きのまま大きなお鍋に入れ、二つのおしゃもじで、種はそのまま、ひたすら潰した。30分程かかったかも知れないが、初めての事であり、少しも面倒でなかった。そのお鍋に、家に有ったグラニュウ糖を500グラム程入れ、弱火で、かき混ぜながら、1時間ほど煮た。横で見ていた妻に言わせれば、砂糖の量を倍くらいにしないとジャムの堅さはでないとの事だったが、甘さを抑えたかったので、砂糖は追加しなかった。煮ている間に、種がどんどん浮いてくるので、すくうように上手に取った。かき混ぜるのと種取りで忙しくもあり楽しくもあったので、時間はあっという間に過ぎた。少しとろみも出てきて、さあ、金柑ジャムの出来上がりだ。
少し冷えて、粘り気が出てきてから、スプーンに取って味見をした。うーん、なんだこれ、うーん、うまい。酸味と苦みが調和した甘さ控えめの金柑ジャムだ。私の口から出た最初の言葉は、「これ、本物だ」だった。何が本物で、何が偽物なのかは良く分からないが、少し興奮して、「本物だ」を5回ほど連発した。次に、妻が味見をする番だ。妻は、私が作った料理を、未だかつて1度も褒めたことがない。その妻が最初に言った言葉は、「あ、これ、美味しい」であった。そうだ、美味しいものは美味しいのだ。市内在住の親類二人にも、小さな瓶に入れてプレゼントしたが、二人共、変わったジャムだけど、すごく美味しかったと言ってくれた。
翌日、木に残っていた半分の金柑を摘み取り、全く同じように、同量の金柑ジャムを作った。味も昨日と同様素晴らしかった。4分の1ほど瓶に詰め、残りは冷凍した。もう二ヶ月になるが、私と妻の二人の昼食はいつもパンで、勿論美味しい美味しい金柑ジャムをパンにのせて食している。
食う食われるの食物連鎖の中、頂点に立つ我々人間は、余儀なく動植物を食して生きている。それは仕方のない事なのだから、動植物に感謝して、美味しいと言って食すれば良いのだ。動植物も我々の血肉となり、分子レベルでは我々と共生するのかも知れないのだ。
これからは、来年も再来年も、毎年毎年、私がお空に帰るまで、金柑ジャムを作り続けよう。金柑達もきっと嬉しいに違いないのだから。
久保貞次郎研究所2022年3月月報(第143回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)
◎3月は4点追加し計1155点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連92点) 土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「ドイツ鯉」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
3月追加作品は4点で、No1152は、神崎温順、型絵染「大和安楽寺」限定50部であり、四国で消息不明になった型絵染作家であるが、全国に少数であっても熱狂的愛好家のいる画家で、私もその一人である。当美術館では26点目の展示作品で、展示点数では日本で屈指かも知れない。No1153,1154は、1995年第1回川上澄生木版画大賞展の準大賞受賞版画家、高久茂「童子⑴」、「童子(Ⅱ)」の30号木版画大作2点だ。奇しくも、準大賞受賞作品「スカーフ」もNo343として当美術館に展示されている。No1155は、日本画壇よりニューヨークで高評価の、土井宏之「たんぽぽ」40号水彩画大作である。水彩画で40号大作は珍しく、芸術性の高い傑作だ。
真岡市田町まちかど美術館で、3月3日から5月5日まで、市のご厚意により、第2回渡辺美術館コレクション展が開催されている。当美術館自慢の作品15点が、整然と展示されていて、荘厳さも感じられる程だ。当美術館の乱雑な展示と違って、作品達も喜んでいるに違いない。
真岡市荒町久保観光記念館美術品展示館では、2月10日から5月15日まで「油絵の魅力」展が開催されている。23点の展示作品の内、何年か前に寄贈させて頂いた安藤幹衛油彩画「ひかり」(25号)、「不安}(100号)の二科展出品作2点が展示されていて、嬉しい限りだ。
2月月報で、エッセイ「金柑ジャムを作って」を掲載させて頂いたが、好評だったので、今月報でも、エッセイ「ドイツ鯉」掲載を許されたい。
エッセイ「ドイツ鯉」
私が小学校に上がる前の事だから60年以上も前の話だ。亡き父の実家が栃木市の北のはずれ、合戦場近くに有ったので、土曜日の午後、父運転のオートバイの後ろに乗って、2ヶ月に1度は実家を訪問した。一晩泊まって日曜日に真岡に帰るのだが、ある晩、タバコの匂いが染み付いた、頑固一徹の祖父と一緒に寝る羽目になった。私は、嫌でたまらず、直立不動を横にしたまま、微動だにせず一晩を明かした。すると翌朝、祖父は、「としぼは寝相いいなあ、ぴくりともしなかったぞ」と褒めてくれた。それはそうだ。横直立不動だから、ぴくりともしないのは当然なのだ。実家の人達と余り馴染めなかったのに、何故父と共に、頻繁に実家を訪れたかというと、真岡より、もっと素晴らしい自然に触れ会えたからだった。当時実家は、畑と小川と小高い森で囲まれていて、こっそり空気銃で雀を撃つ事も出来た。数回雀を撃ち落として、小さな焼き鳥にしてもらった事も有った。
近くに川幅Ⅰメートル水深30センチくらいの小川が流れていて、日曜日の午前中は、一人で小川に入ってよく遊んだ。周囲が竹製の半円形の掬い網で、魚取りをするのだが、元々その小川には魚が少なく、獲れても小さなどじょうで、全て編み目をすり抜けてしまい、収穫は皆無であった。
或る夏の日、雨上がりで濁った水の中、いつものようにセレモニー風に網で掬っていたら、不思議で重厚な感触があった。上に持ち上げたら、50センチ程の巨大な、黄緑がかった黄金色の鯉が網に入っていた。えら近くに大きなうろこが数個だけの不気味な鯉であったが、普段から図鑑を見るのが好きで、魚図鑑で、その鯉がドイツ鯉だと分かっていたのだろう。「ドイツゴイ、ドイツゴイ、ドイツゴイ」と、子供ながらに、絞り出すように叫んだ。そして、その後の事は、何故か全く記憶が無い。その日、鯉濃(こいこく)にしたり鯉のあらいにしたりして食べた記憶も無いので、今想像するに、余りの驚きに、腰を抜かして獲り逃がしてしまったのか、或いは、鯉の存在が余りに荘厳であったので、意図的にそっと逃がしたのかのどちらかであろう。しかし腰を抜かして獲り逃がしたのであれば、かなりの悔しさが残るであろうから、荘厳さ故、そっと逃がした可能性が大である。
ヘルマン・ヘッセは、「青春は美し」の中で、徹夜して、黎明の中、川辺を一人歩けば、自分も、他の人間も、魚達も、川の水も、草木も、風さえも全てが繋がっていて、同一生命体の異種な表れにすぎないのだという事が確信出来ると書いた。だが生まれて間もない純真無垢な子供は、徹夜などする必要はない。黄金色の微光を放つドイツ鯉の存在は、自分と同等かそれ以上の存在であり、同一生命体と思えたから、そっと逃がしたのあろう。たとえ雀を焼き鳥にして食べたとしても、分子レベルでは、自分と雀は体内で共生すると、本能的に理解していたからこそ、少しの罪悪感も無く、おおらかに焼き鳥を食べたのであろう。
1977年に他界した、ギネス認定鯉長寿記録保持者の錦鯉花子ちゃんは、何と226歳まで生きたという。あのドイツ鯉は、今でもあの小川を悠々と泳いでいるのであろうか。今一度、会って、60数年のお互いの人生を語り合ってみたい。
久保貞次郎研究所2022年4月月報(第144回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)
◎4月は4点追加し計1159点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連92点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「階段で消えた猫」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
4月追加作品は4点で、4点とも益子町藍染工房第八代当主日下田博藍染額である。No1156からNo1159で、「湖その2」、「空その2」、「西明寺景」、「西明寺景その2」で、この4点で、日下田博藍染額は計16点の展示となった。No993にも「西明寺」というタイトルの作品が有り、西明寺風景額3点は、同図柄だが、細部を見ると3点とも別作品で、それぞれが1点物である。版画のように同一作品を複数製作する事は、藍染製作工程上不可能であるのかも知れない。だとすれば、藍染額という作品形態は、その芸術的価値を一層高く評価すべき表現形式なのであろう。一度来館され、その微妙な違いを鑑賞して頂ければ幸いである。
昨年の9月月報で紹介した、パリの美術豪商ヴォラール刊、「ルノアールの作品と生涯」(No1132)について、「多数のルノアールオリジナル版画入りなので、版画のみ切り取られ、額入りで最近でも高額で取引されている。版画入り完本は世界中で極めて希少で、日本でも数点しか残っていないだろう」と書いた。「少し大袈裟じゃないの」と揶揄されたので、もう1度調べ直した所、ニューヨーク、マンハッタンに有る有名古書店で完本が1万4千ドルで売られており、この本の中のカラーリトグラフ「サイレンズ(人魚達)」が切り取られ額入りで、2千ドルから3千ドルのエスティメイト(オークション会社の予想落札価格)で、出品されていた。決して大袈裟ではなかったのだ。その資料も一緒に展示したので、興味のある方は、一瞥なされば幸甚である。
2回連続掲載のエッセイが好評だったので、今回も掲載させて頂く事にした。勿論新作である。
エッセイ「階段で消えた猫」
もう30年以上も前の事だ。早朝、2階へ行く階段で、猫の鳴き声がするので目を覚まし、見に行くと階段の中段に野良猫が疲れて横になっていた。何処からか紛れ混んでしまい、途方に暮れていたのだろう。運悪く階段の上に、起きむくれの妻も現れ、仁王立ちしていた。妻と私に、上と下で挟み撃ちに会い、とりわけ起きむくれの妻が余程恐ろしかったのか、その猫は、一瞬にして消えた。本当に消えた。私と妻は、「あれ、今、猫居たよね」と言って、窓の方を見たが、窓は閉まっている。二人同時に同じ夢を見ていたのかと、狐につままれた思いで、二人はまた床に付いた。
二日が経った。階段の壁の反対側にエレクトーンが置いてあり、その奥から、か細い、悲しそうな猫の鳴き声が聞こえて来た。一昨日の謎が全て解けた。その猫は、恐怖の余り、目にも止まらぬ早さで壁を駆け上がり、壁を越えてエレクトーンの下に隠れたのだ。余りの早さに、妻と私には、一瞬で消えたように見えたのだろう。それにしても、その猫には可哀想な事をした。二日間、飲まず食わずで、恐怖に打ち震え、微動だにせず、一声も発する事無く我慢していたのだ。そして、体力の限界が近づき、助けを求める最後の弱々しい声を発したのだ。妻を呼び相談したが、あの一瞬の光のごとき素早さを目の当たりにしているので、二人共、猫を掴んで外に運ぶ勇気は無かった。それで動物好きの中学Ⅰ年生の娘を呼び、外にそっと連れ出して貰った。娘が猫の胴を上から両手でそっと持った時、「あったかい」と呟き、その一言で猫との意思疎通が出来たのか、猫は抵抗せず娘に身をまかせた。
その夜、妻が、「猫ちゃん、二日も飲まず食わずで可哀想だったね。事情を話してくれれば良かったのにね」と冗談を言った。
そうだ、人類は数千年後、動物と意思疎通が出来るようになれば良いのだ。人間と動植物は、異なった進化の旅を続け、人間と動植物の意識形態は明らかに異なるが、「重なり合う部分」も必ず有るはずだ。犬や猫と一緒に暮らした事が有る人なら、「重なり合う部分」を知っているだろう。
かつて、ポーランド人ザメンホフが19世紀末、エスペラント語という世界共通語を創ったが、人類は遙か遠い将来、生物共通語或いは生物共通テレパシーを創れないだろうか。更には、鉱物、液体、気体あらゆる創造物との、創造物共通テレパシーなる物を創れないだろうか。私は、人類には、それを実現する秘められた能力が有ると、心の奥の方で密かに確信している。想像の遙か彼方に有る遠い遠い将来、我が人類よ、全ての創造物と精神を交感し、この地上から、貧困、暴力、差別、諍い、殺戮を駆逐し、全ての創造物が歓喜の中で共生出来る地上楽園を必ずや成就せよ。
既にもうお空に帰っているかな、あの時の猫ちゃん。妻と私もお空に帰った時、また会うことが有ったら、もう消えなくても良いよ。
久保貞次郎研究所2022年5月月報(第145回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)
◎5月は4点追加し計1163点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「父の思い出~特大うな重~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
5月追加作品は4点で、No1160は、久保氏と関係の深い木村光佑のリトグラフ「塔・C」である。この作品で、久保貞次郎関連作品は93点になった。No1161は、杢田たけをのパステル8号「サーカス」で、杢田は、異端の画家であり、少数だが熱狂的愛好家が居て、勿論私もその一人である。No1163も同じく杢田たけをの作品集で、オリジナルリトグラフ2点入り、昭和55年発行限定稀覯本だ。No1162は、5月の目玉展示品で、同じく異端の画家中村忠二「花と虫とピエロと」昭和51年発行肉筆原画1点入り限定610部稀覯本15冊である。何故同じ本を15冊も展示するのかと言えば、各1冊1冊にそれぞれ異なった肉筆原画が同封されているからだ。忠二が他界した時、1万点を超える肉筆原画が残されていた言われたが、どうやら事実のようで、他界1年後に出版された610冊の全ての画集に、異なった原画が同封されたようである。一人の画家が早描きと称して1点数秒で同図柄を描き上げ、画集に添付する例は散見されるが、遺作を、610部の各冊に同封する例は希有であり、快挙である。忠二が、武蔵野の大地を這いながら、虫や花と同じ目線で描き上げた15点の肉筆画を一瞥して頂ければ幸いである。
エッセイ「父の思い出~特大うな重~」
父渡辺寛一は、物部中、久下田中、真岡中などで教鞭を執り、昭和54年、芳賀町立水沼小学校校長として定年退職し、11年後の平成2年他界した。現職中、脳血栓で何度か倒れ、休職を繰り返しながらも、多くの教職員、御父兄、生徒達の温かい励まし、御支援で、定年まで勤め上げた。最後の数年は、手足、口が不自由になり、我々家族も見るに見かねて、早期退職を勧めたが、父は頑として聞かなかった。しかし、ある時、次のような話を耳にして、家族は早期退職を一切口にしなくなった。朝礼時、校長としての父の挨拶は、「本当に」以外何を言っているのか分からなかったが、その必死さ、生き様、児童を思う純真な姿に打たれ、涙する教職員、子供達が少なからず居たという話であった。目頭を押さえながら、私達家族は、父を誇りに思った。
退職してから数ヶ月程して、父の慰労を兼ね、私と妻と、小学低学年の息子と娘の5人で、食事会を開く事になった。市内にあるフルーツショップの2階に、うな重で有名なレストランがオープンしたと耳にして、そこに行くことに決め、5人で出かけた。こぎれいな部屋に案内され、メニューを決めた。全員がうな重にするほど裕福ではなかったので、当然父がうな重で、後の4人は、廉価なメニューだったと思う。最初に4人の料理が運ばれて来て、少し経って父のうな重が運ばれて来た。蒲焼きの尻尾が大きくはみ出ていて、粗雑な盛り付けだと皆思ったが、口にする者は居なかった。妻が、「お父様、長い間ご苦労様でした」と言い、私と孫二人も、想像を絶する父の刻苦に思いを馳せ、「ご苦労様でした」と心を込めて言った。全員で、「いただきます」と言い、父は、お重の蓋を開けた。尻尾が大きくはみ出ていたのは、盛り付けが粗雑ではなかったのだ。ただただ鰻が大きかったのだ。その時全員、余りの大きさに、思わず一斉に「ウォー」と歓声をあげた。部屋が揺れるほどの歓声であった。私は、その後40年、この時ほど純真に大歓声をあげたことはない。そして驚きと喜びで、破顔一笑の父の笑顔を今でも忘れる事はない。食が細っていたにもかかわらず、完食した父は「本当に美味しかったなあ」と、いつになくなめらかな口調で感想を述べてくれた。
マタイによる福音書6章31「何を食べ、何を飲まんと煩うことなかれ」を座右の銘に、私は、学生時代から、母や妻が作ってくれるどんな料理でも、美味しいと言って食べる主義であるが、慰労会や祝賀会は例外なのであろう。皆が喜ぶ料理で、時には歓声をあげ、時には大笑いして、食事を楽しむ事も数年に一度は必要なのかも知れない。
それにしても、あのうな重は本当に大きかった。引きずる足で必死に二階に這うように上がって行く父の姿を見て、お店の方が、有り難くも、特大うな重を特別に用意してくれたのであろうか。あの「ウォー」という歓声は、思い出すたびに、心の奥でこだまして止む事は無く、幸せを分かち合えた喜びと、父が居ない悲しさが僅かに溶け合って、胸を刺す。しかし、傷口から聞こえて来る山びこは、あの喜びの「ウォー」という歓声だからね、父よ。
久保貞次郎研究所2022年6月月報(第146回)
◎渡辺美術館 毎週土曜午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎6月は1点追加し計1164点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随意開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「ナメちゃんラーメン」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
6月の追加作品は1点のみであるが、その1点は、極めて希少でビッグな1点だ。「ザ・イラストレイテド・ロンドンニュース」合本23冊(1860年~1923年)である。この週刊新聞は、1842年に創刊され、1971年まで続き、世界で初めて
ニュースを絵入りで報じた英国の新聞である。この新聞が、世界中の美術関係者を何故魅了し虜にするかと言えば、1800年代の絵は、全て精密で美しい木口(こぐち)木版画だからである。木口木版とは、ツゲなどの硬い木を、円盤形に真横に切って版木とし、銅版用彫刻刀を使い、より細かく繊細な線を彫ることの出来る木版技法である。版木制作にはかなりの刻苦を伴うが、版木が頑強なので、数万枚の新聞の絵を作成出来たようだ。余りに見事な木口木版画故、新聞の絵の部分を切り取り、額に入れて、鑑賞され、高額で販売もされた。1冊の中に千点近い素晴らしい木口木版画が入っているので、何度か来館され、百五十年前の英国の精緻で美しい木口木版画入り23冊をゆっくり堪能して頂ければ幸いである。
エッセイ「ナメちゃんラーメン」
私が高校1年生の時だから、もう57年前の事だ。学校から帰ると、いつものように、母に即席ラーメンを作って貰った。当時は、お湯をかけるだけのカップ麺ではなく、お鍋に乾麺をいれ、煮込むタイプの即席麺であった。母は、粗く切ったキャベツも一緒に煮込んでくれるのが常であり、その日のラーメンは、何時になくとろみが有り、美味しかった。あらかた、汁を飲み干したあと、私は言った。
「お母ちゃん、今日の、とろみが有ってうんまいよ。あれ、すげえ、肉も入ってる。」
「え、肉入れてないよ」
「そう・・・あれ、この肉、こっち見てる。何だこれ。・・・うわー、ナメクジだー」
椀の底に、茹で上がった大きなナメクジが、恨めしげに私を見ていた。おそらくキャベツに紛れて茹でられたのだろう。私は、腹がよじれるほど大笑いした。母を非難する気はさらさら無かった。母は、「としぼ、ご免、、ご免」と言って、涙混じりに大笑いをしていた。
随筆家になった母は、この話を、1994年出版随筆集「心のページ」に、「ナメ君ラーメン」と題して、発表している。ナメ君ラーメンを料理した母が、書き残したのだから、それを食べた張本人も、「ナメちゃんラーメン」と題して書き残さないと、あの世で、母に合わせる顔が無い。それにしても、ここ57年間の私の自慢話の一つは、ナメクジ入りラーメンを残さず平らげた事なので、母も粋な贈り物をしてくれたものだ。
ナメクジは、英語で、スラッグと言い、形容詞はスラッギュシュで、ゆっくりの、のろまな、愚鈍な、の意味になる。私は、ナメちゃんラーメンを全部飲み干して以来、何をやっても、ゆっくりだが粘り強くなった。35年かけて久保研究所を創設し、40年かけて美術館を創った。ナメちゃんのように、愚鈍だが這うように着実に進むことをいつの間にか覚えた。
ナメクジは、広東住血線虫が寄生している可能性もあり、生食は危険だが、煮込んでしまえば、サバイバル状況下では、貴重なタンパク源になるらしい。また、西洋の物の本によれば、ナメクジが小川の向こう岸に渡る時は、こちら側の木々の葉にじっとしていて、体を溶かすように消して、向こう岸の葉のうえにゆっくり出現するという話もある。そう言えば幼少時、残酷にも、台所に居たナメクジに塩を振り掛けて、溶かした事が有った。ナメクジ達は空間移動して難を逃れていたのだろうか。真偽は不明だが、ナメちゃんは、意外と変幻自在なのだ。古希を優に超えた私も、ナメちゃんのように、変幻自在になって、新たな活動を考えるべきなのかも知れない。57年前から、ナメちゃんの精髄が、私の血潮にしっかり溶け込んでいるのだから。
久保貞次郎研究所2022年7月月報(第147回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎7月は1点追加し計1165点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「加齢臭の生物学的意味」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月の追加作品は、6月同様1点のみであるが、今月の1点も、ビッグで希少な大作だ。私が敬愛する、神崎温順の型絵染本「四国八十八カ所霊跡之譜」全4冊である。型絵染90点入り、昭和58年作、限定7部の巨大稀覯本だ。神崎氏は、限定7部本を販売せず、お世話になった人に献呈したと思われ、3番本と記された全4冊を、当美術館で所蔵出来た事は奇跡に近い。手に取って鑑賞出来る所は、おそらく当美術館だけであろう。神崎氏が四国で消息不明になる少し前の作品で、当美術館では27点目の展示作品である。一度来館され、神崎作品を見たいと行って頂ければ、ご案内致します。土曜日3時間では、半分程も紹介出来そうにないかも知れないが、必見の作品群である。そう言えば、思わず合掌しながら神崎作品を鑑賞した方、「木霊之譜」の一作品にふれ、深い感動の余り身動き出来なかった方など、感動の深さでは、全展示作品の中で、神崎型絵染作品は、屈指である。
◎エッセイ「加齢臭の生物学的意味」
5年ほど前、晩秋の或る日、妻と小学生の孫娘が、私の部屋のドア越しで何やらひそひそ話をしていた。「覚悟出来た?行くよ」とか言った後、ドアが急に開き、片手で鼻をつまみ、片手に消臭スプレーを持って突然侵入し、シャー、シャーと一人7,8回噴射して、瞬時に退室してドアをバタンと閉めた。ドアの向こうで、「死ぬかと思った」という声が聞こえてきた。死ぬかと思ったのは私の方なのだが、そう言えば妻が、私の部屋を掃除する度に、「この部屋、少し匂うので換気に気を付けて下さい」と言っていた。私の部屋は窓が2カ所有るが、洋古書が山積みになっていて換気は入り口のドアのみである。加齢臭の染み付いた万年床も有って、洋古書の古びた匂いと私の加齢臭が見事にマッチして、部屋全体が、異臭という香しい香りを醸し出している。慣れきった香りの中で生活している私には、豊穣な異臭は全く気付かないから困ったものである。
調べて見ると、加齢臭とは、高齢者の男女にみられる特有の体臭の俗称で、その正体は、ノネナール、ペラルゴン酸、ジアセチルと言われているが、詳細は未だ不明らしい。我々人類は年を重ねると、頭、足、脇、臍など、全身が臭くなる。特に、猛暑の中、汗だくになりながら家族のために必死で働いているお父さんは、なおさら、加齢臭の固まりだ。だからと言って、世のお子様方、そのようなお父様に、ゆめゆめ、「臭いからあっちに行って」などと言ってはならない。好きで加齢臭を醸し出しているのではないのだから、「お父さん、先にお風呂に入ってください、今日もご苦労様でした、カレーシチュー食べすぎないで下さいね」ぐらいに、ユーモアを交えて遠回しに言って欲しい。
長い人類史の中で、人間は不必要な物を切り捨て退化させて来た。例えば、尻尾、耳を動かす筋肉、虫垂、お猿さんのような体毛などだが、加齢臭については退化する気配は一向に無い。人間にとって必須なのか、加齢臭は一層強さを増して残存している。
人類史の中、存在意義を主張し続ける加齢臭の生物学的意味は、果たして何なのだろうか。調べようが無いので、私なりに邪推してみた。⑴老人だから、気をつけてね、と周囲の人に知らせるだめ。⑵匂いがきつく、若い人に嫌われて、若者に道を譲るため。⑶匂いがきつく集団から追い出され、かえって人類の生息域を広げるため。⑷匂いがきつく、家族に嫌われて、近親相姦を防ぐため。⑸太古の時、もう老人だから、他の獣に、襲って食べても良いと知らせるため。⑹余りの異臭で、本人気づかず昇天して、口減らしになるため。⑵から⑹は余りに悲し過ぎるし冗談混じりで先史時代に当てはまる事なので、私は⑴だと確信する。加齢臭は、車で言えば、70歳以上の高齢者マーク(四つ葉マーク、枯れ葉マーク)の役割を担っているのだと強く確信する。
私を含めて、加齢臭を身にまとった高齢者に出会った時は、お年寄りなので大切に扱って下さいねと、匂いを便りに伝えているのだから、近づいて深呼吸したり、クンクン匂いを嗅いで、オエ!と嘔吐したりせず、優しく温かく少し遠巻きに見守って頂ければ幸いだ。世の高齢者の皆様、加齢臭は、天が授けた人類必須の機能なのだから、恥じる事なく胸を張って下さいね。誰も居ない所で初秋の風に乗せて、その豊穣な香りとともに、私は、愛する人達のためこの地上で精一杯生きていると、天に伝えて下さいね。
久保貞次郎研究所2022年8月月報(第148回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年7月真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎8月は1点追加し計1166点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「お漏らし小僧とその素晴らしき母」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月の追加作品は、6月、7月同様1点のみであるが、今月もビッグな1点になった。謎の出版社と言われた成瀨書房限定本54冊で、No1166番展示作品である。1973年から1991年にかけて出版された限定113部から505部本で、豪華限定本を全部で何点出版したかは不明だが、一説には80点前後とも言われている。私見だが、75点ぐらいだろう。40数年かけて、少しずつ蒐集してきたが、いつの間にか、54点もコレクトしていた。54冊、手に取って鑑賞出来る所は、当美術館だけであろうから、来館なさり、成瀨書房限定本を見たいと言って頂ければ案内致します。
エッセイは6回連続掲載であったが、殊の外好評で、多くの読者に声をかけて頂いている。相対論や量子論などよりは読み易いからなのだろう。気を良くして今号もエッセイにした。ただ「お漏らし」の話なので、お食事中にお読みになるのはご遠慮頂ければ幸いである。
◎エッセイ「お漏らし小僧とその素晴らしき母」
あれは、60数年前、私が小学2年生の、冬が忍び寄る晩秋の午後であった。その当時男の子にとって、学校のトイレは、おしっこは普通に利用するのだが、大きい方は何故か利用するのを憚(はばか)られた。理由は今でも分からない。朝は急いでいて時間が無く、ゆっくり家のトイレを利用する暇が無かったので、学校から帰ってすぐ、大きいのをするのが常であった。便意を催してぎりぎりの時も有ったが、いつも何とか間に合って家のトイレに駆け込んだ。
しかし、その日は違った。学校から家まで、徒歩で25分程の道のりなのだが、学校を出てすぐ、便意が密かに忍び寄るのを自覚していた。もう道半ばで、我慢が始まった。家まで100メートルぐらいの所で、我慢も限界に近く、冷たい脂汗が流れ出ていた。便秘気味の方には羨ましく思えるであろうが、脳と脊髄が締め付けられるような、あの独特で純粋な苦しみは、他に例えようも無い刻苦だ。あと家まで20メートルの所で、限界を超え、全身冷たい脂汗の中、堰を切ったかのように溢れ出てしまった。小学2年生にしては、多量で少し固めであった。そして偶然にも見事に二つに分かれ、両足もとの、裾(すそ)の締まった股引(ももひき)の中に収納された。激しい苦痛からの開放感に変わって、「うんち漏らし小僧」という最悪の羞恥心に駆られながら、両足を広げ、がに股でゆっくり家に向かった。
「おかあちゃん、うんち漏らしっちった」と、針仕事をしていた母に、弱々しく伝えた。私の疲れ切った様子と、がに股の佇(たたず)まいを見て、母は全てを察知したようであった。母は笑いながらトイレに私を連れて行き、股引の中の汚物を上手に落として、次に私をお風呂場に連れて行って体を拭いてくれた。始終笑っていたが、私のしたたるような脂汗をぬぐう時、急に真顔になって、「としぼ、辛かったね、良く我慢したね」と言ってくれた。きかん坊小僧で絶対泣かないと言われた私も、その時は母の胸に顔を埋めて嗚咽を禁じえなかった。もしあの時、大失態を厳しく叱責され、取り返しようのない傷を心に負っていたら、その後は、「お漏らし小僧」と自分を責め続け、心身共に脆弱で惨めな人生を歩んでいたであろう。母の優しい言葉と、母の胸の中の私の涙が、私の傷を綺麗に流し清めてくれたのだ。
世のお母様方、愛するお子様が、私のような無様(ぶざま)な失態を演じたとしても、決して責めないでほしい。本人が一番傷つき辛いのだから、私の母のように温かい優しい言葉をかけて、包み込んで、我が子の傷を癒やしてほしい。それが出来るのは、お母様だけなのだから。
久保貞次郎研究所2022年9月月報(第149回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書渡辺淑寛著作集第9巻贈呈(昨年真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎9月は2点追加し計1168点展示(恩地孝四郎387点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「美味しい美味しい鯉弁当」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
9月の追加作品は、日本美術院院友長澤昭朗の2作品である。No1167は、40号日本画「痕」で、1975年第30回春の院展奨励賞受賞作品だ。No1168は、院展出品作50号日本画「晩秋」である。院展系の日本画家は、普段は,売り絵と称される華美な花鳥風月を主に描いて生計を立てているが、院展出品時は、時代性、思想性を内包した意欲的作品を出品すると言われている。それ故、オークションに出品される院展応募作品は、難解過ぎて不人気であり、額代の半分にもならない価格で数十年前、長澤院展出品作3点を落札した。今回の追加作品は、その3点の内の2点である。40号作品は車で運んだのだが、50号は車に入らず、猛暑の中、汗にまみれ、手で抱えて運んだ。40号「痕」は、暗い画面に、文明史、人類史に疑義を投げかける人達と、都会のビル群が描かれている。50号「晩秋」は、大地と化した根を持つ、生命そのものの大木が描かれている。オークション会場で一目見て気に入ったが、私以外入札する者は誰一人いなかった。
前回のお漏らし小僧のエッセイは、内容の割に意外と好評であったので、気を良くして、今回も8回連続のエッセイとさせて頂きたい。
◎エッセイ「美味しい美味しい鯉弁当」
私は、真岡中学校に入学すると、すぐ野球部に入部した。もう60数年前の事である。野球部の練習はきつく、1年生はほとんど球拾いと練習の準備と後片付けであったので、忍耐を要する日々であった。だが、私には唯一楽しみが有った。日曜日、別な球場で市内の社会人の試合が有ると、野球部部員が審判を頼まれた。朝から夕方まで数試合の審判を務めるので、皆嫌がるのだが、私は進んで志願した。それは、お昼に豪勢なお弁当が出るからであった。お弁当は、日替わりで2種類有って、一つは、いなり寿司と巻き寿司の弁当で、この助六寿司でも、中学1年の男の子にとっては、かなりのご馳走であった。もう一つは、まばゆいばかりの朱色の重厚な弁当箱の鯉唐揚げ弁当であった。最初、、このお弁当は余りに豪奢で恐れ多く、口にするまで時間を要した。目をつぶって初めて鯉の唐揚げを口に入れた時、美味しさの感動と言うものを、生まれて初めて経験した。中1生なので、美味しさの経験など多くは無いのだが、そのようなことを超越して、ただただ美味しかったのだ。濃い下味付けの唐揚げなのか、川魚の臭みなど微塵もなかった。口と脳一杯に美味しさが広がって、至福の時であった。歳を重ね、東京の幾つかの名店に招待された時にも、世界三大珍味だ、などの能書きが多く、鯉の唐揚げ弁当の感動を超える事は、一度たりとも無かった。後から聞いた話では、市内の、ある旅館の名物弁当との事であったが、詳細は今でも不明である。。
鯉と私とは、少し因縁が有った。真岡小学校に通った6年間、帰り道は行屋川の川沿いを通って帰宅したのだが、海潮寺の橋近くに、川に半分程浸かった大きな木製の箱が有り、その中に多くの鯉がうごめいていた。週に2,3度は、階段を降りて、その木箱の上に乗り、鯉を眺め、話しかけたりもした。存在感に満ち満ちた漆黒の鯉の群れを見るのが、ただ楽しかったのだ。鯉達は、口をパクパクさせながら、「小汚い小僧、早く家に帰れ」と言っているようであった。中学1年の時、私の口に入り、感動を与えてくれたのは、あのうごめく鯉達であったのだろうか。
食べ物は、人間の体に入り、分子、原子レベルでは、人間と共生していくと言う識者も居る。あの時の美味しい美味しい鯉の唐揚げは、60数年経った今でも、私の体の一部となって、全ての面でしぶといと言われる私の生命力の源になっているのかも知れない。
それにしてもあの鯉の唐揚げ弁当は、本当に美味しかった。お空に帰る前にもう一度食べたいが、叶わぬ夢であろう。
久保貞次郎研究所2022年10月月報(第150回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎10月は4点追加し計1172点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎芳賀教育美術展について 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
10月の追加作品は4点で、No1169は、真野暁亭(1874~1934)「仏法帖」全5帖、肉筆淡彩65図、1図8号大の木箱入り大作である。暁亭は、河鍋暁斎の高弟で、次女が日光の寺社に嫁いだ事もあり、栃木県と縁の深い日本画家だ。2001年、日光小杉放庵美術館で「河鍋暁斎とその門人たち、真野暁亭を中心に」展が開催された。
No1170は、藤懸静也「浮世絵の研究」全3冊、1943年、雄山閣で、浮世絵のバイブルと言われている名著だが、東京の古書店で散見出来る本で、この3冊だけでは当美術館で展示する程の希少性はない。No1171が、何と、この3冊の毛筆草稿全18巻である。古河市出身東京帝国大学教授藤懸静也(1881~1958)の矜持を見る思いの大変な労作草稿で、訂正皆無の最終草稿であろう。浮世絵研究で東京帝大教授に上り詰めるのは希有であり、その凄まじい信念と刻苦に思いを馳せ、全文毛筆の全18冊を前にして、人知れずこうべを垂れた。
No1172は、久し振りの恩地孝四郎木版画だ。1922年作「植物の世界」の、1993年恩地邦郎刷限定20部で、「芽ぐむ花」という別タイトルも有る秀作である。これで恩地作品は388点展示となった。展示作品数だけなら世界屈指であろう。
◎芳賀教育美術展について
本年で第36回を迎えた芳賀教育美術展、前身の美術展創設時から久保貞次郎氏も運営に関わり、それ故、久保氏が提唱した創造美育運動の理念も継承されている伝統有る美術展である。
9月6日の一次審査会に始まり、12日こども審査会市民審査会、16日最終審査、9月25日から10月2日まで入選作品展覧会、10月2日表彰式、10月4日作品返却と、1ヶ月に渡る一大イベントだ。実際の運営機関は、主催でなく後援に名を連ねている真岡青年会議所である。青年会議所は1年で役職が替わり、「一回限りだから、何としても頑張る」を合い言葉に、想像を絶する苦難を克服して任務を遂行している。責任感に満ちた彼らを目の当たりにして、私はもう十数年になるが、彼らは、少なく無い年会費を払い、声高に自慢する訳でもなく、僅かな賞賛を求める訳でもなく、誰かに媚びる訳でもなく、ただ密やかに、ひたすらに困難な美術展開催というボランティア活動に没頭している。彼らの無私の活動を目にして、「胸が熱くなる」という表現では到底足りない。このような刻苦を経験して、人は成長するのだという言葉を、彼らに、賞賛の花束と共にお贈りしたい。
芳賀教育美術展入賞者7百余名に、久保研究所から副賞を提供させて頂いて今年で12回目になる。前回までは、ギュスタブ・ドレや靉謳の版画を中心に用意させて頂いた。今年は、セル画(アニメ制作用原画)を準備したが、3百点程しか蒐集出来なかったので、余儀なく、拙書渡辺淑寛著作集第7巻、8巻、9巻各240冊計720冊を副賞とさせて頂いた。セル画は、こども審査会の審査員全員に贈呈出来たので、無駄にならず喜んでいる。来年の副賞用に、既に版画等を捜し始めているが、似たような作品を720点収集する事は極めて困難で、昨年までが奇跡だったのかも知れない。
子供達が自由に描く児童画に優劣を付ける事は、本来かなりの困難さを孕んでいるが、賞を決定する美術展である以上、その困難さは甘受しなければならない。更に上位の賞には、デッサン力の有る完成度の高い絵が入り、そうで無い作品は、やや不遇をかこつが、この流れは、大美術展では不可避なのかも知れない。従って銘記すべきは、他の審査会であれば、結果も変わる可能性が十分有るという事だ。だから選外だったので、もう絵は描かないなどと、ゆめゆめ思わないで欲しい。再確認したい。自由に楽しく絵を描く理由は、賞を取るためではなく、精神を躍動させ自らを成長させる為なのである。
久保貞次郎研究所2022年11月月報(第151回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年真岡新聞社より刊行)(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎11月は2点追加し計1174点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連93点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「懐かしい二人の訪問者」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
11月の追加作品は2点で、No1173は、「佐竹本三十六歌仙」土屋秀禾木版絵巻全2巻、明治34年(1901年)。No1174は、「佐竹本三十六歌仙」土屋秀禾木版絵巻全2冊、大正6年(1917年)、(吉川弘文館)で、2点とも同一版木で刷られたと言われている。前者の絵巻全2巻は数十部、後者は百部前後の部数で、2点とも希少作品である。特に木版絵巻全2巻は、現存数が少なく、平成20年(2008年)に、この木版絵巻全2巻をメインに、秋田県立図書館で展覧会が催された程だ。1901年版木版絵巻全2巻と1917年版木版絵巻全2冊を同時に展示している所は希有であろう。
佐竹本三十六歌仙絵巻全2巻肉筆原画は、13世紀鎌倉時代、藤原信実(ふじわらののぶざね)画、後京極良経(ごきょうごくよしつね)書と伝えられていて、秋田藩主佐竹家伝来の絵巻物全2巻であった。1919年に売りに出された時、余りに高額であったため、37枚に切り離され、掛軸装にして当時の大富豪37人に分売された(佐竹本三十六歌仙絵巻断簡事件)。因みに最高売却価格は、「斎宮女御(さいぐうのにょうご)」で当時4万円、現在の貨幣価値では4億円と言われている。37点の断簡作品のうち1点でも手に取って鑑賞することなど夢のまた夢であろうが、断簡事件以前に制作された2点の素晴らしい木版模写作品を手に取って愛でる事で、大富豪達に劣らぬ感動を得られると、我々庶民が虚勢を張るのも一興だろう。
エッセイ「懐かしい二人の訪問者」
先日、二人の教え子が、思いもかけず来訪してくれた。一人は、真岡女子高から難関国立大医学部に現役で進学し、研鑽を重ね、現在米国名門大医学部での研究医兼教官であるという。その米国の大学は、世界大学ランキングでは、東大を凌ぐ世界的有名大学である。真岡市出身の女性の中では、アカデミズムの世界で頂点を極めた数少ない一人であると言って過言ではないだろう。
実に40年ぶりの再会であった。真っ直ぐひたむきに努力出来る子で、才色兼備で実直な塾生であったため、私は、40年間忘れることなく心の片隅で覚えていた。帰国した僅かの合間に、40年後突然私を訪問してくれた事を思えば、日米両国の医学界での想像を絶する苦難の中、40年前の私の教え、言葉が僅かでも力になったのかも知れない。「私が今在るのは先生のお陰です」とまで言ってくれた。渡辺私塾を創り、45年間塾の先生をしていて本当に良かったと、目頭を熱くしながらしみじみ思えた1日であった。
一ヶ月後、すがすがしい好青年が、「先生、久し振りです」と、美術館に訪ねて来てくれた。マスクをしていてすぐには解らなかったが、「空手部で応援団員だったKです」と言うのを聞いてすぐ思い出した。勉強時間が足りず、大学受験では第一志望ではなかったが、小学校の教師になるという夢を見事実現した。彼は、難関大学ではないが、現役合格し、落第する事なく卒業と同時に教員採用試験に合格した努力家で、現在4年生の担任であると言う。それにしても、教員採用試験官や面接官の見る目は驚く程確かである。彼は、小学校教師になるために生まれてきたような高潔好男子で、小学校教師は正に天職であろう。私は彼に次の言葉を贈った。「先生を見定めようとする生徒達の視線は、鋭いものだけど、K君は、今のままで大丈夫。飾ることなく真っ直ぐ生徒達と向き合えば、生徒達は熱い眼差しで迎えてくれると思うよ。児童達にかけがえのない影響を与えることが出来る素晴らしい職に就けて、本当に良かったね」。
更に驚いた事に、手足、口が不自由になったまま、停年まで校長職を全うした父の事を、彼は知っていた。ただただ子供達が好きであったために、頑として早期退職を聞き入れなかった父の事を。話を聞くと、今務めている小学校は、父が勤め上げた小学校を合併した小学校であるという。朝礼時、何を言っているのか解らないが、必死で話そうとする父を見て、涙する生徒、教師達が居たという話を聞いた事が有ったのかも知れない。彼は、父と同様、数十年後、小さな小学校の、子供が大好きな素晴らしい校長先生になるのであろうか。
久保貞次郎研究所2022年12月月報(第152回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(昨年真岡新聞社より刊行)(新年2月、渡辺淑寛著作集第10巻刊行予定)
◎12月は3点追加し計1177点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎檄文「入試に臨む芳賀の大地の少年少女へ」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月の追加作品は3点で、No1175,No1176は、浅香公紀の木版画「アユタヤ」と「スクールガーデン」である。真岡市出身で久保氏と関係の深い優れた版画家浅香氏の当美術館展示作品は全部で15点となり、久保関連作品も95点になった。
No1177は、今年度の末尾を飾る特別な展示作品で「集古十種全85冊」だ。「集古十種」とは、江戸幕府老中松平定信が退職後、谷文晁等当時一流の画家・文化人を総動員して1800年頃刊行した華麗な総木版画の一大文化財図録兼総合美術全集である。名大の美学生時、名古屋の博物館で、この壮麗な木版画本に一瞥で魅了され、苦節26年目にして幸運にも入手出来たのは25年前の事であった。そして当美術館所蔵の全85冊が、弘前藩第9代藩主津軽寧親旧蔵品である事、版木の虫食い状況の研究から日本最古の集古十種全揃い本である事が判明したのは、更に18年後の2016年の夏の事である。江戸期の集古十種は未だ研究途上であるが、当美術館では、種々の江戸異本と明治期後刷り本を多く所蔵しているので、当美術館は「集古十種」研究の最先端基地なのかも知れない。来館なさって、「集古十種」を観たいと言って頂ければご案内致します。
檄文「入試に臨む芳賀の大地の少年少女へ」
⑴21世紀初頭、点数主義は多くの欠点を孕みながらも、富、家柄、性別、情実等を見事に排除出来た、人類の確かな知恵だと知り、潔くこの受験時代を走り抜けよう、次の時代が見えるまで。
⑵合否は、たった今からの君達の努力と覚悟で決まる。
⑶多くの者が不安に駆られている今こそが最大のチャンスだと知れ。
⑷入試に向けて、生まれて初めて身も心も研ぎ澄ませ。
⑸学べる事、受験出来る事に感謝し、世界中の学ぶ事も叶わぬ多くの同胞を代表して入試に臨むのだと自覚せよ。君達は代表選手だぞ。
⑹入試の結果は神聖で崇高。如何なる結果も甘受せよ。そしてその結果を何ら恥じる事無く、今後の君達のかけがいのない糧とせよ。
⑺天は木の葉一枚の行く末も知るという。だとしたら、天は、君達のひたむきな努力をどうして見捨てようか。
⑻勝利の女神は、人知れず努力し、他者を思いやる爽やかな若者にそっと優しく忍び寄る。
⑼何をするにも勇気は必要だが、勉強の継続にも真の勇気が必要だと君達は既に知っている。だが苦渋の中で獲得したその勇気は、君の将来の不動の武器に変わると、今の今銘記せよ。
⑽絶えず苛立ち、自分の努力不足を誰かのせいにする受験生に合格者は少ない。
⑾これから入試に臨む君達が家族の中心になるのだから、笑みを絶やさず、穏やかな心で、周囲の人達に優しい言葉をかけよ。
⑿不安にならない入試など無いのだから、多少の不安、恐怖は勉強の原動力になる。それでも入試間近不安に駆られたら、私は一人で戦っているのではない、家族と、友と、まだ見ぬ同胞と共に戦っていると呪文のように繰り返せ。
⒀周囲に言われるから仕方なく勉強する、受験するなどとうそぶく者は皆無だと思うが、万が一居たら恥を知れ。
⒁大丈夫、成るように成る。胸を張り、勇気に満ちて、君の出来うる最高の答案を書いてこい。大丈夫、桜咲く春が、君達をそっと待っているよ。
久保貞次郎研究所2023年1月月報(第153回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(一昨年真岡新聞社より刊行)(本年2月末に渡辺淑寛著作集第10巻刊行予定)
◎1月は7点追加し計1184点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「新年雑感」
久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新年1月の追加作品は7点で、7点とも、昨年末展示した「集古十種」全揃い江戸本の関連作品だ。No1178は「集古十種」明治32年青木嵩山堂本全88冊の内19冊、No1179は「集古十種」明治35年東陽堂支店本全8冊、No1180は「集古十種」明治38年侑文舎本全21冊、No1181は「集古十種」明治41年国書刊行会本全4冊、No1182は「集古十種」大正4年芸艸堂本全2冊、No1183は「集古十種」昭和55年名著普及会本全4冊、No1184は、集古十種後編と言われている「古画類聚」明治25年彩色木版画本全2冊(松平康友編)である。「集古十種」は木版画本だが、「古画類聚」は肉筆写本36巻で、東京国立博物館に所蔵されている。その「古画類聚」を、松平定信の系譜である松平康友が明治25年に彩色木版画本で刊行したのがNo1184「古画類聚」だ。絵と刷りは、江戸から明治期の狩野派画家「鍬形蕙林」(1827~1909)で、この2冊で刊行は中断したようである。この「古画類聚」木版画2冊も稀覯本だが、No1177の「集古十種」全85冊全揃い江戸本には到底及ばない。
「集古十種」については、様々な江戸異本も所蔵し、明治32年青木嵩山堂本以外の後刷り本は全て揃っているので、当美術館は日本における「集古十種」研究の最先端基地であると言って過言ではないであろう。
◎エッセイ「新年雑感」
⑴過去を振り返って 宇都宮大工学部卒後、名古屋大文学部に再入学し、美学美術史生の時から、稀覯本と版画を少しずつ集め始め、卒業してすぐ真岡に戻り、渡辺私塾を開塾してもう50年になる。脇目も振らず、休日返上で必死に働き、30年前に渡辺私塾文庫を作り、25年前からは詩画集、美術評論、随筆等の拙本を出版し、既に13冊刊行した。本年2月には、真岡新聞社より著作集第10巻が刊行予定である。13年前に久保貞次郎研究所を創設し、8年前に、美学生時から夢見ていた美術館を開館出来た。芸術の大衆化の名の元、スーパーや八百屋さんのように作品を並べ立てるのは、芸術作品を身近で当たり前の対象にすると言う思想故である。更に、学生時代から決めていた事は、美術館開館の暁には、入場無料で来館者の方々に版画などを贈呈させて頂く事であった。8年目を迎えた今でも、版画と著作集の2点を来館者様に受け取って頂いている。
また、芳賀教育美術展では、久保研究所賞を創設して頂き、更に、720余名の入賞者に久保研究所から副賞を用意させて頂いて、今年で13回目となる。久保氏は天で、「良く頑張ってるね」と言って下さるだろうか。卒業生も2万人近くになり、数十年ぶりで、不意に訪問してくれる教え子も後を絶たない。 誰かがウィキペディアに私の事を掲載してくれたようで、恥ずかしさで身を潜め恐縮している。
⑵現在、未来について 休む間もなく塾生達と真っ直ぐ向き合っていたら、いつの間にか古希を迎えていた。精神はいまだ20歳台だが、肉体はさすがに年相応になったので、私塾は跡継ぎに任せ、現在は、美術館、研究所、文庫の管理及び研究、執筆活動、スポーツに集中している。何のことは無い。多忙なのは同じである。
70歳を優に超えて将来の夢など無いと思われるだろうが、まだまだ有る。大きな美術館への移転。週5日の美術館開館。分厚い美術館展示作品集出版。訳の分からぬ私の絵の画集出版。文芸新聞の発行。文芸賞復活。文芸誌再発行。90歳までこの地上に居ること。以前のような無償の講演。抽象油彩画大作の制作などだ。このうち一つでも成就出来れば上出来かも知れない。
人類の一人の夢としては、数千年数万年後、全ての人が芸術家で、戦争も疾病も飢餓も差別も暴力も貧困も貨幣も無い社会が実現する事だ。想像の遙か彼方に有るそのような社会では、一人一人が芸術家、文学者、哲学者、宗教家、科学者、道徳家であり、赤銅色の輝く肉体を持ち、天まで届く歌を歌い、博識の父母からありとあらゆる事を学び、それ故学校も消滅するだろう。希薄化した国家の数少ない役割は、国民に無尽蔵に衣食住福祉を提供し、それ故貨幣もなく、貧困も無く、平均寿命が2百歳を超え、笑顔あふれる多くの国民が、芸術活動、ボランティア活動、祭事に従事する社会だ。これが人類の本当の歴史、本史だと強く夢想する。それまでの人類史は前史に過ぎないのだ。
此処でまたフランスの詩人アルチュール・ランボーの「地獄の季節・別れ」の一節を引用しなければならない。(渡辺かなり改訳)
まだまだ前夜だ 我等は流れ入る全ての精気と情愛をこの身に受け入れよう 暁の時、我等は燃え上がる忍耐の鎧を着て、背中から血を流し光り輝く街中を走り抜けよう 次の時代、本史が見えるまで
久保貞次郎研究所2023年2月月報(第154回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第9巻贈呈(本年2月末に渡辺淑寛著作集第10巻真岡新聞社より刊行予定)
◎2月は4点追加し計1188点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「天まで届け 松茸の芳香~血潮の記憶~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
2月の追加作品は4点で、No.1185は、日本の現代版画「駒井哲郎」限定85部特装本A,B2冊(Aには銅版「海鳴り」、Bには銅版「ゴルゴダ」入り)、1993年。No.1186は、日本の現代版画「萩原英雄」限定75部特装本A、B2冊(Aには木版「標的」、Bには木版「浮遊」入り)、1992年。No.1187は日本の現代版画「長谷川潔」限定95部特装本(木版「たわむれ」、「ダンス」、「少女の首」3点入り)、1993年。5冊共玲風書房で、30年前は高額な限定本であった為、売れ行き不振と言われたが、現在は超希少本で入手困難な版画入り限定本になっている。No.1188は、モーリス・ユトリロ、「霊感の村」、パリ、1950年、2冊で、1冊は外国向け200部のうち、スーパー特装本15冊のうちの9番本である。リトグラフ多数入りで、このスーパー特装本は、果たして日本に何冊有るのであろうか。もう1冊は、外国向け200部のうちNo111番本でリトグラフ12点入り並装本だ。この2冊を手に取って鑑賞出来る所は世界でも希有であろう。
◎エッセイ「天まで届け 松茸の芳香~血潮の記憶~」
あれは、私が高校1年生の時であったから、58年前の事だ。初秋の晴れた日曜の午後、同級生3人で松茸狩りに行くことになった。地元の友人は、小さい頃から近くの森でキノコ狩りをした経験が有り、自宅から自転車で彼の家まで行き、そこから彼の道案内で、あぜ道を少し歩いて、森の中に入っていった。松の大木も有ったが雑木も多く、意外と木々の多い森であった。1時間程捜したが、色鮮やかな毒キノコは見つかっても、松茸は発見出来なかった。もう一人の友人は、「松茸全然ねいべな」と言って、不機嫌そうであったが、真岡市の街中に住む私は、うっそうとした森の中を歩くのが、何故か嬉しく心地よく、「何だかわかんねえけど、森ん中って気持ちいいな」と言って、上機嫌であった。
その当時、森林浴などと言う言葉も概念も無かったが、街中に住む私にとって、正に森林浴であったのだろう。森の樹木は、自らの傷を治したり、害虫を遠ざける為に、フィトンチッドと言う化学物質を出していると言われ、その物質が人間にも様々な効能が有るらしい。だが、今思い返すに、あの心の奥から湧き出る言い様の無い高揚感は、森林浴だけでは説明がつかない。我々人類は、遙か遠い古代の時、豊かな森の中で長期間楽しくし生活し、その記憶が、我等の赤き血潮のなかに残存し、森に戻ると、その記憶がふつふつと蘇るのではないのだろうか。更に、この喜びは、群れ跳ねる魚群を見た時の高揚感と、何故か似ている。遙か先史の「血潮の記憶」の蘇生であり復権なのか。
更に2時間程探索したが松茸は見つからなかった。諦めて帰ろうとした瞬間、私は松の大木の向こう側に、20センチ程の傘の開いた白い大きなキノコを見つけた。地元の友人は、「それ、オオシロカラカサタケとか言う毒キノコかもしんねえから、食べねえ方がええど」と言ったが、私は、「おけらじゃかっこわりから、一応これ持ってくかん」と言って、黒いナップサックに入れた。地元の友人は、「松茸取れねえで悪かったな」言ったが、「一個取ったっぺな」と言ってあげたので、3人とも笑いながら、彼の家まで戻った。
自転車で家路に向かう時、毒キノコを背中に背負うのも気が引けたので、ナップサックを左ハンドルに掛けてペダルをこいだ。ナップサックが、何度か自転車の前輪に絡まったが気にも掛けず家に向かった。途中、化学薬品のようなツンとした匂いを感じたが、気に留めなかった。家について自転車を降りた途端、お隣の駄菓子屋のおじちゃんが、走って来て、「としぼちゃん、松茸一杯取ってきたんだね。ものすごい松茸の香りだよ」と言ってくれた。店の奥で店番をしていたおじちゃんの所まで、松茸の香りが広がっていたのだ。そうだ、このキノコは、毒キノコではなく、正真正銘松茸だったのだ。ナップサックを開けて匂いを嗅いでみた。脳を貫ぬいて卒倒しそうなツアーンとする激しい香りであった。騒ぎを聞きつけて父も母も外に出て来て、「うわー、松茸の匂いだ。どれ、見せてみろ」と父が言った。「これだけ匂いの強い松茸は珍しいね」と母が言った。松茸は、かなり砕けてはいたが、その日の夕食は、豊穣な香りの松茸ご飯と松茸のお吸い物であったのは言うまでも無い。
父も母も、お隣のおじちゃんもお空に帰って、もう居ない。松茸をナップサックに入れ、前輪に絡めれば、松茸の香りは天まで届くのだろうか。いや、きっと届く。天まで届け、松茸の芳香。
久保貞次郎研究所2023年3月月報(第155回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月末日に真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎3月は6点追加し計1194点展示(恩地孝四郎388点 久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎真岡市田町まちかど美術館で開催中の渡辺美術館コレクション「竹下夢二展」について(3月9日~4月23日)
◎エッセイ「子供の笑顔は宇宙のほほえみ」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
真岡市田町まちかど美術館で、当美術館所蔵の夢二作品19点を展示した「竹下夢二展」が開催されている(3月9日~4月23日)。夢二肉筆挿絵原画「ほら男爵の旅」は必見かも知れない。認定美術館を含めた真岡市4美術館は全て入館無料であり、真岡市が誇る独自の素晴らしい市政の一環であって、後世必ずや高く評価され、口々に語り継がれる文化芸術政策であろう。
3月の追加作品は6点ともラウル・デュフィ関連で、No1189は、デュフィ限定233部のうちスーパー特装12部本「強いられたヴァカンス」(1956年、パリ)だ。木版画が多数入った超希少本で、世界で12冊しかなく、当美術館以外、日本で所蔵している所は果たして有るのだろうか。No1190~No1194はデュフィのリトグラフポスターで、「ロンドン テートギャラリー」、「モネのアトリエ」、「ニースからの絵」、「ニースの遊歩道」、「エッフェル塔」の5点である。デュフィは、マティス、ルオー、ヴラマンク、ドラン等のフォーヴィズム(野獣派)の画家に分類されているが、実際は水彩画のような優しい線と透き通る色彩で独自の世界を築き、「色彩の魔術師」と呼ばれている。フォーヴィズムを「写実主義と離れ、目に映る色彩ではなく、心に映る色彩を表現する流派」と定義すれば、デュフィは、正にフォーヴィズムの旗頭の一人である。
◎エッセイ「子供の笑顔は宇宙のほほえみ」
もう15年前になるのだろうか。孫の一人が小学校に入学するので、二人で近くのスーパーに文具を買いに出かけた時の事である。孫と私は、世帯が別で、お互いにまだ遠慮が有ったが、私は孫と一緒に居るだけでただ嬉しかった。買い物が終わってレジの方に向かった時、孫は途中で何かをじっと見ていた。それはおにぎり大の薄い円盤型の「ペロペロキャンディ」だった。孫は私の方を振り向こうとせず、ただ食い入るように見つめていた。もし振り向けば「じっちゃん、これ買って」と言う事になると分かっていたのだろう、小さい子ながら礼節を知る子であった。私は孫に「会計済ませるから、レジの向こうで待っててね」と言って、そのキャンディを気づかれないようにそっと買い物籠の一番下に入れた。
会計が自分の番になった時、私は、そのペロペロキャンディを誇らしく大きくかざして孫に見せた。じっちゃんが自分に、喉から手が出るほど欲しい夢のペロペロキャンディを買ってくれたのだと理解した時、孫はこれ以上無い喜びの笑顔を見せた。「これ以上無い喜びの笑顔」などと言うありきたりの表現では到底足りない。そう、「後光が差すような黄金色の笑顔」がより的確か。いや、それでも足りない。その透き通るような喜びの笑顔は、休み無く働き心身とも疲労困憊の私の心労を、清らな聖水で一気に洗い流してくれる天の恩寵だ。宇宙のエネルギーは、純真な子等の心を通して、一番流れ入ると何かの本で読んだことが有るが、正に本当だ。文具という入学祝いに対し、孫は、虚飾のかけらも無い、純化された無私の笑顔で、私に、何万倍もの「お返し」をしてくれた。
あの純真無垢な喜びそのものの笑顔は、15年経っても、まだ私の心奥に有り、古希をとうに超えた私の生きる力の一つとなっている。孫の笑顔を通して私に与えられた、欠ける事も消え入る事も無い宇宙のエネルギーを、今度は私が多くの人に、笑顔で万分の一でもお返しする番だ。お年寄りの笑顔など気持ちが悪いだけだとおっしゃる方もおられようが、宇宙の光を僅かでも放っている老人の優しい笑顔もそれ程悪く無い。万物の中で、宇宙のエネルギーが一番通りやすいのは、我々人類種であり、その通り道は笑顔であり、それ故我々は笑みを絶やしてはならない。宮沢賢治が「雨にも負けず」の中で、「いつもしずかにわらっている・・・そういうものにわたしはなりたい」と書いたのは、この洞察に他ならない。
孫の至上の笑顔を思い出す度に、私は、「子供の笑顔は宇宙のほほえみ」と復唱している。
久保貞次郎研究所2023年4月月報(第156回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月末に真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎4月は3点追加し計1197点展示(恩地孝四郎388点 久保貞次郎関連95点) 土曜日以外は2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「美味しそうに食べている幼子に、少し頂戴と言わないで」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
4月は3点追加し計1197点の展示となった。No1195は、フランス、マーグ社版画入り「デリエール・ル・ミロワール」誌44冊(1947年~1982年)である。既にNo1149で同誌シャガール版画入り特集号を展示しているので、計45冊の展示となった。20冊前後の展示で美術展を開いた有名美術館も有るほどで、版画入り希少本45冊を手に取って鑑賞出来る所は希有であろう。2階に展示しているので、ミロワール誌を観たいと言って頂ければ案内致します。
No1196は、石井弥一郎作油彩12号「網代風景」だ。1956年個展出品作の貴重な作品である。No1197は、益子町藍染工房第八代当主日下田博藍染額「山水その3」で、日下田博藍染額は17点目の展示作品である。「山水」、「山水図」は4点目だが、勿論4点共異なる作品だ。日下田博藍染画独特の丸みの有る山々を観ると不思議と心が和む。
真岡新聞3月31日号に拙書著作集第10巻刊行の記事が掲載されたので、4月1日は来館者様が多く、全員に第10巻を進呈させて頂いた。今後も、この月報内でエッセイなどを掲載させて頂き、2,3年後に第11巻を刊行する予定である。
◎エッセイ「美味しそうに食べている幼子(おさなご)に、少し頂戴と言わないで」
妻と私と4歳になる孫娘とで、車で買い物に行った10数年前の出来事である。孫娘は家から持ってきたパンを一心不乱に美味しそうに食べていた。いつになく無口で、とても美味しそうに食べているので、私は、浅はかにもうっかり、「少し頂戴」と言ってしまった。友人や家族であったら、「やだ」の一言で済んだのだが、日頃世話になっている祖父からのお願いだから、子供ながらに無視出来なかったのだろう。一瞬、顔を赤らめ、身をよじりながら、親指の爪の先に小さな小さな米粒大のパンの切れ端を乗せて、「じっちゃん、はい」と差し出した。私は、冗談のつもりだったが、はしたない事を言ったものだと後悔しながらも、親指の爪に乗ったパンの余りの小ささに、思わず吹き出し、私と妻は子供のように心の底から大笑いをした。孫娘は、事情が分からず、最初はぽかんとしていたが、祖父母の爆笑と、爪の先にそっと乗る小さなパンの滑稽さに気付き、3人で心を一つにして心ゆくまで笑った。
その日は、思い出に残る楽しい1日であったが、寝床に入ってよくよく思い返してしてみると、私は孫娘にひどい事を言ったのだと悟った。至福の中で、無心で美味しいパンを食べている時、私の「少し頂戴」という言葉は、「悪魔のささやき」どころか焼け火箸で胸をえぐる言葉であったのだ。正に文字通り、「身を切る思い」で爪の先に小さなパンを載せたのだろう。爪の先のあの小さなパンは、孫娘の心の血肉であった。顔を赤らめ、身をよじりながらパンを小さく刻んだのも当然だ。あの小さな小さなパンの切れ端は、孫娘の針のような痛みの化身だったのだ。
数日後孫娘と再会した時、私は彼女に心より詫びた。だが彼女は、「じっちゃん、何で謝ってるの」と言って、全く気にしてはいなかった。4歳の女の子は、そのような小さな傷を全て引き受けて、心の糧として成長していくのかも知れない。言葉とは不思議なものだ。悪態をついた方が傷ついて、悪態をつかれた方は成長の糧としている。彼女は、今度同じ場面に直面した時、「分かった、あげるよ、だけど私のパンは小さいよ」と言って爪の先に小さなパンを乗せ、大きな笑いを取るかも知れない。
10数年経って今思うに、4歳の孫は女性であり、女性は子を宿し、人類を永続させ、進化させねばならない。祖父の戯れ言(ざれごと)などに傷ついてなどいられないのだ。女性達は、男性が持たないしなやかな感性と、本能的危機回避能力と、全てを優しく包む母性によって、営々と続いて来た人類の悲惨な戦いの歴史に終止符をうたねばならない。血丘を知丘に変えねばならない。地球は血球から知球に変わらねばならない。
4歳の孫娘の中に、女性の計り知れない可能性を垣間見たとしても、私の「少し頂戴」という心無い言葉は、心の奥の方で、後悔の念に包まれて時々疼くことが有る。だから読者の皆様、美味しそうに食べている幼子に「少し頂戴」とは、どうぞ言わないで下さいね。
久保貞次郎研究所2023年5月月報(第157回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月末に真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎5月は12点追加し計1209点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎久保記念美術品展示館、田町まちかど美術館で池田満寿夫展を開催中
◎数学未解決問題「コラッツ予想」について 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
5月の追加作品は12点で計1209点の展示となった。No1198からNo1207までの10点は、田中正秋シルクスクリーン版画で日本の祭りシリーズである。既にNo362で「博多山笠」、No662で「栃木子供強飯式」を展示しているので、田中正秋シルクスクリーン版画は計12点の展示となった。有名な日本の祭りシリーズ12点を間近に鑑賞出来る所も多くないので来館なさって頂ければ幸いである。No1208は、松本節子日本画「猫」6号で、愛らしい猫ちゃんにほだされて20年前入手した作品だ。No1209は、清希卓油彩画「耶馬渓」8号で、清希油彩画5点目の展示作品である。5点とも油彩厚塗り重厚作品で、これぞ油彩画と思わせるお気に入りの5作品である。
久保記念美術品展示館で、第36回企画展「久保貞次郎ゆかりの天才アーティスト池田満寿夫展」(4月20日~6月19日)、田町まちかど美術館で、第26回企画展「池田満寿夫とデモクラートの仲間たち」展(4月26日~6月25日)が開催されている。入場無料であり、久保氏が在住した真岡市独自の素晴らしい文化芸術政策である。一度訪館なさり、久保氏が言う如く、「芸術を生活の中に浸透」させて頂ければ幸甚である。なお、田町まちかど美術館には、当美術館所蔵の利根川光人油彩6号「ジェスチャー」が出品されている。
◎懸賞金付き数学未解決問題「コラッツ予想」について
ドイツの数学者ローター・コラッツ(1910~1990)は、1937年、現在も未解決で世界中の数学者の心を躍らせ悩ませもしている「コラッツ予想」を提起した。「コラッツ予想」は、小学生にも理解できる内容で、全ての自然数は、偶数であれば2で割り、奇数であれば3倍して1を足すと、どんな自然数でも最後は1になるという予想である。例えば10であれば、10-5-16-8-4-2-1、例えば11であれば、11-34-17-52-26-13-40-20-10-5-16-8-4-2-1、例えば12であれば、12-6-3-10-5-16-8-4-2-1と最後は1になる。(1の後は4-2-1と繰り返すだけ)
この予想が偽、誤りであることを示すには反例を一つ挙げさえすれば良いのだが、現在スーパーコンピューターを使って2の68乗個「2垓(がい)9514京(けい)7905兆1793億5282万5856個」まではコラッツ予想は正しい事が示されている。今度は逆に、全ての自然数でコラッツ予想が正しい事を数学的に証明すれば良いのだが、これが未だ未解決なのだ。全ての自然数で最後が何故1になるのか、未だ証明出来きていない。2021年、東京の情報通信企業がコラッツ予想の真偽を数学的に証明した者に1億2千万円の懸賞金を与えると発表し話題となった。
以下、コラッツ予想に対して、哲学徒としての私の感想、予感を、厚顔無恥にも述べさせて頂く。第1点。今後どれ程数を増やしても、やはりどんな自然数に対して計算しても最後は1となる。これは哲学徒としての確かな予感である。人間の精神を遙かに凌駕する「宇宙の創造神」、或いはアインシュタインの言う「宇宙精神」は、人間が数字を手段に、宇宙を解析しようとすると綺麗な形で答えを用意しているのだ。これは、0から2分のπまでのsinやcosの面積が1であったり、サイクロイドの面積が円3個分であったり、ローズカーブ(四葉曲線)の面積が円の半分であったりする事と類似している。この操作をすると、一番綺麗な1になるように「宇宙精神」は用意したのだと強く予感する。
第2点。人類が「コラッツ予想」を証明することは永遠に出来ないと強くは無いが予感する。「宇宙精神」は、お茶目な所も有って、最初から証明出来ないように自然数を作ったのだろう。人間の指が両手で10本有って、人間に10進法を思いつかせたたが、何故指が10本有るかは説明出来ない。光は粒子と波の両方の性質を持つが、人類には理解困難である。粒子は飛んで来るボールだが、地震の時地面が飛んで来る訳では無い。振動してエネルギーを伝えるだけだ。だが人類は、光の2重性を、そういうものして受け入れれば良いのである。円柱を真上から見れば円で、真横から見れば長方形だが、どちらも正しい。例えとして、人類には円柱を立体的に見る力が無いと考えれば良いだけだ。
「コラッツ予想」は、全ての自然数を何れだけ調べても1になるが、人類には証明出来ないものだと受け入れれば良いのだろう。そうは言っても、人類は懸賞金など何処吹く風、「コラッツ予想」の証明に営々と挑み続けるに違いない。
そうそう、この二つの予感を、私は、偉そうに、渡辺予感と密かに呼ぼう。
久保貞次郎研究所2023年6月月報(第158回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月に真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎6月は2点追加し計1211点展示(恩地孝四郎388点、久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎久保記念美術品展示館で「富張広司展」」、田町まちかど美術館で「木版画に親しむ」開催中
◎渡辺美術館開設9年目を迎えて 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
6月の追加作品は2点で計1211点の展示となった。No1210は「ラウル・デュフィ水彩・ガッシュ・パステルカタログレゾネ」全2冊、1981年、パリ。No1211は、「ラウル・デュフィ油彩カタログレゾネ」全5冊、1972~1985年、パリ、の2点である。カタログレゾネとは、全作品集の事で、研究者には必携の書であり、発行部数も少なく欧米では驚く程高額だ。特に日本の大学の研究者が洋書専門店に依頼して欧米から取り寄せる場合は一層高額になり、レゾネ本に偶然挟んであった領収書を見ると、10万円単位は普通で、中には百万円を超える場合も有った。日本に入ってきたそれらの高額レゾネ本は、研究室の本棚で数十年過ぎると廃棄本となり、古書店に払い下げになる。渡辺私塾文庫では、日本中から送られてくる古書目録を精査して、それらの希少レゾネ廃棄本をめざとく発見し、半世紀かけて廉価で蒐集してきた。今回のラウル・デュフィレゾネ本2セットもそのうちの2点である。「渡辺私塾文庫」HP「⑹洋書」の末尾に日本画家のレゾネ本も含めて140点掲載しているので、研究者の方、御興味の有る方は、ご連絡頂ければ当美術館で閲覧可能です。大震災で散逸したレゾネ本も有るが、140点のレゾネ本所蔵は日本でも屈指であるかも知れない。
真岡市久保記念美術品展示館で、「新収蔵記念 富張広司展」(6月22日~8月7日)、田町まちかど美術館で「第27回常設企画展 木版画に親しむ」(前期6月28日~8月27日、後期8月30日~10月29日)が開催されている。入場無料で、パンフレット等も自由に頂け、真岡市の美術政策、文化芸術市政は驚嘆に値する。真岡市並びに関係者の皆様に惜しみない賞賛の意を送りたい。
◎渡辺美術館開設9年目を迎えて
2015年5月24日、貧弱ながらも念願の美術館を開設して本年5月で8年が経ち、9年目を迎える事が出来た。半世紀前の美学生であった時から心に秘めていた入場無料及び版画や美術関係書の来館者様へのプレゼントも、8年間継続中である。粗末な建物、狭い場所に1200点余も乱雑に展示するスタイルは、美術品を冒涜していると口走る美術関係来館者も僅かに居た。しかしこのスーパーマーケットのような乱雑な展示方法は、最初から意図したものである。
思い起こせば1974年は、ルーブル美術館蔵レオナルド・ダビンチ作「モナリザ」が日本に初来日した年だ。学生にとって安くない入場料を支払い、長時間待たされ、照明不足で薄暗い中、高い所に鎮座したモナリザの薄ら笑いのようなものしか見えなかったので、止まって背伸びをして良く見ようとした途端、「止まらないで!」と警備員にどやされた。「歩きながらの美術鑑賞など無いぞ」、「名品の名のもと、人間を、大衆を冒涜しているぞ」と言い返す衝動を抑えるのに必死だった。フェルメール作品が来日した時も、同様に「止まらないで」と言われ、日本では状況はそれ程変わっていない。日本人の従順さにつけ込む、このような来館者を小馬鹿にした展示スタイルは、美術の分野で日本を一層の後進国に落とし込め、芸術と大衆の距離を一層遠ざけるだけだという事を、美術関係者は心の奥底に銘記すべきである。
その時から、美術品は、薄暗い堅固な建物の高い所に偉そうに飾るのではなく、来館者と同じ目線で間近に鑑賞出来るよう、スーパーの野菜コーナーのように展示しようと決意した。久保貞次郎氏の小コレクター運動の思想、「一人一人が、オリジナル作品を3点以上持ち、芸術を生活の中に浸透させる」という考えも、私の決意を後押ししたのだろう。
さて、49年前の嫌な思い出は此処までにして、渡辺美術館の今後の夢を語りたい。一つの夢は、点数だけなら世界屈指の恩地幸四郎作品388点を、小さな恩地美術館として近隣に独立させる事。これは経済的問題で今は容易ではない。二つ目は、久保氏が活躍した真岡市で、子供を含めたプロ、アマ競合の、豪華賞品付き大きな美術展を開く事。勿論審査委員は子供だけだ。これも経済的問題、事務的問題で今は難しい。三つ目は、現在土曜日3時間のみの開館時間を、週6回1日7時間の開館にする事。これも私の体力的問題、時間的問題で困難か。四番目は、分厚い当美術館展示作品集を作る事。これが一番実現可能なのだが、1211点を写真に撮り製本するのは専門家に任せるしかなく、費用も時間もかかるであろう。久保氏の万分の一の財力で、更に年齢を考慮すれば、何れも一見不可能に思えるが、少し待って欲しい。二つの国立大を卒業し、零から私塾を始め、たった一人で40年かけて粗末ながらも1200点余を展示する美術館を創設したのは、誰あろう、私ではなかったか。そう、今は、地を這うように密かに半歩ずつでも前進する時期なのだ。夢は、いつまでも持ち続けるから夢であり、安易に棄てられないから夢なのだ。
久保貞次郎研究所2023年7月月報(第159回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月に真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎7月は恩地孝四郎油彩画代表作「三人の女性」50号1点のみ追加し計1212点展示(恩地孝四郎389点 久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎エッセイ「造花考~美術館に薔薇の造花を飾って~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月は1点のみの追加だが、私の誕生日に素晴らしい作品を展示する事が出来た。恩地孝四郎油彩画代表作「三人の女性」で、恩地油彩画最大の50号大作である。1917年第5回二科展出品作で、時代より遙か先を疾走していたためか、落選の憂き目に会った恩地26歳の話題作だ。1988年フジイ画廊恩地孝四郎油絵展図録No1掲載作品である。近年、恩地研究が進み、恩地油彩画二大代表作は、この「三人の女性」と、宇都宮市立美術館所蔵「自画像」(1919年作10号)と言われている。本来、恩地芸術の本質は、生命の輝き、存在の喜びの表現であり、それ故恩地は、生命の源である海を、生命を繋ぐ女体を多く描いている。その延長上で、恩地は、生命の源、生命の尊厳、存在の喜びを持つ黄金色の三女体を描いたのだ。当時そのような理解、洞察が無かったが故に、ほとんどの審査員には、「三人の女性」は、理解不能で毒々しい奇異な作品に見えたのだろう。
この50号代表作は、本来であれば、公立の大美術館に所蔵される作品だが、偶然が重なって、不思議にも当美術館でお預かりすることになった。大美術館の作品購入時期は、予算の付いた4月、5月が多いので、前の所有者は、6月になった今、小回りの効く東京神田の有名古書店に販売を委託したのかも知れない。6月28日、私は、この「三人の女性」の現在の所有者をインターネットで調べていた所、先の古書店のホームページで、これ程の有名作品が、古書店で売られていると知って仰天した。聞いたところ、四日前にホームページにアップしたばかりだと言う。恩地作品388点を展示し、展示数だけなら世界有数の恩地作品展示美術館である当美術館に、天は、粋な計らいで、所蔵出来るように取り計らってくれたのか。
これで当美術館は、二つの恩地目玉作品を展示する事になった。一つは、勿論、アルス日本児童文庫表紙絵恩地肉筆原画55点である。
◎エッセイ「造花考~美術館に薔薇の造花を飾って~」
近くのスーパーの買い物の行き帰り、スーパー内に有る百円ショップの店先の薔薇の造花が余りに鮮やかで、幾度となく目を奪われた。以前は、一目で造花だと解る粗雑感が有ったが、今は違う。特に色彩が年々洗練され、多様な色合いを持ち、遠目では造花だと解らない程だ。大きく言えば、人類の科学技術の発達の恩恵であり、小さく言えば、ポリエステル等の加工・着色技術の進歩の賜なのだろう。
或る日、私の視線を奪うその魅力に抗しきれず、思わず10点程買ってしまった。その10点の行き先は、勿論、小汚いという悪評の当美術館である。その10点を美術館の一隅に飾ると、その場所が明るく光り輝いて見える。私の心に火が付いた。もうどうにも止まらない。その日以来、毎日のように市内の百円ショップ4店舗を回りに回って、いつの間にか300点を優に超え、美術館は、薔薇の造花園なのかお花畑なのか解らないようになった。だがそれはそれで良い。入場無料、土曜日3時間のみの開館、来館者様に版画や本のプレゼントなど、当美術館はユニークさが特徴なのだから、もう一つユニークさが増えたと思えば良いだけだ。
さて此処で留意すべき事が2点有る。1点目は、薔薇の造花と言っても百円ショップの薔薇の造花に限っての話だ。アートフラワーと言う、もっと精妙で高価な造花芸術の存在も承知している。2点目は、今此処で造花が生花を凌駕しつつあるなどと言う気は毛頭無い。季節の度に再生し、脳の奥まで忍び寄る香りに満ちた薔薇の生花と、無臭の造花を比べるのは酷というもので比較にもならない。だが造花にも多くの長所が有る。手入れが楽で長持ちで、コストも安く生活の中に取り入れ易く、茎にワイヤーが入っていて形状が可変で、実際に存在しない色や形の薔薇まで創れる。
造花の歴史は意外と古く、紀元前2千7百年頃、エーゲ文明の王墓に、青銅の造花が添えられていたという説も有る。日本では、10世紀初頭の古今和歌集445番に、「花の木にあらざらめども咲きにけり」と紹介された、木を削った「削り花」という造花が有り、11世紀初頭の紫式部日記第二章15では「心葉」という名の造花が記されている。お葬式に、沢山の生花や造花を飾るのは、巡る季節で再生し花を咲かせる花々が、再生復活生まれ変わりの象徴であるからなのだろうか。
先日スーパーを出た所で、「あら、薔薇、綺麗」と、うら若い女性に声をかけられ、「良し!」思ったのだが、何のことはない、造花を生花と見間違えて思わず口にしただけであった。やはり最近の造花は、百均の薔薇でも侮れない。3百点の造花は、版画1点の価格で購入出来、その3百点で、小汚い美術館が小綺麗とは言えないまでも不思議な美術館に生まれ変わる事が出来た。
是非当美術館に来館なさり、新収蔵の恩地油彩画大作と、小さく顔を出している薔薇の造花達に優しい眼差しを送って頂ければ幸いである。
久保貞次郎研究所2023年8月月報(第160回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後Ⅰ時から4時まで開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎8月は2点追加し1214点展示(恩地孝四郎389点 久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎久保記念美術品展示館、真岡まちかど美術館の今後の展覧会案内 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月の追加作品は2点で、No1213は、実力派日本画家五十嵐晴徳の「蘭」10号である。それ程高名ではないが、これぞ日本画と呼べる清麗な植物画だ。五十嵐氏は1937年新潟県生まれの日展審査員で、高齢でありながら美しい日本画を描き続けている正統派画家である。
No1214は、私のお気に入りの画家、神崎温順の型絵染「平泉」だ。神崎氏は四国で貧困の中消息不明になった型絵染作家で、同じく放浪の俳人種田山頭火の句を型絵染にする事で少しだけ知られている。自由律俳句の巨星山頭火(さんとうか、1882~1940)が、岩手県平泉、中尊寺金色堂を訪れた時、金色堂が補修直後であったためか「余りに現代色が光っている」「何だか不快感を感じて」と日記に記し、次の句を残した。「ここまでを来し水飲んで去る」。神崎温順はこの句に、金色堂を描かず、重厚な石造りの水場を描いた。放浪の俳人と画家の思いは一つだったのだろう。
今月はもう1点美術館に展示した作品がある。恩地孝四郎木版代表作「萩原朔太郎像」だ。この作品はNo176で既に展示しているので新たな展示作品とはならない。恩地「萩原朔太郎像」は三種の刷りが有って、1943年恩地自刷り2部、その後米国の蒐集家に請われ恩地自ら数部制作。1949年恩地の弟子関野準一郎により、同じ版木で20部制作。1955年恩地他界の年、恩地孝四郎遺作頒布会で、刷りの名手平井孝一により同じ版木で20部制作。恩地作品は当時日本では一顧だにされず、それ故恩地は2部しか刷らなかったのだが、朔太郎の苦渋と気概を掘り刻み重厚に表現した「萩原朔太郎像」は、その芸術性の高さ故海外で高評価で、関野刷り、平井刷り計40部が刷り増しされた。その多くは他の作品とともに、プラグマティズム哲学に裏打ちされ、作家名でなく作品の質で判断する米国コレクターによって、海を渡たり、日本で大きな「恩地孝四郎展」を開催する時、恩地傑作は、ホノルル美術館、ボストン美術館、シカゴ美術館、大英博物館等からお借りしている状況である。久保貞次郎氏も、恩地芸術を高評価しなかった事で、1975年形象社、恩地孝四郎版画集「恩地孝四郎を思う」の中、「深い悔恨と自己軽侮の念にかられるばかり」と書いているが、世の多くの美術評論家の中では、久保氏は、恩地芸術に畏敬の念を抱いていた数少ない識者の一人であった。前述の「恩地孝四郎版画集」出版時、海外の恩地作品の写真撮影だけで法外な金額を要求され資金難に陥ったとき、久保氏が救いの手を差し伸べた事は余り知られていない。
当美術館展示「萩原朔太郎像」は2点とも平井刷りであるが、「萩原朔太郎像」同作品2点展示は、無意味と希有が隣り合わせで、かえって面白いと思っている。
◎久保記念美術品展示館、真岡まちかど美術館の今後の展覧会案内
真岡市荒町久保記念美術品展示館では、9月21日から「芳賀教育美術展」関連企画展として、パート1で10月2日まで「歴代の知事賞展」が開催され、「芳賀教育美術展」最高賞である知事賞の歴代受賞作品が展示される。10月5日から23日までのパート2は、久保氏が世界各地から蒐集した児童画の展覧会だ。この世界児童画展は真岡市でしか見られない必見の展覧会である。パート3は、10月26日から11月26日まで、ワークショップフェスタ「描こう!つくろう!みんなの久保アトリエ」の応募作品を展示する予定だ。
続いて11月30日から12月11日は、栃木県立美術館収蔵作品展「挿絵本の世界へようこそ~19世紀フランス・イギリスの美しい書物~」が開催される。更に12月14日以降、第39回企画展として「くらし・いとなみ」展が予定されている。
真岡市田町まちかど美術館では、第27回常設企画展「木版画に親しむ、後期、浅香公紀展」(8月30日から10月29日まで)が開催される。浅香氏は、全国的にはそれ程高名でないが、作品を見ればすぐ浅香木版画と解る版画家で、極めて芸術性の高い作品を生み出した画家であった。続いて11月1日から2024年1月8日まで、第28回常設企画展として「書物をめぐるアート展」が開催される。当美術館の所蔵作品、「恩地孝四郎作アルス日本児童文庫表紙絵原画」6点も出品予定だ。その後は、認定まちかど美術館特別展として、「「趣味の美術館コレクション展」、「渡辺美術館コレクション日本画名品展」が予定されている。
思い起こせば、人類の進化の指標の一つは、「生活の中に芸術を何れだけ浸透させるかだ」と言ったのは、久保氏であり、「一人一人が芸術作品を3点以上持ち、芸術を身近なものとする」という「小コレクター運動」を提唱したのも久保氏であり、その発祥の地は他ならぬこの真岡であった。そして真岡市当局は、久保氏の思いを真摯に受けとめ、久保氏の思想を見事に発展させている。この真岡市の芸術政策は賞賛に値し、後世高く評価されるであろう。具体的には、認定まちかど美術館を含めて4美術館が全て入場無料であり、久保記念美術品展示館では、38回もの企画展が開催され、まちかど美術館でも27回の常設企画展が催された。更に、久保氏の高価な著書が希望者に無料配布されたり、久保氏に関わる座談会も市主導で開催された。また久保氏と関連の深い「芳賀教育美術展」は今年で37年目を迎え、関連企画展も久保記念美術品展示館で何回となく開催され、真岡市は、イチゴの町、SLの町に加えて、胸を張って「美術の町」と声高に言って良いであろう。
久保貞次郎研究所2023年9月月報(第161回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎9月は3点追加し計1217点展示(恩地孝四郎389点 久保貞次郎関連95点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館
◎数学を学ぶ高校生へ、「数学公式は証明してから使おう~例えばヘロンの公式、ブラーマグプタの公式~そして玄奘三蔵法師」
久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
9月の追加作品は3点で、3点とも福井良之助の作品である。No1215は、福井良之助デッサン22点(1982年、1983年作)。No1216は、福井良之助肉筆画帳「投影」(7図掲載)。No1217は、デッサン画「朝顔」(3号)だ。福井良之助(1923~1986)は、浮ついた人気作家でない本物の実力派の洋画家で、コレクターであれば、詩情溢れた淡い色彩の油彩画を、生涯1点は所蔵したいと密かに思っている憧れの画家である。当美術館では、秀作油彩画は高額で未収蔵だが、20数年前に廉価で入手したこの肉筆画帳やデッサン画でも、福井良之助特有の、静寂な詩情は充分感じられる。
残暑厳しい灼熱の9月に入って、遠来の来館者様が多くなり喜んでいる。東京都、茨城県、埼玉県、群馬県、大田原市、高根沢町、宇都宮市、芳賀町、益子町などからで、美術関係者もいらっしゃて、最初から当美術館目当ての方もおられるようだ。7月から美術作品の間に飾りだした造花も5百本を超え、当美術館の乱雑さ、粗雑さ、小汚さを上手く覆い隠してくれている。さすがに、「造花を観に来ました」という来館者は皆無なので、正直ほっとしている。
◎数学を学ぶ高校生へ、「数学公式は証明してから使おう~例えばヘロンの公式、ブラーマグプタの公式~そして玄奘三蔵法師」
3辺の長さが判っている三角形の面積を求める時、余弦定理でCosAを求め、それをSinAにして、最後にS=bcSinA÷2で求めるので、手数が長い。しかしヘロンの公式S=ルートs(s-a)(s-b)(s-c)を使えばすぐ求まる(ただしs=(a+b+c)÷2)。だが長年答案を採点していて、前者の方がヘロンの公式を使った解法より正答率が高い。理由は簡単だ。ヘロンの公式をうろ覚えにしているからだ。多いミスは、ルートの前に2分の1をつけてしまうミス。s=(a+b+c)÷2の÷2が抜け落ちるミス。更にルートの中の最初のsをつけ忘れるミスなどだが、これらのミスを避ける方法がある。それはヘロンの公式を自分で証明する事だ。一見難しそうに見えるがたいしたことはない。手数が長いと言った前者の解法をa,b,cのまま計算すれば良いだけである。1-CosAの2乗を先に因数分解してから余弦定理を代入すると少し楽かも知れない。2,3度自分で証明すれば、2,3年は正確に覚えているものだ。
次に円に内接する四角形ABCDの面積でブラーマグプタの公式の話だ。角B+角D=180度なので、余弦定理よりACの二乗を二通りで表してCosBを求め、SinBにしてS=abSinB÷2+cdSinD÷2=ルート(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)(ただしs=(a+b+c+d)÷2)の公式が得られる。ヘロンの公式と同様、1-CosAの2乗を因数分解してから計算すると楽である。ルートの中の因数分解が面倒に見えるがたいした事はない。sからa,b,c,dをそれぞれ引くだけだからヘロンの公式より覚えやすいし間違いが少ない。そしてdが零の時がヘロンの公式になっていて、ヘロンの公式はブラーマグプタの公式に内包されていると言って良い。論述式でブラーマグプタの公式を使う場合減点覚悟だが、検算にも利用出来、短答式では、即答可能で時間の節約にもなってかなり有利になる。重要な事は、この公式を自分で2,3度証明しておく事だ。そうすれば論述式でも容易に対応出来る。2019年大学入試に限っても、a,b,c,dのまま証明させる問題が京都府立大、4辺が3,4,5,6で面積を求める問題が産業医科大、4辺が2,3,1,2の場合が東北学院大など意外と出題率も高い。
ヘロンは、当時古代ローマの属州であったエジプトのアレクサンドリア生まれのギリシャ人で、西暦10年生まれ70年頃没と言われているが詳細は不明である。現在の自販機の原型を発明したり、風力オルガンを作ったり、簡単な蒸気タービン、蒸気による自動扉を作ったりと、希代の発明家でもあったようだ。
ブラーマグプタ(598~665?)は、インド西部ピッラマーナ生まれのインド人で、数学者、天文学者として著名であり、628年零の概念を確立し、ウッジャイン天文台台長を長年勤めた。
此処で突然、玄奘(げんじょう)三蔵法師(602~664)(以下玄奘)が登場する。孫悟空、猪八戒、沙悟浄を引き連れたインドへの取経の旅(629~645)「西遊記」で有名な三蔵法師だ。取経の旅から帰った翌年の646年、玄奘は「大唐西遊記」全12巻を著したが、第11巻で、ブラーマグプタの住むウッジャインを訪れたと記されている。此処からは推測だが、遙か唐の国からはるばる来訪された高名な法師に対して、ウッジャインの町の著名な知識人文化人であるブラーマグプタが、玄奘一行を歓待したのではと考えても不思議では無い。ブラーマグプタは玄奘に、「円に内接する四角形の面積は・・・」と長々説明したのだろうか。それを聞いていた孫悟空は「何を訳の分かんない事を言ってんだこの野郎」と言って、如意棒でブラーマグプタの頭をポカリとやったのだろうか。妄想が妄想を呼んで興味が尽きない。話を戻そう。
数学を学ぶ高校生に告ぐ。数学を学ぶという事は、ただ公式を丸暗記して数字を当てはめ答えを出すという無味簡素な作業では決してない。自分で公式を喜々として証明し、公式の背後に隠された意味、本質、歴史を学ぶ楽しい作業だという事を、数学を学ぶ全ての高校生に是非知って欲しい。
久保貞次郎研究所2023年10月月報(第162回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎10月は6点追加し計1223点展示(恩地孝四郎393点 久保貞次郎関連97点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館
◎数学を学ぶ高校生へ、「完全順列は漸化式を作って楽しく学ぼう そしてモンモールからオイラーへ」
久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
10月の追加作品は6点で、No1218からNo1221の4点は、恩地孝四郎の珍しい作品だ。最初の2点は、1911年竹久夢二編集美術誌「櫻さく國」(白風の巻)に、恩地が20歳の時掲載した機械刷り木版「大経師」と「アメリカ旅芸人の演じる日本のムスメ」である。112年前の「櫻さく國」(白風の巻」は超希少本で、私がしたように、その稀覯本の2ページを切り取って額に入れる暴挙に出る者はいないだろうから、この2作品は当美術館でしか見られないかも知れない。残りの2点は、「タゴール有閑哲学」(1929年)と「林忠次舞台と史蹟」(1930年)の装幀画稿で、各画稿10枚と9枚である。恩地は、版画も油彩画も存命中はほとんど売れず、本の装幀家として生計を立てていた。本1冊の装幀料は僅かだが、恩地は生涯多数の装幀を手がけ、通説では、装幀数3千数百冊だが、個人的には1万冊近いと思っている。例えば「アルス日本児童文庫」76冊は装幀数1点とカウントされているが、76冊全て異なった表紙絵で別装幀と考えるべきである。また、恩地装幀と記されていない理工系本、写真関連本も多数有るので、「Ⅰ万冊近い」は、あながち荒唐無稽な数字ではないと思われる。百年近く前の本の装幀過程が垣間見える貴重な装幀画稿と実際の本のセットに、御興味の有る方は、是非御来館下さい。
No1222とNo1223は、2点とも久保関連本で、ヘンリー杉本「北米日本人の収容所」1981年、リトグラフ4点入り特装本(久保貞次郎編)と、池田満寿夫「ふじやまげいしゃ」1985年、金守世士夫木版3点入りの特装本だ。11月も、久保関連特装本5点を用意している。
◎数学を学ぶ高校生へ、「完全順列は漸化式を作って楽しく学ぼう そしてモンモールからオイラーへ」
1708年、フランスの数学者ピエール・モンモール(1678~1719)は、トランプで1から13までの数字を、二人がお互いに出し合って、数字が1枚も一致しない確率はどれ程なのか、という問題を提起した。別な言い方では、例えば5人のパーティーで全員がプレゼントを持ち寄り、全員、持参した自分のプレゼント以外のプレゼントを受け取る場合は何通り有るのか、またその確率は?という問題と本質的に同じである。この問題を「完全順列問題」、「モンモールの問題」と呼ばれ、長年に渡って受験生を悩ませて来た。n人がプレゼントを持ち寄って、全員、自分が持参したプレゼントと異なる他の人のプレゼントを受け取る完全順列の個数をA(n)とする。A(1)=0,A(2)=1,A(3)=2である。(A(3)では、1,2,3に対して2,3,1と3,1、2の二通り)、1740年、スイス生まれの大数学者レオンハルト・オイラー(1707~1783)は、完全順列の漸化式を作り一般解まで発見し、モンモールの問題を見事に解決した。大学入試レベルでは、漸化式を作り、A(4)、A(5)、A(6)と順に求めていけば十分であろう。今、プレゼントを持参して1番目からn番目のn人がパーティーに来たとする。完全順列になるには、n番目の人に限れば、1からn-1番目の人のプレゼントを受け取るn-1通りだ。今、n番目の人に1番目の人のプレゼントが来たとする。n番目の人は、1番目の人に「おーい、1番ちゃん、僕のプレゼント貰ってくれる?」と尋ねると、1番目の人は、「うん、頂くよ、有り難う」と言ったとすれば、1番目とn番目は完全順列になったので、残りは2番目からn-1番目のn-2個の完全順列A(n-2)の個数である。もし1番目の人がn番目の人に、「やだよ、君のことは前から嫌いだったから、受け取らないよ」と言ったとしたらその場合は、1からn-1番目の完全順列A(n-1)個となる。これでA(n-2)+A(nー1)だが、n番目の人には、1からn-1番目のプレゼントが来るn-1通りの可能性が有るので、最終的に、A(n)=(n-1){A(n-2)+A(n-1)}である。この漸化式を用いると、A(4)=3(1+2)=9,A(5)=4(2+9)=44,A(6)=5(9+44)=265と順に求まる。A(4)になる確率は9÷4!=0.375,A(5)では、44÷5!=0.367,A(6)では265÷6!=0.368で、オイラーはnが大きくなると、0.367879・・・(1÷e)になることを証明した。
大学入試では、2004年東工大後期に、2問のうち、前述の漸化式を証明する1問が出題され(90分)、入試関係者を驚かせた。東工大後期出願者は数学のエキスパート揃いで、易問だと評する者も居たが、「旺文社全国大学入試問題正解数学編」の解答責任者を12年間務めた受験数学界の大御所は、「過去、多くの大学に出題されている有名問題だが、理解しにくい解説が多く、適切な本を読んでいないと再現が難しいだろう」と正直に述べている。直近では、2022年共通テスト数Ⅰ・Aでも出題され、平均点38点という信じられない低得点の一因となった。
完全順列は、手を替え品を替えて毎年難関大を中心に出題され、相変わらず受験生を苦しめているが、何にもまして大切な事は、前述の漸化式を自分で何度も作ってみることだ。コツは、A(n-2)、A(n-1)を判らないまま使う事で、中学数学で、XやYを判らないまま使うのと同じで難しくない。モンモールやオイラーが数と形と論理で、無限に広がる宇宙の秘密に切り込んで行ったように、私達も自らの頭で考え、自らこの漸化式を証明することによって、モンモールやオイラーが追い求めた夢を僅かだが共有する事が出来る。数学を学ぶ高校生の皆様、数学の美しい公式を自ら証明し、先人達の夢見た世界にほんの僅かでも足を踏み入れてみたら如何だろうか。(2023,10,28)
久保貞次郎研究所2023年11月月報(第163回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(本年2月真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎11月は4点追加し計1227点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連99点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約の上随時開館
◎館長による版画(限定30部、12種計360点)製作開始 既に6種180点完成
◎鯨敏枝氏の芸術~詩画集「春・夏・秋・冬・ときどき猫」に寄せて~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
11月の追加作品は4点で、No1224は、芝田耕「比叡」油彩20号(京都高島屋陽光会出品作)だ。実弟は高名な洋画家芝田米三だが、素晴らしい風景画を描く無名の兄が居る事だけは噂で聞いていた。「比叡」20号が届き、作品と対峙した時、息を飲んだ。福井良之助の澄み渡切った静寂な風景画と違って、静寂さの中に土着性、京都比叡の霊性といったものが美しい形で敷衍している。これだけの風景画を描ける画家は少ないだろうと思いながら、暫く立ち尽くした。No1225は、恩地孝四郎水彩画「大曲玉川畔風景」1951年作で、恩地が他界する4年前の作であり、「秋田県大曲玉川の茶屋から見たる景をうつす」と記されている珍しい水彩画だ。No1226とNo1227は、久保貞次郎と交流の有った利根山光人、「メキシコの民芸」水彩画入り限定特装本(昭和47年、平凡社)と「利根山光人素描集」ミクストメディア入り限定特装本(昭和45年、総合美術社)だ。2冊共綺麗な肉筆画入りで、現在は入手困難な希少本になっている。
美術館創設以来、来館者様には拙書と版画を贈呈させて頂いたが、版画の方が底を突き始め、多くの新たな版画入手も様々な理由で困難になってきた。それで、ふと思い立ち、22年前に文芸社から出版した、訳の分からぬ拙書「詩画集潮に聞け」の原画から版画を制作することにした。版画と言っても、コピー機を駆使した「カラーコピー版画」という分野の作品で、12種各限定30部計360点を予定している。版画製作、手書きでタイトル、限定番号、サインを記し、画賛を額裏に貼り付け、慎重に額に入れるというたった一人の面倒な手作業で、1点を完成させるのに3時間掛かるのだが、何故か苦にならない。何かを生み出すという創造的作業は人間にとって楽しい行為なのかも知れない。既に6作品、「プルートゥ」、「人」、「私達は生きています」、「犬だってCR病院へ」、「僕のイエルニカ」、「箱とK君とそれに時計」計180点が完成した。1972年、今から51年前の美学美術史生時代の落書きで、何故そのようなタイトルをつけたのかも良く覚えていないが、プロの画家で僅かだが、この落書きを絶賛して下さる人も居る。さて、皆様は如何だろうか。
◎鯨敏枝氏の芸術~詩画集「春・夏・秋・冬・ときどき猫」に寄せて~
鯨敏枝氏と初めてお会いしたのは、5年近く前、真岡新聞に「真髙の春の七草粥とK先生の思い出」という拙文を掲載して頂いた翌日であった。K先生の御子息様と奥様お二人で来館して下さり、有り難くも掲載の謝辞を頂いた。お帰りになる際、奥様が、絵を描いていて、市内のレストランで個展を開いているのでお時間が有りましたら是非立ち寄って下さいとのお話だったので、翌日早速妻と個展会場を訪れた。
作品を観て驚いた。比類無き色彩感である。後で知ったのだが、鯨氏は、32年前から、「ガラス工芸アトリエ日和」を開設し、ステンドグラス等を製作し、光と色彩の世界で生きてきた画家であったのだ。この芸術性の高い「色彩感」は、ステンドグラス製作から人知れず獲得した才能に違いない。
そして絵に添えられた短い文章も出色である。例えば、薄紅色に描かれた曼珠沙華の上部余白に、「秋 曼珠沙華を観ていたら 狂ってもいい気がする」と書かれた作品がある。女性ならではの素晴らしい、恐ろしいほどの感受性だ。私も、7年前の「真岡賛歌8,桜咲き、菜の花香る町 真岡」というエッセーの中で、菜の花の強い香りに包まれて、「このまま別の世界に行ってしまってもかまわない」と書いたが、「狂ってもいい」とまでは書けなかった。脱帽である。他にもはっとする短詩は多くあるが、幾つか紹介するに留めたい。「猫 体をなめる黒猫のペロリペロリと 舌はピンク」。文章の中に色彩を滲ませる事は高等技術と言われているが、見事に「黒」と「ピンク」が散りばめられている。「花 山でであった野菊の花は たおれそうでたおれない」。これは生命賛歌だ。「ある時 花は花 虫は虫 鳥は鳥 できることをしている」。これも生命賛歌であり、自然賛歌であり、存在の賛歌だ。「猫 声の出なくなった老猫は 喉を鳴らして嬉しいとしらせる」。これも動物への憐憫と愛情を伴った生命賛歌だ。
鯨氏の詩画集「春・夏・秋・冬・ときどき猫」は、このようなはっとする短詩と、色彩豊かな色とりどりの水彩画に溢れ、芸術性は驚く程高い。「ねぎの花 もぎる手濡れる 君の体液」という中村忠二の詩画を、ふと思い出した。多くは無いが日本中で静かな愛好家を持つ中村忠二(1898~1975)は、武蔵野の荒れ小屋で、拾い集めた紙に地を這うように、虫や草花の水彩画を多く残した。中村芸術を、草花と虫の「地の芸術」と見なせば、鯨芸術は、「光と色彩の芸術」と言って良いであろう。最後に、もう一篇の短詩を紹介して終わりにしたい。「ある時 草原に寝ころんでみたら こうするために生きている気がする」。澄み切った光と色彩の鯨芸術の中には、思想、哲学も潜んでいる。一見高尚に思える、人間の存在目的を我等の生活の片隅にまで、「こうするために生きている」と見事なまでに引き下ろしてくれたのだ、宝石のようにきらきら光る水彩画を携えて。
久保貞次郎研究所2023年12月月報(第164回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(2023年2月真岡新聞社より出版) 版画・洋書プレゼントも継続中
◎12月は8点追加し計1235点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎館長による版画(限定30部、12種計360点)製作開始 既に9種270点完成
◎エッセー「合同式を楽しもう~無限個の整数を有限個へ~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月は年納めとしていつもより多く8点を追加した。No1228は、久保氏と関係の深い木村光佑の200部限定本画集「シンフォニー」で、シルクスクリーン版画入りの稀覯本だ。No1229は、私のお気に入り作家、妹尾正彦20号油彩画「壺中繚乱たり」である。一目見て妹尾作だとわかる名品である。No1230は、久保関連画家、伊藤高義「らん」油彩6号で、見るからにメキシコの蘭だ。No1231は、佐々亮暎「伊豆湯ヶ島風景」油彩12号である。佐々油彩画は、No833で「白蘭」30号を展示しているが、今回の12号風景画の方が芸術性は高い。No1232は,加藤金一郎油彩40号「古川祭起し太鼓」で、日動画廊シールの貼られた大作である。No1233は、大津英敏リトグラフ「公園にて」で、大津作品は油彩とリトグラフを展示中であり、これで3点目の展示作品となった。No1234は、関野準一郎木版「東大安田講堂」で、当美術館では、何と36点目の展示作品である。関野準一郎は恩地孝四郎の愛弟子で、恩地作品と違って入手が容易なのでいつの間にか36点も展示した次第である。No1235は、田中案山子日本画10号「四手網」で、正方形の大きな網を使った漁法が描かれている。絵画にはその時代の伝統風習を後世に伝える役目も担っている。案山子作品はNo846日本画10号「渓流」に続いて2点目の展示となった。
23年前出版した「潮に聞け」(文芸社)の原画から製作しているカラーコピー版画は、9種270点まで、どうにかこぎ着けたが、残りの90点がなかなか進まない。1月一杯はかかりそうなので、来館者様プレゼントは2月からになりそうだ。当美術館には、12種、各15点計180点、プレゼント用に用意する予定なので、お一人様一日1点、先着順でと考えている。詳細は2024年1月月報でお知らせ致します。
◎エッセー「合同式を楽しもう~無限個の整数を有限個へ~」
ドイツの大数学者カール・フリードリヒ・ガウス(1777~1855)は、1801年、「整数論の研究」(ガウス整数論)の中で、合同式の概念を初めて発表した。合同式とは、無数に有る整数を、ある整数で割った余りで分類する方法だ。例えば、3で割った余りは、0と1と2だけなので、合同式では、無数の整数は、0と1と2だけで表記される。驚くべき事に、いつの間にか無限個の整数が僅か3個の整数に突如変貌したのだ。また3で割った余りで議論するする時は、世界共通で、mod3で、と書けば良い。(modとは、modulusの略で、「法」の意味) だからmod3では、5≡2、2+1≡0、2×2≡1のように独特な世界が広がって行く。50数年前、大学の一般教養数学で初めて合同式を知ったとき目を見開いて驚嘆した。そして数年後中学2年の数学教科書に新しく登場した時、多くの中2生は「こんなの簡単だっぺな」と言って、楽しそうに合同式をマスターしていたのを良く覚えている。現在、合同式は高1数Aで登場するのだが、「補足」となっているので、スルーする高校も有るかも知れない。
具体的な問題に入る。「例題1」「nの3乗+5nは6の倍数であることを示せ。nは整数。」「解1、与式=nの3乗ーn+6n=(n-1)n(n+1)+6nで、n-1,n、n+1の何れかは3の倍数、一つか二つは2の倍数。よって(n-1)n(n+1)は6の倍数で、与式は6の倍数の和になるので6の倍数」「解2、数学的帰納法で。略」、「解3,n=6K,6K+1,・・・6K+5として与式に代入してひたすら計算、Kは整数。略) 解1は少し巧妙で、解2はやや面倒で、解3はかなり大変。いよいよ合同式の登場である。「解4、mod6で、n≡0の時、与式≡0、n≡1の時、与式≡1+5≡0,n≡2の時、与式≡8+10≡18≡0,n≡3の時、与式≡27+15≡42≡0,n≡4の時、与式≡64+20≡84≡0,n≡5の時、与式≡125+25≡150≡0,したがって与式は6の倍数である。」小学レベルのかけ算だけなので、一本道であり楽しく解ける。「例題1」は有名問題だが、合同式で解いている参考書は意外と少ない。
「例題2(2022年富山大、理・医・薬)「自然数nで、nの3乗+3nの2乗+2n-3は5の倍数でないことを示せ。」「合同式での略解、mod5で、n≡0の時、与式≡-3≡2,n≡1の時、与式≡1+3+2-3≡3,n≡2の時、与式≡8+12+4-3≡21≡1,n≡3の時、与式≡57≡2,n≡4の時、与式≡117≡2.したがって与式は5の倍数でない。」このようにルンルン気分で簡単に解ける。「5で割った余りは1か2か3であることを示せ」、と出題したほうが良かったかも知れない。
「例題3(2020年茨城大、工)「22の70乗の一の位を求めよ」「略解、mod10で、22≡2より与式≡2の70乗、2の5乗=32≡2より与式≡(2の5乗)の14乗≡2の14乗≡(2の5乗)の2乗X2の4乗≡(2の2乗)X(2の4乗)≡2の6乗≡(2の5乗)X2≡2X2≡4、従って一の位は4である。」一見煩雑に感じるが、実際は指数計算のみで簡単に解いている。合同式を使わなければ(20+2)の70乗とし、2項定理を用いるのだが、少し面倒だろう。合同式は、今後、微分積分と肩を並べて高校数学のスターになる可能性を秘めていると、私は強く予感する。
数学を学ぶ全ての高校生の皆様、ガウスが発見した合同式という「知性の森」の中を、かつての中2生のように楽しく彷徨ってみては如何だろうか。
久保貞次郎研究所2024年1月月報(第165回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈 版画・洋書プレゼントも継続中
◎新年1月は7点追加し計1242点展示(恩地孝四郎394点 久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎館長による版画(限定30部、12種計360点)完成 美術館贈呈用は12種180点で、2月より来館者様希望者に贈呈 お一人様一日1点で先着順とさせて頂きます
◎檄文「入試に臨む芳賀の大地の少年少女へ」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新年1月は7点追加した。No1236は、小杉放庵木版「山中春意」で、No654~656に続いて4点目の放庵展示作品である。No1237は点描画として著名な加藤芳信リトグラフ「天啓」で画集付きの作品だ。No1238は益田義信20号油彩画「清水港夕照」で、氏は、三井財閥創設者「益田鈍翁」のお孫さんであり、この20号は、おおらかで大胆で生活臭と全く無縁な秀作である。No1239は、青柳大雲「赤富士」日本画10号で、多くの画家による「赤富士」の中でもレベルの高い方だと思われる。No1240は、黒沢久油彩変形6号「運河のある風景」で、ヨーロッパの美しい風景画である。No1241は、昨年12月に続いて関野準一郎「東海道五十三次・吉田」で、柳の枝葉が雨のように画面を覆う傑作だ。No1242は西原千司油彩20号「ロアールの古都・水辺の街」だ。西原氏は茨城県出身で、南仏の美しい風景画で著名な実力派の画家である。この20号油彩画を前にすると、ただただ心が洗われる。
本年5月24日で美術館創設10年目を迎えるが、未だに「この絵おいくらですか」と聞かれる。「美術館ですので、絵の売買はしておりません」と丁重にお断りするのだが、場末の汚い画廊と見間違えるのも無理のない話だ。1242点の半分を壁に掛け、半分は近くに重ね置きして、晴れた日だけ外の建物に立て掛ける展示法は、世界広しといえども当美術館だけであろう。ただ下町の八百屋さんのように絵を展示するスタイルは、最初から意図した方法で、自分では「芸術の大衆化」と呼んで、都合良く正当化している。
現代は、長い人類史の中で、大衆と芸術の間の距離が一番遠ざかっている時代なのかも知れない。多くの原始の民は、洞窟や大地に鮮やかな絵を描き、江戸時代、一般大衆は世界の美術界を動かした浮世絵に親しんだが、今は如何だろうか。モナリザや、フェルメールの作品が来日すれば、作品を牢獄のような堅固な美術館の照明不足の薄暗い所に奉って、挙げ句の果てに「止まらないで、歩きながら観るように」と怖い警備員にどやされる始末だ。凡そ、安くない入館料を払っているのに、歩きながら観なければならない芸術鑑賞など決して有り得ない。八百屋さんで野菜を買う時、近づいてしげしげと見るであろう。久保貞次郎氏がかつて言ったように、人類の進化の一つの指標は、「芸術を生活の中にどれ程浸透させるか」なのだが、現代では、一部の美術関係者達が、芸術作品に必要以上の権威を与え、ついでに自分達の権威付けもして、大衆と芸術の距離を引き離している。それでも一般大衆は、花火大会、お花見などで、賢くも、芸術を生活の中に見事に取り入れている。つまり、桜や花火のように、芸術が大衆に近づき、日常的なものになる事が必要なのだ。音源を買いに行く若者は多いが、画集や詩集を求める若者は少ない。芸術作品だと言って、あぐらをかいていると、音霊と言霊を併せ持つ良質な音楽には、美術や文学は到底太刀打ち出来無いであろう。
下町の八百屋さんのような当美術館の展示スタイルは、現代の大美術館へのささやかな抵抗に他ならない。私の命と僅かな財力が続く限り、入場無料、版画・洋書プレゼントを継続して、遙か数千年後の「全ての人が芸術家である社会」にむけて微かな一歩を歩んで行くつもりだ。
◎檄文「入試に臨む芳賀の大地の少年少女へ」
⑴21世紀初頭、点数主義は多くの欠点をはらみながらも、富、家柄、性別、情実等を見事に排除した、人類の確かな知恵だと知り、潔くこの受験時代を走り抜けよう、次の時代が見えるまで。
⑵合否は、たった今からの君達の努力と覚悟で決まる。
⑶多くの者が不安に駆られている今こそが最大のチャンスだと知れ。
⑷入試に向けて、生まれて初めて身も心も研ぎ澄ませ。
⑸学べる事、受験出来る事に感謝し、世界中の学ぶ事も叶わぬ多くの同胞を代表して入試に臨むのだと自覚せよ。君達は代表選手だぞ。
⑹入試の結果は神聖で崇高。如何なる結果も甘受せよ。そしてその結果を何ら恥じる事無く、今後の君達のかけがえのない糧とせよ。
⑺天は木の葉一枚の行く末を知るという。だとしたら、天は君達のひたむきな努力をどうして見捨てようか。
⑻勝利の女神は、人知れず努力し、他者を思いやる爽やかな若者にそっと優しく忍び寄る。
⑼何をするにも勇気は必要だが、勉強の継続にも真の勇気が必要だと君達は既に知っている。だが苦渋の中で獲得したその勇気は、君の将来の不動の武器に変わると、今の今銘記せよ。
⑽絶えず苛立ち、自分の努力不足を誰かのせいにする受験生に合格者は少ない。
⑾これから入試に臨む君達が家族の中心になるのだから、笑みを絶やさず、穏やかな心で家族の人達に絶えず感謝の言葉を掛けよ。
⑿不安にならない入試など無いのだから、多少の不安、恐怖は勉強の原動力になる。それでも入試間近、言い知れぬ不安に駆られたら、私は一人で戦っているのではない、家族と友とまだ見ぬ同胞と共に戦っていると呪文のように繰り返せ。
⒀周囲に言われるから仕方無く勉強する、受験するとうそぶく者は皆無だと思うが、万が一居たら恥を知れ。
⒁もう腹をくくれ、覚悟を決めよ。入試は自らを試す素晴らしい好機ではないか。何の虚飾も欺瞞もない素晴らしい機会ではないか。
⒂大丈夫、成るように成る。胸を張り勇気に満ちて、君の出来うる最高の答案を書いてこい。大丈夫、桜咲く春が君達をそっと待っているよ、まばゆいばかりの桜咲く春が。
久保貞次郎研究所2024年2月月報(第166回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎本年2月は6点追加し計1248点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎エッセイ「買い物の狩猟性~悠久の人類史の中で~」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
本年2月の追加作品は6点で、No1243からNo1246までは、益子町日下田藍染工房第8代(先代)当主日下田博氏の藍染め額4点で、順に「春その2」、「変形円」、「椿図その2」、「四季図その2」である。「その2」とあるのは、藍染め工程で、型を一作品ごとに作り替えるため、版画のような同一作品ではなく、同じ図柄でも大きさ、細部が異なっていて、かえって興味深い。今回の4点で、日下田博藍染額は21点の展示となり、21点展示は当美術館以外は類をみないであろう。No1247は、鈴木敏之日本画30号「朝焼」で、京都、北白川の滝が荘厳に描かれている。No1248は、久し振りの竹久夢二木版「おこそ頭巾」だ。これで夢二作品は89点展示となった。
新展示作品とはしなかったが、No1162の中村忠二「花と虫とピエロと」(昭和51年、東京新聞社、限定610部)を2冊追加し計19冊展示となった。何故同じ本を19冊も展示しているかと言えば、全冊に全く異なった忠二の肉筆画が入っているからである。忠二は、武蔵野の荒れ小屋に住み、拾い集めた紙に、地を這うようにして愛する虫や草花を描いた小作品を1万点余り描き残したと言われているが、「花と虫とピエロと」の610点の肉筆画は、その遺作に他ならない。地に伏して虫や草花と密かに語り合い、1日数十枚の水彩画を喜々として描き続けた忠二という自称「ピエロ」の狂気に比べれば、同じ稀覯本を19冊も購入展示する私の些細な狂気など、忠二の不屈の狂気の前では、塵芥(ちりあくた)のごときである。
エッセイ「買い物の狩猟性~悠久の人類史の中で~」
50年前、真岡市に「渡辺私塾」を開設し、最初の30年は、脇目も振らず無休で仕事に邁進していたが、超多忙の中でも、幾つかの楽しみが有った。一つは、塾生達と笑顔で触れ合い、少年少女の目映い成長振りを目の当たりに出来る喜び。二つ目は、廉価な美術品や稀覯本をささやかに蒐集する喜び。勿論それらの蒐集品が現在当美術館の展示作品になっているのは言を待たない。そしてもう一つ不思議な喜びが有った。以前は深夜まで営業しているスーパーが近くに数店有り、仕事が終わる夜の11時ごろ、週に2,3度買い物に出かける事が無上の喜びであった。最初、その喜びは、店内を数回周遊し運動不足を解消出来るからだと思っていたが、どうも違う、もっと根源的で本能に根ざした喜びだと思うようになった。
人類の歴史は、諸説有る中、石器を使用した200万年前のアフリカ、ホモ・ハビリスやホモ・エレクトス(ジャワ原人)から始まったとすれば、我々人類の歴史は、ほとんど狩猟の歴史であると言って良い。農耕・牧畜・定住を始めたのも高々1万年前。英国の蒸気機関を背景にした第1次産業革命は高々300年前。石油と電気の第2産業革命も高々150年前。コンピューターによる第3次産業革命も50年前。AIによる第4次産業革命に至っては極最近に過ぎない。我々人類は、悠久の人類史の中で、200万年のうち199万年は狩猟生活をおくっていたのだ。腕力の強い男性が狩りに出かけ、生存能力に長け、肝の据わった女性達が家を守ったのだろう。だから、狩猟性が失われた現代社会で、我等男達は、太古の狩りとは大きく変容してしまったが、「買い物」という名のささやかな「狩り」に出かけるのだ。我等男達の中に流れる赤き血潮が、買い物でも良いから狩りに出かけよ、と抗しがたく心地よく呟く続ける。半額や7割引きの食品を買って帰る時は、遙かいにしえの時、素晴らしい獲物を捕った時のように、意気揚々と力強い足取りで家に帰る。家族に、「お父さん、また買ってきたの!冷蔵庫にこの前のが沢山残っているのよ!!まったく!!!」と叱責されるまでは。
この赤き血潮の心地よい誘(いざな)いには、どうにも抗(あらが)いようがなく、家族から何度となく非難されても、後期高齢者になっても、私は今でも40年間営々と買い物という名のささやかな狩りを続けている。私だけでは無い。親類の中に、3名ほど何かに取り憑かれたかのように狩りを続けた男性が居た。その一人とは今でも、とあるスーパーで出くわす事が有り、苦笑いをしながら、会釈を交わす。その苦笑いは、「本能的根源的衝動だから、まったく!!!と言われようが買い物は止められないよね」という共通の認識と確信と少しの恥じらいの表出だ。
世の奥様方、ご主人が白い買い物袋をカサカサいわせて帰ってきたら、「今日の獲物はどうでした?あら、これ7割引きね、お父さん偉い!」と時には褒めてやって欲しい。褒められれば、男は、喜々として家族のために馬車馬のように働くものなのだ。
お、今、太古の狩りの喜びを記憶する赤き血潮がささやいている、「狩人よ、勇者よ、今は狩りの時、いざ!」と。私も行かねばならない、ライバルひしめく街中の猟場へ、槍の替わりに財布を持って。
久保貞次郎研究所2024年3月月報(第167回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎3月は2点追加し計1250点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎3月13日から5月12日まで、真岡市田町まちかど美術館で「渡辺美術館コレクション日本画名品展」開催
◎「数学を学ぶ高校生へ、ユークリッドの互除法を習得しよう」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
真岡市の御厚意により、田町まちかど美術館で5月12日まで「渡辺美術館コレクション日本画名品展」が開催されている。当美術館所蔵の日本画14点が展示されていて、作品は、小杉放庵「永平」、橋本関雪「緑樹白壁」、酒井三良「雪の河」、小川芋銭「収穫」、松本哲夫「龍門の仏」、荒井孝「牡丹」、加藤晨明「百合」、「静物」、入江酉一郎「迎春」、「きつね」、尾山幟「寂」、石川義「暁」、川崎春彦「春浅き山湖」、「山の教会」である。狭苦しい当美術館に展示されている日本画14点は、綺麗なまちかど美術館の白壁で、安堵のため息をつき深々と深呼吸をしているに違いない。
3月の追加作品は2点のみで、No1249は浅野紫露「双鶴」日本画20号で、2羽の鶴の仕草が面白い。No1250は、恩地孝四郎油彩画「三人の女性」50号以来の重要作品で、福井良之助油彩画「風船と少女」15号だ。福井作品は、デッサン22点、肉筆画帳、木炭画を展示しているが、油彩画は初めてである。凡そ多くの絵画コレクターは、静寂な福井油彩画を1点だけでも蒐集する事を願うものだが、真筆の油彩画は高額で希少で大美術館に収蔵されている場合が多く、その願いは叶わないのが常である。私も身分不相応と諦めていたが、幸運が重なって、この15号秀作を廉価で購入出来た。廉価の場合贋作の懸念も有るが、東京美術倶楽部鑑定書が添付されていてまごうこと無く真作である。暫くは入り口の左側に展示する予定なので、来館なさり福井芸術と邂逅して頂ければ幸いである。
◎「数学を学ぶ高校生へ、ユークリッドの互除法を習得しよう」
古代エジプト、アレクサンドリア在住のギリシャ系数学者ユークリッドは、紀元前300年頃「ユークリッド原論」を著し、原論第7章命題1から3において「互除法」について記した。ユークリッドについては詳細不明であるが、ユークリッド互除法は、現在高校1年生必修の数学A第3章で登場し、一見煩雑に見えるので、多くの高校生を悩ませている。互除法は「自然数AとBで、AをBで割った時の余りをRとすると、AとBの最大公約数は、BとRの最大公約数に等しい」という定理なのだが、教科書には証明が載っていないため、互除法嫌いの高校生は意外と多い。
今、厳密な証明を試みる。AをBで割った商をQ,余りをRとすると、A=BQ+Rと書ける。AとBの最大公約数をG、BとRの最大公約数をgとすると、A=GC、B=GDと書け、B=gE、R=gFと書ける。(但し文字は全て自然数)⑴R=AーBQよりR=GCーGBQ=G(CーBQ)、よってB=GDとR=G(CーBQ)よりBとRは公約数Gを持ち、BとRの最大公約数はgなのでg≧Gである。⑵A=BQ+RよりA=gEQ+gF=g(EQ+F)、B=gEよりAとBは公約数gを持ち、AとBの最大公約数はGなので、G≧gである。以上⑴、⑵よりG=gとなり、互除法の定理は示された。
互除法の利用例を挙げる。「例Ⅰ」「自然数19343と4807の最大公約数を求めよ」(2017年立教大)(解答例)19343=4807x4+115、4807=115x41+92,115=92x1+23、92=23x4+0より、92と23の最大公約数は23で、互除法の定理より、19343と4807の最大公約数は23である。
「例Ⅱ」「自然数nと2n+1は互いに素であることを示せ」(2022年明治大)、(解答例)2n+1=nx2+1、互除法より、2n+1とnの最大公約数はnと1の最大公約数に等しいので,2n+1とnの最大公約数は1となり、互いに素である。
「例Ⅲ」「1次不定方程式275x+61y=1の全ての整数解を求めよ」(2017年愛媛大)、(解答例)275x+61y=1・・・①とする。一方互除法で、275=61X4+31・・・②、61=31X1+30・・・③、31=30X1+1・・・④より②から31=275-61X4を③と④に代入すると、61=275-61X4+30・・・⑤、275-61X4=30X1+1・・・⑥となり⑤から30=ー275+61X5を⑥に代入すれば275-61X4=ー275+61X5+1、これより275X2+61X(ー9)=1・・・⑦を得る。①ー⑦より275(x
ー2)+61(y+9)=0、275と61は互いに素なので、x-2=61K、y+9=-275Kと書け、全ての整数解はx=61K+2,y=-275K-9、(Kは整数)である。
互除法では、「例Ⅲ」の煩雑さが際立ち、それ故不人気なのだろうが、互除法の神髄は「例Ⅱ」にある。「例Ⅱ」で互除法を用いなければ背理法で巧妙に解かねばならない。ユークリッドの互除法は比較的新しい分野なので、今後出題者諸兄の研究が進めば、互除法を用いる美しい整数問題が数多く登場するであろう。
数学とは魅力的で不思議な学問である。科学技術がこれほど進歩した現代、世界中で幾千万のうら若き少年少女が、2千3百年前のユークリッド互除法を学んでいる。日本の高校生達よ、ユークリッド互除法を学び、数学の美しさを学び、子や孫や後世の同胞に、数学を学ぶ喜びを伝える事が、21世紀初頭に生きる君達の小さな使命の一つかも知れない。まずは澄み切った精神で互除法の証明から!
久保貞次郎研究所2024年4月月報(第168回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎4月は7点追加し計1257点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約ご相談の上随時開館
◎久保研究所月報掲載紙「真岡新聞」が休刊
◎エッセイ「小さな蜘蛛の生への執念」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
本年4月の追加作品は7点でNo1251はフランスの画家エル・アレクシスの20号油彩画「モンマルトル」だ。アレクシスは最初、お土産用油彩画を描いていた職人であったが、いつの間にか腕を上げ、画家として名を馳せたと言われている。No1252は、田中以知庵(1893~1958)の15号日本画「郷愁の民家」で、以知庵は日展審査員を務めた実力派の日本画家である。No1253は、日展参与で重鎮の小栗潮(1921~2013)20号日本画「洞門の秋」で、No309、30号大作「軍鶏」についで2点目の展示作品だ。No1254は、金子文雄(1944~)の「ポプラ島の古城」1973年作20号油彩画で、フランス風景画の良作である。No1255は、ドイツの女流画家レナータ・ツェルナーの銅版画「プロムナードⅡ」30号で、銅版画で30号の大作は珍しい。No1256は、榑松正利(くれまつまさとし、1916~2008、日展参与)の1973年作10号油彩画「雪の晴れ間」だ。榑松作品は2点所蔵していたが、大震災で現在所在不明になっている。最後のNo1257は、佐藤晨(1935~)15号日本画「カトレア」で、さすが創画会会員、目を見張る傑作である。
月に1度、ご好意で「久保貞次郎研究所月報」を掲載して下さった「真岡新聞」が諸般の事情で休刊になってしまい、月報の発表場所が一つ無くなってしまった。それでも、多くは無いが月報を楽しみにしている方々もいらっしゃるので、まずこのホームページに掲載し、その後著作集第11巻に掲載して公にしたいと思っている。
◎エッセイ「小さな蜘蛛の生への執念」
4月末の事、トイレの洗面台のシンクの中腹に2ミリぐらいの黒いゴミが付いていたので、蛇口から水を出してゴミとおぼしき物を流した。2時間ほど経って、再び洗面台に行くと、また同じような黒いゴミが付いていたので、不思議に思いながらも、今度はコップに入れた水で同様に流した。3時間程経ったのち、トイレに立ち寄ると、洗面台に同じような黒いゴミが一つ有り、理解に苦しんだ。もしや、ゴミではなく生き物なのでは、という思いがよぎり、虫めがねで観察すると、何と小さな小さな蜘蛛であった。そして確かに、存在の厳しさに耐えかねて震えるように動いている。
同一の蜘蛛だとすれば、5時間前に水道の排水口から流され、流し台の下のU字管から、微かな光を頼りに必死に命懸けで這い上がって来たのであろう。その挙げ句、心無い人類種の私に、またも悪魔の所業の如く無慈悲にも流されてしまったのだ。生き物の蜘蛛だと理解した時の正直な気持ちは、小さな蜘蛛に対して、2度も濁流に放り込み、心無い行為だった、人類の思い上がりだ、本当に申し訳ない、すまないという後悔の念と、蜘蛛の生命力、生への執念、根性、気概への驚嘆の思いであった。
それにしても、洗面台の中腹に、何故命懸けで3度も震えながら居るのでだろうか。はっと、気がついた。この小さな蜘蛛君は、垂直の白磁の壁は登れないのだ。芥川龍之介の「蜘蛛の糸」ではないが、蜘蛛を潰さないように細心の注意を払って、微かに震え続けている生命そのものの蜘蛛君を指先に乗せ、薔薇咲く庭にそっと放してやった。万分の一の罪滅ぼしになっただろうか。
善行と悪行の狭間で生きて来た私が、もし地獄に落ちたら、この小さな蜘蛛君が垂らす蜘蛛の糸に決して頼らず、蜘蛛君と同様、微かな光を頼りに、必死に命懸けで地獄の壁を這い上がろうと思う。この小さな蜘蛛君との出会いで、そう覚悟を決めた。震える小さな蜘蛛君は、漆黒の闇の中、地獄の壁を2度も這い上がって来たのだから。
久保貞次郎研究所2024年5月月報(第169回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎5月は4点追加し計1261点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約ご相談の上随時開館
◎エッセイ「フェミニストの蛇マフラー」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
5月の追加作品は4点で、No1258は、益子町日下田藍染工房第8代当主(先代)日下田博藍染額「山水その4」である。同じ図柄の山水図でも、細部が微妙に異なっていて全作品が1点物と考えて良いであろう。日下田博藍染額はこの作品で計22点の展示となり、展示数では他に類をみないと思われる。
No1259は、1926年千葉県生まれ日展会友根本峯男作「夢の架け橋」(日本画8号)だ。木更津、中の島大橋を、浮世絵の様に大胆な構図で描いている。
No1260は、1942年愛知県生まれ日展評議員市野龍起「三日雛」(日本画15号)だ。市野龍起は、同じ日本画家である父の市野亨と共に自宅に百羽を超える種々の鳥を飼い、日々スケッチに励み研鑽を積んだと言われている。「三日雛」とは、生まれて三日の雛のことだろうか。
No1261は、昨年11月月報で紹介した芝田耕の20号油彩画「古城と樹」である。No1224、20号油彩画「比叡」も傑作であるが、この「古城と樹」も名作だ。芝田耕は、高名な実弟の芝田米三に比べて無名に近いが、その芸術性の高さは多くの洋画家の遙か彼方に有る。開館時、晴れた日には、多くの作品を屋外に展示するのだが、この2点の20号油彩画は、最後に屋内に収納することにしている。しみじみと鑑賞して心の静寂を取り戻したいからだ。
◎エッセイ「フェミニストの蛇マフラー」
私は、小さい頃から女性に対しては畏敬の念を持っていた。何故かは解らない。「畏敬の念」の半分は憧れで、半分は女性からよく思われたいというよこしまな思いなのかも知れない。今でも、数十歳も年下の親類の多くの女性に敬語をを使っている。ほとんどの男性に対してはため口なのに、女性には他人行儀と思われようが気がついたら無意識に敬語を使っているのだからどう仕様もない。いわゆる生まれながらのフェミニスト(女性の権利を尊重し、女性に優しく接する男性)なのだろうか。
このフェミニストぶりは、小学生から発揮していた。半世紀以上も前、学校の給食では、脱脂粉乳の牛乳が必ず提供され、女の子の中には、鼻をつまみながら飲み干す子も居た。冗談なのだろうが、全部飲まないと家に帰れないという暗黙のきまりを口にする先生も居た。毎日、給食時間が終わりに近づくと、半分程残った牛乳を絶望の眼差しで見つめる女の子が4,5人居るのが常であった。私はそっと近づき、飲めずに残った牛乳を全部一気に飲み干し、何事も無かったかの様に静かに席に着いた。当然の如く、私は、想像以上に感謝され、女児の人気者であった。一方、男の子には、悪魔のようないたずらをした。男児の一人が牛乳を飲んだ瞬間大声で「鼻から牛乳!」と叫ぶのだ。そして3回に1回は、本当に鼻から牛乳を吹き出す子が居て、不思議な事だが、吹き出した方が悪く、吹き出させた悪童が勝ちという妙な雰囲気が有った。それに勉強も少し出来たので、牛乳飲みすぎ栄養過多で小太りであったが、クラス一の人気者であった、小学5年のある事件までは。
当時小学校の運動場の裏は緩やかな坂で、低木、雑木が生い茂り季節には蛇も散見された。あれは9月の晴れた日だったと思う。坂下を上から覗いていると、中腹に、やや小ぶりの青大将が居るのがわかった。運動場の方を見ると、同じクラスの女の子が7,8人遊んでいた。良し、女の子達を喜ばせてあげようと一念発起し、坂を降りて蛇を捕まえ、頭と尻尾を持って首に巻き、女の子達の方にニヤニヤしながら近づいて行った。首のマフラーが蛇だとわかった瞬間、全員きゃーと叫びながら一斉に逃げ出した。あの天にも届く「キャー」は喜びの極致なのかとも思ったが、少しやり過ぎたかという自覚も有った。案の定、迷惑そうな眼差しの蛇をもと居た所に放して教室に戻ると、女の子全員、私を忌み嫌うかのように遠巻きにして一切の接触を避けた。そして翌日から、牛乳を残す女児は皆無になった。あの蛇マフラー小僧に飲まれる位なら、泣きながらでも自分で飲み干した方がましだと思ったのだろう。蛇マフラー事件は、現在なら完全なハラスメントだが、今でも誓って言える。大失態ではあったが、動機には、女の子達を喜ばせたいというフェミニズム思想が根底に有ったと。
そうそう、私がもともと蛇好きだったという訳ではない。その証左に、家に帰ってすぐ、お風呂場で、「何やってんだっぺ、おれ、オエー」と言いながら首の周りを石けんで数十回洗ったのだから。
久保貞次郎研究所2024年6月月報(第170回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎6月は5点追加し計1266点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎エッセイ「造花考~その2~生物的生命と造形的生命」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
6月の追加作品は5点で、NO1262は、庚端倪(こうたんげい)(本名小野塚幹雄、1911~2001)日本画12号「只見晩秋」1985年作である。端倪は福島県出身の院友で、仏画を得意とするが、この風景画は不思議な静けさを持つ日本画だ。NO1263は、湘南の洋画家大貫松三の4号油彩画「いちご」で、小品だが、いちごの町真岡市にふさわしい名作である。No1264は、名古屋出身の木版画家堀江良一2000年作「弧のある風景00-1」木版大作だ。堀江良一は「弧の有る風景」シリーズ木版大作を営々と創り続けている特異な版画家である。No1265は、関野準一郎木版「御手洗港」(1983年作)で、当美術館では関野作品は35点目の展示作品だ。以前にも書いたが、関野準一郎は恩地孝四郎の1番弟子と言われており、多くの作品が海外に流出して日本では希少の恩地作品と比べて、関野は多作版画家で比較的蒐集が容易で廉価なので、35点目の展示作品となった次第だ。最後にNo1266は、伊藤髟耳(ほうじ)の15号日本画「石仏」である。髟耳は院展評議員、日本芸術院会員で、緑色を多用し、畏敬の念を持って「緑の髟耳」と呼ばれている。No325と326で、緑のリトグラフ「羅漢」、「庭園」を展示しているが、髟耳の緑の日本画を展示したいという長年の小さな夢がやっと叶った6月であった。
◎エッセイ「造花考~その2~生物的生命と造形的生命」
昨年の久保貞次郎研究所7月月報(159回)に、「造花考~美術館に薔薇の造花を飾って~」という拙文を書いた。書いた時点では、市内4ヶ所の百円ショップから買い求めた薔薇の造花は300点余であったが、その後薔薇以外の綺麗な造花にも魅了され、新年1月にはいつの間にか900点近くになっていた。その900点の造花を展示絵画作品の前に無造作に飾ったので、心有る来館者様から、作品が鑑賞しずらいというご助言を頂いた。それで一念発起し、家に有った二十数点の益子焼の花瓶に造花を束ねて飾ることにした。一つの花瓶に造花を十数本入れたが、造花が多すぎて花瓶が足りず、輪島塗の大椀や大きな黒い帽子などを総動員して、自宅に16点、美術館1階に32点、2階に23点、計71点の造花のブーケが誕生した。そして驚いた事に、このブーケ達は、思いのほか掛け値なしに美しいのだ。これは私の造花の生け方が上手なのでなく、造花1本1本が完成された一つの作品だからなのだろう。昨年7月月報でも書いたが、人類の科学技術の進歩の証、結晶の一つは、素晴らしい造花の登場とその進化だと、私は確信する。我々は、造花を投げ合って戦争など決してしない。造花は、人類史科学史の中で紛れもなく平和的に花開いた結実であり象徴なのだ。
紀元前2千7百年頃、エーゲ文明の王墓に青銅の造花を飾った人達、日本でも10世紀初頭、木を削った「削り花」という造花を刻苦の中で創りあげた人達が、ポリエステル、ポリエチレンを素材に精妙な造形着色技術の結晶である現代の造花達を目の当たりにすると、どう思うであろうか。大袈裟に言えば、余りの精妙さ、美しさに泡を吹いて卒倒してしまうのではないだろうか。
造花は、どうせ作り物で、命の通わない花にすぎないと蔑視なさる方々もおられるであろう。その人達に、強く言いたい。ゴッホの「ひまわり」も、キャンバスと絵の具で出来た作り物で、命の通わない花ではないのかと。モネの「睡蓮」もしかり。何故、人類はそのような命の通わない花々に天文学的金銭価値を見いだすのであろうか。それは、「ひまわり」や「睡蓮」や造花は、「生物的生命」は皆無でも「造形的生命」が宿るからなのだ。ポリエチレンとポリエステルと発色剤でひとたび薔薇になったら、その瞬間その薔薇は「造形的生命」を見事に宿すのだ。凡そ、全ての芸術作品は「造形的生命」を所有し、生け花や舞台芸術は、「生物的生命と造形的生命」を同時に持つが、長時間持続不可能でいわゆる短命芸術である。ロダンの「考える人」は、青銅で出来ていて「生物的生命」は零だが、長命芸術で、幾世紀にも渡って我々に素晴らしい「造形的生命」の微光を放ってくれる。
百円ショップで求められる1本の深紅の薔薇の造花を侮る事なかれ。愛する人や動物に先立たれた時、薄暗い部屋で優しい光を放つ1本の造花をじっと見たことは有りませんか。悲しい思いがほんの少し和らいだと思った事は有りませんか。今、私の眼前を飾る3輪の薄紅色の薔薇の造花に、永久(とわ)に近い命を授かった薔薇の造花に、自販機の缶1個の価値も無いとおっしゃるのですか。
久保貞次郎研究所2024年7月月報(第171回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎7月は5点追加し計1271点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連101点) 土曜日以外2名以上の来館者で様電話予約御相談の上随時開館、
◎「渡辺美術館開設10年目を迎えて」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
7月の追加作品は6月と同様5点であった。No1267は、私の好きな洋画家大貫松三作6号油彩画「紅椿」だ。毎週来館なさる英文学者が、「浮き上がる点描」と称した秀作である。No1268は、益子町日下田藍染工房第8代当主(先代)日下田博作「山水図その2」だ。日下田博藍染額は既に23点目の展示作品となった。No1269は妹尾正彦作4号油彩画「猫とてんとう虫と蝶」である。妹尾油彩画は4点目の展示作品だが、どの作品にも、子供、動物、虫、蝶、植物が登場する。全ての事物は、宇宙の小さな「現れ」で、全て「繋がっているよ」、「同胞仲間だよ」、「仲間同士何故争うの?」と言っているように思えてならない。No1270は、恩地孝四郎の愛弟子関野準一郎の木版「晩夏の譜」(1972年)である。希少で高価な恩地作品に比べて、関野木版は比較的入手しやすいので、何と37点目の展示作品となった。No1271は、鳥の日本画家市野龍起水彩6号「筍」だ。鳥を描きながら修練を重ねたのだろう、今にも画面から飛び出しそうな筍が見事に描かれている。
◎「渡辺美術館開設10年目を迎えて」
昨年6月月報で「渡辺美術館開設9年目を迎えて」という拙文を書かせて頂いたが、節目の10年目を迎えたので、再度同趣旨の拙文を書くのを許されたい。2015年5月24日、貧弱ながらも念願の美術館を開設して本年5月で9年が経ち、あっと言う間に10年目を迎えた。
半世紀前名大の美学生であった時から、心に秘めていた事が有った。一つは、何十年かかろうと美術館を開設する事。実に40年の時を要した。二つ目は、入場無料で来館者様全員にオリジナル版画や本をプレゼントする事。三つ目は出来るだけ多くの作品を展示する事。四つ目は、どれ程乱雑に見えようが、作品を、スーパーの野菜コーナーのように、来館者様の間近に展示する事の4点である。四つの事を10年目に入っても歯を食いしばって継続している点は、自分でも上出来だと思っている。四つ目に関しては、無造作に立て掛けてある有名油彩画を見て「作品が可哀想」と非難の言葉を口にした美術関係者も居たが、作品の展示方法では、私は全く異なった考えを持っている。日本では、堅牢で薄暗い美術館内にまばらに作品を展示するスタイルが主流だが、それでは返って、作品と鑑賞者の距離を遠ざけてしまう。つまり芸術と人間を遠ざけてしまうのだ。「一人一人がオリジナル作品を3点以上持ち、芸術を生活の中に浸透させる」と言ったのは久保貞次郎であったが、恩地孝四郎も「本は文明の旗だ、だから本は美しくあらねばならぬ」と、かつて断言した。二人が言いたかった事は、芸術や美しい本が我々の生活にどれ程浸透しているか、我々が芸術を愛でる心の余裕を生活の中でどれ程持てるか、それこそが人類の進化の尺度であり一里塚でありマイルストーンだと言う事なのだろう。
それ故現代日本の美術館の展示スタイルは、久保や恩地の高尚な文明論と真逆の位置にある。一般大衆の至宝であるはずの多くの芸術作品に必要以上に権威を与え、ついでに美術関係者にも無意味な権威を与え、我々から芸術を遠ざけている。「モナリザ」やフェルメーの作品が日本に来ると、今でも、「止まらないで!」と警備員にどやされる始末だ。「歩きながらの芸術鑑賞など有り得ない!」と主催団体に怒鳴り返したい衝動に何度と無く駆られた。「作品が可哀想」なのでなく、来館者である一般大衆が可哀想なのだ。
北関東の外れの貧弱な美術館で、このような愚痴を言って数十年になるが、知り合いの美術館関係者の中には、出来るだけ多くの作品を観て貰おうと壁一面敷き詰めるように作品を飾り、展示スタイルを変える人達も出てきているのは、嬉しい限りである。
最後に、ここ1年の展示作品で、私が特に気に入っている作品を10点列挙して終わりとしたい。⑴恩地孝四郎50号油彩画「三人の女性」、⑵芝田耕20号油彩画「比叡」、⑶妹尾正彦20号油彩画「壺中繚乱たり」、⑷福井良之助15号油彩画「風船と少女」、⑸佐藤晨15号日本画「カトレア」、⑹市野龍起15号日本画「三日雛」、⑺芝田耕20号油彩画「古城と樹」、⑻大貫松三4号油彩画「いちご」、⑼伊藤髟耳15号日本画「石仏」、⑽妹尾正彦4号油彩画「猫とてんとう虫と蝶」。
久保貞次郎研究所2024年8月月報(第172回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第10巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎8月は11点追加し計1282点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連111点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約ご相談の上随時開館
◎エッセイ「百足(ムカデ)騒動」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
8月の追加作品は、何時になく多く11点であった。No1272は、恩地孝四郎の愛弟子関野準一郎木版「白梅紅梅」で、関野木版38点目の展示作品だ。No1273から1282までは北川民次関連作品で、No1273は、「北川民次画集」(1974年日動画廊、久保貞次郎編)特装本とスパー特装本2冊である。特装本は、リトグラフ「化粧」、「三河童」2点入りで、スーパー特装本は、肉筆水彩画「林間」入りだ。2冊の希少な特装本を同時に展示している所は希有であろう。以下No1274から1282の9点は、全て北川民次版画である。順に、銅販「裸婦」、リトグラフ「海芋」、リトグラフ「バラ」、リトグラフ「リンゴを持つ母子像」、リトグラフ「水浴の母子」、リトグラフ「猪突猛進」、リトグラフ「果実を売る女」、リトグラフ「トマト売り」、リトグラフ「バッタと群像」の9点だ。ほとんどが、レゾネ本と言われている「北川民次版画全集」(1977年、久保貞次郎編、名古屋日動画廊)に掲載されている有名作品である。8月は北川作品10点追加で、さしずめ北川民次特集月間と言って良いのであろう。久保氏と関係の深い北川作品が今まで4点のみの展示であったが、今月の北川作品10点追加で、久保貞次郎関連作品も10点増え計111点にする事が出来た。9月も北川作品6点を展示予定なので、久保氏も天で喜んでおられるであろう。
◎エッセイ「百足(ムカデ)騒動」
1ヶ月程前の深夜の事だ。午前2時頃、寝入りばな、漆黒の天井から何かが顔に落ちてきた。ゾッとしてとっさに手で振り払った。多分ゴキブリだろうと思い電気をつけて正体を確かめると何と20センチ近い大きな百足であった。恐怖に駆られ、近くに有ったゴム製のスリッパで鬼の形相でその百足を思いっきり叩いた。2,3回ではびくともせず、数えてはいなかったが数十回は叩いたのだろう。潰れた百足をティッシュで幾重にも包み、荒い呼吸で外のゴミ箱に棄てた。少し経って、冷静になって心に浮かんだ思いは、何故すぐたたき殺してしまったのかという後悔の念であった。10年ほど前、孫が長靴の中に潜んでいた百足に足先を刺され紫色に腫れ上がった事を知っていたためか、恐怖心に支配され、そうするしかなかった、そうせざろう得なかった。人間は恐怖に支配されると、相手を殺戮する場合が有ると言う事を初めて知った。但し、人類種が節足動物百足より上位でより強いという驕りが前提に有るのは言うまでもないのだが。
日本語でムカデは百足と書くが、英語でも、centipedeと書いて、百の足だ。centは百の意味で(century「百年」、centuple「百倍する」、centimeter「1㎝、1メートルの百分の一」)pedは足の意味で(pedal「ペダル」、pedestrian「歩行者」)英語でも百足なのである。地上に存在する如何なる生物にも、何か役目、使命が有ると言う賢者も居るが、殺戮された百足の存在意義は果たして何なのだろうか。
百足騒動には続きが有る。2日後、妻が「ムカデちゃんに一晩添い寝しちゃった」とあっけらかんに言ってきた。詳しく聞くと、目を覚ましたら枕元に5㎝程の小さなムカデが居て、多分一夜を共にしたのだろう、との事であった。子供のムカデが、軽率愚鈍な男に叩き殺されたお父さんを捜しに来たのだろうか。再度後悔の念が心の奥の奥を支配した。
子孫を残し人類を永続させる宿命を背負った女性の方が、男性より強靱でしなやかで、環境への適応能力が勝っているのかも知れない。妻は、その子ムカデを新聞の上に静かに乗せ、何事も無かったかのようにトイレに流したと言う。恐怖に駆られ狂気の如くスリッパを振り上げ、残酷に殺戮した私とは大違いで有る。情け容赦なくスリッパを振り下ろした男性の狂気の中に、人類が21世紀初頭になっても戦争を続けている理由の一つが潜んでいるのかも知れない。
今後家の中でムカデちゃんに出会ったら、今度こそは薔薇香る庭にそっと放す事にしよう。
世の全てのムカデよ、自らの存在意義に気付き、何のための百の足なのかを熟慮し、高尚な使命を自覚して、この大地を自由に這い回れ。愚鈍な人類種の私より。
久保貞次郎研究所2024年9月月報(第173回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎9月は5点追加し計1287点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連116点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎エッセイ「真桑瓜(メロン種)を植えて」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
9月の追加作品は5点で、No1283から1286までは、北川民次版画4点であり、今月で久保貞次郎関連作品は116点となった。順に、エッチング「母子像」、リトグラフ「母子像」、エッチング「アダムとイブ」、エッチング「陶工」で4点とも有名作品である。10月も北川作品2点を追加展示する予定でいる。最後のNo1287は、久し振りの日本画大作で、佐藤晨120号「壇ノ浦 死霊の前で」だ。この作品は、2019年池田20世紀美術館「佐藤晨の世界」展出品作で、代表作でもある。佐藤晨は創画会の実力派会員で、売り絵を描くよりも、創造的に独自の世界観を表現する日本画家だ。佐藤作品は、No1257「カトレア」日本画15号に続いて2点目の展示作品となった。このような120号代表作が、地方の弱小美術館で入手出来たのは、奇跡に近いが、この上なく喜ばしい奇跡である。
8月24日、横浜からの来館者が有った。突然の来館であり、30年ぶりなので、すぐに誰とは解らなかったが、私の教え子で、現在医師として活躍中との事、高校生の時から物静かで真っ直ぐな若者であったが、やはり立派な素晴らしい医師になっていた。電車とバスを乗り継いで、当美術館来館の為だけの来訪との事であり、嬉しさの余り、絵や稀覯本を鑑賞しながら、2時間以上も心弾ませて歓談した。
◎エッセイ「真桑瓜(メロン種)を植えて」
70年近く前になるのだろうか、近所の悪童達と一緒に、八百屋さんの店先に山積みになった黄色い真桑瓜を5円で買って、各々自分の歯で皮を剥いて、遊び回りながら美味しく食べたものだ。そのような事を鮮明に覚えているので、5月、近くのホームセンターを訪れた時、「真桑瓜」と書かれた苗木を見て、言い様の無い感慨が湧き起こり、思わず二株買ってしまった。
帰宅してすぐ、遠い昔の思い出を胸に、わくわくしながら薔薇の木の間に植えた。安定するように鉄製の緑の支柱を添え、水をたっぷりかけて、さあ終了だ。毎日午後見に行くと、日々5㎝くらい成長している。1週間も経つと、つるを出して支柱に絡み付き、上へ上へと大きくなっていった。真桑瓜や西瓜は、地面を這うように生長し、地面に実を置くと記憶していたが、この真桑瓜は空に向かってまっしぐらだ。仕方無く、より背の高い緑の支柱をどんどん追加していった。
1カ月くらい経った時、30個ほどの綺麗な黄色い花を付けた。そして1週間も経たないうちに、花の下が膨らみ始め、計7個の緑の実を付けた。以前の中村メロンと同じ薄緑色だ。最初に腐葉土を入れただけで、肥料はやらなかったが、水だけは欠かさないようにした。素人の私が植えたのだから、花も咲かず枯れてしまうだろうと思っていたので、もうこの頃になると、愛おしさが募り生活の中で大切な物になっていた。野球のボールくらいになった実は、重そうだったので、桃を包んでいた白い網目状のカバーを実の下に入れ、紐で支柱に結んで、実を吊ってあげる形にした。かなり面倒な作業だったので、吊るのは2個だけにして、残り5個は真桑瓜の自主性に任せた。
此処で驚いた事は、吊らなかった5個は、自分の弦で実と枝の間に絡み付き茶色く硬くなって落下するのを自ら防いでいて、吊った2個はそれをしないという事だ。妙な表現だが、植物は人間の意識とは異種の意識、人間の精神の遙か遠くに有る精神を所有しているかのようである。
次の問題は、何時収穫するかだ。2,3日思いあぐねていると、真桑瓜君がそっと教えてくれた。薄緑の実に細長い割れ目が出来始めている。「もう収穫の時だよ」と告げているのに違いないので、赤ちゃんを抱くように順に大切に収穫した。
「大切に育てた真桑瓜を残酷にも食べてしまうの?」と心配なさる方もおられるであろうが、大丈夫。私は、食については、ある考えを持っている。食べ物は食べられると、細胞、分子、原子レベルで、体内で同化し、一緒に生きていくという考えを。マタイによる福音書6-31「何を食べ、何を飲み、何を着ようと煩う事なかれ」に書かれている通りだと思う。我等地上の者は、天が授けた食べ物を感謝して食すれば良いのだ。
さて、真桑瓜君の食感を書かねばならない。妻は、私が作った料理、私が育てた果実、野菜を食して、滅多に褒めない。こんな不味い物食べたこと無いという表情でただ黙っているだけだ。その妻が、孫娘までもが、思わず「美味い」と呟いた。私もその食感に驚いた。昔の黄色い真桑瓜のように硬くないのだ。「シャリシャリ」感と言うべきか、少しだけ甘い新鮮な西瓜を食しているかの様である。
9月初旬だというのに、庭の真桑瓜は、人類とは異種の精神で我等の喜びを察知したのか、けなげにもちいさな4個の実を付け、幾つかの黄色い花を未だ咲かせている。遙か遠い未来、人類と植物の意思疎通が可能となる時の到来を暗示するかの様に。
久保貞次郎研究所2024年10月月報(第174回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第10巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎10月は6点追加し計1293点展示(恩地孝四郎395点 久保貞次郎関連118点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎エッセイ「今年も柿がなる」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
10月の追加作品は6点で、No1288は、北川民次の水彩画「母子とリンゴ」、No1289は北川民次1976年作銅版「抱く」で、今月で北川展示作品は計20点となり、久保貞次郎関連作品も118点となった。No1290は、清水錬徳油彩画10号「花瓶に薔薇」で、清水油彩画は計4点の展示である。No1291は、福井良之助1銅版「風化」で、銅版画ながら、福井独自の静寂感荒涼感に溢れ、息をのむ。No1292は、No1260とNo1271の日本画家市野龍起の実弟市野鷹生の日本画8号「映」だ。表現力では兄が勝っているように思えるが、弟鷹生は、独自の優れた色彩感を持っている。最後のNo1293は、恩地孝四郎木版「童女浴後」で、恩地オリジナル作品は久し振りの展示である。10数年前、とある公立美術館が、驚く程の高値でこの作品を入手して話題になったが、それ程恩地オリジナル作品は、ほとんどが海を渡っていて、この日本では希少で高額なのだろう。読者の皆様ご心配なく。資金欠乏だが、恩地に関して知識豊富な当美術館は、廉価購入の名手で、推定だが、今回数十分の1の価格で購入出来た。
真岡市田町まちかど美術館で、11月17日まで、第31回常設企画展「たてもの紀行~旅する絵描きたち~」が開催されてる。そのうちの2点、芝田耕「古城と樹」(油彩20号)と西原千司「ロアールの古都 水辺の街」(油彩20号)が当美術館の出品作品で、市の学芸員は、当美術館の建物にまつわる百点程の日本画、油彩画、版画から、躊躇らわずこの2点の秀作を選ばれた。さすが学芸員、驚く程の鑑識眼である。
◎エッセイ「今年も柿がなる」
以前にも書いたが、20年程前、溢れかえる書籍を収納するため 書庫を増築した時、リンゴ、葡萄、さくらんぼなど実のなる樹木をやむなく伐採した。1年後、殺風景になった庭を見て、近くのホームセンターで求めた百目柿の苗を1本植えた。「桃栗三年柿八年」と言われるが、5年後背丈も3メートルを超え、釣り鐘型の大きな実を8個付けた。肥料はストーブの灰をまく位なのだが、その後毎年交互に、少数の大きい柿、多数の小さな柿の順に実を付け、15年間8月から10月まで、有り難く美味しく頂いている。
今年は、多数の小さな柿の年で、案の定小さな実を今までに無く鈴なりに沢山付けた。少し経つと、柿の木君は、このまま実が大きくなったら枝がもたない、身がもたないと思ったのか、賢くも不思議にも、自ら半分程の実を落とした。落ちた実は、栄養になるようにと毎日木の根元に戻した。それでも、細い枝に4個の実を付けているのを見て、ためらいながら1個間引きをした。木の根元に返そうとも思ったが、実の中の様子を知りたくなって、半分に切ってみた。中学1年生ぐらいの緑の柿ちゃん、生意気に「コーガフイテイル」。「コーガフク」とは方言なのか「粉が吹く」の意味なのか不明だが、甘柿の紛れもない証拠である黒い斑点がしっかり出ている。食してみたらカリカリと猛烈に美味しい。昨年までは、黄色く色づくまで待っていたのだが、今年は違う。有り難くも、毎日3個程緑柿を食べ続けている。
日本において、柿の歴史は意外に古い。約170万年前の岐阜県瑞浪市第3地層から、柿の化石が発見され、縄文時代や弥生時代の遺跡からも柿の種が見つかっている。ただその当時は渋柿のみで、上流階級の人達が干し柿にして食していた貴重な高級食品であったのだろう。
鎌倉時代1214年、現在の川崎市で、突然変異によって甘柿が登場し、これが世界最古で日本固有の甘柿であると言われている。その後、16世紀初頭南蛮貿易でポルトガル人によってヨーロッパに渡り世界中に広まったらしい。それ故、柿の学術名はディオスピロス・カキ(diospyros kaki)で、ディオスピロスは「神の食べ物」の事。それだけ柿は貴重な嗜好品であったのだろう。
正岡子規1895年の句「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」は余りに有名だが、二百年遡って、1694年松尾芭蕉の「里古りて柿の木持たぬ家もなし」という句もある。芭蕉が他界する数ヶ月前、故郷の伊賀上野に戻りしみじみ詠んだ句だが、「伊賀上野は古びた町で、それに相応しい柿の木がどの家にも有って、風情があるなあ。これが日本の原風景なのかなあ」ぐらいの心情か。
栄養の面からも柿は優れた健康食品で、ビタミンC、カリウム、βカロチン、タンニン、食物繊維が豊富であり、疲労回復、老化防止、免疫力向上、高血圧予防、動脈硬化予防、風邪予防などの効能が有ると言われている。
芭蕉があの世に持ち帰った、柿の木のある家という日本の原風景を胸に、庭の有るお方は、甘柿の木を1本植えてみては如何だろうか。
緑柿 少年の味 悲しくもあり
久保貞次郎研究所2024年11月月報(第175回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書著作集第11巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎11月は8点追加し計1301点展示(恩地孝四郎395点 久保貞次郎関連118点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎渡辺淑寛著作集第11巻11月11日もおか新聞プラスより刊行
◎エッセイ「納豆考」 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛(連絡先℡090 5559 2434)
11月の追加作品は8点で、No1294は児玉徹日本画10号「松林後景」だ。松林の背後に寺院が描かれている独特な構図である。No1295は佐々亮暎油彩4号「紫の薔薇」で、紫の薔薇が目にしみる。No1296,No1297は、私のお気に入りの洋画家芝田耕の油彩画12号「風景」と油彩画8号「スペイン・アビラ遠望」である。これで芝田耕の重厚な油彩画は4点の展示となった。No1298は日下田博藍染額「倉」で、益子町日下田藍染工房第8代当主の作品は24点目の展示である。No1299は「緑の髟耳」の異名を持つ伊藤髟耳リトグラフ「官休庵の路地中門」で、No1300は、芝田耕の実弟芝田米三の気色の良いリトグラフ「ユーゴの娘」だ。No1301は、城を多く描く木版画家橋本興家「山の夕」で、15号水彩画は極めて珍しい。
本年11月11日に渡辺淑寛著作集第11巻がもおか新聞プラスより刊行された。来館者様にもれなく贈呈の予定ですので、是非お立ち寄り下さい。
◎エッセイ「納豆考」
「畑の牛肉」とか「大地の黄金」と言われる栄養豊富な大豆を、もし人類が発見し栽培していなかったら、人類は現在まで生存していたかどうかは疑わしい。更に人類は、いや日本人は、タンパク質など体内で消化しにくい大豆を、納豆菌で発酵させる事によって、各種ビタミンなどの副産物を発生させ、動脈硬化予防及び血栓予防物質「ナットウキナーゼ」を生み出す不思議な恐るべきスパーフード食品「納豆」を作り出した。
納豆の起源は諸説あり、1万年近く前の縄文時代に既に食べられていたという説、1400年前聖徳太子が発見したという説、2千年前の弥生時代、床の藁の上に煮こぼれ大豆が落ちて発酵し納豆が偶然誕生した説などが有り定説は無い。
納豆の長所は、極めて栄養価が高く、廉価で入手しやすい等で、短所は粘ついて食べずらい、匂いがきついという点かも知れない。今は、藁の中ではなくパックに入っているので食べやすくなっているし、我々年配者は、納豆の匂いに慣れている。70年前の事だが、当時、幼児は町内の共有財産だという意識が少し残っていて、テレビも携帯も無い時代、子供達は同じ年頃の幼児が居る家々に毎日遊びに行った。するとその家の皺くちゃのお婆ちゃんが出て来て、「ぼうず、乾し納豆食べるかい、良い匂いだよ」と言い、にやっと笑って円筒形の缶に入った乾し納豆をカラカラいわせながら、子供達の鼻先で、突然蓋を開けるのだ。缶の中で密封熟成された乾し納豆の匂いは、それはもう想像を絶する鋭利な匂いで、「ハニャー!」と叫んで倒れる仲間も居た。お婆ちゃん達も私達子供も一緒に笑い転げるこの儀式を、我々の世代は、何回となく経験しているので、今の納豆の匂いなど、薔薇の香りだ。
最後に、70年以上納豆を食してきた私から、読者の皆様に「通」の食べ方を紹介したい。パックの中に、タレと辛子が付いているのが普通だが、私は一切使わない。パックを開け数十回かき混ぜて素のままの納豆を一気に口の中に入れ、よくよく噛んで大豆の本来の味を楽しむのだ。物足りない、味気ないと感じる人も居るだろうが、それはただ塩味に慣れすぎているだけなのだ。商品によっては最初から塩分入りの納豆もあるので、ここ10年は、タレ無し辛子無しで塩分微少の銘柄を探し出し、1日2個食している。些末な話で恐縮だが、タレ辛子無しの商品は廉価で、今日も美味しく頂いた定番納豆は、3パック入り57円で、何と1パック19円という事になる。十数年前、20種ほどの納豆を食べ比べてみたが、結果的に最安値の納豆に落ち着いた。日本人の食に対する知恵、納豆食品会社に感謝しながら、今日の夕餉(ゆうげ)も、よくかき混ぜて一気に頬張り、本来の大豆の味をしみじみ噛みしめよう。
久保貞次郎研究所2024年12月月報(第176回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画・洋書プレゼントも継続中)
◎12月は8点追加し計1309点展示(恩地孝四郎395点 久保貞次郎関連118点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎エッセイ ~ゲーテ「ミニヨンの歌」を読み、レモンの苗木を植える~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
12月の追加作品は11月と同様8点で、No1302はシルクロードを描く画家小田和典リトグラフ「ベドウィンの少女」だ。No1303は造幣局彫金レリーフ「花と少女」、No1304は国立印刷局凹版美術集「西洋名画集15点」と「日本名画集10点」である。貨幣を製造している大阪の造幣局と、紙幣を製作している東京の国立印刷局は、どちらも極めて高水準の技術を持ち、彫金や凹版画など容易に作れるよ、と言っているかのような芸術作品になっている。No1305は、私のお気に入りの画家大貫松三4号油彩画「白玉椿」で、5点目の展示作品だ。No1306は山田説義20号油彩画「花に花瓶」で、今は無名に近いが、昭和22年の示現会創立メンバーである。No1307は、フランスの版画家ジャン・ソロンブル銅版「砂浜風景」で、No1308は著名な版画家金守世士夫木版「湖山ペルシア」だ。両版画とも秀作である。No1307は湘南の実力画家金子保の油彩8号「奥日光」で、金子油彩画は4点目の展示作品となった。
◎エッセイ ~ゲーテ「ミニヨンの歌」を読み、レモンの苗木を植える~
50数年前、静岡の地方を旅した時、至る所に自生している黄金色の柑橘類を見て、何故か言い知れぬ感動を覚えた事が有った。それは、五行川を遡る鮭の魚群を見た時の喜びと似てもいるが、「南方」を暗示する金色に輝く色彩をまとった歓喜の方がやはり大きかった。ゲーテが寒々としたドイツからブレンナー峠を抜けてイタリアの地でレモンやオレンジの黄金色に出会った時、その色彩感、南方感に酔いしれたと言われている。北関東に住む私にとっても、あの黄金色の歓喜は、似たような感動であったのかも知れない。
ゲーテの「ミニヨンの歌」の冒頭に「Kennst du das Land,wo die Zitronen bluhen,..Im dunkeln
Laub die Gold-Orangen gluhen....」という一節が有る。英語では「Do you know the land,where
lemons bloom, in dark leaves gold-oranges glow...」和訳では「君は知っているか、レモンの花咲く国を。暗き葉陰にも金色のオレンジが輝く国を、君は知っているか。」ぐらいか。(英訳、和訳とも筆者)余談だが、日本の公用語はフランス語にすべし、と言ったのは志賀直哉であったが、この独文、英文、和文を読み比べれば、表現にもよるが、和文もなかなか力強く捨てがたいと思える。
さて本題に入る。今年も玄関先に金柑がたわわに実った。木漏れ日の中、数多くの小さな金粒を見上げながら、ふと思った、ゲーテのようにレモンの花が見たいと。「思い立ったが吉日」ではないが、近くのホームセンターに直行し、レモンの実の付いた苗木を2本購入し、狭いが日当たりの良いところに植えた。正解かどうかは不明だが、少し深く掘り、腐葉土と水を入れ、土を被せてまた水を注いだ。翌日、まだ苗木を植える場所が有ることに気がつき、もう居ても立っても居られずレモンの苗木3本を購入し喜々として植えた。昔の歌の文句ではないが、こうなったら、「もうどうにも止まらない」。翌日に伊予柑の苗木を2本、翌々日甘夏の苗木と不知火の苗木各1本植えた。更に後日、控えめで可憐なリンゴの花が見たいと思い、リンゴの苗木を3本植えた。酒タバコは勿論、車も持たず交際費零の私なので、これぐらいのプチ贅沢は許されるであろう。
その日以来、晴れた日には毎朝、12本の苗木を見に外に出ているが、雨巻きの山々から吹く風の中、生育の兆しはまだだ。この苗木達は、北関東の厳しい冬を、果たして越せるであろうか。雪を背負って天に向かい屹立出来るであろうか。私にしても、この地上に居る間に、レモンの花や、リンゴの花を、果たして見られるのであろうか。いや、12本も植えたのだから、這ってでも生き延びて、レモンの花を、リンゴの花をこの目に焼き付けなければならない。お、ふと気が付いた。何よりも貴重な生きる意欲を、この苗木達から、ゲーテから頂いていると。
久保貞次郎研究所2025年1月月報(第177回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎新年1月は9点追加し計1318点展示(恩地孝四郎398点、久保貞次郎関連118点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その1~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
新年1月の追加作品は9点で、No1310からNo1312は恩地孝四郎木版「手」、「無題」、「男の首」である。この3点は、昭和3年井上康文 「詩集手」から切り取り額に入れた作品だ。恩地オリジナル作品のほとんどが海外に流出し、日本の美術市場で見かけることが希有になったので、恩地木版入り稀覯本を目ざとく発見し展示した次第だ。No1313は、文人で美術評論家藤林靖晃4号油彩画「鳥と少年」で、心打たれる秀作である。No1314は中堅実力洋画家三上知治30号油彩画「春」で、No1315は、米国現代画家ジョン・チャスティーンのアクリル12号「平静」で、いかにも現代アメリカ絵画風である。No1316は、シャガールのリトグラフ代表作30号「ロメオとジュリエット」で、ポスター作品で無い貴重後刷り作品である。No1317は、現代前衛画家木原木呂の2016年作墨ミクストメディア12号「水墨抽象」で、木原芸術の新境地が垣間見える。最後のNo1318は、康端倪10号日本画「観音」で、不思議な静けさを漂わせるNo1262「只見晩秋」に続いての2点目の展示作品となった。
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その1~
久保貞次郎氏(1909~1996,以下敬称略して久保)は、美術評論家、美術品コレクター、跡見学園短大学長、町田市立美術館館長、エスペラント学会会長、現代版画プロデューサー、創造美育運動並びに小コレクター運動の提唱者、ヘンリー・ミラー絵画の紹介者、多くの芸術家のパトロン等多くの顔を持つ、真岡市出身屈指の文化人であり、未だその全貌は謎のままだ。
一方恩地孝四郎氏(1891~1955、以下恩地)は本の装幀家として生計を立てていたが、欧米で評価の高い版画家であり、また詩人でもあった。更に写真や作曲活動もしていて、写真では稀覯本「飛行官能」が有名であり、1939年恩地孝四郎支那風景画展には写真も出品している。作曲は、恩地が鶴見花月園少女歌劇部主任の時、小代尚志の名で作曲に携わり、1935年新生堂「童話歌劇小曲集夢」の中に6曲掲載されている。余談で推測だが、「小代尚志」は、孝四郎から小代(こしろ)を取り、尚志は、小代に直したよ、という茶目っ気なのだろう。
1964年久保小論「恩地孝四郎の思い出」によれば、久保と恩地の接点は、1954年3度、1955年1度の計4回有った。恩地が他界したのは1955年なので、恩地最晩年の時であり、深い交流はなかったようだ。久保は、前述の小論の末尾で、「この独創的で詩情豊かなスケールの巨きな作家の芸術が持っている真の価値を、かれが生きているあいだに見定めることのできなかった、ぼくの能力の低さを軽べつし、あわれんだ」と自らを卑下し、逆説的に恩地をこの上も無く高評価している。この賞賛はお世辞ではなく、恩地研究の礎になった1975年形象社「恩地孝四郎版画集」出版時、資金繰りに困窮した時、惜しみなく支援したのは久保であった。恩地版画集出版が、何故資金的に困窮したかと言えば、恩地版画の半分近くが外国に有り、わざわざ外国に行って写真を撮らなければならなかったうえ、撮影代金がかなり高額だったためらしい。例えば、渡辺美術館でNo947として展示している「1949年藤沢薬品工業木版カレンダ-」は3点の恩地木版作品が入っているが(版画集補遺No18,19,20)、作品の裏面の撮影許可が下りなかったのだろう、タイトルが正確でない。No18は「失題」とあるが、裏面に印刷されたタイトルは「内海にのる」、No19は、「舞妓」になっているが「京の雪」、No20は「失題」とあるが「銀座のたそがれどき」だ。この様に、写真撮影自体も容易ではなかった様である。この木版カレンダーは当時無料で配布されたと思われるが、国内では注目されず、外国のコレクターが芸術性の高さ故大切に保存していたのだろう。しかし日本で所蔵している公的機関は希有であり、調査では、当美術館と、京都の伝統有る帯屋さんだけであった。
ここで、久保が何故、生前の恩地を評価出来なかったのかについて私見を述べたい。久保は東大出のインテリで、地方の大富豪である。恩地は、東京地方裁判所検事で後に宮内省式部職につく恩地轍(わだち)を父に持つ名家の出で、本の装幀で細々と暮らしてはいたが、気位が高く鼻っ柱が極めて強い芸術家だ。東京芸大在学中、教授の評価に反抗し退学した話は有名である。
恩地と久保はいわば水と油であったのかも知れない。久保が版画家を評価するという事は、版画を作らせ、それを買い上げる事も意味するので、恩地は、そのような申し出が有れば当然の如く断ったであろう。恩地版画の刷り部数は、1点から数点であり、多くが外国コレクターの手に渡ったので、久保が恩地作品に無縁であったのはむべないことであり、「ぼくの能力の低さを軽べつし」は謙虚すぎる。(その2に続く)
久保貞次郎研究所2025年2月月報(第178回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎2月は9点追加し計1327点展示(恩地孝四郎394点、 久保貞次郎関連119点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その2~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
2月の追加作品は9点で、No1319は、1928年28歳の若さで夭折したパリのデザイナー、シャルル・ジェスマールの12号水彩画「show」で希少作である。No1320は速水御舟(伝)3号日本画「花図」で可憐な小品だ。No1321は、久保関連画家木村利三郎20号スクリーンプリント「Paris」で息を呑む構図の傑作である。No1322は、茨城県出身須田惣太郞変形15号油彩画「栃木路」で、真岡市の風景画も描いている。No1323は、お気に入りの洋画家芝田耕油彩8号「フランドル城」で、5点目の展示作品となった。No1234~1236の3点は、孤高の画家中村忠二の水彩画3点である。順に「アロイ」、「チイサイオンナノコ」、「野花の内いるがお」だ。No1327は中村忠二と山本蘭村の水彩合作「レモンのクリスマス」で、放浪の画家山本蘭村と異端の画家中村忠二とは何か引きつけ合うものが有ったのかも知れない。
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その2~
久保は、恩地評論を3編残していて、1964年版画第4号「恩地孝四郎の思い出」、1975年恩地孝四郎版画集「恩地孝四郎を思う」、1978年NHK日曜美術館第7集「一枚摺りの恩地芸術」だ。3編とも恩地芸術を正当に高評価する内容であるが、最後の「一枚摺りの恩地芸術」の中で、強い違和感を覚える箇所が有った。他界するまでエスペラント学会会長を務め、人知れず左翼の芸術家まで支援し、3点以上のオリジナル作品を所有し生活の中に芸術を浸透させるという小コレクター運動を提唱した久保は、差別も暴力も戦争も無い社会、貨幣も国家も無い社会、全ての人が芸術家である社会という人類の壮大な夢を密かに夢見ていたのではないかと、私も夢想する。もしそうだとすれば久保は、遠大な文明論者であり人類学者と言う事も出来る。それ故、この違和感は、同郷の心より尊敬する久保氏の文章では唯一の強い違和感だった。
恩地芸術には「前衛的であるためにもつべき拒絶性の欠如がある。前衛的芸術は古きものとの訣別の態度を、鋭い拒絶の精神によって表現する。しかし恩地の絵画の中には、その厳しい否定の感情は見られない。」と書かれている。だが恩地は自分を前衛画家などとは思ってもいないし、「前衛」の定義も明確ではない。久保は、「前衛」という言葉自体におもねり、酔い、未だ謎の芸術家恩地に「前衛」を期待したのではないだろうか。その時代「前衛」と呼ばれた芸術家が、時が過ぎるとその時代の補完物にすぎない事は良く有る事だ。
私見だが、恩地を大きな視点で表現すれば、「希代の装幀家」でも「詩人」でも「抽象版画の開祖」でも無く、久保と同様「文明論者」だと思っている。1952年恩地「本の美術」の中に「本は文明の旗だ、その旗は当然美しくあらねばならない」という有名な文言が有る。人類の進化の尺度は、本の美しさで判断出来る、という意味であり、恩地は戦争関連本も美しく装幀した。唾棄すべき本でも「美しくあらねばならない」から装幀を引き受けたのだ。多くの従軍画家が「戦争責任」を追求される中、無名だから故、その難を逃れたが、もし追求されていたら「悪魔の本だからこそ美しく装幀したのだ」と強面に言い張るであろう。恩地は、1921年30歳の時、工房雑記「幸福へ到る道」で、「人は何故争わねばならないのか」、「人と人、人間と人間との間に血が欲せられなければならないのは何故か」、「ああ幸福へ到るの道。・・・そこは一滴の血をも要しない。否、血ぬられてはならない道である」と書き、人類の歴史が血の歴史であった事を嘆いている。同じ工房雑記「万人の芸術」の中で「芸術が人類生活に最早なくてはならないものであることは改めて云うまでもないと信じる」、「芸術は何故万人の生活の中心であらねばならないか。それは心賢き人には分かりすぎている。芸術は実に生々として、硬化していない、神の具体であるからだ」とも書いた。「神の具体」に抵抗があるならば、「宇宙の真理の表れ」と換言すれば良いだろう。驚いた事に、芸術が生活の中心だという点では久保も恩地も本質的に同じである。前衛とか非前衛の問題は既に止揚され、二人共人類史の遙か彼方を見ていたのだ。久保の「恩地非前衛論」は久保の数少ない勇み足であったかも知れない。久保氏も天で、「不肖の同郷の士よ、よく指摘してくれたな、有り難う」と言って下さるのではないかと密かに願っている。(その3に続く)
久保貞次郎研究所2025年3月月報(第179回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎3月は7点追加し計1334点展示(恩地孝四郎394点、 久保貞次郎関連119点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その3~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
3月の追加作品は6点で、No1328は、アメリカの現代画家ケネス・アウチマン50号油彩画「Sea 3 D」で1994年の大作だ。No1329は、吉田友三40号油彩画「龍口のある風景」で1954年の作だが、しみじみとした情感溢れる風景画である。No1330は、関野準一郎木版シート9点東海道53次シリーズで、「戸塚」、「三島」、「府中」、「島田」、「日坂」、「白須賀」、「掛川」、「平塚」、「大津」だ。No1331からNo1333も同じ関野作品で順に木版「フィレンツェの甍(縮図)」、「木版「鳩と小石」、銅版「奥尻島」で、関野43点目の展示作品となった。関野は、師匠の恩地孝四郎程ではないが、日本より欧米の方が評価の高い版画家である。恩地版画は存命中ほとんど売れなかったので、一作品数部しか摺らず、その数部も米国コレクターによって米国に渡ってしまった為、日本の美術市場で見かけることは希有だ。一方関野は多作版画家で、摺り部数も多く、現在でも容易に廉価で入手出来る。存在の喜びとその持続を目指した孤高の師恩地と違って、関野芸術は、浮世絵版画の伝統を咀嚼しながら版画の「大衆性」を目指し、日本の美しい風景を版画で残そうとする芸術である。そして多くの作品群を俯瞰すれば、その目的は成就され、関野版画は日本美術史の中で燦然と輝いている。
◎美術評論「久保貞次郎と恩地孝四郎」~その3~
「自同律の不快」と言ったのは小説家埴谷雄高であったが、恩地芸術の本質は、存在の不安でなく、存在の喜悦、「自同律の快」なのだ。埴谷によれば「自同律の不快」をバネに人は飛翔出来ると言う事なのだろうが、「自同律の快」では飛翔する必要は無い、既に喜びで震えながら躍動している。
この地上では、存在の始まりは海であるので、恩地は海について多くの作品を残した。更に人間の誕生は女体からなので女性を多く描く。1917年若き恩地26歳の油彩画50号「三人の裸婦」(当美術館展示作品)について、有島生馬を訪ね批評を乞うたが、余りに躍動しすぎて荒削りであった為、有島は内心閉口し、第5回二科展でも落選している。それでも恩地は、気にもかけず「存在の喜悦」を表現し続ける。「童女浴後」などの少女像も発表するが、恩地がロリコンなのではなく、女体の源を知りたかった為なのであろう。更に恩地は、海、女体、生命、虫、動物を描き、抽象版画を製作しながら、素晴らしい肖像版画も発表する。恩地の最高傑作は何かと問われれば、私はためらわず1943年「氷島の著者・萩原朔太郎像」を挙げる。苦渋に満ちた、それでいて表現者の強靱さと矜持を滲ませるこの木版画を見る度に、氷島の一篇「帰郷」を想起する。二人の童女を置いて去った妻と離別し、夜汽車で前橋に戻る難渋苦渋の一篇だが、強い的確な言語で、表現者の底知れぬ強靱さを示唆している。この木版画とこの詩は、根底で不思議にも重なっているのだ。そして多くの皺の中から滲み出る言い様も無い悲しみと気概は、強い線描が可能な木版画でしか表現され得ないと確信している。
恩地を「抽象表現の先駆者」、「抽象版画の開祖」と括ってしまう考えには、私は決して組みしない。恩地は表現したい方法でただ表現したにすぎないのだ。萩原朔太郎像発表の同じ年、半抽象の素晴らしい詩画集「蟲・魚・介」(木版10点入り)を著している。私は、抽象絵画を卑下するつもりは毛頭無い。対象を描写するのも人間の自然な行為だか、自分の思い、情念を形と色で表現するのも、人間にとって自然な営みなのだ。以前、クレヨンで無心に画用紙に何かを描いている児童に、不覚にも「何描いてるの?」と聞いてしまった。その子は、驚いた様子で、「え?ただ描いてるだけよ」と言って、素敵な抽象画を隠すような仕草をし、嫌悪の目で私を見た。その子は、「抽象画」などという言葉も知らないまま、自分の思いを色と形にして楽しんでいただけだったのだ。大学の美学美術史学科で、一体何を学んできたのかと自問し、自らを恥じた。それ以来「何を描いてるの?」と訪ねる事は禁句だ。更に、個人的には、「具象」より「抽象」の方が、人間の表現として本道であると思ってもいる。
恩地は、この抽象表現の純粋性を本能的に察知していたのだろう、音楽による感動を抽象木版で表現して、周囲を驚かせた。繰り返しになるが、それでも恩地は、写真、作曲、装幀も含め自由に色々な表現方法で、ただ表現しただけにすぎない。それ故、恩地を「抽象版画の開祖」と括ってしまうのは、恩地芸術の本質を見誤る事になる。恩地芸術の本質は「存在の喜び」の表現なのだ。「存在」は持続せねばならず、それ故、植物にとって、花は生殖器なので、詩画集「日本の花」で恩地は、肉感的な花を描いた。
私の「恩地論」は、異端中の異端なので、今は一顧だにされないが、何時の日か日の目を見る時も来るかも知れない。9年前、NHK日曜美術館で恩地孝四郎特集番組が有り、取材での来訪時、上述のような事を述べたので、番組の趣旨にそぐわなかったのか、怪訝な顔をされ、困惑の表情が見て取れた。それもそのはず、その「困惑」の理由は、久保氏と同様恩地も、輪郭さえも掴めない未だ闇の中の謎めいた巨人なのだから。
久保貞次郎研究所2025年4月月報(第180回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎4月は11点追加し計1345点展示(恩地孝四郎394点、、久保貞次郎関連119点) 土曜日以外2名以上の来館者様で電話予約御相談の上随時開館
◎美術評論~コンスタン・トロワイヨン8号油彩画「羊と少年」を展示して(その1,出会い)~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
4月の追加作品は11点で、No1134は、長澤昭朗日本画10号「朝靄」で、当美術館では3点目の展示作品である。No1135はエミリオ・グレコ彫金作品5号「腰かける女」で、No1336は米国のマルチタレント現代作家マルタ・ワイリー水彩画20号「金閣寺と富士山」だ。No1337は相沢常樹ミクストメディア20号抽象画「沈黙」で、No1338は、当美術館開館10周年を記念するコンスタン・トロワイヨン8号油彩画「羊と少年」である。No1339は山口硯閑12号油彩画「水辺」で独特な色彩が漂う秀作だ。No1340は笠井正博シルクスクリーン版画「組曲波Ⅷ」でタイトルが洒落ている。No1341は、関口恭子刺繍画15号「森への道」で刺繍画は初の展示作品である。No1342は、スペイン生まれニューヨーク在住の画家サンティ・モイッシュアクリル画15号「水色の花」で、全面透き通った水色の絵だ。No1343は狩野派の末裔ながら洋画の道に入った狩野寿一油彩画12号「サンマルコ広場」で、最後のNo1344は、自然染色家とか魔法の染色家と呼ばれている須貝風子の「ひまわり」30号である。対象物を布に押し当て高温の蒸気で染色すると言われているが詳細は不明だ。それにしても30号染色画は希有であろう。
◎美術評論~コンスタン・トロワイヨン8号油彩画「羊と少年」を展示して(その1、出会い)~
コンスタン・トロワイヨンは、1810年パリ近郊セーブルで生まれ、1847年までは他のバルビゾン派の画家と同様バルビゾン村近辺の風景を主に描いていたがそれ程評価されなかった。1847年オランダ旅行から戻ると、画面に生命感溢れる牛や羊などの動物を描き始め、欧州ばかりでなく英国米国でも名声を博し、バルビゾン派7星の一人と評されようになった。(他の6星は、ミレー、コロー、テオドール・ルソー、ドービニー、ディアズ、デュプレ)ただ1865年54歳の若さで早逝し、動物を描き出して17年に満たないので、作品数も少なく、全作品集(カタログレゾネ)も日本では出版されていない。86歳まで睡蓮を描き続け、2千点以上の作品を描き残したクロード・モネとは大違いで、トロワイヨンの動物画は多くて3百点ぐらいであろうか。蛇足ながら、トロワイヨンは、1859年、19歳のモネに、絵の技法を教えたと言われている。
日本のトロワイヨン作品所蔵美術館も少なく、少し古い資料だが山梨県立美術館2点、山寺後藤美術館4点、あとは1点所蔵で東京富士美術館、国立西洋美術館、大山崎山美術館、島根県立美術館、北海道立美術館、千葉市立美術館、長野県信濃美術館、北海道立帯広美術館、栃木県立美術館などで、個人所蔵作品を含めても日本に有るトロワイヨン作品は20数点であろうと推察される。
半世紀以上前、名大美学美術史生の時から、印象派よりバルビゾン派の方がお気に入りであった。一部の美術関係者が、「印象派と名を打てば、二流の作品でも集客出来るよ」とうそぶくのを目の当たりにしたからかも知れない。またバルビゾン派の展覧会では、相当数の名品を展示しない限り集客はおぼつかず、それ故、閑散とした展示会場で、心ゆくまで鑑賞出来たのもバルビゾン派好みになった理由だ。
美術館開設という50年来の夢を10年前に実現し、倉庫を改造し、足の踏み場もない乱雑な美術館でも充分満足してきたが、バルビゾン派好きが高じて、NO368シャルル・E・ジャックのエッチング「雌牛」とNo545テオドール・ルソー鉛筆画「森の中の村」を目立たぬ所に飾って一人悦に入っていた。特にルソーの鉛筆画は、サザビーズの証明書付きだが美術館に展示する程の作品でなく、後ろめたい思いも有った。
西洋では、17世紀から19世紀、宗教画を含む歴史画、肖像画、風俗画、風景画、動物画、静物画の順で低評価になる時期も有ったが、そのような格付けは枝葉末節の事だ。絵画表現の目的の一つは、一般人には思いもよらぬ素晴らしい色と形で、対象物の生命感を生き生きと表現する事だと思っているので、バルビゾン派のなかでは、動物の生命感を見事に描き出すトロワイヨン油彩画に憧れ、奇跡が起こって1点でも展示出来ればと、不可能だと解っていても夢想していた。
長期間密かに思いを募らせていれば、突然願いが叶う時も希に有るものなのか、本年正月末、東京の有名古書店から定期的に古書目録が送られてきた時の事だ。古書目録の小冊子13ページに来た時、下段に、何と、トロワイヨンの油彩画「羊と少年」とパリの有名画廊の証明書がカラー図版で掲載されているではないか。息を飲みながら、28ページ先の価格蘭を見た。廉価だ。質の悪い印象派油彩画の数十分の一の価格だ。これなら、なけなしの貯金を下ろさなくても買える。すぐに電話をして、在庫を確認し、即注文した。注文時、「値段、一桁違っていませんよね」と大人げなく2度も尋ねたので、電話相手の店員さんの失笑をかったが、私の、天にも昇る心持ちがお相手にも伝わり、夢のような時間であった。少し経って、西洋美術に造形が深く、本も出されている店主の方からお電話を頂き、年代等の説明も受けた。これがトロワイヨン油彩画との出会いの顛末であり、「羊と少年」が、渡辺美術館所蔵作品となった経緯である。(その2に続く)
久保貞次郎研究所2025年5月月報(第181回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎5月は9点追加し計1353点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連119点) 土曜日以外2名以上の来館者で電話予約御相談の上随時開館
◎美術評論 ~トロワイヨン油彩画「羊と少年」を展示して(その2、トロワイヨンの牛と米陀寛の牛)~ 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
5月の追加作品は9点で、No1345は、スペインの女流画家カルミア・ミランダ12号油彩画「薔薇」だ。No1346は、安藤幹衛50号油彩画「踊り」で、1982年名古屋日動画廊安藤幹衛回顧展図録の表紙絵を飾った安藤の代表作である。数十年気にかけていたが、幸運に幸運が重なって偶然入手出来た秀作だ。No1347は、後藤よ志子8号油彩画「コートダジュール」で、女性で初めて「安田火災東郷青児美術館大賞」を受賞した実力派画家である。No1348は田中正秋シルクスクリーン版画「相模大凧まつり」で、日本の祭りシリーズ13点目の作品だ。No1349は、水彩連盟初代理事長三橋兄弟治8号水彩画「スペイン・サグント」である。No1350は、彫刻家から漫画家に転身したエルド吉永5号ミクストメディア
「龍子」だ。No1351は川崎春彦12号日本画「高原の朝」で、春彦4点目の日本画である。No1352は、宮内義也油彩画10号「静物」で、春彦作品も宮内作品共静寂な青を基調とした秀作で、日本画洋画の違いはあるが、芸術性という点では同じ高みに達している。No1353は、田中春弥20号油彩画「静物」でこれも秀作である。
◎美術評論~トロワイヨン油彩画「羊と少年」を展示して(その2,トロワイヨンの牛と米陀寛の牛)~
1846年、風景画に行き詰まったトロワイヨンは、オランダを1年近く旅し、28歳で早逝したパウルス・ポッテルの「若い牛」(1647年作、オランダ、マウリッツハイス美術館蔵)に邂逅する。中央の2頭の牡牛と1頭の山羊、2頭の羊が描かれている「若い牛」は観る者を圧倒する迫力で、特に2頭の牡牛には、早逝したポッテルの魂が宿っているようだ。その後、バルビゾンに戻ったトロワイヨンは、風景の中に、主に牛、羊を描き、特に、トロワイヨンの描く牛は、ポッテルの魂を受け継ぐが如く生命感に溢れ、「牛のトロワイヨン」とも呼ばれるようになった。
「牛の・・・」と言えば、日本画壇にも極めつけの牛の画家が居る。終生宇都宮市で活躍した米陀寛(1917~2005,日展参与)だ。「牛の米陀」と呼ばれ、馬、鳥、魚、人物も描いたが、とりわけ大地を踏みしめる、画面一杯の重厚な牛を得意とした。渡辺美術館でも、米陀寛4号日本画「牛」(No565)を展示しているが、素描に近く、1994年「牛と少年」、1995年「赤牛」、1996年「黒い牡牛」(3点とも個人蔵)の迫力には到底及ばない。
以前、米田寛御存命だった時、氏のアトリエを訪ねた事が有った。食事を共にしたあと、氏がアトリエで、空を走る鳥の絵を描いている所を拝見できた。その時、私は、不遜にも思わず「この鳥、飛んでいない」と失礼な事を口走ってしまった。それ以来、出入り禁止だが、何かの縁なのか、当美術館には、氏の飛んでいない鳥の日本画10号「かわせみ」、「キセキレイ」2点が展示されている。やはり、米陀寛は、牛を描く極めつけの画家なのだ。米陀の描く牛は、米陀の理想の牛であり、あくまで日本の牛であり、人間と共生する牛だ。1998年作「角牛図」の闘う2頭の牛でさえも、優しい日本の牛である。だが、これだけは言える、日本美術史上、牛の絵を描かせたら、米陀寛の右にでる者は居ないと。
一方、トロワイヨンの牛は、日本画と油彩画の差を考慮しても、米陀の牛と根源的に違う。「牛の揉みしだき」(1859年、オルセー美術館)、「嵐の前」(1860年頃、ブタペスト国立西洋美術館)、「草地の牛」(1852年、エルミタージュ美術館)を観るまでもなく、トロワイヨンの牛は、人間と共生などしていない。ゴツゴツした肉体で、自立し、自然と闘い苦闘している。「牛の揉みしだき」の牛を観るが良い。愚鈍で重厚な肉体を持て余し、自らの肉体をそぎ落とそうと大木にこすり付けている。そして、牛という存在を恨むが如く、悲しい眼差しを我々に投げかけている。やはり、存在感では、「トロワイヨンの牛」の方が「米陀の牛」より私の胸を突く。
今回、当美術館で展示したトロワイヨン油彩画は、牛でなく羊と少年の油彩画だが、羊に草を与える図柄は珍しく、羊の毛並みも秀逸で、是非来館なさり鑑賞なさって頂ければ幸いである。170年近く前に描かれた絵が、海を渡り、遙か極東の、北関東芳賀の地のみすぼらしい一美術館に展示されるのも、何かの縁なのだろう。全ての芸術作品は、完成されたとき「造形的生命」を持つと言うのは本当だ。「羊と少年」も当美術館の二階の片隅で、日夜目映い微光を放っている。
久保貞次郎研究所2025年6月月報(第182回)
◎渡辺美術館 毎週土曜日午後1時から4時開館 入場無料 来館者様に拙書第11巻贈呈(版画洋書プレゼントも継続中)
◎6月は7点追加し計1360点展示(恩地孝四郎394点、久保貞次郎関連119点) 土曜日以外2名以上の来館者で電話予約御相談の上随時開館(℡090 5559 2434)
◎「人間の生きる意味」への一つの解答~アインシュタイン「私は信じる」より~その1 久保貞次郎研究所代表 渡辺美術館館長 渡辺淑寛
6月の追加作品は7点で、No1354は中村忠二色紙水彩画「秋日」で1967年の作だ。No1355は、彫刻家オーギュスト・ロダンの5号水彩画「裸婦」で、あまり周知されていないが、ロダンは水彩画も多く描いている。日本でも1999年、静岡県立美術館で、「ロダンの水彩画とデッサン展」が開催された。No1356は、須田寿リトグラフ「鳩」で、須田寿は生き生きとした鳩をよく描く画家だ。No1357は、佐藤真一油彩画15号「パリ・ジャコブ街」で、No878油彩画20号「川沿いの家」につずいて2点目の展示作品である。No1358は、妖艶な線描版画家城景都「face」で、10点目の展示作品だ。No1359は、オクサナ(Oxana)の変形25号水彩画「スケートをする人達」で、詳細不明の画家だが、息を飲む程の精密描写で傑作である。最後のNo1360は、名古屋市出身浪打栄光3号水彩画「ペルー・アヤクチョ村」で、50年前学生時代、名古屋の大画廊の展覧会で何度か作品を見かけた画家である。その時から1点は欲しいと思っていたが、50年が過ぎて小品水彩画ながらやっと入手出来た作品だ。
◎「人間の生きる意味」への一つの解答~アインシュタイン「私は信じる」より~その1
宇都宮大学では、工学部執行委員、全学中央委員などを務め暴れん坊であったが、高度成長期であったためか、4年生時、数社の有名企業から熱心なお誘いを受けた。成績も悪くはなかったので、先生方からは院で学ぶことも勧められた。だが、顔に似合わず内心はナイーブで、小学生時代から「死」について考え「死の恐怖」に恐怖し、高校生の時には日本文学を読みあさり、「人間の生きる意味」についていつも考えていた。企業戦士で一生を送るのも、化学の専門家として生涯を閉じるのも悪くはないのだろうが、「人間の生きる意味」を置き去りにして、そのいずれかの道に進むことはどうしても出来なかった。それで、その思いを父母に伝え、許されるなら再受験し、文学部哲学科で、お仕着せで無い本当の勉強がしたいと、声を詰まらせながら話した。すると、思いもよらず、父母は即座に快諾してくれた。「我が子が、もっと勉強したいと言って来たら応援するしか無いよね、母さん」と父は、母に語りかけ、母は目頭を熱くしながら「そうですね」と静かに答えた。今思えば、母の涙は、少しの喜びと、これからの生活の苦しさの予感からだったのかも知れない。それは当然だ。サラリーマンになり給料を頂ける身分になる息子から、時にはお小遣いを貰えるかも、と思っていた矢先、また4年間、再受験のため浪人すれば5年間仕送りをせねばならない。
母の心境を察すれば、浪人など間違っても出来なかった。卒論発表の翌日が名大入試日という過酷な日程ながら、無事合格し、浪人留年せずの8年間で二つの大学を卒業した。名大の一般教養課程の2年間で、むさぼるように本を読み、美術芸術だけは独学が容易でなかったので、3年次からは美学美術史を専攻し、今、粗末ながら小さな美術館の館長をしている。それでも名大の4年間は、「人間の生きる意味」を探す旅であった事は言うまでも無い。
様々な哲学や宗教、人生論に触れたが、どうも腑に落ちない。ご立派だが、偉そうでどうも胡散臭い。そんな時2年生の冬、或る文章に出会った。1930年アインシュタイン51歳の文章「What
I believe」(私は信じる)だ。人類史上最高の物理学者と言われるアインシュタインは、「man is here for the sake
of other men」(人間は他者の為にここに存在する)と恐ろしいほど単純明快に言い切っている。「生きる意味」を探す旅人の暗い疲れた心に、旅の終わりを暗示する目映い稲妻が走った。我々人間は、他者の幸せのためにこの地上に生まれた、と言っているのだ。アインシュタインについて「相対論」を含めて直ぐ調べだした。以前「相対論と量子論」という拙文を2回に分けて、真岡新聞、小山まるごと新聞に、掲載させて頂いたのもその時の知識からだ。
「他者の為に生きる」とは具体的にどう言う事なのだろうか。まず人は衣食住で何とか満ち足りなければならない。そのためには一定程度の金銭を得るため、自分と家族のために働かねばならない。そして誰にでも様々な欲望が有る。その状況下で、「他者の為に生きる」とは、どのような生き方なのだろうか。(その2に続く)