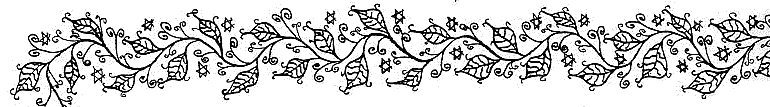
「久保貞次郎研究所2011年2月 月報」
久保貞次郎研究所
「久保貞次郎研究所2011年2月 月報」
「真岡・浪漫ひな飾り展」を観て
「海老原真砂米寿記念展」を観て (真岡新聞2011年2月4日号)
渡辺私塾台町本校塾長 久保貞次郎研究所代表 渡辺淑寛
新年1月10日、寒さの中にも、春の息吹を予感させる快晴の午後、市内荒町岡部記念館「金鈴荘」に、「真岡・浪漫ひな飾り展」を観に行った。(3月3日まで開催)
江戸、明治、大正、昭和期の作品から、近作の真岡木綿雛まで23組が、大座敷に並べられ壮観で厳粛な空気も漂っていた。歴史文化の結実の一つである雛飾り展と、県指定有形文化財である金鈴荘との出会いは、至高の邂逅であり、真岡市及び同市観光協会の関係者の方々のご努力に、一市民として感謝と賞賛の意を表したい。
一点一点のひな人形の表情を見つめながら、40年前の学生時代の思い出が鮮やかに蘇った。美学美術史専攻の卒業論文で、様々な芸術を比較研究する「比較美学」のタイトルで論文を書き進めたとき、人形芸術についても触れたかったが、力不足でどうしても立ち入ることが出来なかった。優しい柔和な表情の中に秘められた悲しいほどの美しさの秘密が解らなかったのだ。だが40年経って初めて気が付いた。「人形」とは、人の代わりに、あらゆる災難、刻苦を身代わりになって引き受けてくれる「ひとがた」であると。観賞用人形や、衝突実験で砕けてしまう人形、案山子(かかし)などの実用的人形もあるだろうが、人形の本質は身代わりの「ひとがた」なのだ。そう言えば、副葬品の埴輪も不気味なほど美しい。人形の美しさは、悲しい「殉死の美」なのだろうか。そのような人形の中で、お雛様は、優しさと悲しさが溶け合って透き通ってしまいそうで一番美しい。
1月16日、益子町外池酒造店ギャラリーカフェ涌に、「海老原真砂米寿記念展」を見に行った。益子町の三田絵画研究所で海老原氏と同窓生である娘から、虚飾のない純朴な絵を描く、と聞いていたので、一度観たいと思っていた。会場の関係で大作は展示されていなかったが、初期の作品から近作まで25点の油彩画が、適切な照明を受け輝いていた。全作品とも、想像以上に完成度が高く、高名作家の急仕上げ作品などより、余程存在感がある。これは、毎年、東京の日洋展に多数の入賞者を輩出する三田絵画研究所の優れた指導の賜なのだろうが、それに加えて、これらの秀作は、海老原氏特有の資質の表出でもあるに違いない。氏との話のなかで、氏は風景や静物を見て描きたくなると、かなり時間をかけて、一生懸命描くと言う。美しい風景や静物に感動し、それを心の中に留めるだけでなく、その感動を油彩画という形で純粋に具現化しているだけなのかも知れない。だが感動の表出と具現化という芸術の原初形態を、多くの芸術家が忘れかけている昨今、氏の作品の素朴さ、純粋性は、一層輝きを増している。
それにして米寿を間近にして初の個展とは、何という快挙だろう、何という行動力だろう、何という勇気だろう。日常に忙殺されている我々にとっては、夢のような素晴らしい生き方である。近隣で氏のような理想の芸術家を目の当たりにすると、遥か北関東の地にいても、人類は、全ての人が芸術家である社会に向けて確実に進化していると確信する。そう、存在とは進化だから。
宇都宮美術館「荒井孝展」を観て (真岡新聞2011年2月18日号)
渡辺私塾台町本校塾長 久保貞次郎研究所代表 渡辺淑寛
冷たい冬の風に震えるように揺れる木々の梢が春の予感を微かに感じ始めている2月2日、宇都宮市長岡町に宇都宮美術館「荒井孝展」を観に行った。(4月3日まで開催)
荒井氏は院展を中心に活躍している宇都宮在住の日本画家で、「裏彩色・裏箔」等の古典的技法を用いた幽玄な作品で知られ、栃木県を代表する作家である。
百点を超える作品を観ながら、静寂な感動に浸り、私は2つの事を考えていた。一つは10年前、都美術館で観たフェルメールの「手紙を書く女性」の事である。あの作品は、微かな光に触発され、3世紀前のオランダ、デルフトの光を観る者に強く放射していた。荒井氏の作品は、多くの光を吸収し、それを純化し、優しい慈光で私達を照射してくれる。
2年前国立博物館で観た伊藤若沖「動植彩絵」30幅の「裏彩色」は、色彩を際だたせるためのように思えたが、荒井芸術では、色彩を再編し純化しているように感じられる。そう言えば15年ほど前、渡辺私塾文庫開設のため、絵を少し収集していた時、或る画商さんが7点の絵を携えて来宅した事があった。6点は高名な作家の作品だが凡作で、すぐ引き取ってもらったが、残る1点は、明るい自然光を浴びて目映く微光を発している宝石のような日本画の小品であった。高額で購入できなかったが、それが荒井作品との最初の出会いである。叶わぬ夢だろうが、本展の大作群を、強い自然光の中で観てみたいと夢想する。どんな光を何処へ放つのだろうか。
もう1つ考えていた事は、荒井氏の作品は「競い絵」ではないと言うことである。それぞれの作品が、凛として自立した芸術作品であり、例えば片岡球子の強烈な人物画、富士と比べたら、荒井作品自らその場を退くであろう。それこそ、これだけの作家が、院展内の序列で優遇されていない理由なのかも知れないが、序列などどうでも良い。芸術的評価は、最後にはアカデミズムが決めるのではなく大衆が決めるのであり、もっと正確には、後世の大衆が決めるのである。そして既に一般大衆は荒井芸術に気付き始めている。今回の100点を超える出品作の多くが個人蔵であること、前述の7点の作品のうち荒井作品が、多くの愛好者がいるため、群を抜いて高額であったことは、その証左であろう。何れにしても、100年後、日本美術史上に荒井孝の名は確かな足跡を残しているに違いない。
また将来美術、芸術の道を歩もうと若者に、図録の末尾にある谷新美術館長の「荒井孝論」を精読し、芸術作品を生み出す刻苦、それを受け止め見守る評論家の強靱でしなやかな精神を垣間見てもらいたい。谷氏は、作品1点1点精緻に分析しながら、荒井氏の画業を解説し、結びで、日本近代史において、日本が「発展期」から「成熟期」に移行している今、荒井氏の「裏彩色・裏箔」の実験的試行、表現方法は、その変遷の象徴であり、時代指標であり、文化的に社会学的に再考される必要があるとまで言及している。美術界に限らず、「発展期」の力任せの「量的美」から、「成熟期」の精妙な「質的美」への移行の必要性を僅かでも実感できる昨今、谷氏の論は、傾聴に値する。
ところで、地方の中核美術館の使命の1つは、郷土の埋もれた作家の発掘と再評価であるが、当文庫にも1点出品依頼のあった、2005年平塚市美術館「大貫松三展」などはその良い例であろう。使命のもう1つは、何れは世に出る作家にいち早く光を当て、その画業を遍(あまね)く世に知らしめる事である。その意味で今回の宇都宮美術館「荒井孝展」は白眉であり、関係者のご英断ご努力に、最高の敬意を表したい。